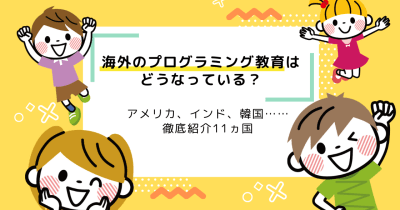次世代の科学技術系人材をはぐくむ「SSH(スーパーサイエンスハイスクール)」

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
今回は、そんなSSHとは一体なんなのか、海外・日本での現状はどのようになっているのかについて、簡単にご紹介します。
SSHの背景となった「理科離れ」
スーパーサイエンスハイスクール(SSH)とは、未来を担う科学技術系人材を育むことをねらい、中高一貫校・高校において、理数系のハイレベルな教育を行うための取り組みです。開始されたのは2002年で、2021年度(令和3年度)には218校がSSH指定校となっています。SSHがスタートした頃には、子どもたちの「理科離れ」が大きな問題となっていました。経済協力開発機構(OECD)や国際教育到達度評価学会(IEA)の調査から、国民の科学技術に対する関心が低いこと、「理科が好き」「将来科学を使う仕事がしたい」と回答する子どもの割合が、なんと先進国21ヶ国の中で最下位であることが明らかになったのです。
子どもの頃から理科に対する関心がないと、大人になってもなかなか関心を持つことができません。そうなると、国際的な競争力にも関わってきます。
そのため、危機感を抱いた文部科学省は「科学技術・理科大好きプラン」を打ち立て、そのうちの一つとして、SSHをスタートさせたわけです。
SSHではどのようなことをしている?
SSHには、「科学技術系人材の教育」としての役割だけでなく、「研究開発学校」としての役割も与えられています。これはつまり、「新しい学習指導要領(ルール)を作るために、まずはSSHで新しいスタイルを試してみて、効果が出たら、すべての学校に取り入れよう」という取り組みです。そのためSSHでは、一定の条件下で、学習指導要領の範囲を超えた活動を行うことができます。「認められた範囲」「受験勉強に使える範囲」に閉じこもってしまうことなく、発展的な活動を行えることが、SSHの大きな特徴といえるでしょう。
具体的な活動としては、
- 大学や研究機関等と連携した授業
- 企業や実験施設などの見学
- 充実したクラブ活動
- コンテスト・研究会への出場
最近では、よりグローバルな社会に対応するため、海外への留学や英語プレゼンテーションなども活発に行われています。さまざまな側面で、子どもたちの興味・関心を引くようなカリキュラムが組まれているのです。
SSH指定校にはどのような学校がある?
SSH指定校になるには、それぞれの学校が文部科学省に応募して、審査を受ける必要があります。採択されてSSH指定校になると、科学技術振興機構(JST)からサポートを受けながら、さまざまな活動をすることになります。指定校のうち、大多数は公立高校です。学校によっては、一部のクラスだけをSSH対象としている場合もあります。
SSH指定校の4年制大学理系学部への進学率は、全国平均と比べると男子で約2倍、女子で約3倍となっており、高い効果を感じさせられます。
地域のバランスをとるため、今ではすべての都道府県にSSH指定校が置かれていますが、とくに多いのは有名な大学に近い地域のようです。このような地域のSSH指定校は、大学との交流・連携も盛んに行なっています。
なぜいま、SSH指定校が注目されるのか
これまでの学校の授業スタイルは、先生が教科書に基づいて授業を行い、生徒はそれを聞いて覚えるだけ……という暗記・詰め込み型になりやすいことが指摘されてきました。その結果、成長した子どもたちに対して「自分でものを考えられない」「指示待ち人間」といった批判がされるようになり、大きな課題となってしまいました。また、「テクノロジーが進歩していく中で、人間だけが持っている力は創造力だ!」という意見もあり、子どもたちがより自主的に、創造的な活動を行えるような教育のニーズが高まってきたのです。
文部科学省は、マークシート方式のセンター試験を廃止し、「思考力・判断力・表現力」を問う、新しいスタイルの大学入試に切り替えていくと発表しました。これが、2020年度の大学入試改革です。
一方、SSH指定校からは、特許出願や、アメリカの学会誌への論文掲載を果たした高校生も出てきています。
SSH指定校では、グループ学習・個人学習など、形式は学校によってさまざまですが、何かひとつのテーマに対して仮説を立て、実験を行なって考察する……という、創造的なスタイルの活動が行われているのです。
時代的にも、制度的にも、求められる教育が大きく変わる中で、自分で課題を探し、それを解決していく能力を養ってくれるSSH指定校の人気が、ますます高まっています。
SSHでの学びをどう活かすのか
前述したように、SSH指定校の活動では、仮説を検証するという能動的な学びが重要視されています。これは、大学などに進学しても必須になるスキルです。また、社会人になっても、あらゆる場面で必要になる能力であるともいえます。仕事においても人生においても、誰かが正解を知っているわけではありません。「こうした方が良いんじゃないか?」という仮説を立ててみて、それを時間と予算の許す範囲で実行・検証して、より良くしていくしかないのです。受験勉強などで知識を獲得しておくことももちろん大切です。しかし、大学進学以降の人生で困らないように、SSHなどの取り組みを通して能動的に知的創造をしていくことも非常に重要なことではないでしょうか。
知識を得て、そこから問題を設定し、仮説検証していく。この一連のサイクルを高校生のうちに身につけられるというのは、とても良いことだと思います。
まとめ
「理科離れ」をきっかけに構想され、今では200校以上が指定されるSSH。テクノロジーの進歩やグローバル化、大学入試の変化などによって、これまで以上に注目が高まっていくでしょう。実施当初は「エリートにだけ予算を配分する制度だ」という批判もあったSSHですが、最近では、実践結果が教育全体に与える影響も大きくなってきています。これからの展開に期待が高まっています。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
DXハイスクールの内容と申請要件とは?未来のデジタル人材を育成!
あらゆる産業分野でデジタルやAI技術が進化し、わが国でも世界で活躍できる人材を育成するためには、早期のデジタル教育が欠かせません。全国の大学で理系・文理融合の学部が次々と設置される動き...
2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部
-
ICT化で学校教育現場はどう変わる?メリット・効果・海外の事例まとめ
2020年、ついにプログラミング教育が小学校で必修化します。それに伴い、学校教育現場のICT環境整備も進められています。海外と比較して遅れていた日本のICT環境。整備が進むとどのような...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
日本の教育水準はどうなっている?PISA・TIMSS・PIRLSなど
現代社会においてITに対する知識、英語力などが海外より遅れていると言われている日本。 少し前にはゆとり教育や学力低下という話も問題になり、近年では教育格差という言葉もよく耳にするよう...
2026.01.02|コエテコ byGMO 編集部
-
1億人以上の人口の国では強い!日本の教育の強い点は?
日本の学力は一般的には高いといわれていますが、実際のどうなのでしょうか? 日本だけでなく、他の国がどのような教育を行っているのかも気になるところですね。すべての分野で1位を獲得してい...
2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部
-
海外のプログラミング教育はどうなっている?徹底紹介(11選まとめ)
小学校でプログラミング学習が必修化されます。そこで気になるのが一足早くプログラミング教育をはじめている海外の動向。世界の先進国や急速に発展している途上国では、どのような教育が行われてい...
2025.04.18|コエテコ byGMO 編集部