「技術は善にも悪にもなります」。プログラミングキッズの育む「思考」
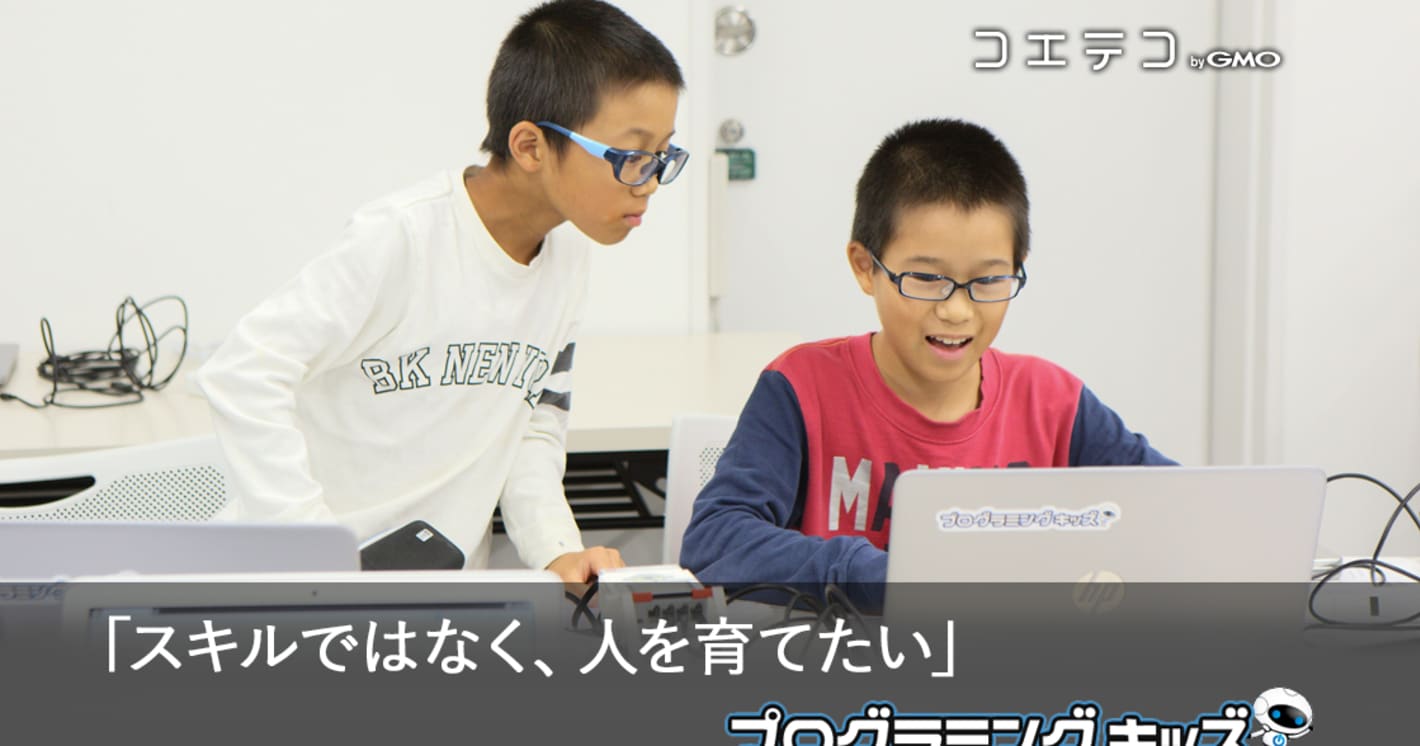
「スキルではなく、人を育てたい」。今回はそんなプログラミングキッズの授業を取材しました。

授業の流れ
「みんなも将来、発明しようね」近未来映像で子どもの知的好奇心は頂点へ
プログラミングキッズで授業をするのは、現役のシステムエンジニア・プログラマです。さっそく、3つの約束の確認から始まります。
①大きな声であいさつしよう
②手をきれいにしよう
③お互いに教え合い支え合おう
 現役のシステムエンジニア・プログラマの方が講師をつとめる
現役のシステムエンジニア・プログラマの方が講師をつとめる
約束の趣旨は「スキルを学ぶだけが目的ではないので」とのこと。とくに2つ目の「手をきれいにしよう」は、衛生面だけでなく「みんなで使うものをきれいにしよう」というしつけを表しているそうです。
約束の確認が終わると、本日のテーマが発表されました。今回のテーマは「未来の駐車場」。ロボットが自動で車を運び、整理して駐車してくれるという近未来の技術です。
「駐車って、けっこう大変なんだよね。空きスペースを探すのも大変だしね。未来の駐車場では、それをロボットが自動でやってくれるんです」
導入が終わると、映像がスクリーンに映し出されます。ロボットの動きに子ども達は興味津々。将来、イメージしやすい技術だからこそ、知的好奇心がくすぐられます。
「ロボットが代わりに駐車してくれたら、すごく助かるね。ところでみんなは、ロボットはどうやって自動で車を整理していたと思う?」
先生の問いかけに、さっそく手が挙がります。
 プログラミングキッズの教育方針のひとつは「イノベーション教育」。将来、プログラミングなどを活用して世の中にイノベーションを起こせる人材づくりを目指しており、ITリテラシーだけでなく、創造力・発想力を育む授業を行っている。
プログラミングキッズの教育方針のひとつは「イノベーション教育」。将来、プログラミングなどを活用して世の中にイノベーションを起こせる人材づくりを目指しており、ITリテラシーだけでなく、創造力・発想力を育む授業を行っている。
「カメラで車輌の大きさを測ってる!」
「車種を調べてる」
「センサーで大きさを区別して、情報共有して、人工知能がどこに停めるか決めている?」
発言の高度さもさることながら、手の挙がる勢いに驚きます。ちなみに正解は「センサーで大きさを判別している」。「みんなも将来、発明をしようね」と促し、授業内容に入っていきます。

「シール1枚」でも子どもは休まなくなる
発言の活発さには「教え方」の試行錯誤がありました。
プログラミングキッズでは、授業中に手を挙げたり、課題をクリアしたりするとポイントがもらえるのです。20ポイントを超えるとシールがもらえるので、がんばりが可視化されます。
「ちょっとしたシールがあるだけでも、子どもはやりがいを感じるんです。授業も休まなくなるんですよ」とのこと。細かな工夫は授業の随所にみられました。

2時間みっちり集中できるコンテンツ
授業は120分で、前半はScratchを使ったゲームプログラミング、後半はレゴ®︎マインドストーム®︎EV3でロボットプログラミングです。前半と後半で大きく内容が変わる上、どちらも濃密な課題ですが、子ども達は驚くほど集中して取り組んでいます。


ここでも光るのが的確な指導。ロボットがうまく進まない子に対し、初めはヒントを与える程度の声かけ。失敗が重なると、より具体的なアドバイスをされます。
「速度をちょっと変えてみようか」
「もう少し遅くしてみたら?」
「今、(速さの値が)100くらいだよね。20とか、30でもいいんじゃないかな」
初めから答えを出してしまうと、子どもの学びを奪ってしまいます。かといって、いつまでもうまくいかないとやる気を失ってしまいます。絶妙なさじ加減のインストラクションです。


最後はがんばりを発表して終了
最後は「頑張ったこと」「面白かったこと」「よくできたこと」から一つ選んで発表です。

「発表するときには、姿勢が重要です。ワークシートを下げて、発表する人の方を見て話しましょう」
「今日頑張ったことは、キーを使って動かせるようにしたことです」
「間違っていたプログラムを、最後に直せました」
「『コピー』を使ってプログラムできました」
取材が入っていることもあり、子ども達は少し緊張していた様子。それでもしっかりと顔を上げ、それぞれの感想を発表してくれました。

代表者インタビュー

「いい社会人」というゴールから逆算

—さっそくですが、プログラミングキッズをスタートされたきっかけ・思いについてお伺いできますか。
弊社(株式会社ナンバーワンソリューションズ)は2002年から事業をスタートさせまして、ブロックチェーン技術を使ったシステム開発などを行っています。
未経験のエンジニアを教育する機会も多かったので、この教育ノウハウを子ども達へも展開していけるのではないかと考え、2016年から準備を始め、2017年に「プログラミングキッズ」をオープンさせました。
子ども達への教育を始めたのは、蓄積してきたノウハウだけでなく、社会へ貢献したい、教育を変えていきたいという思いがあったためです。

これまで大人相手の教育を行ってきて、どういう人材が「いい社会人」なのかというビジョンはすでにありました。
①自分で調べる・探ることができる。
②技術のしくみ・基本がわかる。
③現状を当たり前と思わず、興味・関心を持ち続ける。
こうした力がついていると、現時点では必要なスキルを持っていなくても、あとからどんどん伸びてくるんです。じゃあ、その準備を子どもの頃からさせてあげたいし、弊社ならいい教育ができるんじゃないか。そう思い「プログラミングキッズ」をスタートしたわけです。
 教室内では「教え合い、支え合う」のがルールの一つ
教室内では「教え合い、支え合う」のがルールの一つ
—教室のパソコンを見ると、種類がいろいろありますね。Windows機だけでなくMacもありますが、どういう工夫でしょうか?
考える力を育てる上で、特定の環境に依存して「これしか使えない」状況になるのはよくないと思うんですね。今は主流でも十年後はどうなるか分かりませんので、さまざまな環境に触れてもらおうと。
—やはりここでも、環境に依存しない、基礎的な力を育むことに重点を置かれているのですね。
ええ。本校の授業目的は、プログラミングの「スキル」を学ぶことではなく、プログラミング的「思考」を学ぶことです。
ロボット(レゴ®︎マインドストーム®︎EV3)を使うのは、視覚的に分かりやすいためです。ロボット自体が目的ではないので、組み立ては一切行いません。あくまで、考える力の育成に重きを置いています。

—プログラミング教育に関しては、IT感度の高い方こそ「家でもできるのでは?」と感じられるように思います。オンライン受講なども増えてきた中で、教室へ来て学ぶことの良さとは何でしょうか。
ひとことで言うと「学ぶ雰囲気づくり」かなと思います。
もちろん、親御さんが教えられるのであれば、それがベストだとは思います。ただ、他の教科でも同じだと思うんですが、ご家庭だとなかなか学ぶペースが作りづらい。
相手がパパ・ママだと思うと甘えてしまいますしね。教室に来ていただくことで、スムーズに学ぶ雰囲気に入っていきやすいんじゃないでしょうか。
 授業中の様子を講師が撮影し、保護者に送信。取り組んでいる姿を見ることができるので、家庭内でのコミュニケーションが生まれる
授業中の様子を講師が撮影し、保護者に送信。取り組んでいる姿を見ることができるので、家庭内でのコミュニケーションが生まれる
大人しい子の「ニヤリ」を見逃さない
—実際の映像を見せるのが素敵だなと感じました。あいまいな「未来」の形ではなく、本当にある技術なのが良いなと。大人の私もワクワクしました。
コンテンツを作る際には、子ども達と接点があるものを選ぶようにしています。未来の形を具体的に見せることで「大人になったら発明しよう!」と考えてもらいやすいかなと。
—授業中、生徒が獲得したポイントをホワイトボードに書き出すなど、子ども達の頑張りを細かく見られているのだなと感じました。指導で気をつけていらっしゃることはありますか?
子どもの「目」をよく見るようにしています。大人しい子でも、何かに気付いたときには「ニヤッ」と笑うんです。その目をとにかく大切にしてあげたい。
気付きのポイントを奪ってはいけないと考えているので、こちらの押し付けにならないように注意しています。たとえば「横からマウスを奪って正解を教える」なんて絶対にNGです。

それから、考えのプロセスをリスペクトし、認めてあげることですね。
プログラミングは○か×かではないんです。たった一つの正解通りに作るのがゴールではありません。仮に失敗したとしても「この方法では出来ないんだな」と気付けるのが進歩ですよね。そこを認めてあげないと、手を挙げたくなくなるんです。
科学技術は二面的なもの。善にも悪にもなるからこそ、まず触れてみる
—子どもの主体性を最大限に生かす方針なのですね。でもそうなると、指導する側にも力量が求められるように思います。授業中、トラブルなどは起こらないのですか?
はい。ときには進行がうまくいかないときもあります。
たとえば、基本的にロボットとパソコンはケーブルでつないで動かすのですが、Bluetooth(無線)で動かしたとき、他の子のロボットにつなげて勝手に操作した子がいました。
—ええっ!それは、いわば遠隔操作事件ですね……。そのときは、どのように声かけをしたんですか?
まず、「勝手に操作した子」ではなく「勝手に操作された子」に声をかけました。
「した子」を優先してしまうと「悪いことをすると注目される、かまってもらえる」と考えます。だから、先にフォローすべきは「された子」なんです。
ロボットを勝手に動かされたことに対して「どう感じた?」と声をかけ、その子の気持ちを伝える。行為を反射的にとがめるのではなく「誰かが傷つくことをしてはいけないよ」と伝えるんです。
—なるほど。何かトラブルがあったとき、どうしても大人は反射的に取り上げてしまいがちですが、そうはしないと。
ええ。というのも、科学技術はそういうものだと思うんです。
同じ技術でも、人のためになることもできれば、人を傷つけることもできる。「危ないから触ってはいけません」ではなく、実際に触れながら「どういう使い方をすると危ないのか」を学ぶほうが大切なんです。
今回は友達を傷つけてしまったけれども、行為自体は、その子なりに「もしかしたら他のロボットも操作できるのでは?」と考えた結果なんですね。だから、反射的に禁じるのではなくて善悪の判断をさせる。それが、科学技術と付き合っていくために重要なんです。
—ありがとうございました!


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
(取材)子ども向けプログラミングスクール「Crefus」実際の授業風景を潜入取材!
Crefus(クレファス)は実績があり、人気の高いロボットプログラミングスクールです。基本からスタートしてハイレベルなスキルと理数系知識を積み上げ、課題解決力を伸ばします。今回はコエテ...
2025.05.30|大橋礼
-
「特別研究員、増員中!」キヤノンITソリューションズのプログラミング教室
キヤノンITソリューションズは、ITを通じてさまざまな課題を解決する企業です。そんな同社が子ども向けのプログラミング教室を開講しているのはご存知でしょうか?社会貢献を目的とした同社の取...
2024.11.06|夏野かおる
-
(取材)塾・予備校向けEdTechサービス「チエテラス」サポート万全のオンライン教材で『情報Ⅰ』の定期テスト・共通...
「情報I」に特化した塾・予備校・スクール向けカリキュラムのEdTechサービス『チエテラス』が2023年3月にリリースされました。予備校や塾への手厚いサポートもあり、導入も簡単なことか...
2025.09.10|大橋礼
-
プログラミング教育HALLO「オンライン校」自宅でPlaygramが学べるオンラインレッスンの様子を紹介します!
初心者からハイレベルへ、無理なくステップアップできるカリキュラムが人気のプログラミング教育 HALLO。ビジュアルプログラミングからPython(プログラミング言語)でのテキストコーデ...
2025.05.30|大橋礼
-
先生に「正解」を求めない子どもに。ステモンのSTEM教育レポート!
「主体的・対話的で深い学び」と表現される新しい学び。自ら興味を持ち、得た知識を活用することが求められます。子ども達の自発性・創造性に重きを置いたカリキュラムを展開するSTEM教育スクー...
2024.11.06|夏野かおる







