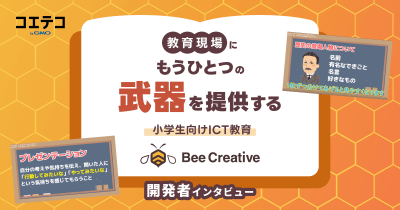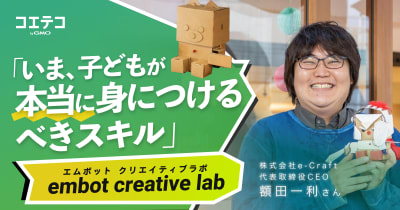(インタビュー)FULMA Academy(YouTuber Academy)の教育とは?|FULMA株式会社 中條武さん

今回インタビューする「FULMA Academy(旧称:YouTuber Academy)」は、そんなYouTuber体験を通した小学生向け教育プログラム。
キャッチーな名称が話題になりがちな同スクールのカリキュラムとは、一体どのようなものなのでしょうか。
見えてきたのは、驚くほどしっかりとしたICTリテラシー教育と安全意識、子どもの自己肯定感を育みたい!という教育ポリシーでした。

かなり踏み込んだICTリテラシー教育に力を入れている
動画は原則、限定公開
—さっそくネガティブな質問になり申し訳ないのですが、「YouTuberAcademy(現FULMA Academy)」と聞くと「YouTubeが永遠にあるわけじゃないしな……」と感じてしまいます。実際のところFULMA Academyで学ぶねらいは何なのでしょうか。
おっしゃる通りで、「YouTubeというプラットフォームに依存しているのでは」という批判をいただくことがあります。キャッチーな名前なので、誤解を生みやすいですよね(笑)。
「FULMA Academy」の本質は、言ってしまえば動画制作の習い事です。
たとえば、子どもの頃にサッカーを習っていた方はそれなりに多いと思うのですが、みんながみんなプロを目指したかというとそうではないですよね。

FULMA Academyもそれと同じで、なにも全員でHIKAKINさんを目指すというわけじゃないんです。
5G* の時代が来ればテキストと同じくらい動画での表現力が大事になってくるのではないかと考えていて。新しい時代に即した表現力や技術を育てるために、YouTubeというツールを使うイメージです。
ですから、動画は原則として限定公開* ですし、コメントも承認制にしていて、講師が確認したものしか反映されないようにしています。
カリキュラムの4つの柱
—限定公開と聞いて安心しました。「YouTuberになって稼ぐ」のがねらいではなかったんですね。では改めて、カリキュラムの概要を教えていただけますでしょうか。FULMA Academyのカリキュラムには4つの柱があります。
① 撮影・編集の技術
動画の編集は、最初から最後まで子ども達の手で行ってもらいます。たとえば、大人の目から見ると「ちょっとBGMが大きすぎて、声が聞こえにくいんじゃないかな?」といった場合もあるんですが、子ども達にも色々なこだわりがあるので、勝手に手を加えることはしません。
また、子どもに動画を撮影してもらうと、どうしても「バカ」とか、ネガティブな発言が飛び出すこともあります。
そうしたケースでも講師が勝手に編集することはなく、子ども達としっかり話し合った上で、自分の手で再編集してもらうようにしています。

② ICTリテラシー教育
とくに力を入れているのがICTリテラシー教育です。「個人情報を書き込んではいけない」といった内容だけでなく「ネット依存症」など少し踏み込んだ内容についても教えています。授業ではアニメーションを使ったり、クイズ大会をしたりして噛み砕いて説明しています。「YouTubeに投稿する」というゴールがあるので、普通に講義を聞くよりも積極的に勉強してくれるんです。
我々のカリキュラムのうち、ICTリテラシー教育の講座だけを小学校で実施させていただく(出前授業をする)こともあります。

文京区立青柳小学校での出前授業

実際のカリキュラム一覧。フェイクニュースについて教えるなど、一歩進んだリテラシー教育を提供している
③ 企画力
3ヶ月ごとにテーマを1つ決め、それに沿った動画を制作してもらいます。どうやったら面白くなるか工夫してもらう過程で、企画力が鍛えられます。FULMA Academyは12人で1クラスなので、1つのテーマにつき12本の動画が完成するわけですが、それぞれ切り口が違っていて、個性が現れて面白いですね。
たとえば、一番最近のテーマは「スライム」だったのですが、色をつけたり、ビーズを混ぜて触感を変えたり、中にはスライムを使って人形劇のようなことをしてくれた子もいました。
「桃太郎」の話だったのですが、見応えがあって面白かったですよ。
④伝える力
動画というのは誰かに向かって話すツールですので、練習する過程でプレゼンテーションスキルが向上していきます。加えて、FULMA Academyでは作った動画を自分で見返すことになるので「この表現は分かりにくかったな」とか、「このしゃべり方は改善した方がいいかも」といったことに気付けます。
これはまだ計画段階なのですが、実は企業の研修としてFULMA Academyのワークショップを活用したいというお話もいただいています。動画を撮影し、客観的に編集することで「一番伝えたい商品の魅力はどこなのか?」「どうすれば伝わるのか?」を考えられるためです。
「楽しい」だけではダメ
—カリキュラムの内容を聞いてずいぶんイメージが変わってきました。とくにICTリテラシー教育の充実感はすごいですね。FULMA Academyがスタートしたのは2017年の3月で、ちょうど2年が経ちました。最初の1年は単発のワークショップという形で開講していて、スクールを始めたのは2018年の4月からです。
今でこそICTリテラシー教育に力を入れていますが、当時はそこまで思いが至らず、単純に「楽しい体験」をしてもらえるカリキュラムを提供していました。テキストも、編集技術に関する内容だけだったんです。
たとえば、金魚すくいのポイ(紙でできた網)に撥水スプレーを振りかけて「無限にスーパーボールがすくえる!」という動画を制作してもらったり。

—うわあ、楽しそう(笑)。私もやりたいです。
子どもの人数分、水を入れたボウルを用意したのですが、子ども向けのワークショップで水を使ってはいけないと学びましたね(笑)。こぼすわ、濡らすわで服がビショビショになってしまって、親御さんに「ごめんなさい!」とお詫びしっぱなしでした。
—眼に浮かぶようです(笑)。そこから現在のような(ICTリテラシー教育に力を入れた)カリキュラムにされたのは、どういったきっかけがあるんでしょうか。
先ほども言ったとおり、ワークショップは3月からスタートしたのですが、5月ごろにぐっと参加人数が減ってしまったんですよ。
というのも、「楽しい」だけで終わってしまうワークショップでは親御さんの理解を得られなかったんです。単なる遊びでしかないと、繰り返しの参加にはつながらない。初めこそ、キャンセル待ちが出るほど集客に成功していたのですが、リピーターの獲得に失敗したんですね。
それで、教育としての価値をしっかりつけていこうと考えまして、ICTリテラシー教育を重視する今のカリキュラムになりました。

FULMA株式会社 COO 中條 武(ちゅうじょう・たけし)さん。
柔和なお人柄が印象に残った
避けては通れない「安全」の話
—本当に遠慮なく聞いちゃいますけど、中にはわいせつな目的でキッズ動画を見る方もいらっしゃるわけじゃないですか。そうした面については、どこまで踏み込んで教えていらっしゃるんでしょうか。はい、そこはもう、親御さんが心配されるところではありますよね。
もちろん教室でも「アップロードするというのは、知らない人がいっぱい見るってことなんだよ」と伝えてはいますが、そこまで踏み込んだ注意喚起ができているか?と言われると……具体的なお話はできていないのが正直なところです。
ただ、YouTube自体が健全なプラットフォームになるための施策を講じていて、まさに最近、子どもが登場する動画へのコメント機能が無効化されるという発表がありました。
これまでも13歳以上しかアカウントを持つことはできなかったのですが、今後もこうした施策は広がっていくと考えています。

今や、キッズYouTuberも少なくない
もちろんFULMA Academyでも安全対策はしていて、冒頭でも述べたとおり、動画は原則としてスクールと親御さんの限定公開にしています。
とはいえ、親御さんが無防備にSNSにアップロードしてしまったり、共有してしまうと意味がないので、親御さんに対しても丁寧にご説明をしています。
—動画サイトといえば、Tik Tokなんかはどうなんでしょう。

YouTuberのHIKAKINもTik Tokアカウントを開設した
Tik Tokは動画が上げやすく、かつ見やすいので、子ども達からの人気は相当なものです。
とはいえ、初期のYouTubeと同じく安全対策が追いついていない面があり、「出会いの場」になってしまっているのも事実です。
—「出会いの場」!?Tik Tokはちょっと触った経験しかないんですけど、あそこでどうやって「出会う」んでしょうか……
たとえば、プロフィールの画像がLINEのQRコード* になっていたりとかですね……。
何度もお伝えしているとおり、FULMA AcademyではICTリテラシー教育に力を入れていますので、もしかすると今後、Tik Tokにも教育的アプローチをしていくかもしれませんね。
FULMA Academyの真意
—今回、しっかりとお話を聞いたことで、いろいろな誤解が解けたと思います。最後に、改めてFULMA Academyの目指すところを教えていただけますか。たとえば子どもが「サッカー選手になりたい」と言ったら、ボールを買ってあげる、サッカーを習わせてあげる、という方法で応援することができますよね。でも、子ども達が今すごく興味のある「YouTuber」という夢に関しては、応援の仕方が分からないと思うんです。
「どうせHIKAKINにはなれないよ」とか、「ネットは怖いからやめておきなさい」という反応になってしまうだろうなと。

でも、それって子どもの内発的動機をつぶしちゃうと思うんですね。
小さいときに「やりたい」と思ったことを応援されたか、止められたかっていうのは、その後の人生に影響すると考えていて。
やりたいことを応援してもらえた、自分の手でできた、という体験は自己肯定感、自己効力感につながります。こういった自信は、大人になっても大切なことだと思うんです。
正直なところ、FULMA Academyでの学びはテストの点数に直結しないかもしれません。算数の点数が上がるとか、国語の能力が伸びるとは言い切れません。
でも、たとえYouTuberに興味がなくなっても、得られた自己肯定感は次のチャレンジに活かすことができます。
FULMA Academyの理念は「子どもたちのやりたいをカタチに」です。我々の取り組みが習い事の新定番になればいいなと考えています。
—ありがとうございました。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
Bee Creative 開発者インタビュー|教育現場に"もうひとつの武器"を提供する小学生向けICT教材とは
小学生向けICT教材「Bee Creative」は、教育現場に+αとして導入できる教材で、非認知能力の向上を目的としています。今回は、Bee Creative 開発のきっかけや込められ...
2025.09.09|鳥井美奈
-
プログラミング“だけ”じゃない!ICTスクールNELオンラインの一歩すすんだレッスン内容とは?
デジタル庁の創設やハンコ廃止など、社会全体がデジタル化に向けて大きなうねりを見せています。 そんな時代にあっては、小学生からICTリテラシーを身に付けておくことが新たな常識になるかも...
2025.09.10|大橋礼
-
2人に1人以上が利用中、子どもと「LINE」どう付き合う?(インタビュー)
気軽にやり取りできる一方で、トラブルのきっかけにもなるSNS。子どもがうまく付き合うには?今回はLINE株式会社を取材し、実際のトラブル事例も交えながら同社の取り組むデジタルリテラシー...
2025.06.24|夏野かおる
-
(取材)embot creative lab|CEO額田さんに聞く、子どもに本当に身につけてほしいスキル
今回、コエテコではembotの生みの親である株式会社e-Craft代表 額田一利(ぬかだ・かずとし)さんにインタビュー。NTTドコモからの独立についてや、自身の体験から生まれたというe...
2024.11.06|夏野かおる
-
北千住 キッズ向けプログラミング教室「プログラミー」- 講師は社内のエンジニアが中心!
東京の下町「北千住」 で小学生向けプログラミング教室「プログラミー」が開校します。プログラミーの2018年3月の開校に向けた無料体験会にはなんと1ヶ月間でおよそ200人以上の予約が入っ...
2024.11.06|コエテコ byGMO 編集部