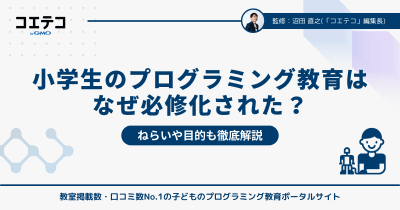ICT教育とは?ITやIoTとの違いと学校での活用事例を徹底解説
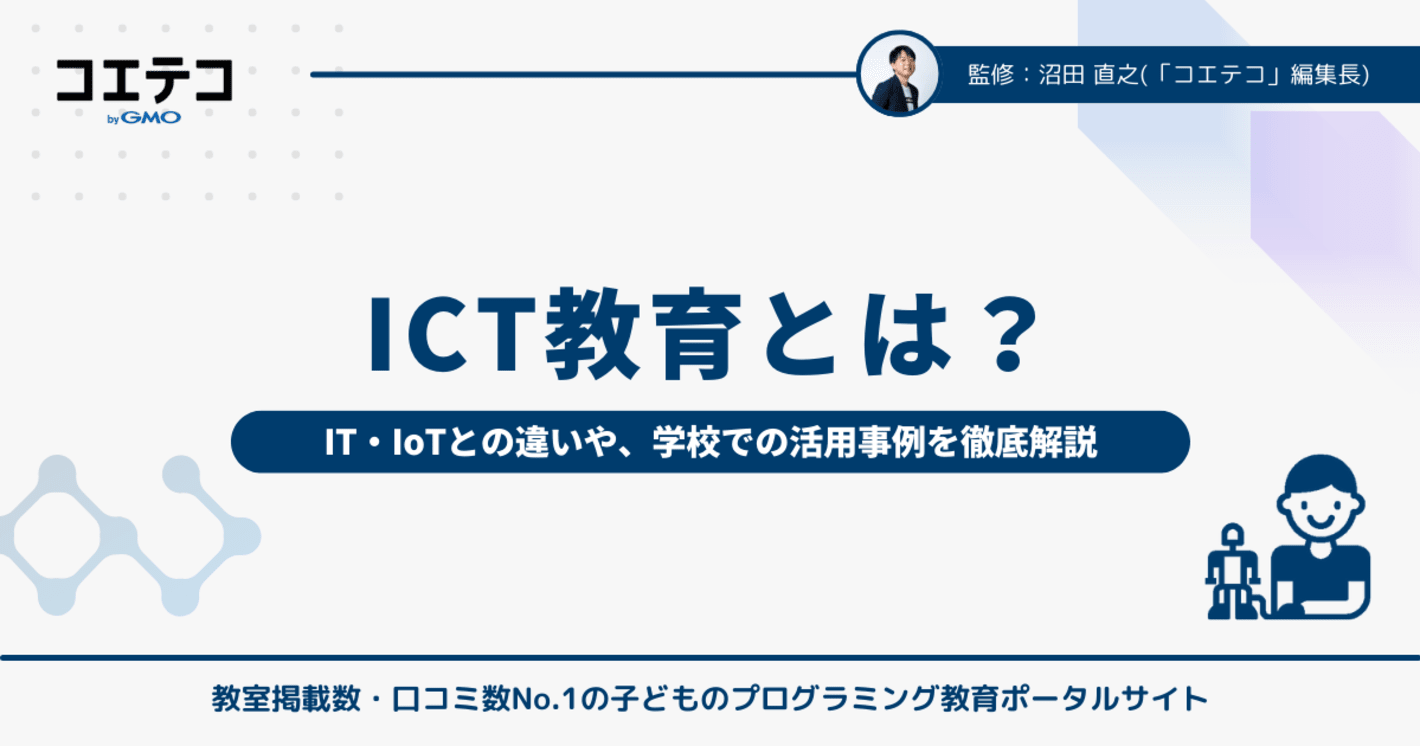
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
ICTとは何か、IT・IoTとはどう違うのかを明確にしながら、教育現場での実践例を交えてわかりやすく解説します。
ICT教育が進んでいる自治体の取り組みも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
ICTとは?ICT教育(教材)とは?
「ICT教育(教材)」とは、コンピューターやインターネットなどを活用した教育(教材)を指します。「ICT」は、コンピューターやインターネット、モバイル通信などを活用して情報を収集・加工・伝達する技術や仕組みのことを指し、ICTのツールや仕組みを授業や学習活動に取り入れることで、教育の質を向上させ、学習の効率化や生徒の主体的な学びを促進する取り組みです。学びの幅を広げることや、生徒の主体性をも引き出す効果も期待できます。
ICTとITとの違い
ITが情報技術を意味するのに対し、ICTは情報通信技術を意味します。ITよりも、ICTの方が広い範囲の技術を指しているのが大きな違いです。また、ITはコンピューターやソフトウェア、ネットワークの技術が中心ですが、ICTは情報技術と通信技術を融合させて情報を効率的にやり取りし、活用することを目的としています。つまり、ITは情報の処理や保存に重点を置いた「技術そのもの」を指すのに比べ、ICTは情報と通信技術を統合し、「人や組織をつなげること」に焦点を当てた広範な概念だといえるでしょう。
ICTとIoTの違い
IoTとは、「モノのインターネット」のことです。インターネットに接続された物理的な「モノ」がデータを生成、送受信し、互いに連携して動作する仕組みを指します。「モノ同士」をつなぎ、自動化やデータ活用を進めることがIoTの目的なので、情報を「人や組織間」で効率的にやり取りして活用するICTとは定義が異なるのです。ICTの対象が人や組織、社会なのに対し、IoTno対象はモノ(家電や車両、機械など)。範囲も、ICTは人間が使用する通信技術全般に使われますが、IoTはインターネットで接続されたデバイス間の通信のみで、全く異なります。
ICT教育が推進されている背景
ICT教育が推進されている背景には、社会や教育現場の変化、そして未来を見据えた学びの必要性が高まっていることが挙げられます。現代は、インターネットやAI(人工知能)などの技術が社会の基盤になりつつあり、日常生活や仕事の多くの場面でICTの知識やスキルが求められる時代です。この流れに対応するため、教育現場でもICTを活用し、生徒が将来必要とするスキルを育む姿勢が求められています。また、生徒の興味や学力、学習ペースに合わせた「個別最適化学習」が重要視されているのも、ICT教育が推進されている理由の一つです。ICTを活用すれば、学習データを活用した個別指導や、タブレットやデジタル教材を使った自主学習も容易に行えます。ICT教育を導入することは、生徒だけでなく教師にとっても大きなメリットです。授業の準備や業務を効率化でき、仕事を効率よくこなせるようになります。
日本では、文部科学省が2019年に打ち出した「GIGAスクール構想」により、小中学校で1人1台の端末と高速通信環境が整備されました。この構想がICT教育の加速を後押ししています。
NEXTGIGAでICT教育はどう変わる?
「NEXTGIGA」とは、文部科学省が推進するGIGAスクール構想の第2フェーズを指す言葉です。GIGA2.0やセカンドGIGAとも呼ばれており、GIGAスクール構想をさらに発展させ、ICT環境の更新や進化を図ることを目指しています。具体的には、1人1台端末のさらなる利活用や、通信ネットワーク環境の見直し、端末の計画的な更新などの取り組みが実施される予定です。まだ整備や設備が不十分な学校への拡充や、適切な利用方法の確立も含まれています。NEXTGIGAにより、ICT教育がさらに進み、個別最適化された学びの実現や教育の多様性と選択肢の拡大が予想されるでしょう。
学校でのICT活用の例
学校では、以下のような場面でICTが活用されています。- 授業
- 出欠管理や連絡システム
- 自主学習や家庭学習
- 教員の業務短縮・効率化
授業
学校の授業では、以下のようなICT活用が主です。- プロジェクタの使用
- 電子黒板やタブレット
- 調べ学習でのインターネットの活用
- 動画コンテンツやアニメーションコンテンツの活用
- 学習ドリルなどのデジタル教材の活用
- オンライン教材の活用
授業でICTを活用することにより、学習をより効果的にしたり、子どもたちの関心を集めたりする効果が期待できます。
出欠管理や連絡システム
出欠管理システムとは、欠席や早退などの連絡をスマートフォンアプリやWebブラウザ上で行えるシステムのことです。出欠連絡をする側と受け取る側の手間を最小限にすることができ、手作業で1人ずつ確認する必要がありません。連絡システムがあれば、保護者に連絡したい内容を一斉に知らせることができて便利です。紙ではなくデジタルなので、一括管理も簡単に行えます。
自主学習や家庭学習
学校の授業内容に対応したアプリをタブレット端末にインストールすれば、自主学習や家庭学習でも利用できます。自宅でも適した学習ができるようになることで、より理解を深めやすくなるでしょう。学校を休んだ場合でも、学校と繋がっているタブレットがあれば、リモートで授業を受けることが可能です。教員の業務短縮・効率化
学校でICTを活用することは、教員の業務短縮や効率化にもつながります。例えば、以下のような場面で活用されています。
- 成績や出席の管理
- 授業で使う教材の資料などの収集
- 教員間の指導計画や指導案の共有
- 学校ウェブサイトやメールでの家庭や地域との情報共有
- 図書や保健の管理
- デジタル教材の活用
学校でのICT活用環境の実態
令和5年度の文部科学省の「令和5年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」では、全国の公立学校を対象にICT整備の状況を調査しています。普通教室の電子黒板の設置率は平成17年3月期には1.5%でしたが、令和6年3月には89.6%まで増加しており、驚異の増加率です。電子黒板を授業で活用することで、黒板上に映写したPCの画面を簡単に操作することや板書の内容を保存しておいて次回の授業での復習の場面で使うことなどができます。
また、教育用コンピューター1台あたりの児童生徒数も改善されています。平成17年3月には1人につき8.1台でしたが、令和6年3月期には1.1台となっており、ほぼ1人で1台を使っている状況です。
ICT活用の実態は、各自治体によって力の入れ具合が大きく異なります。上記した「普通教室の電子黒板の設置率(大型掲示板設置整備率)」と「児童生徒1人あたりの学習者用コンピュータ台数」に2項目に関して、1位と最下位の県は以下の通りです。県内でも、市町村により差が大きい場合もあります。
普通教室の電子黒板整備率(平均値:89.6%)
| 順位 | 都道府県 | % |
|---|---|---|
| 1位 | 愛媛県 | 98.2 |
| 最下位 | 岩手県 | 71.8 |
児童生徒1人あたりの学習者用コンピュータ台数(平均値:1.1台)
| 順位 | 都道府県 | 人/台 |
|---|---|---|
| 1位 | 宮城県、秋田県、高知県 | 1.2 |
| 最下位 | 埼玉県、千葉県、東京都、滋賀県、奈良県、島根県、徳島県、沖縄県 | 1.0 |
引用:文部科学省「令和5年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果
ICT教育が盛んな愛媛県での活用事例
ここでは、愛媛県のICT教育の実態や活用事例を紹介します。全国トップクラスの指導力
愛媛県のICT教育が盛んな背景には、教員の高い指導力があります。愛媛県は、令和5年度の文部科学省の調査において、「普通教室の電子黒板整備率」のみならず「教員のICT活用指導力」でも1位を獲得しました。「教員のICT活用指導力」は、以下の項目で評価されます。- 教育効果を上げるために、コンピュータやインターネットなどの利用場面を計画して活用する。
- 授業で使う教材や校務分掌に必要な資料などを集めたり、保護者・地域との連携に必要な情報を発信したりするためにインターネットなどを活用する。
- 授業に必要なプリントや提示資料、学級経営や校務分掌に必要な文書や資料などを作成するために、ワープロソフト、表計算ソフトやプレゼンテーションソフトなどを活用する。
- 学習状況を把握するために児童生徒の作品・レポート・ワークシートなどをコンピュータなどを活用して記録・整理し、評価に活用する。
全国の平均値が88.5%なのに対し、愛媛県は99.0%で、圧倒的な1位でした。教員の99.6%がICT活用に関する研修を受講していることからも、ICT教育に力を入れていることが分かります。
引用:文部科学省「令和5年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果
活用事例
愛媛県の小学校・中学校では、以下のように活用されています。- タブレットを用いた話し合い活動
- タブレットを用いたリーフレットづくり
- タブレットを用いたパネルディスカッション
- タブレットを用いた調べ学習
- アプリを活用したプログラミング学習
- タブレットを用いた振り返り活動の充実
- タブレットを用いた英文作成
- タブレットを用いたプレゼンテーション
- ウェブ会議システムを活用した交流学習
- タブレットを用いたリズムづくり など
引用:愛媛県教育委員会「愛媛県ICT推進ガイドライン:ICT活用事例集」
佐賀県でのICT活用事例
佐賀県では、活発にICTを学校教育の場で活用されています。実際の活用の事例の一部を紹介します。
ホームルームでの活用
朝のホームルームでは、児童生徒一人一人に与えられた学習用PCで出席の確認を行うことができます。また、1日の予定の確認や行事の確認、進路希望調査などのアンケートに回答する活用方法も可能です。帰りのホームルームでは、教員が翌日の連絡事項などを学習用PCに送信することができます。児童生徒側も教員に相談したい事項を送信可能です。
このように、紙面では他の児童生徒に知られたくないことを共有できたり、重要な連絡事項をいつでも確認できたりする共有方法が実現されます。
SEI-Net を使ったデジタル小テスト
佐賀県ではSEI-Netという学習システムを導入しています。教員用の学習管理システム、児童生徒用と教員の相互通信がベースとなる教材管理システムが用意されており、教員も児童生徒も活用することができます。
SEI-Netの活用例として、授業の中の小テストの場面を挙げます。

日々の授業で小テストを実施する場合、問題作成、印刷、採点、答案返却、成績入力…と大きなコストがかかります。
そのような場面でICTを用いると、教員側は印刷や採点、成績入力の作業を省くことができます。採点ミスの心配もなくなります。
また、児童生徒側は、間違えた問題をいつでも確認することができ、自分の弱点を把握することができます。プリントの管理が難しい子でも、すぐに確認できるので便利ですね。
学校に通うことができない事情がある児童生徒への復帰支援
ICTを活用することで、遠隔での授業が可能です。そのため、長期の入院や学校不適応などの理由で学校に通うことが難しい子どもたちに新しい学習の場を提供することができます。
授業内容の送信も容易ですし、デジタル教科書を活用すればPCがあれば教科書にアクセスできます。
このように、学校への復帰の支援としてICTが役立ちます。
ICT活用の課題
使いこなせば教育の現場にさまざまなメリットをもたらすICTですが、現状では県や市町村、学校ごとに差があり、十分に活用されていない学校があるのが事実です。1人1台端末が整備されたと言っても、教員に指導する力量がなければ効率的な活用はできません。そのため、今後は、教員の指導力が最大の課題として挙げられるでしょう。課題を解決するためには、教員の指導力アップのために研修を充実させることが重要です。必要に応じて、ICT支援員や大学講師など、外部から人材を呼んで専門的な研修を行うことが求められます。教員同士でICT活用に関するアイデアや知識を共有できる場やプラットフォームを設けるのも、指導力アップに効果的です。
また、教員間のITリテラシーの格差の問題もあります。日々多忙な教員の方にとって、従来の授業法のほうが便利に感じることもあるでしょう。また、これまでにICT機器を使い慣れていない教員だと、研修等での学習が大きな負担になる場合も。ICT教育に抵抗のある教員が多い学校の場合、ICT機器に詳しい教員への負担が増えるという課題も存在します。
まとめ
まだまだ課題がある学校でのICT活用ですが、教員の仕事が効率化されたり、子どもたちの学習の幅が広がる点は非常に魅力的です。NEXTGIGAにより、今後はICT教育はさらに進み、個別最適化された学びの実現や教育の多様性と選択肢の拡大が予想されます。

Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
世界の教育分野のICT利用率ランキング|日本の順位は?
2020年からプログラミング教育が必修化します。海外に比べて遅れを取っていると言われる日本のICT教育ですが、実際のところどうなのでしょうか? この記事ではOECDの調査結果を確認し...
2025.05.30|コエテコ byGMO 編集部
-
日本は遅れてる?海外のプログラミング教育の現状!
日本では小学校のプログラミング教育が2020年から必修化されることになっており、中学校では2012年から「技術・家庭科」で「プログラムによる計測・制御」が必修の授業として行われています...
2025.06.24|さえ
-
小学生のプログラミング教育はなぜ必修化された?ねらいや目的も解説
2020年から小学生でプログラミング教育が必修化されることになりました。プログラミング教育は本当に必要なのでしょうか?なぜ必修化されることになったのでしょうか?プログラミング教育の目的...
2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部
-
STEAMS(スティームス)教育とは?
プログラミング教育必修化がせまる中で『STEAMS(スティームス)』といった言葉を見かける機会が近年増えてきました。これまでには『STEM(ステム)』、『STEAM(スティーム)』など...
2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部
-
プログラミング能力検定とは?難易度や対策を徹底解説
2020年4月からの小学校でのプログラミング教育必修化で注目の「プログラミング」の能力をはかる試験として注目の「プログラミング能力検定」を徹底解説。 気になる試験内容・難易度・受験料...
2025.05.27|コエテコ byGMO 編集部