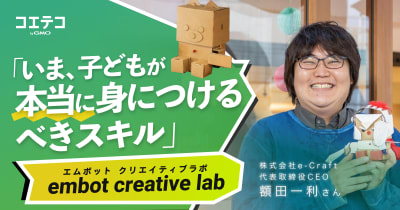みんなが「作る側」になれば世の中はもっと面白くなる ― 株式会社しくみデザイン 中村俊介

-
今回お話を伺った方
-
株式会社しくみデザインCEO(最高経営責任者)
中村俊介氏名古屋大学建築学科から九州芸術工科大学大学院へ進学、ユニバーサルデザイン研究の傍ら、メディアアートとインタラクション設計に強み。“シクミスト”の肩書きで2005年に株式会社しくみデザイン創業。科学館・商業施設展示や、世界的なメディアアート / 音楽ソフト「KAGURA」などを開発、2013年Intel主催コンテストで世界一受賞、芸術工学博士及び福岡市文化賞受賞、九州工業大学客員准教授、情報経営イノベーション専門職大学超客員教授歴任。『note』などで新時代の体験デザインやSTEAM教育を多数発信。“楽しい”を科学し続ける日本STEAM×表現領域の革新者。
-
その代表を務めるのは、芸術工学博士であり、平成30年度 福岡市文化賞を受賞されるなど実力派クリエイターで知られる中村俊介(なかむら・しゅんすけ)さんです。
そんな中村さんが力を入れるのが、デジタルネイティブ世代へのクリエイティブ教育。
最近ではビジュアルプログラミングアプリ「Springin'(スプリンギン)」を発表し、「絵日記感覚でプログラミングができる!」と評判です。
中村さんの描く未来の学びとは、一体どのような形なのでしょうか?
この後編ではいよいよ、中村さんが教育に情熱を注ぐ理由と大注目のアプリ「Springin'」について詳しく語っていただきます。

株式会社しくみデザイン CEO 中村俊介(なかむら・しゅんすけ)さん
しくみデザインのビジュアルプログラミングアプリ「Springin'はこちら(iOSのみ、無料)
App Store でSHIKUMI DESIGN, Inc.の「Springin'」をダウンロード。スクリーンショット、評価とレビュー、ユーザのヒント、その他「Springin'」みたいなゲームを見ることができます。

https://itunes.apple.com/jp/app/springin/id1184243692?mt=8 >
インタビュー前編へはこちら
言葉のいらない「しくみ」を作る ― 株式会社しくみデザイン 中村俊介
「将来のために」に覚える違和感
—しくみデザインさんは「クリエイティブ教育ラボ」など、子ども達への教育にも力を注がれていますね。現状のプログラミング教育に関して、中村さんが感じる課題はありますか。
手段と目的が逆なんじゃないかなあ、と感じています。
勉強って「将来役に立つから、今はつらくても頑張れ」という人が多いでしょう。でも本来は、やりたいことや作りたいものがあってこそ勉強するんだと思うんです。
僕は学生時代に「KAGURA」の原型となる作品を作りました。身体を動かすと音が出て、音楽を習った経験がなくても気持ちよく演奏できる楽器です。

中村さんが学生時代に手がけられた作品

現在の「KAGURA」
音楽理論なんてまったく知らなかったし、プログラミングも体系立てて学んだわけでなかった。
でも、作品を作るうちに「どうして不協和音が出るんだろう?」と音楽理論に触れ、「画像認識が必要だ!」とプログラミングを学んだんです。

「まずは音楽理論から勉強しろ」と言われていたら、きっと楽しくなかったでしょう。
こういう作品が作りたい、という目的が先にあったからこそ、そこに向けての勉強を自然としたんです。
現代になっても「作る」ハードルは高いまま
—「作りたいものがあって、勉強する。それが本来の学びでは?」は、新学習指導要領の考え方* にも合致していますね。作る楽しみについて、もっと詳しく伺えますか。
しくみデザインも15年目を迎え、参加型広告やアトラクションを多数手がけてきました。作る人(クリエイター)として経験を重ねる中で、「作るって楽しいな」と改めて感じているんです。
でも、大人になるとあまり作らなくなる人が多いですよね。ちっちゃい頃はみんな絵を描いたり、思い思いに作っていたはずなのに……
—大人になっても創作活動を続ける人は少ないですよね。
なんで作らなくなるのかな、と考えてみて「面白い反面、大変だから」という結論に行き着いたんです。
今は色々なサービスが充実していて、誰かが作ったものを簡単に利用できます。その一方、作る側に回るハードルは高くなっているんじゃないかと。

—プログラミングもそうですよね。すでにあるアプリを使うのは簡単だけど、作るのは大変そう……みたいな。
だけど、動画や写真に関してはInstagram(インスタグラム)やTik Tok(ティックトック)みたいに消費する人と作る人が混じり合う環境が出来上がっているでしょう。
テクノロジーが発達して、簡単に入り込めるツールがあるおかげです。だけど、プログラミングってまだまだハードルが高い。それって適したツールがないからでは?と思ったんですよ。

写真投稿型のSNS、Instagram(インスタグラム)。「フィルター」を選ぶだけでプロのような表現効果が得られ、手軽に画像加工を楽しめる
プログラミング教育のツールは色々ありますが、習熟するまでが大変だったり、紙でできることをデジタル化しただけだったり……などの物足りなさを感じていました。
紙の代替物ではなく、デジタルならではの表現をしたい。それでいてハードルはどんどん下げて、あらゆる人に作る楽しみを感じてほしい。
そうすれば、世の中がもっともっと楽しくなるはずです。僕やしくみデザインだけでは、生み出せる数に限界がありますから。
「Spring」の持つ3つの意味

—「Springin'」には「世の中を楽しくしたい」という中村さんの夢が詰まっているんですね。
iPadという気持ちのいいデバイスが出て、絵を描いたり、音を入れたり、自分の作りたいものをダイレクトに表現できる準備が整いました。
じゃあ次は、描いたものを動かしたいよねと。そんなシンプルな思いから「Springin’」は出発しました。
アプリを見ると分かるのですが、言葉による説明はまったくありません。子どもがあちこち触りながら自然と表現を生み出せるツールなんです。
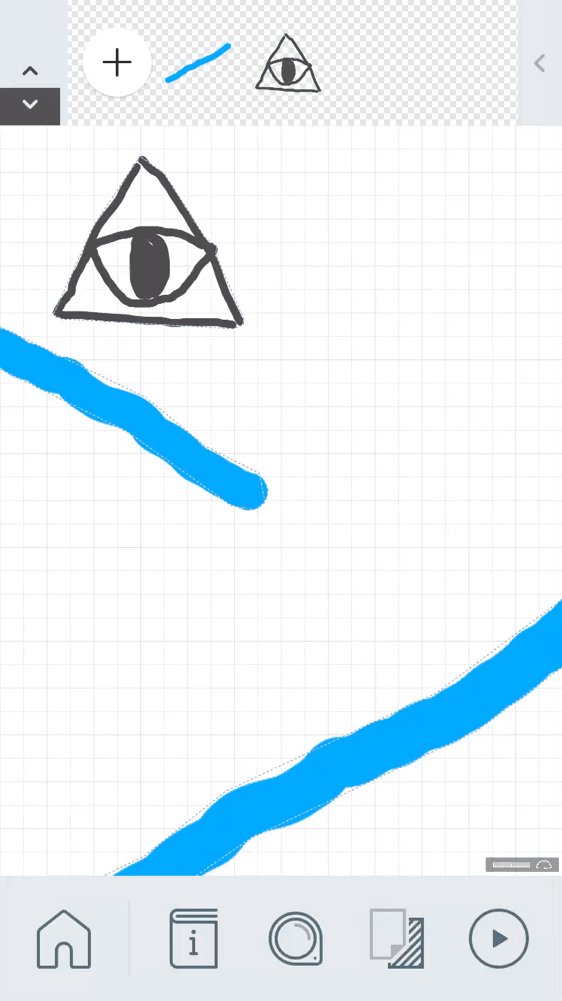
「Springin'」の画面。それぞれの機能はアイコンで表現され、説明書きは一切ない
—「Springin’」という名前にはどういった意味が込められているのでしょう。
「Spring」の持つ3つの意味が込められています。
ひとつは、アイディアが芽吹くイメージ。ふたつ目は、作ったものがぴょんぴょん動くことから、バネのイメージ。最後は、泉のように命が湧き出るイメージです。
それを現在進行形(-ing)にして、動きのある名前にしました。アイコンも、泉からしぶきが飛び出すデザインにしたんですよ。
—公式サイトには「Springin’」を絵日記代わりに利用している男の子の記事がありましたが、他に中村さんの心に残ったエピソードはありますか。
リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://www.shikumi.co.jp/springin-more-than-papers/ >
僕には娘がいて、今年の5月1日に水族館へ行ったんです。イルカショーを見たのですが、ちょうど「令和」初日だったので、ショーでも「令和」パネルが小道具として登場しました。
水族館から帰ったあと、娘が「今日のを作る!」と言ってSpringin’でこの作品を作ってくれたんです。
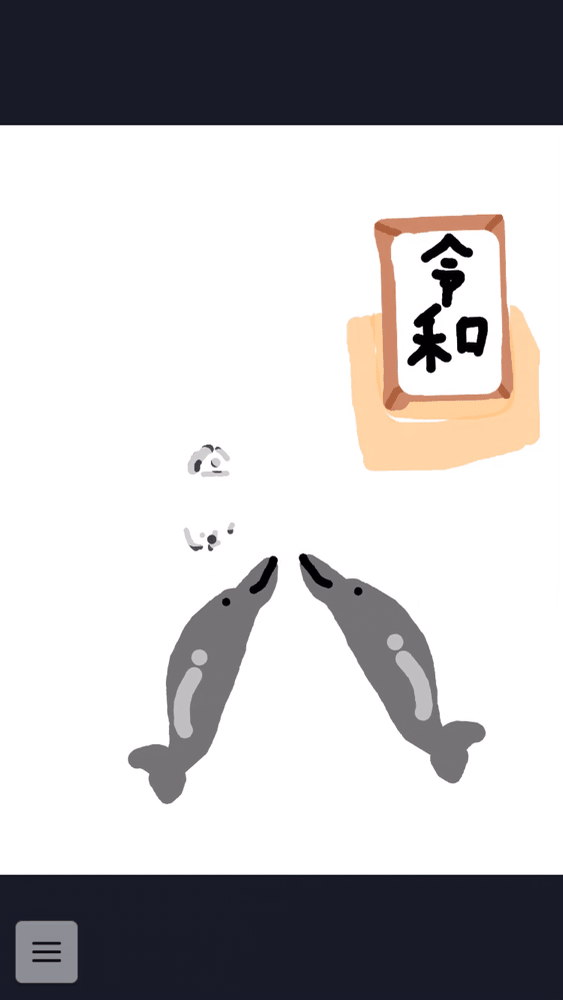
ゲーム内容を一部抜粋。おじゃまキャラクターを避け、2匹のイルカに「令和」パネルを渡す。これを絵日記感覚で作れるとは
娘の様子を見て、プログラミングは子どもの表現ツールとして成立しうる、と確かな手応えを感じました。
「プログラミングは大変」と身構える方も多いですが、ツールさえ整えれば動画撮影や写真加工のように日常化できると確信したんです。
プログラミングは怖いものじゃない
—来年度からプログラミング教育が必修化します。「なにか家庭でできることは?」と感じている保護者の方に、メッセージをお願いいたします。保護者の方を見ていると、プログラミング教育を「怖いもの」と捉える方が多いのかな……と感じます。
どうして怖いのかというと、自分が知らないから。自分では教えられないけど、子どもが授業に遅れないように何かしなくちゃ……そんな方が多いのではと。
僕の作った「Springin’」は、事前知識がまったくゼロでも「楽しい!」から始められるプログラミングアプリです。お子さんはもちろん、親御さんもハマるくらい楽しいツールにしましたので、ぜひ一緒に触れてみてください。
とりあえず触ってみれば、意外となんとかなります(笑)。プログラミングが「怖いもの」ではなく、「楽しいもの」になってくれたら嬉しいです。
先生がすべて知っている時代は終わった

—続けて、ICT教育・プログラミング教育に携わる先生、事業者の皆さんへのメッセージをお願いいたします。
多くの先生は「教えなきゃいけない」という固定観念に囚われているように思います。プログラミングの授業もそう。まずは先生自身が予習をして、すべてを知り尽くしてから教えなきゃいけない……と。
でも、これからの時代、先生が学習内容をすべて把握するのは難しくなります。プログラミングだけでなく、英語も教科として入ってくる。先生がすべてを知っておくスタイルは限界だと思うんです。
現職のエンジニアだってプログラミングを全て理解しているわけではありません。先生が気負いすぎると、子どもの表現を制限する指導にもつながります。
「Springin’」は「予習しなきゃ」という不安を吹き飛ばせるツールとして作りました。一緒に始めて、一緒に学んでいく。これからの学習スタイルのおともとして、授業に取り入れていただければ幸いです。
—ありがとうございました。
「Springin'」のダウンロードはこちら
しくみデザインのビジュアルプログラミングアプリ「Springin'」のダウンロードはこちらから。App Store でSHIKUMI DESIGN, Inc.の「Springin'」をダウンロード。スクリーンショット、評価とレビュー、ユーザのヒント、その他「Springin'」みたいなゲームを見ることができます。

https://itunes.apple.com/jp/app/id1184243692 >
分かりやすいアイコンで直感的に操作でき、他の作り手の作品を遊んだり、アレンジしたりすることができます。
自分の作品がダウンロードされるとアプリ内で使えるコインがもらえるため、「どんな作品が人気かな?」「作品の魅力をどうやって伝えよう?」と研究するモチベーションになるのが魅力。
無料で利用できるので、ぜひこの機会にプログラミングに触れてみてくださいね。中村さん、ありがとうございました!


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
言葉のいらない「しくみ」を作る ― 株式会社しくみデザイン 中村俊介
言葉を一切使わないビジュアルプログラミングアプリ「Springin'」を開発、運営する株式会社しくみデザイン。今回はCEOである中村俊介さんにインタビューし、中村さんとしくみデザインの...
2025.07.31|夏野かおる
-
「Springin'」教育カリキュラムが来年4月提供開始。「女子」獲得の強い味方に!
「絵日記感覚でプログラミングが学べる」と話題のビジュアルプログラミングアプリ「Springin’(スプリンギン)」を開発・運営する株式会社しくみデザインが「Springin’」のプログ...
2025.06.24|夏野かおる
-
KOOVはプログラミング教育に対するメッセージ ― ソニー・グローバルエデュケーション代表 礒津政明
男女ともに人気があり、大手塾への導入も進むブロックプログラミング教材「KOOV(クーブ)」。今回は開発/運営元である株式会社ソニー・グローバルエデュケーション代表取締役社長 礒津政明氏...
2025.07.31|コエテコ byGMO 編集部
-
(取材)embot creative lab|CEO額田さんに聞く、子どもに本当に身につけてほしいスキル
今回、コエテコではembotの生みの親である株式会社e-Craft代表 額田一利(ぬかだ・かずとし)さんにインタビュー。NTTドコモからの独立についてや、自身の体験から生まれたというe...
2024.11.06|夏野かおる
-
Robloxでプログラミング!楽しみながら学ぶ「デジタネ」の魅力を開発者と代表が語る
小中学生向けプログラミング教材「デジタネ」のRobloxコースなら、ゲーム制作を通して楽しくプログラミングスキルを習得できます。Roblox社公式教育機関であるエデュケーショナル・デザ...
2025.09.10|大橋礼