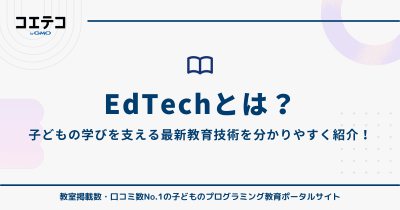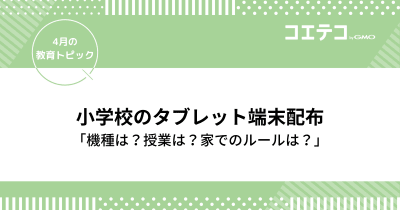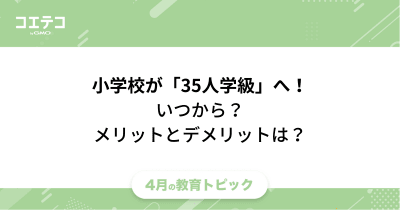文科省のGIGAスクール構想とは?小学校に1人1台タブレットはいつから?
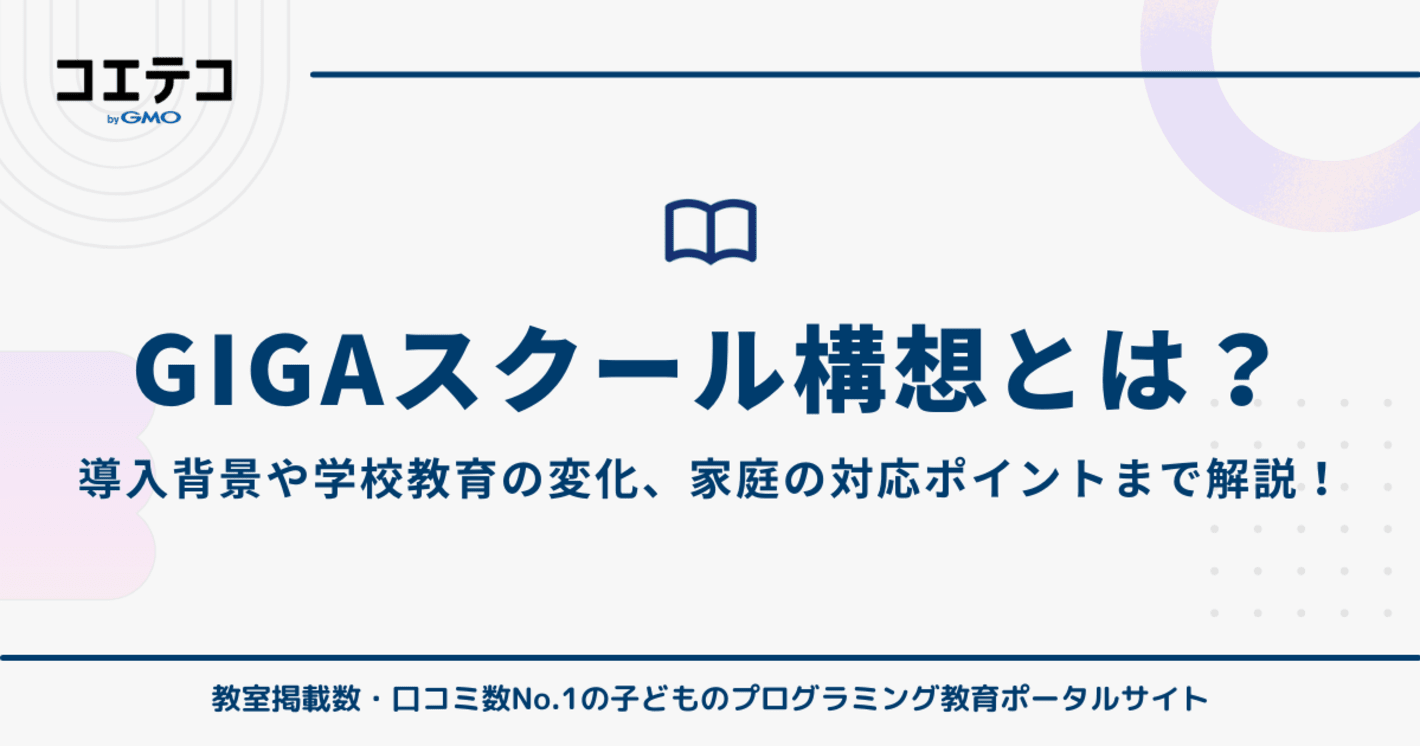
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
文部科学省が推進するGIGAスクール構想によって、今や小中学校では一人一台のタブレット端末が当たり前の光景となりました。
「いつから始まったの?」「学校の授業はどう変わるの?」といった疑問や、「うちの子はちゃんと使えているかな?」などの不安をお持ちの保護者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、GIGAスクール構想の基本から、タブレット導入による教育の変化、ご家庭でできるサポートのポイントまで、保護者の皆さまが知っておきたい情報をわかりやすく解説します。
タブレットを活用できれば子どもの学習効率がアップするので、ぜひ参考にしてくださいね。
GIGAスクール構想とは?一人一台のタブレットはいつから始まった?

GIGAスクール構想は、子どもたち一人ひとりに最適化された学びを実現するため、1人1台の学習者用端末(タブレットなど)と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備する文部科学省の取り組みです。
GIGAとは「Global and Innovation Gateway for All」の略で、すべての子どもたちにグローバルで革新的な学びへの扉を開くという想いが込められています。
この構想は2019年12月に閣議決定され、当初は2023年度までの段階的な整備が予定されていました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行を背景に計画が大幅に前倒しされ、2021年度には、ほとんどの小中学校で一人一台端末の環境が実現しています。
参考:小学校タブレット
なぜ?GIGAスクール構想が導入された背景

なぜ今、これほど大規模なICT教育改革が進められているのでしょうか。
その背景には、これからの社会で求められる力の変化があります。
Society 5.0時代を生き抜く力の育成
AIやIoTが当たり前になる「Society 5.0」時代では、情報を活用し、新しい価値を創造する力が不可欠です。GIGAスクール構想は、子どもたちが早期からICTに親しみ、未来を生き抜くスキルを育むことを目指しています。
誰一人取り残さない個別最適な学びの実現
これまでの画一的な一斉授業では、個々の理解度に合わせた指導が困難でした。一人一台のタブレット端末を活用することで、子ども一人ひとりの学習進度や興味に合わせた、きめ細やかな指導が可能になると期待されています。
教育格差の是正
家庭環境や地域によるICT環境の差が、教育格差につながるという懸念がありました。全国の学校で端末とネットワークを整備することで、どこに住んでいても質の高い教育を受けられる環境づくりを目指しています。
タブレット導入で学校教育はどう変わる?期待される5つの効果

一人一台のタブレット端末が導入されたことで、教室の風景は大きく変わりつつあります。
タブレット導入により期待されている効果を5つ紹介します。
効果1:一斉授業から「個別最適化された学び」へ
従来の一斉授業では、先生の話を聞いてノートをとるのが中心でした。タブレットがあれば、先生は全員の解答状況をリアルタイムで把握し、つまずいている子には個別にヒントを出したり、クラス全体の理解度に合わせて授業のペースを調整したりできます。
これにより、誰一人取り残されることのない、きめ細やかな学びが実現しやすくなります。
効果2:主体的に学ぶ力を育む「アクティブ・ラーニング」の推進
GIGAスクール構想は、子どもたちが受け身で学ぶのではなく、自ら課題を見つけ、調べ、考え、表現する「アクティブ・ラーニング」を後押しします。タブレットを使って情報を集めたり、自分の考えをまとめたり、クラスメイトとオンラインで意見交換したりと、主体的・対話的で深い学びを実践しやすくなります。
こうした活動は、国際的にも重要視される「読解力」や思考力の育成につながります。
効果3:必修化された「プログラミング教育」の質の向上
2020年度から小学校で必修化されたプログラミング教育でも、一人一台の端末は不可欠です。実際にタブレットを操作しながら試行錯誤すると、プログラミング的思考(論理的思考力)をより実践的に、そして楽しく学べます。
GIGAスクール構想は、プログラミング教育の環境を整え、その効果を高める上で大きな役割を担っています。
プログラミング教育が必修化されて数年が経ちましたが、子どもたちがどのようなことを学び、将来にどうつながるのか、気になっていませんか。プログラミング教育は単なる技術の習得ではなく、論理的思考力や創造力など、AI時代を生きるうえで欠かせない本質的な力を育む教育です。本記事では、プログラミング教育とは何か、その本当の目的や必修化の背景、そしてお子さんが身につける3つの具体的な力をわかりやすく解説します。
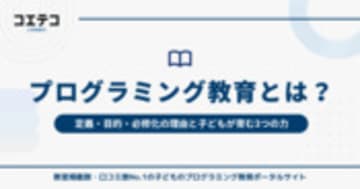

2025/10/29

効果4:さまざまな教科での学習活動の深化
タブレットは、特定の教科だけでなく、あらゆる学習活動の可能性を広げます。| 社会・理科 |
インターネットで情報を収集する「調べ学習」が効率的に。動画やシミュレーション教材で、より深く現象を理解できます。 |
| 国語 | 考えをまとめる、意見を共有する、漢字をドリルで練習するなど、多様な活動に活用できます。タイピングスキルの習得にもつながります。 |
| 算数 | AIドリルなどを活用し、自分のペースで問題演習を進め、間違えた問題をすぐに復習できます。 |
| 図工・音楽 | お絵かきアプリや作曲アプリを使えば、道具の制約なく、誰もが自由に創作活動を楽しめます。 |
| 体育 | 自分のフォームを動画で撮影して確認したり、トップアスリートの動きと比較したりして、技能の向上に役立てられます。 |
効果5:教材のデジタル化と教員のスキルアップ
GIGAスクール構想では、デジタル教科書やAIドリルなどの新しい教材の活用も進められています。また、先生方がICTを効果的に使いこなせるよう、研修やICT支援員の配置などの指導体制の強化も図られており、ソフト・ハード両面から教育の質の向上が目指されています。
参考:タブレット学習
保護者が知っておきたいタブレット利用の注意点と課題
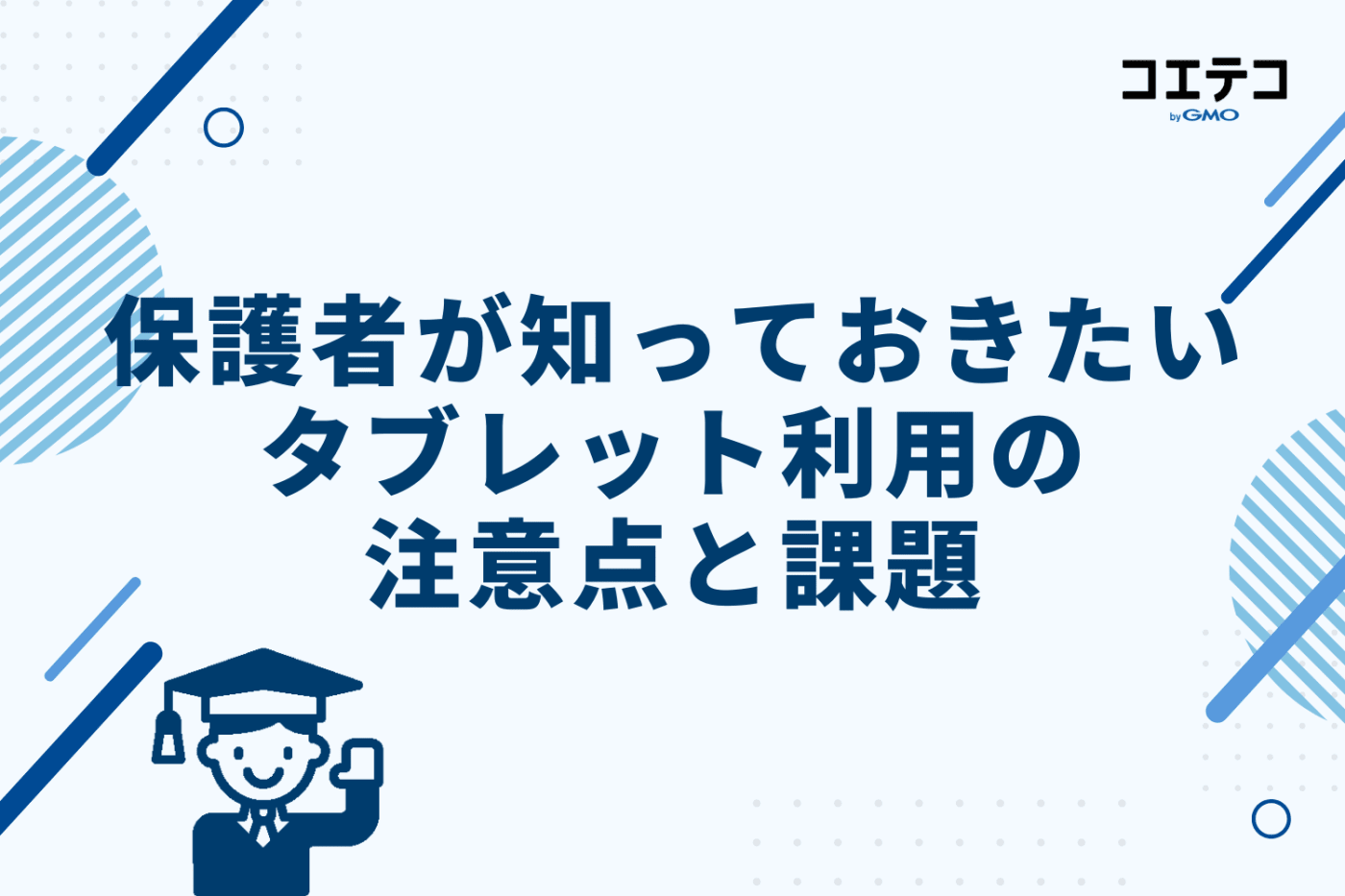
多くのメリットが期待される一方、タブレットの利用にあたってはいくつかの注意点や課題も指摘されています。
保護者として知っておきたいポイントを見ていきましょう。
課題1:手書きの機会が減ることへの懸念
タブレットでの入力が増えることで、「漢字などを手で書く機会が減り、定着しにくくなるのでは?」と心配する声もあります。タブレットでの学習と、従来通りノートと鉛筆を使う学習のバランスをどう取るかは、今後の課題の一つとなるでしょう。
課題2:学習と遊びの線引き
便利なタブレット端末ですが、一歩間違えればゲームや動画視聴などの遊びに夢中になってしまう可能性もあります。学校のルールに加え、家庭でも利用のルールを決めるなど、学習ツールとしての適切な使い方を子ども自身が意識できるように導きましょう。
課題3:インターネットの危険性
一人一台のタブレット端末を持つことで、子どもがインターネット上のトラブルに巻き込まれるリスクも考えられます。SNSでの個人情報の扱いや、不確かな情報の見極め方など、ネットリテラシーを親子で一緒に学ぶ機会を設けること重要です。
参考:ネットリテラシーとは?
課題4:端末の破損や紛失のリスク
「ランドセルごと投げてタブレットを壊してしまったら…」と心配になる保護者の方も多いかもしれません。端末は学校からの貸与品なので、物を大切に扱うことを教えてあげましょう。
故障した場合の対応(修理費用の負担など)は自治体や学校によってルールが異なるため、事前にルールを確認しておくと安心です。
家庭でできるサポートは?タブレット活用の3つのポイント

GIGAスクール構想による教育の変化に対応し、タブレットを有効活用するためには、学校任せにせず、家庭でのサポートも大切になります。
家庭でできるサポート内容を3つ紹介します。
サポート1:親子で一緒に「家庭のルール」を決める
学校のルールとは別に、家庭でのタブレットの使い方を親子で話し合い、ルールを決めておくことをおすすめします。- 使う時間(例:平日は夜8時まで、宿題が終わってから30分)
- 使う場所(例:リビングなど、保護者の目が届く場所で)
- 困ったときの相談(例:わからないことや嫌なことがあったら、すぐに相談する)
一方的に押し付けるのではなく、子ども自身が納得して守れるルールを一緒に作ることが長続きの秘訣です。
サポート2:ポジティブな声かけで興味を引き出す
「ゲームばかりしないで!」と叱るよりも、「そのアプリで何ができるの?」「学校で何を調べたの?」と、子どもの活動に興味を示す声かけを心がけましょう。保護者がICT活用に前向きな姿勢を見せれば、子どもは安心してタブレットを学習に活用できるようになります。
GIGAスクール構想が一気に加速し、皆さんのご家庭でも、学校から貸し出された端末をお子さんが持ち帰ってきていませんか? どんな機種が配布され、どのような授業や使い方をしているのか、破損した場合や保険について、他の皆さんの体験が気になりますね。今回はタブレット配布が行われた家庭を対象に、トラブル体験や感想も含めて取材しました。


2025/12/25

サポート3:ネットリテラシーを一緒に学ぶ
インターネットの危険から子どもを守るには、利用を制限するだけでなく、危険を正しく理解し、自分で判断して行動できる力を育むことが重要です。フィルタリングサービスを活用しつつも、「知らない人とつながらない」「個人情報を安易に教えない」などの基本的な約束事を話し合う機会を持ちましょう。
タブレット学習をさらに伸ばすには?プログラミング教室も選択肢に
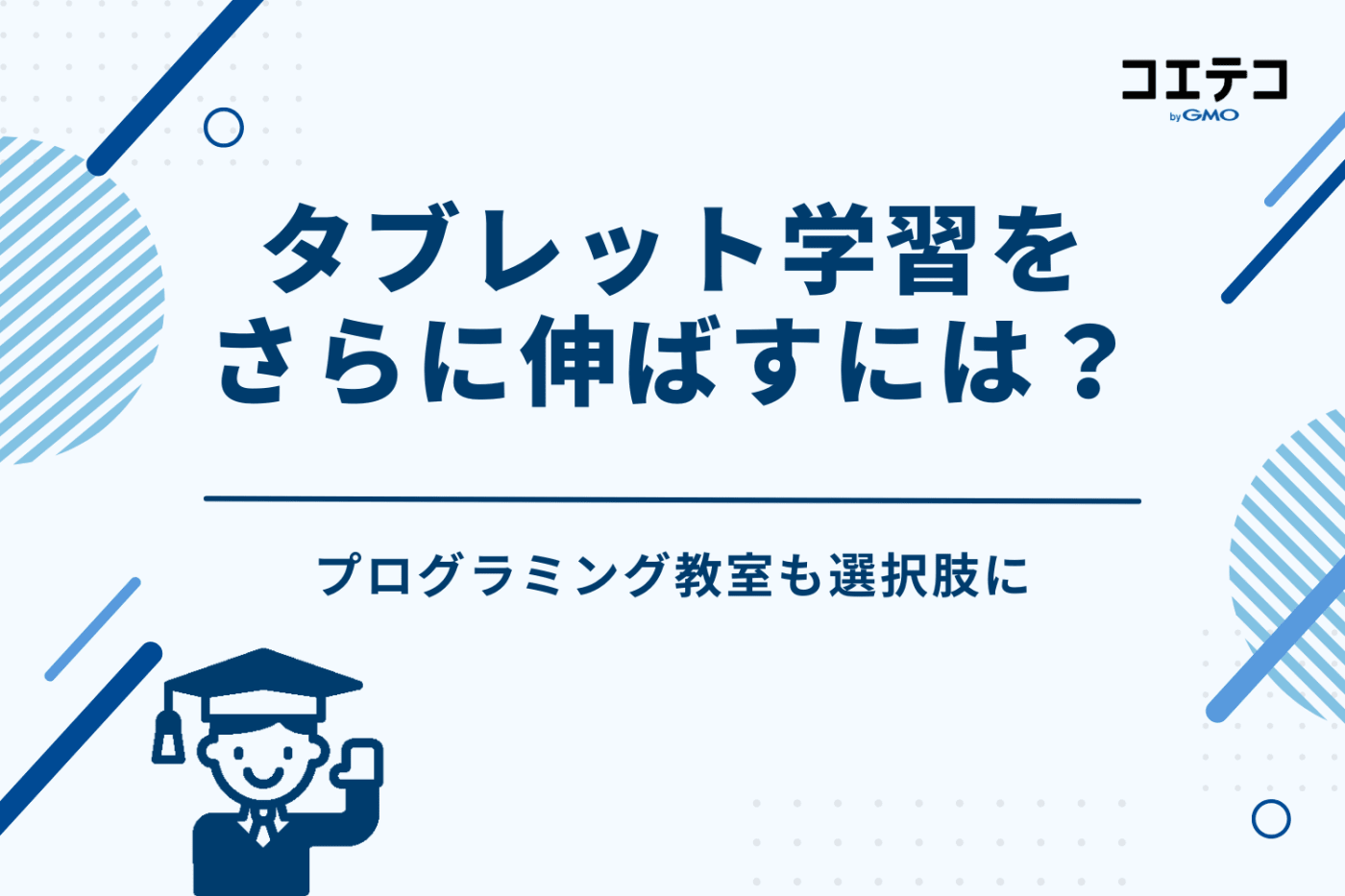
学校のタブレット学習をきっかけに、お子さんがプログラミングやパソコン操作に強い興味を示す場合もあるでしょう。
プログラミング教室では、専門の講師から論理的思考力や問題解決能力を体系的に学べます。
独学での学習はつまずきやすい側面もありますが、スクールであれば子どもの興味やレベルに合わせた指導が受けられます。
いきなり入会するのは不安という方は、まずはお子さんと一緒に無料体験に参加し、教室の雰囲気や授業内容がお子さんに合っているか確かめてください。
2020年度、ついに小学校でプログラミング教育が必修化しました。コロナ禍の影響もあいまって、自宅からプログラミングが学べるオンラインスクールへの注目が集まっています。 この記事では子どもにおすすめのオンラインプログラミングスクールをまとめました。
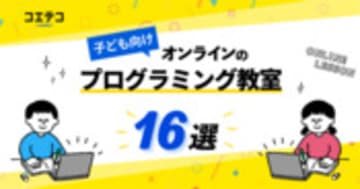

2026/01/02

まとめ:GIGAスクール構想は、子どもの未来を拓くチャンス

この記事では、GIGAスクール構想の概要から、タブレット導入による教育の変化、そして家庭でできるサポートまでを解説しました。
一人一台のタブレット端末は、これからの社会を生きる子どもたちにとって、鉛筆やノートと同じように当たり前の学習ツールとなっていきます。
変化のスピードに戸惑うこともあるかもしれませんが、これは子どもたちの可能性を大きく広げるチャンスです。
ご家庭でもタブレットの活用法について積極的に関わり、お子さんの学びを応援してあげましょう。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド
-
NEXT GIGAとは?GIGAスクール構想の課題と文部科学省・学校の取り組みを解説
NEXT GIGAは、文部科学省が推進するGIGAスクール構想の第2期として、日本の教育現場でのICT活用をさらに深めるための重要な取り組みです。本記事ではGIGAスクール構想の課題や...
-
EdTechとは?子どもの学びを支える最新教育技術を紹介!
オンライン授業やタブレット学習など、教育現場で急速に広がる「EdTech(エドテック)」。これは、IT技術を活用して子どもの学びを進化させる新しい教育の形です。この記事では、EdTec...
-
ICT教育とは?ITやIoTとの違いと学校での活用事例を徹底解説
2020年、プログラミング教育が必修化します。そんな中でよく耳にするのが「ICT」という言葉。「IT」とはどう違う?学校にICT環境が整うとどんなメリットが?現状、実態は?くわしく解説...

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
NEXT GIGAとは?GIGAスクール構想の課題と文部科学省・学校の取り組みを解説
NEXT GIGAは、文部科学省が推進するGIGAスクール構想の第2期として、日本の教育現場でのICT活用をさらに深めるための重要な取り組みです。本記事ではGIGAスクール構想の課題や...
2025.05.30|コエテコ byGMO 編集部
-
小中高で情報教育が大幅強化!2030年代に向けて親が知っておくべきこと
2025年9月、文部科学省が2030年代に向けた教育改革の方針を発表しました。注目すべきは「情報教育の抜本的強化」です。小学校から高校まで、子どもが学ぶ情報教育の内容が大きく変わります...
2026.01.02|大橋礼
-
小学校のタブレット端末配布「機種は?授業は?家でのルールは?」みんなに聞いてみた
GIGAスクール構想が一気に加速し、皆さんのご家庭でも、学校から貸し出された端末をお子さんが持ち帰ってきていませんか? どんな機種が配布され、どのような授業や使い方をしているのか、破...
2025.12.25|大橋礼
-
(教育トピック)小学校35人学級へ!いつから?メリットとデメリットは?徹底解説
小学校の1クラスの定員上限数が40人から35人へと変わります。いつから、何が変わり、なぜ行われるのか。35人学級のメリットやデメリットは?親であるわたし達が知っておきたい学級編制と定員...
2025.05.30|大橋礼
-
小学校「宿題の量が多い!」いつやる・どうやる・どうしてる?|4月の教育トピック④
最近はドリルやプリントに加えて「タブレット端末でやる宿題」もプラスされ、新しい学習方法に親が戸惑うことも少なくありません。今回の教育トピックでは主に小学校1年〜6年のお子さんがいる保護...
2025.09.10|大橋礼