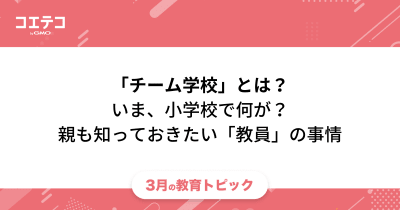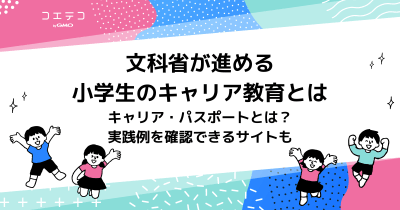2020年の教育改革とは?3つのポイントをわかりやすく解説!
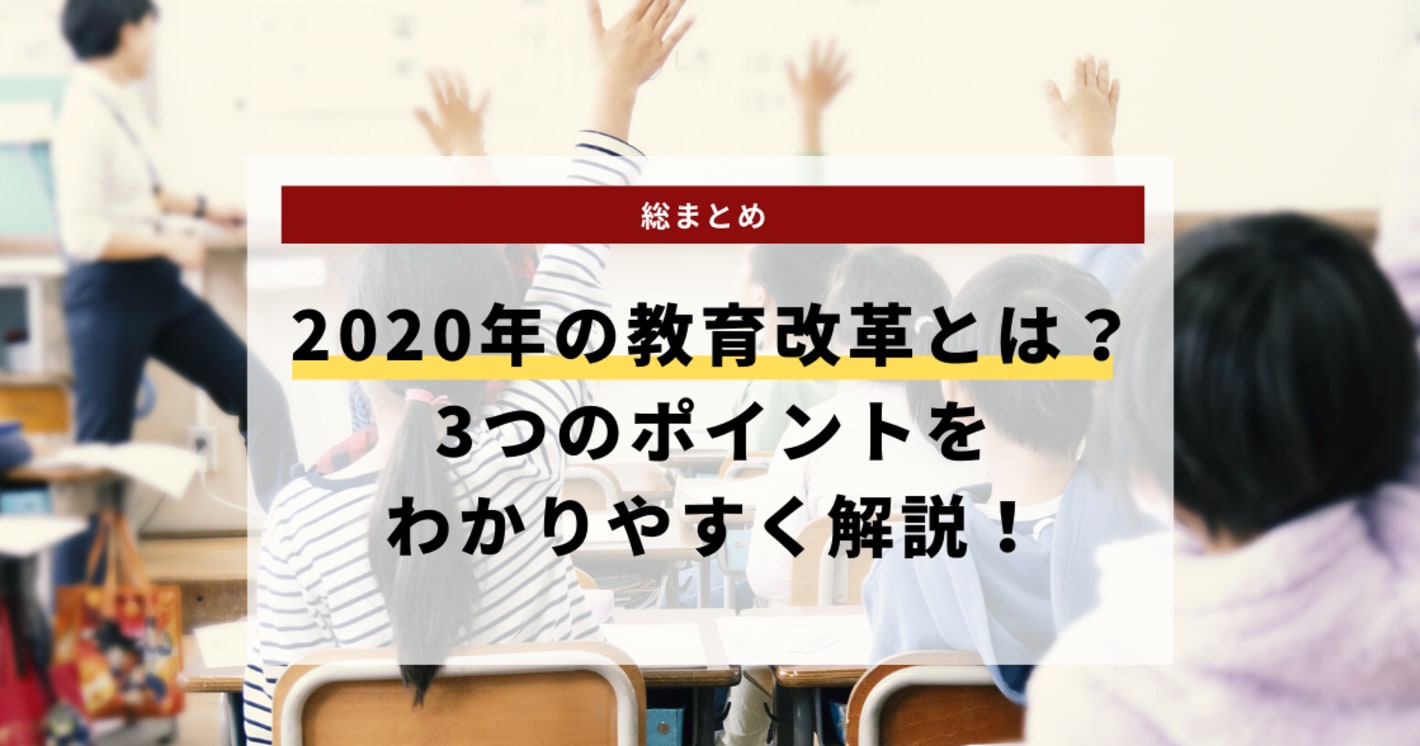
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
なんとなくニュースなどで耳にしたことがあっても、具体的に何が変わったのかまでは想像がつきにくいのではないでしょうか。
実は、コエテコでも多くの記事を扱っているプログラミング教育以外の分野でも教育現場に大きな変化が生じました。
本記事では、2020年教育改革を3つのポイントに分けて解説していきます。
2020年教育改革とは?
新学習指導要領の導入
「学習指導要領」とは、全国である程度の水準の教育を提供することを目的として、文部科学省が定めているカリキュラムのことを指します。学習指導要領をもとに、時間割や教科書の内容が決められていきます。
この学習指導要領は10年に一度改訂されるのですが、2020年度は新しい学習指導要領が適用された年度です。
新学習指導要領による学習は、小学校では2020年度、中学校では2021年度、高校では2022年度から実施されました。
今回導入された学習指導要領では、「生きる力」のその先の力を育成する「社会に開かれた教育課程」が重要視されています。
特に、主体的で深い学びを実現する「アクティブ・ラーニング」
子どもや地域の実態に即した教育を実現する「カリキュラム・マネジメント」を実施し、学びに向かう力、人間性、知識及び技能、思考力・判断力・表現力の3つの力をバランスよく育成することが宣言されています。
英語教育改革
グローバル化のすすむ社会でも対応できる英語力の育成に重点が置かれるようになりました。後述する小学校での英語教育の充実化や教科化に加え、中学校や高校での英語の授業は基本的に英語で行うことが発表されていました。
また、センター試験に代わり2021年から導入された「大学入学共通テスト」では、英検やGTECといった英語の民間試験に加えて従来の「読む・書く」の2技能ではなく「読む・聞く・書く・話す」 の4技能を評価すると発表されていましたが、家庭の経済状況や地域の格差の問題などが指摘され、実施の延期が表明されました。
その後、新課程に移行する2025年1月以降の英語の試験においても英語の民間試験の導入を断念すると表明されています。
大学入試改革
大学入試の仕組みの変更も発表されています。従来のセンター試験が廃止され、大学入学共通テストが2021年1月から実施されています。大学入学共通テストでは、英語での4技能の評価や、国語や数学での記述式試験の導入が表明されていましたが、試験実施や採点の公平性の観点などで問題が指摘され、2021年7月にはどちらも導入を断念すると表明されました。
また、大学ごとの個別試験にも変化があります。
一般試験においても、志望理由書の提出が求められる場合や、小論文や面接が課される場合があります。
さらに、AO入試は「総合型選抜」に、推薦入試は「学校推薦型選抜」に名称が変更され、学力による試験が課せられる場合もあります。
加えて、高校からの調査書をこれまでより重視していく方針も発表されています。
2020年の教育改革の背景
21世紀は新たな知識・情報・技術が社会のあらゆる基盤となる「知識基盤社会」であると言われています。キャシー・デビッドソン氏(ニューヨーク市立大学大学院センター教授) によると、子どもたちの65%は将来、今は存在していない職業に就くとの予測がされています。
さらに、マイケル・オズボーン氏(オックスフォード大学准教授)によると、今後10年~20年程度で半数近くの仕事が自動化される可能性が高いとも言われています。
このような変化の要因には、グローバル化、情報化の面での急速な社会の変化が考えられます。
2020年教育改革では、このような社会の急速な変化に柔軟に対応する力をつけることが必要と考えられていました。
これからの時代に適応していく「社会に開かれた教育課程」が2020年からの教育改革のキーワードとなっています。
また、文科省が述べている「社会に開かれた教育課程」で身につけさせたい力は以下の通りです。
2020年教育改革では、これからの激しい社会の変化に対応できる力の育成が求められ、学校側も社会との連携をはかっていくことに重点が置かれるようです。
- 社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を持ち、教育課程を介してその目標を社会と共有していくこと。
- これからの社会を創り出していく子供たちが、社会や世界に向き合い関わり合い、自らの人生を切り拓いていくために求められる資質・能力とは何かを、教育課程において明確化し育んでいくこと。
- 教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用したり、放課後や土曜日等を活用した社会教育との連携を図ったりし、学校教育を学校内に閉じずに、その目指すところを社会と共有・連携しながら実現させること。
文部科学省「2030年の社会と子供たちの未来」より
2020年度から新課程が実施された小学校では具体的にどのように変わった?
2020年度から新しい教育が実施された小学校では、具体的に教育内容がどのように変わったのでしょうか。プログラミング
小学校では、2020年度よりプログラミング教育が必修化になりました。小学校におけるプログラミングの授業では、プログラミングの技能やプログラミング言語を覚えることが学習の主たるねらいではありません。
自分の意図する挙動の実現のために論理的に考える「プログラミング的思考」の育成に重点が置かれています。
また、プログラミングという教科ができるのではなく、各教科の中でプログラミング的思考を育成することが求められています。
2020年度、ついに小学校でプログラミング教育が必修化しました。コロナ禍の影響もあいまって、自宅からプログラミングが学べるオンラインスクールへの注目が集まっています。 この記事では子どもにおすすめのオンラインプログラミングスクールをまとめました。
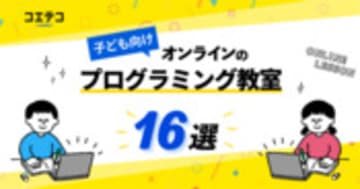

2026/02/03

英語の教科化
2020年3月までの小学校のカリキュラムでは、5,6年生で「外国語活動」の時間が設けられており、教科としての扱いではないので、成績はつかない授業となっていました。ですが、2020年度からグローバル化に対応できる基礎的な力の育成のために、小学校3,4年に年35時間の「外国語活動」を、5,6年生に年70時間の教科としての「外国語科」が新設されています。
これにより、これまでより早期から英語教育が始まるようになりました。
また、5,6年生からの「外国語科」は教科としての扱いですので、国語や算数のように成績がつく授業となっています。
2020年から小学校でも英語が必修化され、これまで以上に英語が重要な科目として位置付けられるようになりました。本記事では、小学生向けおすすめ英語塾ランキングをご紹介します。
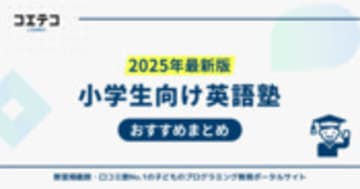

2026/02/14

まとめ
以上、2020年教育改革についてのまとめ記事でした!小学校から大学入試まで幅広く影響があることがわかります。
小学校での英語の教科化やプログラミング教育の必修化に加えて、のちの入試内容までガラッと教育内容が変わるので、注意が必要です。
参考資料
文部科学省「平成29・30年改訂学習指導要領のくわしい内容」
文部科学省「2030年の社会と子供たちの未来」
文部科学省「【総則編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説」


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
「チーム学校」とは?教員の長時間労働が問題に!小学校という現場
学校の先生は「ブラック企業に勤めているようなもの」という声も今だに多く聞かれます。 「チームとしての学校のあり方と今後の改善方策について」は2015年に中央教育審議会が答申しています...
2025.09.10|大橋礼
-
小中高で情報教育が大幅強化!2030年代に向けて親が知っておくべきこと
2025年9月、文部科学省が2030年代に向けた教育改革の方針を発表しました。注目すべきは「情報教育の抜本的強化」です。小学校から高校まで、子どもが学ぶ情報教育の内容が大きく変わります...
2026.01.02|大橋礼
-
STEAM教育とは?STEM教育と何が違う?用語の定義や具体的な実践例を解説
変化の激しい21世紀に適応していく「21世紀型スキル」を身に着ける教育としてSTEAM教育が注目されています。 似ている用語であるSTEM教育とはどのような違いがあるのでしょうか。 ...
2025.05.30|小春
-
文科省が進める小学生のキャリア教育とは?実践例や導入理由を徹底解説
子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しており、早期から将来のキャリアを考えることは重要です。 本記事では一人ひとりの子どもたちが自立できる基礎となる能力や態度を育成するキャリア教育と...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
【小学校】“SSS””CS”って何のこと?「先生」以外の学校スタッフ
小学校の職員と言えば、校長先生、副校長先生、担任の先生たちは想像がつくでしょう。実は、それ以外にも学校スタッフはたくさんいます。中には、略称になっていて、職名だけでは仕事内容がよく分か...
2024.06.06|コエテコ byGMO 編集部