(インタビュー)北原達正|2歳からプログラミングやAI・データサイエンスを学べる「e-kagaku Academy(イーカガク アカデミー)」

いよいよ昨年(=2020年度)からプログラミング教育が必修化し、1人につき1台の学習用端末を与える「GIGAスクール構想」も進行し始めました。「変化の速さについていけない!」 という保護者も、多いかもしれません。
長年プログラミング教育にたずさわる北原達正さん(以下、北原先生) は、2003年に「子どもの理科離れをなくす会」を設立。10年後の科学技術者の育成をテーマに、2歳からプログラミングやAI・データサイエンスを学べる「e-kagaku Academy(イーカガク アカデミー)」を運営しています。

これからの教育方法は、一体どうなっていくのでしょうか? わかりにくい言葉も多いICT教育の現在とこれからについて、4歳と3歳の息子をもつライターの下谷内(しもやうち)が、北原先生にお話を伺います。
プログラミング教育はなぜ必修化した?
10年に一度のペースで改訂される、「学習指導要領」。2020年度の改訂で話題になったのは、小学校のプログラミング教育の必修化でした。それにともない、コロナの影響はあったものの、民間のプログラミングスクール市場も盛り上がりをみせています。きっかけは、中央教育審議会での議論です。
- 生活がデジタル化し、10年先の未来を予測することが難しくなっている
- そんな時代の子どもたちに必要なのは、「コンピュータを受け身ではなく、積極的に活用する力」や「プログラミング的思考(論理的思考力)」である
一方で、プログラミング教育の授業内容には、具体的な基準がまだありません。文部科学省の調査によると、2019年11月の準備段階では、7割の学校が実施済みであるものの、各地域で大きくばらつきがあることがわかりました。
学習指導要領は、改訂後すぐに実施されるわけではなく、数年の準備期間が設けられたのちに実施されます。2019年11月は、準備期間だったということになりますね。
学校どころかクラスによって格差がある

——小学校でプログラミング教育が必修化されて1年が経ちましたが、学校や地域による格差について、北原先生はどう思われますか。
結論から言うと、ものすごく大きな格差が生まれています。
——それはなぜでしょうか。
ICT教育(コンピュータを勉強に取り入れること)へ価値観が、私立と公立、都心と地方で著しく違うのです(都心の私立>地方の公立)。学校どころかクラスによって、あるいは先生によって、その違いを否定しきれません。
——クラスによって差があるのですか?
そうです。同じ学校内でも、ICT担当の先生とそうでない先生では、教えられる内容に格差があるのです。「プログラミング教育やSTEAM教育に力を入れています」と謳っているような私立でも、それは同じです。
自治体によって異なる理由
——公立間でも、地域(自治体)によって差が出ているという話も聞きます。それについては、どうお考えですか?仰るとおりです。「総合教育会議」をご存知でしょうか? 市町村長が任命した教育長が中心となって、さまざまな教育問題について議論する、法律で定められた会議です。その議事録を読むと、自治体による温度差がわかります。
市町村と教育委員会の関係性
↓ |
知事/市町村長 |
各自治体の長。 |
↓ |
教育委員会 |
市町村(自治体)ごとに存在する。 |
↓ |
事務局 |
総務課、学校教育課、生涯学習課などからなる。 |
教育機関 |
学校、図書館、公民館などが該当。 |
- あまり乗り気ではない自治体
- 積極的にやろうとしている自治体
- 市長は積極的だが、教育委員会が乗り気ではない自治体
——そのような理由で格差が生まれているのですね。その中でも、プログラミング教育に成功しているような学校はあるのでしょうか?
誤解を恐れずに言えば、国内ではひとつもありません。というのも、単に授業のなかでプログラミングをやっただけでは、子どもたちが自ら積極的にコンピュータを活用するまでいかないからです。そういった意味で、成功している事例はないと考えます。
先生の経験値に依存している現状

——先生による授業内容の違い、自治体による格差のお話がありましたが、現状のプログラミング教育の問題点について、北原先生はどうお考えですか?
先生自身にプログラミングを使った経験、活用した経験がないこと。そして、その先生が、子どもたちに教えようとしていることです。とくに小学校は、7割以上の先生が「文系だ」と豪語している世界です。いまだに、手書きでテストをされていますよね?
——先生がつくったテストを、生徒が手書きで回答する、という意味ですね?
そうです。たとえば算数なら、
- 「1/2+1/3」と「1/7+1/11」という問題は、どのくらい難易度が違うのか
- この問題を何年生で解けたらよいのか

——「学校に任せていれば安心」という時代では、もうないのですね。
教える人の経験値に頼り切っているのが課題です。情報の教科書は存在しますが、どこまでの範囲で、どのレベルでやったらよいのか。その基準となるガイドラインがないため、先生によって授業のゴールが大幅に変わるのです。
私費(自腹)で講習に参加する先生も
——では、その課題点を、現場の先生たちはどう感じているのでしょう? 何か取り組んでいることは?はい。現状をなんとかしようと、私費で講習に参加する先生方もいます。じつは、私が講師をつとめる講習会にも、約80名の先生が受けに来られています。自腹で講習に参加してくださる先生ですから、問題意識は非常に高いです。
一方で、私が子ども向けの問題を出したときに、「ちょっと待ってください。息子が帰ってきたらわかると思うのですが……」と仰られます。そのくらい、先生たちは何をしたらよいのかわからず、困惑しているのです。


——先生が自腹で講習会に。参加されているのは、私立と公立、どちらの先生が多いですか?
どちらかというと、公立の先生が多いです。幹事校(地域全体の教育方針の模範をつくるモデル校のこと)の教頭先生が、複数人でいらっしゃることもあります。
——なるほど。ちなみに、今年度(=2021年)から中学、高校と順にプログラミング教育が必修化されますが、小学校とは状況が変わると思われますか?
高校で多少変わるでしょう。とくに私立の受験校には、論文を書いたことのある先生が集まります。論文を書くということは、情報量や、いわゆる探究型の授業ができる可能性が、一般の先生よりは高いわけです。
一方、東京を除いて、すべての県庁所在地にデータサイエンスや探求型講座に対応できている高校があるかというと、そうではありません。子どもたちも、そこに至るまでの準備ができていない。端的に言えば、小学校の「自由研究」の質を、まず上げるべきでしょう。

——現状を変えるには、どうしたら良いのでしょうか。
私の個人的見解では、「地域クラブ」をつくっていくしかないだろうな、と。私の会も、総務省の「地域ICTクラブ(地域課題の解決などをテーマに、住民と学校児童が一緒になってICTスキルを磨く活動)」に参加しています。学校に依存してしまうと、その学校以外の子供たちは切り捨てることになります。それっておかしいですよね。「どんな職業にもコンピュータを中心としたICT力が必要」と言うのなら、どの地域の、どの学校に通ったとしても、「最低限これだけは学べる」というものが普遍化しないと、国全体の力にはなりません。
2024年の大学入試「情報」新設が大きなトピックに

——GIGAスクール構想が進み、春から1人1台の端末が行きわたりますが、これから教育環境はどう変わるかについて、北原先生のご意見をお聞かせいただけますか。
あと2年は動かないでしょう。なぜ2年かというと、3年後、大学入試に「情報」が新設されるからです。ここ1年以内に、情報に関する教科書や本、問題集がたくさん出てくると思います。それが淘汰され、質のよいものが主流になるのに、1~2年はかかるでしょう。
それにともない、小・中学校から大学入試に直結するようなキャリア教育をする保護者が増えてくると、学校の先生にも圧力がかかります。そこで変化があるでしょう。入試に「情報」が入るのは、大きなトピックだと思います。
——先生への圧力とは、具体的にどのような?
「データサイエンス」のできる人材を先生に雇う傾向が、より強くなります。じつは、約7割の大学で、データサイエンスの先生が不足しています。地方の大学なんて、壊滅状態です。
自分のことで恐縮なのですが、この春から、順天堂大学医学部大学院の講師を務めることになりました。
——医学部! 北原先生の専攻は。
私は理学部です。というのも、現代の医学は、CTスキャンにしても遠隔医療にしても画像が必須です。画像には膨大な量のデータが必要で、そのデータを分析する人が要るのです。
——教える人が圧倒的に足りないのですね。
じつは日本の小中学校では、日本国籍をもたない人を雇えません。そのため、海外の優秀な人材を先生にできないのです。したがって、「教える側」の整備に、大幅な時間がかかります。少なくとも、あと5年かかるでしょう。とにかく教える人を増やさないかぎり、今の環境は、やったことのない人に「悪いけどこれやっといてね」と言っている。そういうふうにしか聞こえないと、私は思います。
——なるほど。一方で、先取り学習に興味のある保護者も多いと思いますが、幼児向けのマーケットはどうなっていくと思われますか?
間違いなく拡大するでしょう。ただ、どのスクールへ通って、どの科目のどの問題集をやれば良い、ということではなく、お子さん自身が楽しいと思えるかどうかが重要です。

今後の情報化教育に必要なのは、自ら学ぶ力
——ここ数年「データサイエンティスト(データを分析し、さまざまなビジネス課題を解決する仕事)」が人気職ですが、どのような力を身につけたら良いでしょう?データサイエンティストになるには、3つの力が必要です。経済産業省と内閣府が、指針を出しています。
1 プログラミング力
2 ビジネス力
3 数学
2のビジネス力は、論理的に問題をひも解いていく手法のことです。「ロジカルツリー(ロジックツリー)」がその代表ですね。

ツリー状の構図を使って、問題の根本的な原因を探り解決する方法
小学生に置き換えてみると、「自分で決めた勉強時間を守れるか?」「明日の遠足の準備をひとりでできるか?」ということになります。親や学校がすべてを準備してあげるような環境では、ビジネス力は育ちません。
3の数学とは、統計学やアルゴリズムのことです。計算力なら、コンピュータのほうがはるかに勝っているからです。
——そもそも、「アルゴリズム」とは?
「段取り」です。たとえば、
- 6時まで勉強する
- このページが終わるまで勉強する
——1~3の力を踏まえて、今後の情報化社会に本当に必要な力は何だと思われますか。
自分で勉強する力、私はそう思います。プログラミングは、一言で言えば、小学校の自由研究なのです。
- 何を調べたいと思っているのか
- そのために何をしたらよいのか
- 手法には何があるか
- テーマにオリジナリティはあるか
小中学生の人工衛星打ち上げは世界初!「e-kagaku Academy」の取り組み

——北原先生の「e-kagaku Academy」では、どのような取り組みをされていますか?
2019年に始動した「宇宙プロジェクト」の一貫として、同年10月、小学4年生から大学院生までのメンバー 20名が、「100均の材料などでつくった探査機を成層圏に打ち上げる」というプロジェクトに挑戦しました。
そのなかで、「輪ゴムを成層圏に出して、その張力がどれくらい変化するのか」を調べた中学3年生の男の子がいました。正直、輪ゴムが成層圏にいるのは10数分なので無理だろう、と思いましたが、見事に、トヨタやNASAでも使っているMATLAB(マトラボ)というデータ分析ソフトで、統計学的にも劣化状態がわかるデータが取れたのです。
——MATLAB(マトラボ)というデータ分析ソフトを、子どもが使うケースは珍しいのですか?
小学生からMATLAB(マトラボ)を使うのは、世界でもうちだけでしょう(笑)。
上記の子は、その後、MATLAB EXPOというプロのシンポジウムで発表し、ベストプレゼンの3位を獲得。その後JAXAのシンポジウムでも成果を発表しました。彼はもう、基本的に大学はAO入試で受かるでしょうし、すでに企業からインターンの誘いもきています。

——中学3年生で企業から声掛けが。
今年の1月には、「GPS衛星を活用した琵琶湖環境調査」というプロジェクトも行いました。中学1年生の女の子が、琵琶湖にマイクロプラスチックのゴミがあるかどうかを調べるために、「醤油さし」にマイクロプラスチックを入れるシステムをつくったところ、採取に成功したのです。私は、絶対に無理だろうと思ったのですが(笑)。

試行錯誤の経験がある子どもは、空想を形にして、現実のものにできます。すると、大人からも評価され、次のステップを踏めます。たとえば、包丁を使えない人に、新しい料理のレシピを考えろ、というのは無理な話ですよね。私は、道具としての「包丁」にあたる、コンピュータとプログラミングを教えているのです。
2023年には、人工衛星の打ち上げも予定しています。小・中学生が人工衛星を打ち上げるのは、世界初です。
——なんだかものすごいです。どんな子でも受けられますか? たとえば、うちのやんちゃな4歳と3歳の息子とか。
もちろんです! スポーツと同じで予選審査がありますので、それなりに勉強していただく必要はありますが(笑)、未就学児から大人まで、年齢や性別に関係なく、どんな方でも受けられますので、ぜひ気軽にチャレンジしてみてくださいね。

子どもの「好き」「夢中」を応援してあげられるか

——-最後に、保護者の皆さんへメッセージをお願いします。
ICTの「C」は「コミュニケーション」です。保護者のなかには、「コミュニケーション=みんなと仲良くすること」だと思われている方もいるかもしれません。
以前、私の教室に、絵を描くのが大好きな子どもがいました。しかし、そのお母さんは、「子どもがお友達と遊ばないんです」と悩み、キャンプやイベントなどに積極的に連れ出していました。そこでも一人で、地面に絵を描いているような子で。
そのお母さんに、私の会のサポーターである大学生がこう言いました。「心配なお気持ちはわかりますが、表面上ただ仲良くするだけの友達って、今の世の中、本当に必要なのでしょうか。集中して黙々となにかに取り組めることは素晴らしいし、なぜそれを否定するのでしょう?」と。
すべて「こうである」というone-issue(ワンイシュー)の考え方は、情報化社会にはいりません。たとえばお子さんが、アイドルや声優、テニスプレイヤー、ピアニストになりたいと言ったときに、応援してあげられるかどうかです。好きなこと、夢中になれることを認めてあげるかあげないかで、その子の居場所や、人生観までが変わってしまいます。「コンピュータ = ゲーム=重要ではないもの」と思われている保護者や関係者の方々に申し上げたいのは、コンピュータでプログラムに一生懸命取り組んでいる子は、毎日ピアノの前に座って練習している子となんら変わらない、高いモチベーションを持っている子どもだということです。
全国どこにいても受けられる!「e-kagaku Academy」で本当に必要な力を身につけよう
北原先生が代表を務める「e-kagaku Academy」では、これからの時代に本当に必要な「自ら学ぶ力」を身につけ、未来の科学技術者の育成をめざす取り組みをしています。わが家の息子2人は、常に屋内外を走り回っているようやんちゃものです。そのため、「プログラミングか‥‥‥うちとは無縁だな」と感じていました。ですが、本日北原先生のお話を伺ってみて、「好きなことに夢中になる」それだけでも良いんだと、ハードルがぐんと下がりました。
同会では、全国どこにいても授業を受けられる「e-kagaku遠隔講座」も実施中です。NHKや新聞でも取り上げられた「e-kagaku Academy」のレッスンを、ぜひお気軽に受けてみてくださいね。


おもちゃではない。「本物」で学ぶ10年後のためのSTEAM教育を子どもたちに。e-kagakuは、科学を通した人間教育、グローバル人材の育成を目指します。 理系・文系の枠を超え、科学教育の機会均等化・継続的学習環境の整備に取組みます。

https://e-kagaku.com/ >


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
(取材)AI/IoTサービス『Gravio(グラヴィオ)』|コーディング不要でAI/IoTシステム開発が学べる!研...
高校での情報Ⅰでは、データサイエンス分野やAIについても学びます。しかし、データ解析やシステム開発を楽しく体験できる教材は残念ながらそう多くありません。 複雑なコード(プログラム)を...
2025.05.30|大橋礼
-
(インタビュー)FULMA Academy(YouTuber Academy)の教育とは?|FULMA株式会社 中...
「FULMA Academy(旧称:YouTuber Academy)」はYouTuber体験を通して自己表現力を身に付ける小学生向けスクール。この記事では株式会社FULMA COOの...
2024.11.06|夏野かおる
-
教室での学びと体験が、夢への道標に。 ヒューマンアカデミーロボット教室のOBインタビュー
ヒューマンアカデミーロボット教室は、ヒューマンアカデミーが運営するオリジナルロボットの組み立てから動かすまで、ロボット制作の一貫を学ぶことができる教室。今回は、東京都多摩市にある「多...
2025.06.24|KAWATA
-
「プログラミングは数学のできる本物のプログラマーに習ってほしい」
国語、英語、プログラミング言語のトライリンガル教育に力を入れる「YESインターナショナルスクール」。校長を務めるサイエンスライター竹内薫さんに、ユニークなカリキュラムやプログラミング教...
2025.05.30|工樂真澄
-
「コエテコEXPO2023秋(2日目)」レポート|AI時代に必要なプログラミング教育とは?子どもが楽しく継続できる...
プログラミング教育サービスと課題解決などのノウハウが集結するオンライン展示会「コエテコEXPO2023秋」。2日目は9名が登壇し、AIの進化が今後のプログラミング教育に与える影響や、こ...
2024.11.06|大森ろまん







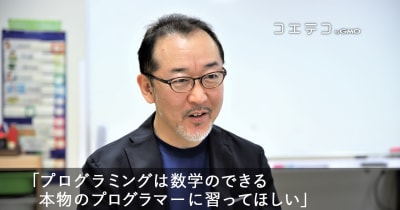

学習指導要領というのは、文部科学省が定めた「教育課程の基準」のこと。学校の教科書や時間割は、これを元につくられていますよ。