「寺子屋方式」驚きの指導法、2年連続でembotアイデアコンテスト受賞者を輩出するTENTO(テント)に話を聞いてみた
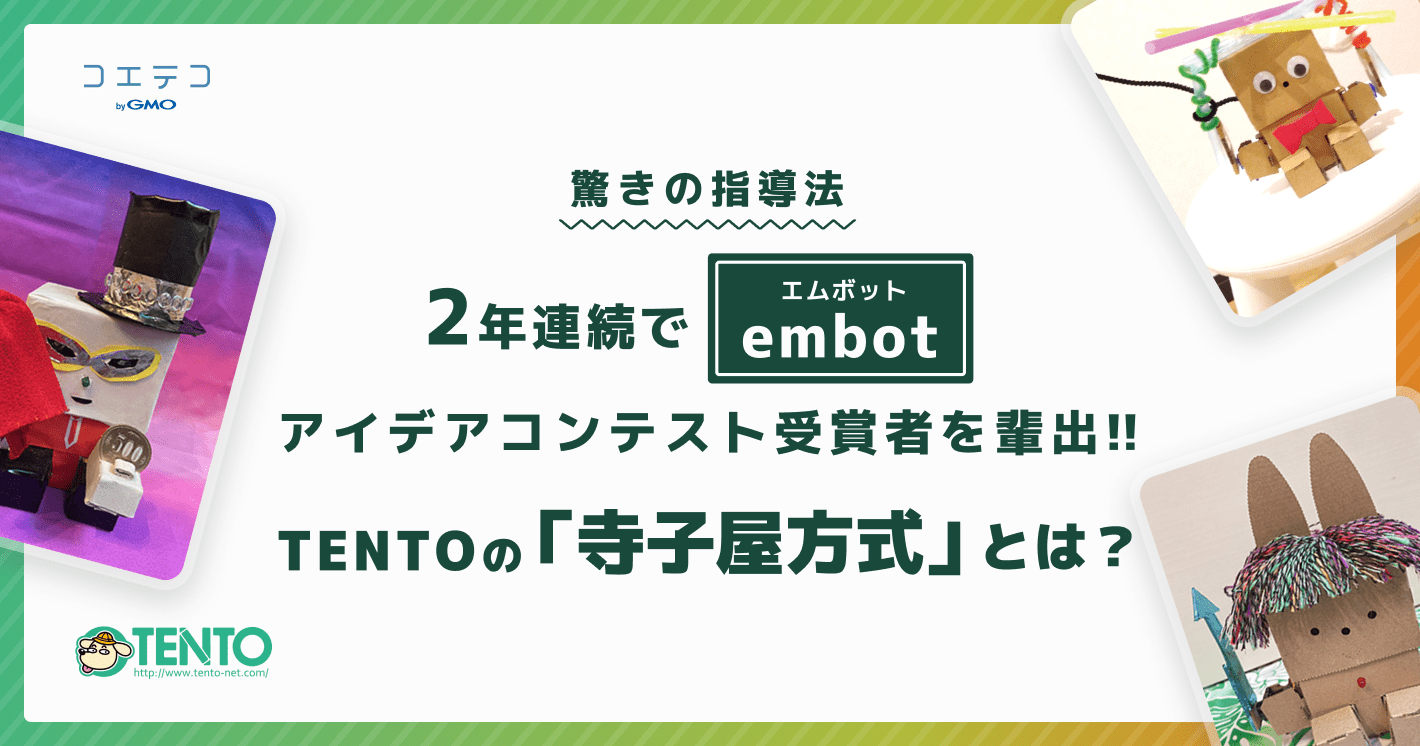
リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://embot-contest.com/ >
さて、そんなembotアイデアコンテストで、過去2回にわたり、複数の入賞者を出しているのがプログラミングスクールTENTO(テント)です。
今回はTENTO代表 竹林先生に、embotアイデアコンテストで好成績をおさめてきた理由や「寺子屋方式」と呼ばれる独自の指導法についてお話をお伺いしました。
embot/embotアイデアコンテストとは?
embotとは、セットに入っている本体と、思い思いの材料を組み立てて「自分だけのロボット」が作れるロボットキットです。専用のアプリでプログラミングすることで、さまざまな動きや音をつけることもできます。
『プログラミングのスキルを用い、アイデアを形にする”デジタルなモノづくり”に挑戦してもらいたい』という想いから始まった、embotアイデアコンテストは、今年で3回目の開催に。想像力を発揮すれば、なんでも作れちゃうのがembotの魅力なんです!

2020年embotアイデアコンテスト最優秀賞の作品。制作者の佐藤航くんはTENTO枚方教室の生徒さんです。
スターターキットだけでも可愛らしいですが、おうちにある材料を組み合わせれば、より個性的なロボットが作れるはず。専用アプリケーションはもちろん、無料で利用できるので、誰でも手軽に始められるのも魅力!ぜひ素敵なロボットを作ってコンテストに参加してみましょう。
それではいよいよ、embotアイデアコンテスト連続入賞スクール「TENTO」代表・竹林先生に、指導の秘訣をうかがいます!
失敗は成功のもと。大人が限界を作らない「寺子屋方式」がTENTOの核

――編集部
今日は、TENTOの生徒さん達がembotアイデアコンテストで好成績をおさめている秘訣や、TENTO独自の指導法について、代表の竹林先生にいろいろとお話を伺いたいと思います。まずは簡単に、TENTOプログラミングスクールについてご紹介頂けますか?
――竹林先生
ありがとうございます。私たちTENTOは、小学生から高校生までが学べるプログラミング教室です。教室は全国にあるのですが、細かなカリキュラムは教室によって異なるのが特徴です。
――編集部
教室ごとにカリキュラムが違うのですか?
――竹林先生
そうなんです。といっても、教室ごとに異なる、というよりも、ひとりひとりによってカリキュラムが違う、というほうが近いかもしれません。
TENTOは「寺子屋方式」の名前通り、リラックスしてプログラミングができる、自由な教室です。TENTOに通う子ども達は、自分達で自由に学ぶ内容を選ぶため、結果的にカリキュラムがバラバラになるのです。
もちろん、教室にはいろいろな教材をご用意していますし、最低限のベースになるカリキュラムはあります。ただ、「必ずこれをやりなさい」という方針ではなく、子ども自身に選択させるよう、各教室にお願いしているという形です。
――編集部
なるほど。たとえばですが、その子にはまだ難しいかな?というレベルでも、お子様の選択を尊重するということでしょうか。
――竹林先生
ええ。私は、子どもの成長に限界を求めたくないと考えていますので、なるべくお子様のご希望を叶えるようにしています。
なぜなら、限界を作るのは常に指導者側だからです。「こんな難しいことをやってもどうせ失敗するだけ」という風にね。大人が勝手に限界を設けてしまうことで、子どもがチャレンジする機会をつぶさないように、という考えがありますので、ご年齢に対して難しい内容であっても、本人がチャレンジしたい内容なら、どんどんやってもらいます。
――編集部
失敗する可能性が高いとわかっていても、チャレンジさせてみるのが大切なのですね。
――竹林先生
そうなんです。どんな子でも、年齢以上のレベルにチャレンジすれば、たぶん失敗するでしょう。
でも、うまく失敗をさせてあげることこそ、僕らの役目なんですよね。失敗こそ、新たな学びのチャンス。ですから、あえて失敗する機会をとりのぞくようなことはしません。
一部繰り返しになりますが、TENTOの「寺子屋方式」とは、いろいろな学年の子ども達がいる中で、それぞれが自由に学べるスタイルなのです。その分、どんなレベルの内容であってもサポートできるプロの講師陣が教室を運営しているのがTENTOの魅力と言えるでしょう。
embotの魅力は「プログラミングとものづくりが地続きなところ」

TENTO枚方教室の山本先生と生徒たち!そして代表の竹林先生がオンラインで共演♪
――編集部
ここまでのお話で、TENTOの指導方針の核となる部分がよく見えてきました。続いては、embotアイデアコンテストについて教えてください。
先ほど、取材をさせていただいたTENTO枚方教室からは大勢の入賞者が出ていますが、数あるロボットコンテストの中で、embotアイデアコンテストが優れていると感じる点を教えて頂けますか?
――竹林先生
embotアイデアコンテストは、名前に「アイデア」があるとおり、アイデアを重視しているところがいいですよね。
僕は、子ども達のクリエイティビティーをとても大切にしています。ものを作る、embotはロボット工作キットでありながら、素材を切ったり貼ったりする点で、普段の「ものづくり」と乖離していません。ダンボールという身近な素材がベースになっているので、子どもでも非常に扱いやすい。プログラミングとものづくりが地続きであるところが、とても優れていると感じています。
――編集部
プログラミングの大会というと、大人でも驚くようなハイレベルな作品が出てくるイメージがあります。いち保護者としては、「うちの子にできるかな」と不安になる点ではありますが……。
――竹林先生
確かに、プログラミングの大会の中には、優れたアルゴリズムだったり、難しいプログラミングをしていたりするかどうかを重視するものも多いのですが、私たちの教育方針では、完成度だけを重視したくはないのですね。
TENTOでは子ども達の将来の可能性を広げることが重要だと考えていますので、現時点でどれだけ複雑で難しいプログラミングができるかよりも、楽しく自由に、あくまでプログラミングに対するポジティブなイメージを持ってもらうことが大切であると考えています。
その点でも、ロボットのアイデアに着眼点を置いているembotアイデアコンテストは私たち教室の考えとも共通していると感じます。
――編集部
先ほど、竹林先生は失敗することが大事とおっしゃいましたよね。TENTO枚方教室の生徒さん達も、embotを作りながら失敗して何度もやり直して、ようやく完成したと話してくれました。
――竹林先生
ええ。失敗をしないように、と考えるのであれば、同じ教材で、テキスト通りに作れば失敗はしません。でも、それは貴重な学びの機会を失っていることになるのではないかと。
その点、embotはシンプルなキットでありながら、それぞれが自分で考え、それぞれのやり方で、違うものを作る仕様になっています。その過程において、当然ながら失敗をし、何らかの学びを得る。その特徴が、TENTOの方針にもぴったりマッチしているんですよ。
グッとこらえて、余計なことは言わない指導
――編集部embotコンテストに参加するための指導について、特に注意していることはありますか?
――竹林先生
普段の授業と同じく、コンテストに応募する作品についても、なるべく手を出さないようにしています。先生は辛いと思いますよ。当然プロの講師ですから、ここをこうすればずっと良くなる、こうすればより高度なプログラムが作れる、と分かっているわけです。
でも、グッとこらえて、余計なことは言わない。質問には答えるけれど、先生の方からアレコレと指図はしない。そんな自学自習が基本なんです。
――編集部
どうしても大人は、先回りして準備を手伝ってしまいがちですもんね。せっかくなら賞を取って欲しいと、お膳立てしてしまったり。
――竹林先生
ええ。でも、コンテストって、子どもが自分で参加することが何よりも大事なんですよ。高校野球なんかと同じ感じですね。予選に出る、試合に出ることが大事だし、結果が出て甲子園に行ったとなれば次の子ども達も「自分達も甲子園に行くぞ」となる。
embotアイデアコンテストも同じで、参加した子たちの話を聞くことで、やってみようかなという気になる。さらに入賞した子が出てくると、自分にもできるかもとやる気も高まります。これだけ入賞者が出てくれたのは、周囲から受ける影響、みんなと交流する中での効果が大きかったのではないかと思います。
子ども同士で交流し、作品がレベルアップ
――編集部自学自習という言葉が出てきましたが、TENTOではどのような指導法を実践しているのか、具体的に教えていただけますか?
――竹林先生
そのあたりは、実際に指導にあたられている先生に伺いたいところですね。(TENTO枚方教室の)山本先生、どうでしょう?
――山本先生
はい。先ほど竹林先生からもあったように、TENTOは寺子屋方式で、子ども達のコミュニケーションを大切にしています。枚方教室でembotの制作をしている時も、他の子が作ったものを見て刺激を受け、質問をしたり、話し合ったりしていたのが印象深かったですね。
――編集部
なるほど。みんなで話し合うことで、より完成度の高い作品ができあがっていったのですね。逆に、一人で取り組む形だと、少し難しいでしょうか?
――山本先生
いえいえ。embotはひとりでも、充分コンテストに応募できると思います。工作やプログラミングの方法もわかりやすく、動画コンテンツなども充実しているので、入口が広いためです。
ただ、コンテストに限らない話ですが、他の子から良い影響を受ける点で、教室などに所属するメリットはあるかもしれません。
――編集部
具体的には。
――山本先生
たとえば、枚方教室ではタイピングも大事にしているので、低学年の子どもであっても、すごく速い子もいるんです。ところがあるとき、高校生の生徒さんが入ってきて、タイピングで苦労されていて。
小学生からすると、高校生ってもはや大人ですよね。すると、無邪気に「なんでやろ、大人なのに」「なんで遅いんやろ」と口にしちゃうわけです。
高校生の生徒さんはそこで一念発起して、あっという間にタッチタイピングを身に付けました。そりゃあ、いざとなったら、高校生ですからね、すぐに追いつきます。
この出来事から分かったのは、「タイピングに慣れて早く入力できるようにならないと大変だよ」と指導するよりも、教室にいる子ども達の存在が闘争心に火をつけたり、やる気をアップさせたりしてくれること。もちろん、個人でも充分伸びる子はいますが、教室に所属することで、こうした好影響を受けられる可能性があるのではないでしょうか。
誰だってはじめは初心者。年齢にかかわらずビギナー体験を
――竹林先生(山本先生の話を聞いて)なるほど。寺子屋方式は、生徒の学年も異なり、やっていることもバラバラです。でも、そこが教育に好影響を与えるはずだ、と思っていたので、素晴らしいエピソードを聞けて安心しました。
1点、山本先生の話に補足しますと、こうした環境はモチベーションをアップさせるだけではなく、もうひとつ大切なことを学べる機会も与えてくれるんです。
――編集部
というのは?
――竹林先生
〝初心者〟という立場に慣れることです。人間、いくつになっても、何か新しいこと、新しい環境で物事をこなさなくてはならない場面が必ずありますよね。自分より若い人たちの中で、教えてもらいながら仕事を覚えることもあるでしょう。私達は永遠に、どこかで初心者となり得るわけです。
そう考えると、寺子屋方式で、学年も年齢もバラバラの中で学ぶことには大きな意義があるんじゃないかと。たとえば先ほどの高校生が、もっと小さい子にタイピングのスピードで負けるようなことが、社会でも起こりうる。そのときに、「なんで遅いんやろ」と言われてもヘコまずに、だったら早くなろうと頑張れるかどうかが大切だなと思うんです。
こういう体験を積み重ねておくことで、社会人になってから、どこかで初心者の立場に置かれても、周囲とコミュニケーションをとり、さまざまな人の中でも全く新しいことでもやっていけるだけの芯の強さが育まれるのです。
――編集部
確かに、誰でも最初は初心者ですもんね。小さな頃から、年齢に関わらず“初心者”の立場におかれる経験を積んでおけば、社会人になってから大きな強みになりそうですね。
オンライン授業は2つのスタイルから選べて安心

TENTOオンライン教室は毎週開講中です!
――編集部
ところで、TENTOではオンライン授業も受けられるそうですね。
――竹林先生
はい。オンラインには2つのスタイルがあって、寺子屋方式をオンラインで行うスタイルと、マンツーマンで行うスタイルからお好きな方を選べます。
――編集部
オンライン授業は自宅で受講できて便利な一方、embotをはじめとしたロボット系の教材では指導が難しいのでは、と思いますが……
――竹林先生
確かに、難しさはあります。たとえば、小型コンピュータのRaspberry Piなどは、先生と生徒でバージョンが違うこともあるうえ、基盤を見せてもらっても、パッと状況が分かりにくい。そういう苦労はあるのですが、なんとか工夫して対応しています。
――編集部
たとえばどんな工夫をしているのでしょうか?
――竹林先生
たとえば、生徒さんがカメラを2個使って、先生とうまくコミュニケーションをとるなどですね。オンライン授業は難しい面はありますが、授業を録画して繰り返し観られるメリットもあります。TENTOでは、オンラインでも講師と生徒達が積極的にやり取りしながら、プログラミング学習を進めていますので、安心して受講できるはずですよ。
TENTO竹林代表からのメッセージ
――編集部では最後に、TENTOへの入会を検討している保護者へのメッセージをお願いします。
――竹林先生
教室だけでなく、ご自宅でもぜひ、子ども達が自由にプログラミングを楽しめる時間を与えてあげて下さい。子どものうちのプログラミング教育はあくまで興味・関心を拓くきっかけですから、今現在、何ができるか?だけに注目するのではなく、何が将来につなげられるかを考えていただければ、きっと子どものためになると思います。
――編集部
自学自習スタイルで、子どもの興味・関心を大切にして、自由にプログラミングを楽しめるスクールっていいですね。コンテストで優秀な成績をおさめているのも、その自由さにあるのかもしれないと感じました。竹林先生、今日はありがとうございました!
embotは工作好きなお子さまへのプログラミング導入に最適!
竹林先生・山本先生のお話にもあったように、embotはプログラミングスクールの教材としても優秀です。- 工作好きなお子さまにアプローチできる
- 低学年の生徒でも扱いやすい
- 女の子も親しみやすいロボット教材
- 子ども同士のコミュニケーションも活発になる
作り方やプログラミングも簡単でわかりやすいので、低学年のお子様はもちろん、男女問わず取り組みやすいところもembotのメリットですね。洋服を着せたり、かわいくデコレーションしたりと、embotには女の子たちが大好きな要素もたくさん詰まっています。
ひとりひとりが違うロボットを作り、ひとりひとりが違うプログラミングを考えられる教育的効果もembotの特徴。とくにスクールでは、子ども同士が盛んに情報交換し、見せ合ったり相談したりする場面が展開しますので、コミュニケーションを重視する教室の教材としてもおすすめです。
ライターの感想
教室名のTENTOには、「情報化の嵐から子ども達を守るテント」という意味があるそうです。同時に、「ずっとテントに引き込もるのではなく、守り育てたら世界へ送り出す」のがTENTOのポリシーなのだとか。決して過保護になり、両腕に抱えるのではなく、大きなテントの下でいろいろな仲間と切磋琢磨し、好きなことを好きな形で学び、楽しい時間を過ごしていく。TENTOは、そんな懐の深い教室という印象を持ちました。自由でリラックスした雰囲気が、子ども達の想像力も創造力をも育み、embotのようなアイデア重視のコンテストでも良い成績を残しているのでしょう。
embotはお値段もお手頃で、教室の教材としてだけでなくご家庭でも購入しやすいのが大きな魅力です。プログラミングのアプリは無料でダウンロードでき、とっても簡単。夏休みの自由研究にもピッタリですね。素敵なロボットを作って宿題も完成!さらにコンテストに参加するワクワクドキドキをこの夏、ぜひお子さんに体験させてあげましょう!
embotアイデアコンテストの公式サイト、および、TENTOの紹介ページはこちら!気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://embot-contest.com/ >
TENTO(テント)の口コミや料金、カリキュラム情報をわかりやすく紹介!子供・小中学生向けプログラミング教室の特徴や体験レッスン情報も満載。Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン実施中!運営本部:TENTO
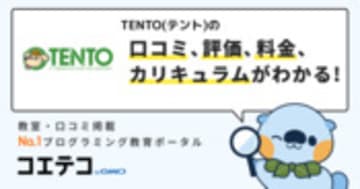
https://coeteco.jp/brand/tento >


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
(取材)「embotアイデアコンテスト」2年連続で入賞者を輩出、TENTO枚方教室のキッズに制作秘話を聞きました!
2019年・2020年と開催されたembotアイデアコンテストにおいて、2年連続で複数の入賞者を出しているTENTO(テント)枚方教室。 今回、コエテコではTENTO枚方教室の生徒さ...
2025.05.30|大橋礼
-
「embotアイデアコンテスト2021」が7月1日〜開催!プログラミングが学べるダンボールロボット「embot」で...
株式会社インフォディオは、embotアイデアコンテスト2021実行委員会と共同で「embotアイデアコンテスト2021」の開催を発表しました。すでにembotを持っているお子さんはもち...
2025.05.30|大橋礼
-
(取材)Crefus武蔵小杉校|2つ目の校舎をオープン!人気殺到の子ども向けロボット教室に突撃取材
Crefus(クレファス)はブロックでプログラミングを学べる人気の教室。Crefus武蔵小杉校は生徒が増えたことから武蔵小杉駅前に2つ目の教室をオープンしました。今回はCrefusの人...
2025.09.10|大橋礼
-
小学生が夢中になる!コードオブジーニアスジュニア・オンライン校の魅力に迫る
「コードオブジーニアスジュニア・オンライン校」は、オンライン環境で質の高い指導を提供するプログラミングスクール。今回、同校の運営責任者・中村さんと講師の三木先生にインタビューを実施し、...
2025.09.05|大橋礼
-
『未来の先生』は大学でどんな勉強をしているの? 畿央(きおう)大学 教育学部の取り組み
2020年から小学校でプログラミング教育が始まることになり、学校ではその準備が急ピッチで進められています。その中でも急がれるのは、子どもたちの指導にあたる先生を中心とした人材の育成です...
2025.05.26|工樂真澄






