フレネ教育は子どもの自由な思想を育む教育メソッド!導入されている学校は?
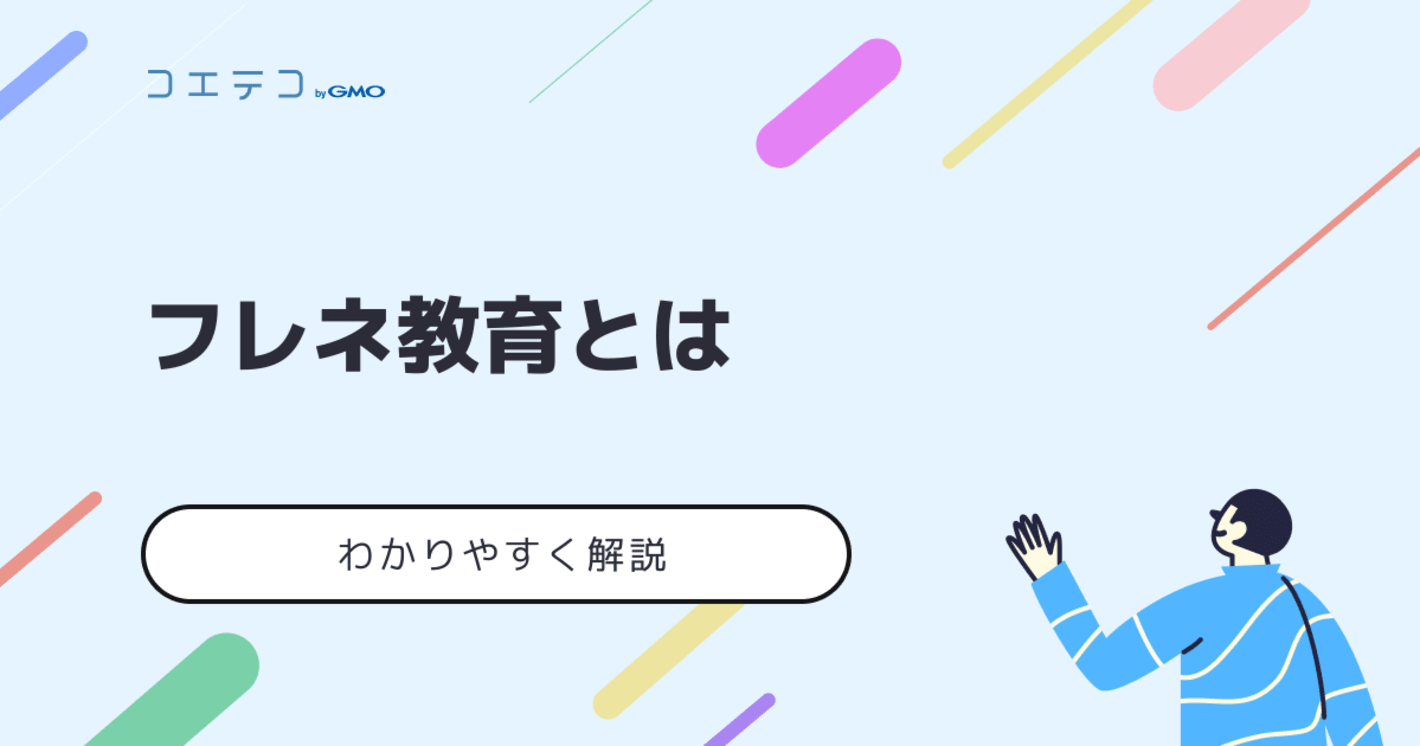
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
世界的に広がる教育メソッドのなかでも、注目を集めているのはフレネ教育です。子どもが主体となることを重要視するフレネ教育は、子どもの意欲を伸ばしやすいメソッドだといえます。
この記事では、フレネ教育が生まれた背景や特徴、導入されている学校について詳しく紹介します!
子どもの自由な表現を活かすフレネ教育が生まれた背景
フレネ教育は、教師であるセレスタン・フレネ(1896−1966)が考え出した教育メソッドです。1920年に南フランスの小学校に赴任したセレスタン・フレネは、教育現場に疑問を抱くようになります。当時の授業は、教科書の反復練習を行うばかりで、子ども達の学習意欲を削いでしまう内容でした。それによって学習意欲が低下した子ども達は、集中して授業を受けることが困難な状況に陥ります。そこで、セレスタン・フレネは子ども達に自然やさまざまな仕事場を肌で感じとってもらいたいと考え、散歩教室を始めました。すると、子ども達には活気が戻り、好奇心旺盛に教師に質問する姿もみられるようになりました。
散歩教室で学んだことや感じたことを、教室に戻ってからノートに書く自由作文を導入することで、子ども達は意欲的に読み書きするようになったそう。このような働きかけで子ども達に変化をもたらしたことが、フレネ教育の始まりだといわれています。
フレネ教育の特徴を知ろう!
フレネ教育には、大きく分けて4つの特徴があります。1つ目は、子どもの思いを言語化するための作文です。フレネ教育における学習の主軸は作文にあるため、自身が関心を寄せる対象をテーマに作文をすることで表現力を育みます。2つ目は、他の子どもの作文を共有し、多様な価値観に触れることです。他の子ども達の考えや視点を知ることで、新たな発見を得ることにもつながります。3つ目は、コミュニケーション能力を伸ばす対話です。フレネ教育では、朝の会や帰りの会においても議論をする時間が設けられることが特徴です。そして、4つ目は、1人1人の個性に合わせた学習計画です。年齢に合わせた教科書を用意するのではなく、子どもの学習レベルに応じた環境を整えることが重要とされています。
このようなフレネ教育の特徴は、子ども達の自由な表現を尊重し、活き活きと発言しやすい環境を構築しやすいといえるでしょう。
フレネ教育の授業内容
フレネ教育の授業では、子ども達が書いた作文が教材になります。どの作文を選ぶかは子ども達の投票で決定するため、「教材になるかもしれない」と考えて書く作文は自然と推敲が重ねられるでしょう。選ばれた作文は教材にするために、子ども達が共同作業で作り直しなどを行います。こうして制作された教材は、子ども達にとって興味関心が高まる内容となり、意欲的に子ども達が学びやすくなります。
また、「活動計画表」に沿って学習するフレネ教育では、子ども自身が学習計画を立てることが特徴です。学習の進捗を自らチェックし発表する場を設けることで、子どもの自信にもつながりやすくなります。
フレネ教育によって得られるメリット
フレネ教育は、子どもの興味関心を中心に学習が行われるため、自主性を育みやすいといわれています。自由作文を授業に導入することによって、自身の個性を発揮し、他者の思想を尊重する姿勢も学べます。また、学年が違う子ども達と共に学ぶフレネ教育では、相互理解の能力が向上しやすいとされています。低学年の生徒に対する思いやりが育めることも、フレネ教育のメリットだといえるでしょう。
フレネ教育のデメリット
フレネ教育のデメリットは、日本ではまだまだフレネ教育で学べる環境が少ない点です。フレネ教育は「モンテッソーリ教育」や「シュタイナー教育」に比べてメジャーではないことから日本国内では近くにフレネ教育を行っている学習施設がなく、フレネ教育を受けたいと思っても対応しているスクールが少ないのが現状です。また、フレネ教育は子ども達だけで学習プランを進められる訳ではなく、教師が学習計画を立てる時のサポートやプロデュースを行うため、教師が担う影響力が強くなります。そのため、教師によって教育で得られる効果に差が出ることが考えられます。
フレネ教育が導入されている学校や幼稚園
フレネ教育は、国内では以下の3校が導入されています。- ジャパンフレネ(東京都)
- けやの森学園幼稚舎・保育園(埼玉県)
- 箕面こどもの森学園(大阪府)
けやの森学園幼稚舎・保育園では週に2回、林のなかで過ごす時間を設けており、自然に触れる体験を大切にすることが特徴です。さらに、夏と冬にはキャンプが催され、子どもの自立心や仲間と協力する心を育みます。1~5歳までの子どもが関わりをもつ縦割り保育を採用しているため、子ども同士がコミュケーションの方法を工夫する姿が見受けられるそうです。
小学校1年生から中学校3年生までの子どもが通えるのは、箕面こどもの森学園 です。小学部では、読み書きや計算などを個別学習で学んでいきます。そして、毎学期ごとにテーマを決め、クラス全員で学びを追求し、テーマに関連した場所や人に話を聞きに行くなどの取り組みを行っています。
フレネ教育は、表現することが得意な子どもを育てる
自由作文を取り入れるフレネ教育は、日ごろから自身の考えをアウトプットする習慣を身に付けられます。日本ではフレネ教育を導入している学校は少ないですが、興味がある場合には見学会などに参加するようにしたいですね。

Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
探究学習とは何のこと?学習内容や事例を徹底解説!
多様なテーマについて、自分で考え答えを導き出す探求学習。探求学習の多くは、フィールドワークを行い生徒自身が情報を得るスタイルになっています。この記事では、2022年から高校の授業で導入...
2025.12.19|コエテコ byGMO 編集部
-
サドベリースクールとは?教育の中身やおすすめを解説
子どもの自主性や個性を重んじるのは、サドベリー教育です。カリキュラムや学年、クラスなどが設けられていないサドベリースクールでは、学ぶ内容や学校のルールを生徒自身が決定できます。この記事...
2025.08.20|コエテコ byGMO 編集部
-
反転授業とは?メリットとデメリットを徹底解説
反転授業を導入することが決まった場合、従来の授業とどのように異なるのか不安に感じる人もいるでしょう。反転授業はオンライン授業が進められるなかで、導入される学校も増えてきました。この記事...
2025.08.20|コエテコ byGMO 編集部
-
ドルトンプラン教育を導入しているのはどの学校?特徴や歴史を詳しく解説
子どもの多様性を尊重し、学習の意欲を高められる学習法として注目を集めるのはドルトンプラン教育。日本では導入している学校は数少なく、入学をためらうケースもあるでしょう。この記事では、ドル...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
ルーブリックは子どもを正しく評価できる方法?特徴と導入例を解説
教育現場で、新たな評価方法として注目を集めるルーブリック。アクティブ・ラーニングが授業に導入されるようになり、ルーブリックが採用される大学や高校も増加傾向にあります。この記事では、ルー...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部














