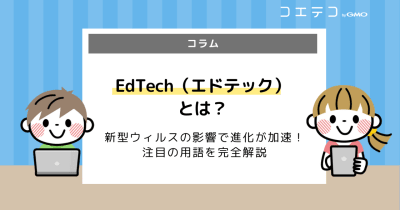ルーブリックは子どもを正しく評価できる方法?特徴と導入例を解説

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
そこで、2010年以降から注目を集めているのがルーブリックと呼ばれる評価方法です。新しい評価方法であるルーブリックは、子ども達の"考える力”を評価しやすいと教師からも評価を得ています。
この記事では、ルーブリックの特徴や導入例をわかりやすく解説します。
ルーブリックの特徴を知ろう!
ルーブリックは、表を用いて子どもの学習達成度を評価する方法を指します。この評価方法は、ポートランド州立大学の名誉教授を務めるダネル・D・スティーブンスが提唱しました。通知表では子どもを評価する範囲が狭いことが難点でしたが、ルーブリックではテストの点だけに囚われない評価をすることが可能です。具体的には、ルーブリックを導入することで発表する場での生徒のパフォーマンスや学習する姿勢に対して適切な評価が行えます。
通知表と最も異なるポイントといえるのは、生徒自身や他の生徒が評価を行う点です。生徒同士の相互評価や教師の評価も含めるため、多角的な視点から生徒の長所や成長を評価できるといえるでしょう。
ルーブリックでは生徒の何を評価するか?
ルーブリックで評価するのは、以下のような点です。- 知的獲得力
- 表現力
- 創造力
- 問題解決力
- 組織的行動力
- 口頭コミュニケーション力
- 文章コミュニケーション力
評価基準が複数に分かれていることから、生徒自身は「自分に何が足りないのか」を明確に知る術にもなるでしょう。
ルーブリックとアクティブ・ラーニングの関係性
ルーブリックが導入された背景には、「アクティブ・ラーニング」の認知が広まったことがきっかけとされています。アクティブ・ラーニングとは、体験学習やグループディスカッションに重点を置いた能動的に学ぶ学習方法を指します。従来のテストのような評価方法では、アクティブ・ラーニングにおける学習は評価することが難しい点が課題でした。そこで、生徒の学習に対する姿勢を評価しやすいルーブリックが採用されるようになりました。生徒自身が評価を行うルーブリックは、アクティブ・ラーニングにおける振り返りを行いやすい面があります。
ルーブリックにおけるメリットとデメリット
今後、国内で広がりをみせることが予想されるルーブリックには、メリットとデメリットが存在します。あらかじめポイントを押さえておきましょう。ルーブリックを導入するメリット
ルーブリックを導入することで、生徒が能動的に学びやすくなるといわれています。これまでに点数化することが難しかった生徒の"表現力”や"意欲”に対して、公正な評価が行えます。意欲的に授業に参加していた生徒にとっては、自身の姿勢を評価してもらえることで、学習意欲の向上にもつながるでしょう。また、教師にとっては、詳細に評価方法が明記されているルーブリックを用いることで、生徒を客観視しやすいというメリットもあります。さらに、教師の観点に変化をもたらすこともルーブリックは効果的とされており、授業のねらいが明確になることで授業の質そのものが向上しやすいといわれています。
ルーブリックを導入するデメリット
世界的に注目を集めるルーブリックですが、評価表を作成することが難しいのがデメリットとされています。日本では、ルーブリックの制作方法を模索している段階だといえます。製作するうえで基盤となるルーブリックが少ないため、実際に授業に導入する際にはハードルが高いことが課題だといえるでしょう。ルーブリックの導入例
日本国内では、大学や高校で実際にルーブリックが導入されています。ここでは、実際のルーブリックの導入例を紹介します。関西大学におけるルーブリックの導入例

関西大学における「プレゼンテーションに関するルーブリック」では、評価の観点を以下のA~Dの4種類に分けています。
- A:主張・論点の提示
- B:視覚情報・資料の扱い
- C:プレゼンテーション・全体の構成
- D:発表の態度
レポートの課題が出される際にルーブリックも配布されるため、プレゼンテーションの際に「何を配慮するべきか」が生徒側からも理解しやすいメリットがあります。
ルーブリックを活用している企業事例
教育現場などで利用されているルーブリックは、大手旅行会社である株式会社JTBは研修制度に利用されています。JTBでは、研修制度の評価にレベル1からレベル4までの項目を設定しています。それぞれの項目では、レベル2が必要な到達レベル、レベル3が研修で身に付く力、レベル4が研修後に目指す姿という形で評価を設定しています。社員はルーブリック評価を確認しながら自分で目標設定をした上で研修を受講し、さらに研修後には学んだ内容の活用法を検討します。
研修にルーブリック表を設定することで、社員はそのレベルを目指して研修に取り組むことができます。
令和の日本における学習スタイルをサポートするルーブリック
学校教育において教育改革が推し進められている昨今では、ルーブリックが今後の日本の学習スタイルに沿った評価方法として定着していく可能性もあるでしょう。授業に導入する教師だけではなく、生徒や保護者もルーブリックについて正しく認識し、理解を深めておくようにしたいですね。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
ドルトンプラン教育を導入しているのはどの学校?特徴や歴史を詳しく解説
子どもの多様性を尊重し、学習の意欲を高められる学習法として注目を集めるのはドルトンプラン教育。日本では導入している学校は数少なく、入学をためらうケースもあるでしょう。この記事では、ドル...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
反転授業とは?メリットとデメリットを徹底解説
反転授業を導入することが決まった場合、従来の授業とどのように異なるのか不安に感じる人もいるでしょう。反転授業はオンライン授業が進められるなかで、導入される学校も増えてきました。この記事...
2025.08.20|コエテコ byGMO 編集部
-
EdTech(エドテック)とは?なぜ注目されているのかを解説
EdTech(エドテック)とは、教育現場にテクノロジーを取り入れ、さまざまなイノベーションを起こす動きやサービスのことです。学校現場のICT化が急速に推し進められ、EdTechへの注目...
2025.07.17|コエテコ byGMO 編集部
-
アクティブラーニングはもう古い?文部科学省が推進する理由や事例を紹介
教育が変わろうとしています。先生が一方的に授業をし、生徒は受け身で聞くだけ……というパッシブ(受動的)な学びではなく、生徒がみずから学ぶアクティブ(能動的)な授業に変わろうとしているの...
2025.11.12|コエテコ byGMO 編集部
-
必修科目「情報Ⅰ」に備えよう!共通テストや定期テスト対策も詳しく解説
2020年に小学校、2021年に中学校でプログラミング教育が全面的に実施されました。一方高等学校では既に2003年から「情報」が導入されましたが、2022年度には科目が再編され「情報Ⅰ...
2025.11.27|コエテコ byGMO 編集部