(イベントレポート)Kids VALLEY プログラミングサマーキャンプ2022 渋谷のITキッズが語る!プログラミングの魅力とは!?
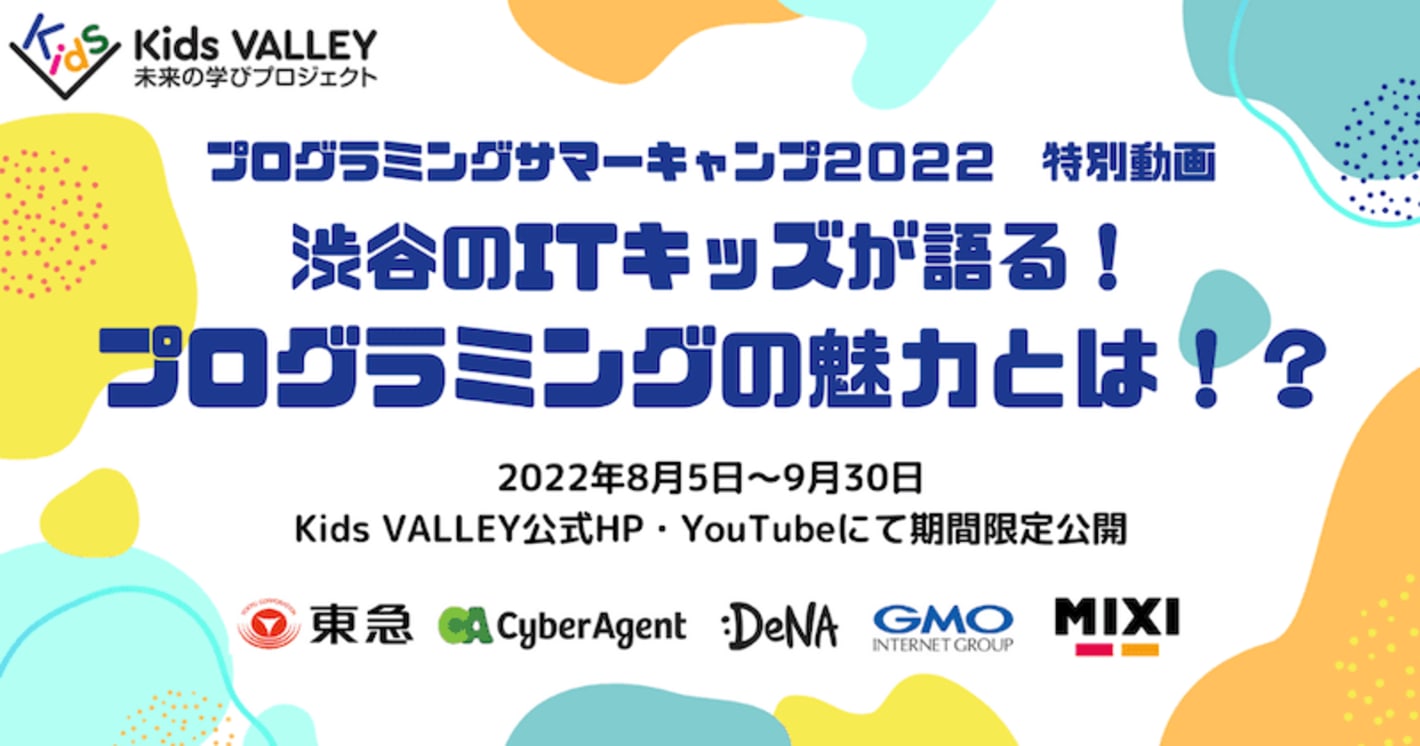
東急、渋谷のIT企業サイバーエージェント、DeNA、GMOインターネットグループ、ミクシィが、2022年の夏休みに全国小中学生向けのプログラミングイベント「プログラミングサマーキャンプ2022」を開催!オンライン・オフラインで、プログラミングを楽しく学ぶ機会を提供します。

https://coeteco.jp/kidsvalley_2022 >
例年夏休み期間に開催されているこちらのイベント。2022年は渋谷会場や企業オフィス、オンラインでイベントが行われ、渋谷会場に行ける人はもちろん、全国から小・中学生や保護者が参加できました。
更に、今年はKids VALLEYが後援の「渋谷区プログラミングコンテスト」2021年度受賞者による特別動画「Kids VALLEY プログラミングサマーキャンプ2022」も期間限定で公開中!
動画では渋谷のITキッズが、プログラミング作品やプログラミングの魅力について熱く語っているほか、Kids VALLEYのプログラマー講師のメッセージもあり、盛りだくさんのコンテンツとなっています。
当記事では、そんな「Kids VALLEYプログラミングサマーキャンプ2022特別動画」を詳しくレポート!子どもたちが語る様子とともに、動画の魅力をたっぷり伝えていきます。
Kids VALLEYサマーキャンプ2022の特別動画を期間限定公開中
2022年8月に開催された「Kids VALLEY 未来の学びプロジェクトpresentsプログラミングサマーキャンプ2022」。今年はリアルイベント・オンラインイベントに加えて、Kids VALLEYが後援する「渋谷区プログラミングコンテスト」の2021年受賞者が出演する特別動画が公開されました。子ども目線でプログラミングの魅力を伝えてくれる内容となっていて、これまでプログラミングに触れたことのないお子さんも「プログラミングっておもしろそう!」と思えるような内容となっています。
具体的には、受賞作品の紹介や、作品づくりのきっかけ、今後プログラミングで作りたいもの……など。一人ひとりのお子さんがプレゼン形式で発表している様子や、インタビューに堂々と答えている姿に驚かれる方も多いでしょう。
動画では、以下5名のお子さんの受賞作品とプレゼンテーション、インタビューを見ることができます。
お名前 |
学年 | 作品名 |
| 岡本理久さん | 小学6年生 | ゴミ拾いカー |
| 中村颯来さん | 小学4年生 | 野生動物の命を救え! |
| 五十嵐駿真さん | 小学6年生 | 上からの石から逃げろ |
| 大塚弘貴さん | 中学1年生 | エラーのマルのプラットフォーマー |
| 富永駿也さん | 中学1年生 | ウィルスキラー |
動画内にはKids VALLEYで講師を務めるプログラマー・成瀬さんからのプログラミングをはじめたい子へのメッセージなどもあり、プログラミングに興味があるお子さん・保護者の方は必見です。
なお、本動画は2ヶ月間の限定公開のため、興味のある方はぜひお早めに視聴してください。公開は好評につき、公開を12月末まで延長いたします!の予定です。また「2022年渋谷区 プログラミングコンテスト」も同日まで応募できるため、動画を見てチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
ここからは、お子さん一人ずつの詳しい作品内容やインタビューの様子をご紹介していきます。
受賞者の作品紹介・インタビュー
小学6年生・岡本理久さん「ゴミ拾いカー」

プレゼンテーターの1人目は、小学6年生の岡本理久さんです。これまでプログラミングスクールに通ったことはなく、何を作るか、どうやると動かせるのか、全てが手探りの状態からスタートして、作品「ゴミ拾いカー」を作り上げたのだそう。

ゲームを作ったきっかけ
「ゴミ拾いカー」のゲームを作ったきっかけは、毎朝のランニングであると、理久さんは話します。
岡本理久さん:
僕はほぼ毎日、朝ごはんの前にランニングをします。休日で長いときには10km以上走りますが、朝早い渋谷の街は、たいていゴミがあふれています。
僕は年に何度か、ボランティアで街の清掃を手伝っていますが、ゴミがたくさん集まると、まるでゲームのようで、楽しくなります。このようなことから、ゴミを拾うことと自動車ゲームを組み合わせてみました。
作品紹介
理久さんが作った作品はこちらです。

岡本理久さん:
道に落ちているマスクや紙くずなどゴミと車がぶつかると、ゴミ拾いが完了します。ゴールラインを越えたところで、ゲームは終了。タイムと拾ったゴミの数によって、36通りもの評価が表示されます。
苦労したのは、最後の結果画面で、変数を使ってゲームの達成度を表すところです。

今後の展望

岡本理久さん:
ゴミ以外の障害物を準備したり、道を複雑にしたりと、追加したい機能もたくさんあります。今後は僕のプログラミング能力の向上だけでなく、ゴミ拾いの楽しさが広がり、街の美化向上にもつながれば良いなと思います。
この写真のような、いつでもきれいな渋谷の街が、僕は大好きです。
インタビュー

——「ゴミ」をテーマに作品を作ったきっかけは?
岡本理久さん:
渋谷の街のゴミがあふれているのを見ていたので、ゴミ拾い関係のゲームを作ってみようかなと思いました。
——作品を作る上で一番がんばった点は?
岡本理久さん:
最後の結果の画面で、変数を使って評価を表示していったのが、がんばった点です。
——どんな人にこのゲームで遊んでほしい?
岡本理久さん:
ゴミ拾いに参加していない人とか、逆にゴミを捨てている人です。
小学4年生・中村颯来さん「野生動物の命を救え!」

受賞者の2人目は、小学4年生の中村颯来さんです。ハキハキと自己紹介をして、趣味や得意なこと、将来の夢を紹介してくれます。

ゲームを作ったきっかけ
颯来さんの作品は、「野生動物を救え!」というタイトル通り、野生動物の命を救うことを考えられる内容となっているのだそう。
中村颯来さん:
失われゆく野生動物種と、その動物を救う方法について考える作品を作ってみたいと思いました。なぜ野生動物が失われていくのか、どうすれば救うことができるのか、動物が好きな僕はその答えが知りたかったです。
専門家によると、この50年間、森林伐採や大気汚染などによって、野生動物種が68%減っています。その動物を救う方法について、考えるチャンスに繋げるゲームを作ってみました。
作品紹介
ゲームは、プログラミング学習ツール「Scratch(スクラッチ)」を使って作成したのだそう。遊ぶだけではなく、野生動物についても学べる内容となっています。

中村颯来さん:
好きな野生動物を選び、動物に関する情報を読んでもらいます。それからゲームスタートボタンを押します。
真ん中にいる動物に、いろいろな危険なものが近づいてきます。動物の命は3つ。危険なものにあたったら、命が一つずつなくなります。命が全部なくなったらゲームオーバー。ゴールにたどりついたら成功です。

今後の展望

中村颯来さん:
今度は飲み水が家までくる仕組みをシミュレーションしたいと思います。これからも、サイエンスのプロジェクトをスクラッチを使って勉強したいです。
算数とサイエンス、プログラミングが大好きです。これからもがんばって、世界を変える人になりたいです。
インタビュー

——なぜコンテストに応募してみた?
中村颯来さん:
2020年、コロナで学校が長く休みで、Scratchを勉強するいいチャンスになりました。
——作品を作るうえで一番がんばった点は?
中村颯来さん:
ゲームを作るとき、バグがたくさんあったので、難しかったです。でも、バグが起きても集中して解決できるようにがんばりました。
——プログラミングの好きなところは?
中村颯来さん:
自分の想像したことを作れるのが大好きです。外国語を習うときと同じく、コンピュータ言語を習うことで、コンピュータとコミュニケーションをとれることも大好きです。
インタビューで「自分の想像したことを作れるのが大好き」と話す颯来さんから、プログラミングの無限の可能性を教えてもらえました!
ゲームが入り口にあると、たくさんの人が問題に気づくきっかけにできそうですね。
小学6年生・五十嵐駿真さん「上からの石から逃げろ」

小学6年生の五十嵐駿真さんの作品は「上からの石から逃げろ」です。駿真さんはゲームを作って、実際に友達にプレイしてもらって改善を加えていったのだそう。機能が豊富で、発表の随所からゲームへのこだわりを感じられました。
自己紹介後は、早速作ったゲームをプレイして見せてくれます。
作品紹介
ゲームには、ポーズ機能やゲーム進行に関するお知らせ機能もあるのだとか!こだわりの作品であることがわかります。
五十嵐駿真さん:
上から降ってくる石をよけながら、「?(はてな)」をとってポイントをためるゲームです。矢印キーで左右に動いたり、ジャンプをしたりして、少しでも多くのポイント獲得を目指します。2回だけバリアが使えます。石に当たるとゲームオーバーになります。


五十嵐駿真さん:
すべての動くキャラクターに対して、ポーズのメッセージを受け取ったら動きを止めるようにプログラムをして、ポーズ解除のメッセージを受け取ったら普段どおりの動きができるようにプログラムを入れるのが大変でした。

五十嵐駿真さん:
楽しくわかりやすくするために、左下に「100ポイント達成」や「バリアは出せません」などのお知らせが出るようにしました。また、便利かな、と思い、左上に現在の時刻が出るようにしました。


五十嵐駿真さん:
自分で試してみて、様々な機能を追加しました。自分で色々な発見をしながら作ったのですが、新しいことができるようになると楽しかったです。
できたゲームを、学校の友達に休み時間にやってもらって、改善点を見つけたり、クラスのポイントランキングを作ったりしたことが、プログラミングをするモチベーションになりました。
インタビュー

——作品を作ったきっかけは?
五十嵐駿真さん:
学校でタブレット係だったこともあるのですが、雨の日、教室にずっといてひまだったので、その時間を楽しくできないかなと思って作ってみました。
——作品を作るうえで一番がんばった点は?
五十嵐駿真さん:
ポーズ機能をつけたところです。自分でやってみて、ずっとやるゲームなので、止められないと席を離れられないので、ポーズ機能をつけました。
——プログラミングをはじめたきっかけは?
五十嵐駿真さん:
4年生のおわりころ、プログラミングゼミをさわってみて、おもしろいな、と思いました。
作ってプレイして、試行錯誤。なかなか大変そうに感じますが、友達にやってもらったり、ポイントランキングを作ったりするのも、とても楽しそうですね!
自分の作った作品をプレイしてもらえることも、プログラミングの魅力ですね。
中学1年生・大塚弘貴さん「エラーのマルのプラットフォーマー」

続いての受賞者は、中学1年生の大塚弘樹さんで、作品名は「エラーのマルのプラットフォーマー」。こちらのゲームは、なんと無限スクロールできるゲーム!
他にもたくさんのこだわりが詰まった作品となっています。

作品紹介
カラフルな丸がかわいい背景、ギミックなど、ゲームの世界が細かく作り込まれていて、弘樹さんの作品に込める思いが伝わってきます。
大塚弘樹さん:
「エラーのマル」というキャラクターが、スクロールしている床に乗り継ぎ、バネなどを使って、うまくマグマをよけながらゴールに向かうという、スクロールのプラットフォーマーゲームです。

大塚弘樹さん:
こだわったポイントは、背景の丸や無限スクロール。それと効果音などを入れるのもこだわりました。
インタビュー

——作品を作ったきっかけは?
大塚弘樹さん:
コンテストがあるので、応募しようと思いました。そこから自分の好きなゲームを作ろうと思って作りました。
——プログラミングをはじめたきっかけは?
大塚弘樹さん:
きっかけは、あるプログラミングスクールの体験会です。そこでアカウントをゲットして、いろいろ始めるようになりました。
——作品を作るうえで一番がんばった点は?
大塚弘樹さん:
がんばったところは、スクロールのプログラムや、BGMを入れたのもこだわりです。他にもいろんな細かいところまで作りました。
こだわりのギミックや背景、効果音などがとても細かく作られていて、作品にかける思いが伝わってきます。
「自分の好きなゲームを作るのは楽しい」ということが、とてもよくわかりました!
中学1年生・富永駿也さん「ウィルスキラー」

最後の受賞者は、中学1年生の富永駿也さんです。2020年からはじまり、2022年になっても依然続くコロナ禍。そんな中で作った作品が、今回の「ウィルスキラー」です。

ゲームを作ったきっかけ
「ウィルスキラー」はシューティングゲーム!コロナ禍が続き、ストレスがたまっている人も多いのではないでしょうか。ストレス解消にも、おすすめのゲームですね。
富永駿也さん:
小学校の夏休みの課題の中にプログラミングコンテストがあって、もともとプログラミングに興味があったので、せっかくなので応募してみようと思ったからです。
ウィルスを退治するコンセプトのゲームを作った理由は、コロナ禍であまり自由に生活できていないと思ったからです。例えば学校行事が中止になったり、旅行に行くのが制限されたりしました。だからこのゲームでウィルスを倒して、コロナのストレスを発散してほしくて作りました。
また、学校で「フォートナイト」というゲームがはやっていて、フォートナイトみたいに武器を切り替えられるシューティングゲームを作ってみたいと思って作りました。
作品紹介
小学3年生からプログラミングをはじめた駿也さんが、プログラミングゼミで、1ヶ月ほどの期間で作成したゲームです。武器の設定が細かく、楽しくプレイできそうですね。
富永駿也さん:
このゲームは、紫色の土管から出てくるウィルスを、銃で射撃して倒す狙撃ゲームです。銃は4種類あります。


富永駿也さん:
弾がなくなったら、上からランダムな時間に、ランダムな場所に宝箱が降ってきます。


富永駿也さん:
操作方法はシンプルです。十字キーで移動。スペースキーで弾がうてます。数字キーの1〜4で銃の種類を変更できて、Zキーで爆弾を投げられます。

富永駿也さん:
敵に当たると、ダメージを受けて半透明になり、半透明の間はダメージを受けません。敵はたまにジャンプすることもあり、その時間はランダムです。HPがゼロになってしまうとゲームオーバーとなります。
ステージ数が上がるにつれて敵の数も多くなるので、迎え撃つのが大変になります。
一番苦労したところは、各ステージを設計するところです。大変でしたが、毎回同じ形のステージにすることを実現したかったので、自分で考えた通りの動きができたときは、とても嬉しかったです。

プログラミングをはじめたきっかけ
富永駿也さん:プログラミングは、3年生ぐらいのときに放課後に友達とやってみておもしろかったので、はじめました。
プロゼミは他の人が作った作品を実際にプレイしたり、コードを見たりできるので、遊んでみておもしろかった作品のコードをマネしているうちに、いろんな動きができるようになりました。
今後の展望

富永駿也さん:
もし次に作るのなら、他の難しいプログラミング言語を学んで複雑なゲームにしたり、効果音やBGMも入れて、よりおもしろくしたいです。
インタビュー

——コンテストに応募したきっかけは?
富永駿也さん:
夏休みの課題の中にプログラミングコンテストがあって、プログラミングにもともと興味を持っていたので挑戦しました。
——作品を作るうえで一番がんばった点は?
富永駿也さん:
各ステージを設計するところで、そこが一番プログラムが必要となりました。
——プログラミングをはじめたきっかけは?
富永駿也さん:
3年生のころに、放課後に友達とプログラミングをやっていたところ、おもしろかったので、興味をもってやりはじめました。
身近な問題や話題が、作品作りのヒントになるのですね!
きっかけは「プログラミングゼミ」なのだそう。興味のある方は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか?
Kids VALLEY講師・成瀬さんのインタビュー!

5名の受賞者によるプレゼンテーション・インタビューのあとは、Kids VALLEY講師でもあるGMOインターネット株式会社の成瀬さんのインタビュー・メッセージを見ることができます。
——子ども達の作品を見た感想は?

成瀬さん:
いろんな作品があったので、一言で表すのは少しさみしいのですが、全体を通して私が思ったことは、1から10まで自分で考えて形にして、更にコンテストまで応募するということができていることがすばらしいということです。
その経験をしている人はわずかです。これからこの経験が生きてくると思います。自信を持ってくれたら、と思います。
——プログラマーの仕事内容はなんですか?
成瀬さん:
そうですね、プログラマーと一口に言っても、本当にいろんな働き方があるのですが、私が一番よくやる仕事は企画している方がいて、その方の「こうしたい」という要望を、コンピューターとプログラムを使って叶える仕事です。
——プログラミングをはじめたのはいつですか?
成瀬さん:
私自身は社会人になってから転職をしており、実際に始めたのは25、6歳ぐらいのころです。みなさんが小学生から取り組んでいるのに比べると、非常に遅く始めたことになります。
小学校からプログラミングという世界に触れることができるのは、すごくうらやましいと感じています。
——プログラミングは社会でどう活用されているのですか?
成瀬さん:
私たちの生活を豊かに、生活のちょっとしためんどうなことを解決するために、時間を節約するためにプログラムが使われているイメージがあります。
——プログラミング=ゲームのイメージが変わりますね。
成瀬さん:
教えていく中で変わってきたこととして、最初の1年目・2年目ですと「プログラミングってなんのためにやりますか?」という質問をすると「ゲーム」という言葉が出てくるんですよね。
でも最近は先生の顔をうかがってかはわかりませんが、「生活を豊かにする」とか「私たちの生活を便利にする」という言葉が、ちらほら出てくるようになりました。
これは、コンピュータを使うことで、生活を豊かにできる、ということをみんなが気づいてきたのかな、と思います。
——プログラミングの魅力はなんですか?

成瀬さん:
人は奉仕の精神というか、誰かの役に立つとすごく嬉しいんですよね。自分でなにかを考えて、それを実現して、いろんな人に使ってもらう。例えば便利にするとか楽しんでもらう、という考え方・楽しみ方があります。
オタク的な話になりますが、私自身はプログラミングに対してアーティスティックな側面を感じています。どういうことかというと、プログラミングって、結局文章なんですよね。みなさん文章を読むときに、美しい文章って聞いたことありますよね。文章は美しくできるんですよ。ということは、プログラムも美しくできるんですね。
プログラムの美しさが何かというと、機能美を追求して、将来にわたって使われるプログラムを作る。このことに快感を覚えています。
——これからプログラミングを始める子へメッセージ

成瀬さん:
コンピュータ上のことなので、失敗しても良いんです。とにかく動かしてみて、少し動きを変えて動かす。トライ&エラーするのが、プログラミングを覚える一番の近道かな、と思います。
——これからコンテストに挑戦してみる子へメッセージ
成瀬さん:
冒頭にお話したとおり「1〜10まで作る経験」というのは、本当に得がたいものです。それを実際に経験して、応募しようというところまでこぎつけるのは、すごい努力だと思います。
このことは、絶対無駄にはなりません。例え応募したものが入賞しなかったとしても、その経験自体が、まず得がたいものであるということを、ぜひとも認識してください。

受賞者のITキッズから視聴者へのメッセージ
動画のラストは、受賞者のITキッズたちからの視聴者へのメッセージです。岡本理久さん:
アイデアをよく考えて、それをちゃんと形にあらわせるように、プログラミングするのをがんばっていってください。
中村颯来さん:
プログラミングを使って、想像した自分だけの作品を、ぜひ作ってみてください。
五十嵐駿真さん:
プログラミングはすごい楽しいので、みんなもとっておきの作品を作って応募してみてください。
大塚弘貴さん:
好きなものや、自分が作りたいって思って、熱中して作れるようなものを作ってみたら良いと思います。
富永駿也さん:
プログラミングに興味を持っていない人もいるかもしれないんですが、プログラミングはとても楽しいです。自分で思ったとおりにすることができるので、はじめて夢中になってもらえたらすごく嬉しいです。
まとめ
動画の内容は以上となります。プログラミングにはじめてチャレンジしたお子さんや、以前から取り組み続けているお子さんから、たくさんの熱量を感じられる内容となっていました。「プログラミングって楽しい!」「自分の想像が実現できる!」など、プログラミングの魅力もたっぷりと感じられましたね。また、Kids VALLEY講師でありプログラマーの成瀬さんのお話からも、プログラミングのすばらしさや、挑戦することの大切さを教えてもらうことができました。
動画を見て「プログラミングをはじめてみたい」と感じたお子さん・保護者の方は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか?「2022年渋谷区 プログラミングコンテスト」も、2022年9月30日まで作品を募集中です。
コエテコでは、子ども・大人問わずプログラミング学習に関する情報を発信しています。興味を持たれた方は、ぜひ他の記事も読んでみてください。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
(イベントレポート)『プログラミングサマーキャンプ2021 トークセッション』
2021年8月20日(金)、『プログラミングサマーキャンプ2021 トークセッション』が行われました。このイベントは渋谷区と、渋谷区に集う大手IT企業が官民連携で取り組む『Kids V...
2024.11.06|夏野かおる
-
DeNA主催のKids VALLEYイベント「プログラミングサマーキャンプ2019」レポート
2019年8月4・5・7日にKids VALLEY「未来の学びプロジェクト」による「プログラミングサマーキャンプ2019」が開催。このイベントは、渋谷区の小中学生を対象にしたプログラミ...
2025.06.24|KAWATA
-
小学生がIT企業に潜入⁈プログラミングサマーキャンプレポート~スイカ割りのプログラム化に挑戦~
2019年8月4・5・7日にKids VALLEY「未来の学びプロジェクト」による「プログラミングサマーキャンプ2019」が開催。このイベントは、渋谷区の小中学生を対象にしたプログラミ...
2024.11.06|Yukiko
-
Scratchを使ってゲームを開発!サイバーエージェントでの「ゲームクリエイター体験講座」レポート!
2019年8月4・5・7日にKids VALLEY「未来の学びプロジェクト」による「プログラミングサマーキャンプ2019」が開催。このイベントは、渋谷区の小中学生を対象にしたプログラミ...
2024.11.06|千鳥あゆむ
-
(イベントレポート)Kids VALLEY 2020|今年はオンライン活用で全国の小・中学生向けのプログラミングイ...
2020年8月、東急、サイバーエージェント、DeNA、GMOインターネット、ミクシィの5社は「Kids VALLEY 未来の学びプロジェクト presents プログラミングサマーキャ...
2024.11.06|千鳥あゆむ


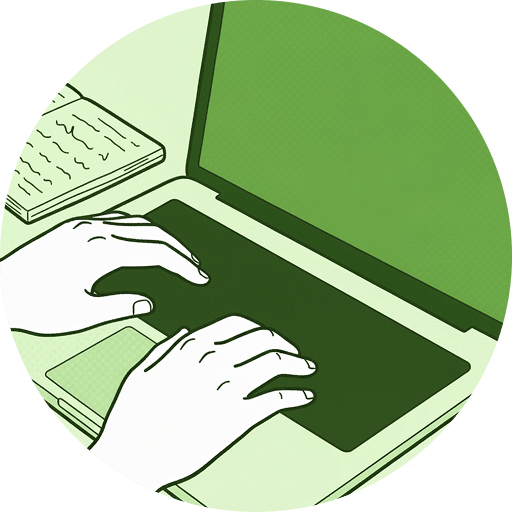






「プログラミング」と聞くと難しそうに感じますが、未経験で手探りの状態から一つの作品を完成させた理久さんからチャレンジの大切さを教えてもらいました!
興味を持っている方は、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか?