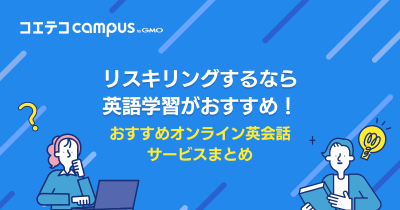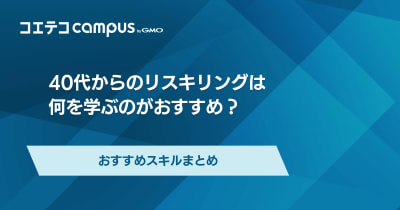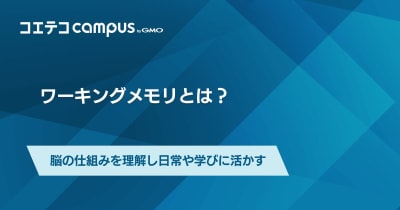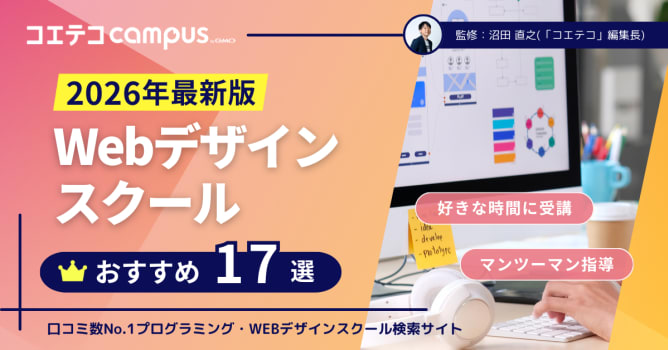学童保育指導員の仕事内容や資格の取り方を解説
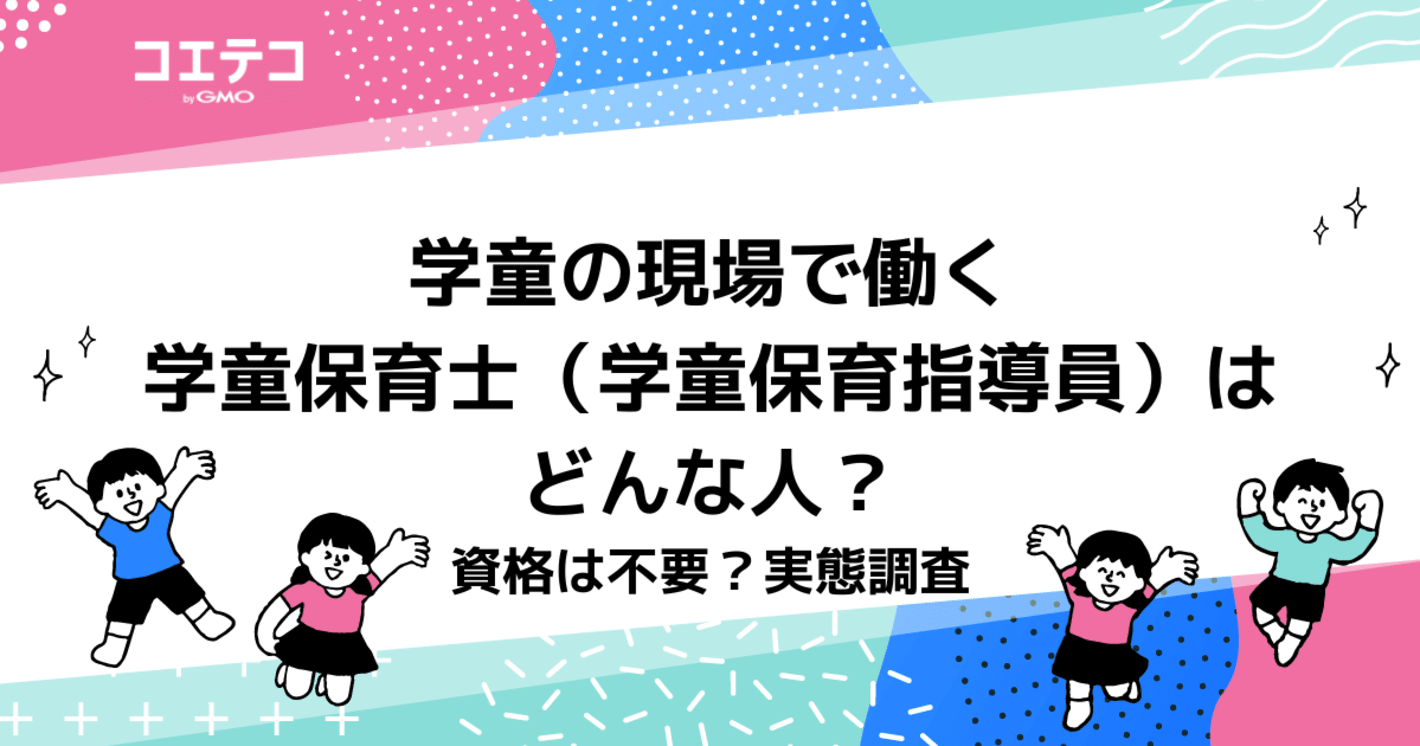
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

小学校再開までの間、朝から晩まで子どもたちを預かり、安全・安心を守ってきたのが、学童保育指導員の方々です。
この記事では、まだまだ知られていない公設学童保育の現場で働く人たちに注目。どんなお仕事をしているのか、解説します。
学童保育の指導員の現状・実態・課題
学童保育とは、共働きやひとり親家庭の小学生を、放課後や長期学校休業日に保護者にかわって保育をすることです。児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、全国の市区町村で学童保育は実施されています。
学童保育が行われる場所を「学童保育所」と言いますが、区市町村によって呼び方は様々です。
「学童クラブ」「放課後キッズクラブ」など地方自治体によって違います。
その学童保育で児童に接する学童保育士は、「学童保育指導員」とも呼ばれています。
学童保育士(学童保育指導員)とは?仕事内容と役割
学童の基本的な内容は、学校が終わって通所してきた児童が、遊んだり宿題をしたりするのを見守り、安全を確保することです。子どもたちは学童保育の施設に到着すると、宿題をして、おやつを食べて、遊んで過ごします。保育園と異なり、同じ場所で40~60人に子どもが過ごします。
複数の子どもたちが集まれば、ケンカも起きるしトラブルもあります。
子どもの変化に気づき、思いや感情を受け止めながら、仲裁に入り、子どもたち自身で解決できるように指導員は見守ります。
そのためには、一人ひとりの子どもの性格や家庭環境を理解し、子どもとの信頼関係を築いていかねばならなりません。
6~12歳の子どもたちは発達段階も異なります。発達段階に応じた関わり方も必要です。
子育て経験があれば誰にでもできるわけではない、大変なお仕事です。
出退勤時間などは施設や働き方によってまちまちで、学校の先生のように勉強の指導は行いませんが、施設によってその職務は異なる場合があります。
季節ごとにイベントも行なわれます。
施設は、学校がお休みの土曜日や、春・夏・冬の長いお休みの間も開設をしています。
小学校臨時休校中は朝から開校していました。
関連記事:保育士転職エージェントのおすすめ
関連記事:保育士転職サイトのおすすめ
学童指導員に資格は必要?2015年より放課後児童支援員資格が新設

学童に勤務する人の中で資格を持っている人を「放課後児童支援員」と呼び、資格を持っていない人を「学童指導員」と呼んでいます。
内閣府の「子ども・子育て支援新制度」では、学童保育施設1カ所に付き職員は2人以上、そのうち1人以上はこの「放課後児童支援員」でなければならないと定められています。
保育士や社会福祉士、教員資格等を有するか、高卒以上で2年以上児童福祉事業に従事している人が、都道府県が実施する研修を受講することで資格を取得でききます。
厚労省が発表した2020年7月1日時点の放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の最新状況では、放課後児童支援員等の数は、16万5725人(前年比1万2311人増)です。
職種内訳は、放課後児童支援員が9万5871人(前年比 3034人減)、補助員が6万9854人(前年比1万5345人増)です。
放課後児童支援員9万5871人のうち、認定資格研修を修了した者は86,677人(前年比16,198人増) 認定資格研修修了率90.4%となっており、認定資格研修が広く浸透している、と言えます。
関連記事:ゼロから始める保育士への道
放課後児童支援員の資格取得方法
「放課後児童支援員」になるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。- 保育士の資格を有する者
- 社会福祉士の資格を有する者
- 高校卒業後、2年以上児童福祉事業に従事した者
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者
- 大学で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
- 大学で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する 課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、大学院への入学が認められた者
- 大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当 する課程を修めて卒業した者
- 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
- 高校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めた者
先の厚労省の公表によると、放課後児童支援員の主な資格の状況は次のようになっています。
- 保育士:2万3917人(24.9%)
- 高等学校卒業者等で、2年以上児童福祉事業に従事した者:3万1727人(33.1%)
- 教育職員免許状を有する者:2万4461人(25.5%) 等
- ※( )内は放課後児童支援員の総数(9万5871人)に占める割合
関連記事:保育士になるには?やりがいや方法を徹底解説
子どもに関わる資格が取れるおすすめ通信講座4選
子どもに関わる仕事において、資格持っていると就職や転職の際に優遇されるケースもあります。また資格取得の勉強を通じて、子どもとの接し方や児童保育に関する専門的な知識を習得していくこともできるでしょう。
ぜひ本項目で紹介する、おすすめ通信講座も参考に、資格取得を目指してみてはいかがでしょうか。
関連記事:保育士資格通信講座おすすめ4選!
ユーキャン保育士講座

受講生の約9割は初学者が占めており、初めての方でも無理なく学びやすいよう工夫が凝らされたオリジナル教材が提供されています。
全10回の添削課題もあり実技試験対策もバッチリなので、万全の体制で資格試験に挑めるでしょう。
添削課題はすべてWeb添削に対応しているから、詳しい回答と解説がスムーズに返ってきます。
コンピュータ分析を受けられるため、自分では気付きにくい弱点も一目瞭然です。
ユーキャン保育士講座が気になる方は、公式サイトの「相性診断」を試してみてはいかがでしょうか。
保育士講座が自分に向いているのかを気軽にチェックできます。
キャリカレ

- 保育士
- チャイルドコーチングアドバイザー
- ベビーシッター
- 乳幼児救急救命支援員
- 乳幼児リトミックインストラクター
キャリカレの特徴は、わかりやすい教材が用意されていてサポートが充実している点です。
初心者でも理解しやすいように、テキストではやさしい表現と適度な文章量で解説されています。
イラストや図解が多いため、直感的に理解しやすいでしょう。
添削サポートや質問サポート、学習フォローなど、効率よく学びやすく挫折しにくい環境も整っています。
開業したい人向けのホームページ制作支援や学習修了後のフォローもあり、身につけたスキルを活かしやすいのも魅力的です。
複数の講座を受講したい場合は、学び放題プランがおすすめ。
140講座を年額26,400円(税込)で好きなだけ学べます。
LINEやチャット、メールから24時間問い合わせできるため、お気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
ヒューマンアカデミー チャイルドマインダー講座

少人数保育のスペシャリストであるチャイルドマインダーとしての活躍に向けて、安全管理能力・健康管理能力・緊急時対応能力・食育・遊び環境などの多様な知識習得を目指します。
なお講座は動画視聴型のため、何度でも好きな時間に受講可能。
受講期間は6ケ月間、7,600円〜/月で受講できます。
習い事価格で受講できる点も嬉しいポイントと言えるでしょう。
なお受講後は、グループ内の人材サービスとの提携を活かした、就職・転職全面サポートを受けられます。
受講から就職・転職まで一貫して支援を受けられるため、ヒューマンアカデミーでの学びを確実にキャリアとして活かしていくことができるでしょう。
アガルートアカデミー 保育士試験(提供終了)
難関資格試験の通信講座・予備校であるアガルートアカデミーが提供する『保育士試験』は、短期間で保育士試験に合格した現役保育士講師が指導に携わる講座です。全コンテンツが動画視聴になっているため、自分のペースで学び進めていくことができるでしょう。
なおコンテンツには、短期・一発合格に必要不可欠なノウハウが詰まっており、多くの受講生が最短合格を実現しているとのこと。
また、学習経験者・再受験を目指す人はもちろん、初学者・初受験の人にとっても1からしっかりと知識習得に励める内容になっています。
公式サイトからは、約1.5時間分のサンプル講義を視聴できます。
どのような講義が展開されるのか事前に知れるため、入会・購入後に後悔することもないでしょう。
保育士試験受験を目指す上で自分にピッタリの勉強方法を探している人は、ぜひアガルートアカデミーも選択肢の1つとして検討してみてはいかがでしょうか。
放課後児童支援員に対する研修
放課後児童支援員になるための条件を満たした人は、都道府県が行う研修を修了することで、初めて「放課後児童支援員」として認定されます。基本的な研修は、合計約24時間の講義・演習が、2~3か月の期間で行われます。
また、保有する資格によっては、研修科目の一部が免除になる場合もあります。
研修科目は次の6科目です。
- 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解
- 子どもを理解するための基礎知識
- 放課後児童クラブにおける子どもの育成支援
- 放課後児童クラブにおける保護者・学校・地域との連携・協力
- 放課後児童クラブにおける安全・安心への対応
- 放課後児童支援員として求められる役割・機能
6~12歳の子どもたちは発達段階も異なります。発達段階に応じた関わり方や保護者や地域との連携など、様々な専門知識と経験が、学童保育の現場では求められているのです。
学童保育士(学童保育指導員)さんの処遇改善に向けて

これには2つのねらいがあります。
1つめは、指導員の勤続年数や研修実績等に応じた賃金改善に必要な費用を、国県市が補助し、一般的に他業種に比較して低いといわれている学童保育指導員の賃金を上げること。
2つめは、指導員の学びに応じた賃金制度を実施しやすくすることにより、保育の質を高めることです。
処遇改善を通じて、長く働き続けられる見通しがあれば指導員確保にもつながり、学童保育が抱える人手不足問題を解決する糸口になります。
より優秀な指導員さんが働き続けることで、学童保育の質の向上も期待できます。
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業とは?
「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」とは、放課後児童支援員の勤続年数や研修実績等に応じた賃金改善に要する費用が補助されます。補助率は国1/3、都道府県1/3、市町村1/3です。
具体的には、
- 事業所長(マネジメント)的 立場にある勤続年数10年以上の 放課後児童支援員で年額37万2千円(月額約3万円補助)
- 育成支援の内容の向上を担うため、 より専門性の高い研修を受講した勤勤続年数5年以上の放課後児童支援員で年額24万8千円(月額約2万円補助)
等の内容になっています。
しかし、放課後指導員のキャリアアップが進められている一方で、気になる点もあります。
先ほどの厚労省が発表による、2020年7月1日時点の放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の最新状況を見ると、放課後指導員の人数を3034人減らし、補助員を1万6198人増やしています。
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善が進められていますが、補助員さんは、契約社員やパート・アルバイトさんが中心で、今報酬変更はありません。
放課後児童支援員キャリアアップに向けた研修の内容
キャリアアップ事業における「研修」には2種類あります。1つめは、先の放課後児童支援員に対する研修です。
2つめは、勤勤続年数5年以上を対象とした「より専門性の高い研修」です。
都道府県や市町村が実施または委託する研修で市町村が適当と認めた人を対象に、「放課後児童支援員等資質向上研修事業」に基づく研修と同程度の内容を学びます。
各市町村の放課後児童支援員キャリアアップ事務局が企画しますので、 地域の保健センター長が講師となり「災害時の対応や新型コロナウィルス感染予防」の講義や、地域NPO法人による「いじめや虐待への対応」など、それぞれの地域の課題をタイムリーに学べます。
具体的には下記のとおりです。
- 実践発表会、ワークショップ形式の事例検討
- 安全指導と安全管理・危機管理、育成支援の記録
- 遊びや製作活動・表現活動
- いじめや虐待への対応
- 発達障害児等配慮を必要とする子どもへの支援
- 子どもの人権と倫理、個人情報の取り扱いとプライバシー保護
- 家庭における養育状況の理解
等々、より専門性の高い研修を受講し、より高度な技術を学んだうえで、キャリアアップの道が開かれてきました。
学童の地域格差

放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の補助率は国1/3、都道府県1/3、市町村1/3。
日本弁護士連合会による2017年度のデータによると、放課後児童健全育成事業を実施している市町村の数は1614、処遇改善等事業を実施している市町村の合計が297、①非常勤を含む職員の賃金改善に必要な費用の一部を補助する事業のみを実施している市町村は192、②常勤職員を配置するための追加費用の一部を補助する事業のみを実施している市町村は38、①②いずれの事業も実施している市町村は67です。
処遇改善事業やキャリアアップの実施状況が市町村で異なることは、学童保育の「質」の面での地域格差に直結する問題です。
放課後児童支援員の待遇に関する状況が広く知られることで、処遇改善事業やキャリアアップを実施する全国の市町村の増加につながることを期待しています。
関連記事:民間学童保育おすすめランキング!公立学童との違いも解説
まとめ
子どもたちにとって、学童保育所は家庭に代わる毎日を過ごす「生活の場」です。学童保育指導員さんは、子どもを近くで見守ってくれる頼れる大人であり、親代わりにもなります。その仕事や役割の重要性が認知され、処遇改善とさらなるスキルアップが進めば、子どもたちがより安全・安心に過ごせる豊かな放課後の時間をつくることができるでしょう。
WRITERこの記事を書いた人
RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
リスキリングするなら英語学習がおすすめ!人気の理由も解説
一人ひとりの経験や能力を仕事で活かす方法の一つとして、リスキリングが注目されています。新たなスキルを取得することで、現在の仕事や時代の変化に応じてより良いキャリアプランを設計できます。...
2025.11.17|コエテコ byGMO 英語編集部
-
40代からのリスキリングは何を学ぶのがおすすめ?おすすめスキル3選
新たな職に就くために必要なスキルを学び直すこと、と定義される「リスキリング」。2021年に経済産業省によって提唱されたもので、働き方の多様化が進む現代において非常に注目されています。し...
2026.01.05|コエテコ byGMO 編集部
-
ワーキングメモリとは?脳の仕組みを理解し日常や学びに活かす方法
ワーキングメモリとは、情報を一時的に記憶するだけではなく、情報を操作し、思考や判断、行動に活用する機能のことを指します。このワーキングメモリの能力は、仕事や日常生活の精度や効率に大きな...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
無料でリスキリングするには?おすすめ講座13選を徹底比較
近年、昇給やキャリアアップ、転職を考えている人の間で注目されているリスキリング。最近は個人でリスキリングを始める人も多いようです。独学の場合スクールや教材を利用するのが一般的なため、「...
2025.12.15|コエテコ byGMO 編集部
-
パソコンスキルがないと仕事ができない?必須スキルの時代に!
求人情報でよく見かけるのが「基本的なパソコンスキル」という条件です。いったいどんなパソコンのスキルが「基本」なのでしょうか。 今回の記事ではパソコンスキルがない方向けに、意外と知らな...
2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部