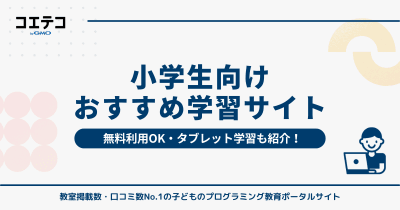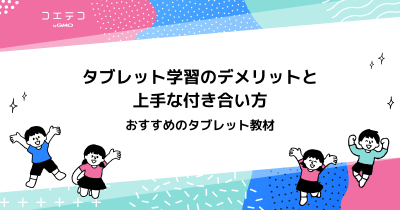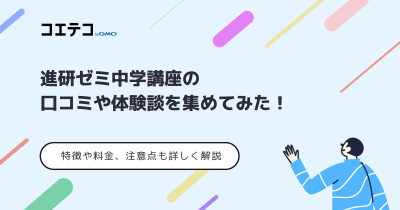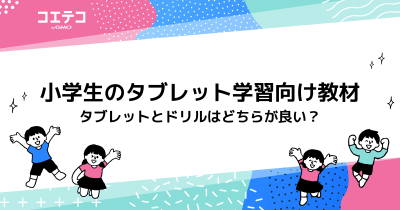小学生向け算数ドリルおすすめ11選!ハイレベルも【2025年最新】
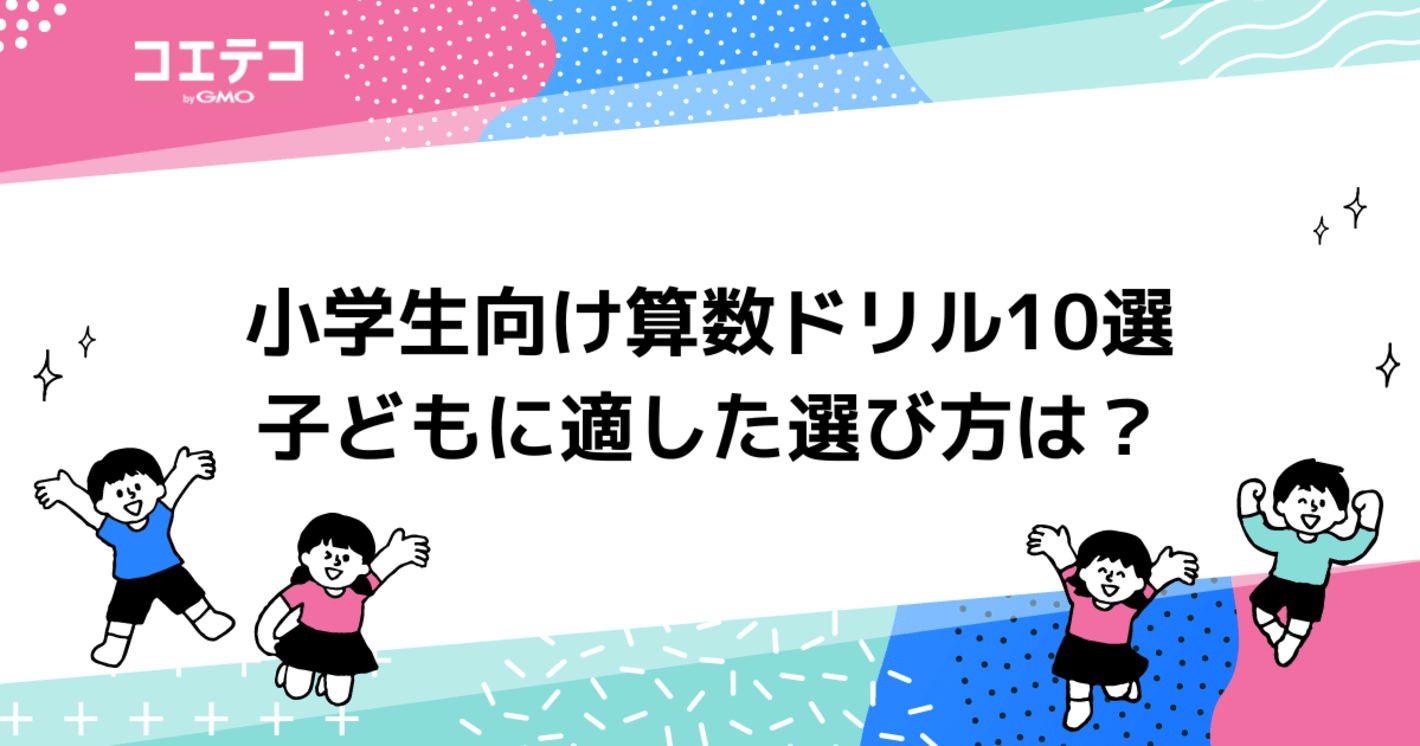
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
小学校から配られる算数のプリントに手こずっていたり、その反対に物足りなさを感じる場合は、自宅で算数ドリルに取り組むことが理解促進につながるでしょう。
この記事では、どんなドリルがあり、どのような基準で選べば良いのかを紹介します。
小学生向け算数ドリルの選定基準

①学年で選ぶ
自宅学習で使うドリルは、子どもの学年で学ぶ単元が網羅されている問題集であれば、漏れなく理解を深めることができるでしょう。文部科学省の資料をもとに、学年別の主な学習内容をまとめました。
| 学年 | 数と計算 | 図形 |
| 1年生 | ・個数を比べること/個数や順番を数えること ・1桁のたし算とひき算 など |
・形とその特徴の捉え方 ・方向やものの位置 など |
| 2年生 | ・2分の1や3分の1などの簡単な分数 ・2桁のたし算とひき算 ・かけ算(九九) など |
・三角形、四角形 ・正方形や長方形の面で構成される箱の形 など |
| 3年生 | ・万の単位、10 倍、100 倍、1000 倍 ・3桁や4桁のたし算とひき算 ・2桁や3桁の数字に1桁や2桁の数字をかけるかけ算 ・1桁や2桁のわり算 ・小数や分数 など |
・二等辺三角形 ・正三角形 ・角 ・円、球 など |
| 4年生 | ・億、兆の単位 ・概数が用いられる場合、四捨五入 ・1桁〜3桁までのわり算 ・小数のたし算やひき算 ・小数を含むかけ算やわり算 ・同分母の分数のたし算やひき算 など |
・直線の平行や垂直の関係 ・立方体,直方体などの立体図形 ・平面図形の面積 ・角の大きさ など |
| 5年生 | ・整数の性質( 偶数、奇数/約数、倍数) ・小数のかけ算やわり算 ・異分母の分数のかけ算やわり算 ・数量の関係を表す式 など |
・平面図形の性質 ・立体図形の性質 ・三角形、平行四辺形、ひし形及び台形の面積の計算による求め方 ・立体図形の体積 など |
| 6年生 | ・分数のかけ算やわり算 ・文字を用いた式 など |
・縮図や拡大図,対称な図形 ・円の面積 ・角柱及び円柱の体積 など |
②学習の目的で選ぶ
自宅で算数を学習するときは、理解を深めるためにも目的を明確にしておきましょう。- 学校の授業の予習や復習をしたい
- たし算、ひき算、かけ算、わり算の計算力を安定させたい
- 三角形の面積を求めるような図形問題を解きたい
- 中学受験に向けた算数問題に慣れたい
それぞれ、目的によって選ぶべき問題集やドリルも変わってくるでしょう。
学習目的を明確にするには、子どもが算数とどう向き合っているかを確認する必要があります。
授業の内容を理解できているか話を聞いてみたり、テストの結果を確認したりして、算数自体が得意なのか不得意なのか、文章問題だけが苦手なのかといった現状をよく理解してあげましょう。
また、自宅学習用の教材は、子どもが取り組みやすいかどうかといった意見を取り入れながら選ぶと、自習も効果的に進むはずです。
関連記事:小学生の家庭学習におすすめ教材12選徹底比較!やり方も徹底解説
③伸ばしたい能力で選ぶ
学習したい目的よりも、もっと具体的な能力を伸ばしたい場合もあります。多くのドリルは学年ごとに作られており、該当学年で学ぶ内容が総合的に掲載されています。
そのなかで「かけ算とわり算」「図形問題」「文章問題」といった単元に分かれているパターンが一般的です。
バランス良く算数力を伸ばすのであれば、こうしたタイプのもので問題ないでしょう。
同じタイプのドリルのなかから1冊を選ぶ際は、解説が詳しいか、一日でこなす問題量が妥当かなどをチェックしてあげることが大切です。
より具体的な能力を補強したいときには、単元に特化したドリルを選んでも良いでしょう。
ひき算が苦手ならひき算のみの問題集、計算ミスが多いのであればたし算、ひき算、かけ算、わり算を多く解ける教材、算数的な思考力を伸ばしたいのであればパズル系やクイズ系のドリルを選ぶといったように、伸ばしたい能力にフォーカスした教材選びを検討しましょう。
小学生向け算数ドリルおすすめ11選
算数ドリルには、キャラクターと一緒に解いていくもの、量をこなすもの、短時間の積み重ねを重視したもの、中学受験を見据えたものなどなど、様々な種類があります。特色を打ち出し、人気を得ている問題集を紹介します。
学年、算数の学習目的、伸ばしたい能力という3つの基準と照らし合わせながら、子どもに向いている教材を選びましょう。
関連記事:小学生向けオンライン算数塾おすすめ9選!中学受験対策も
すらら
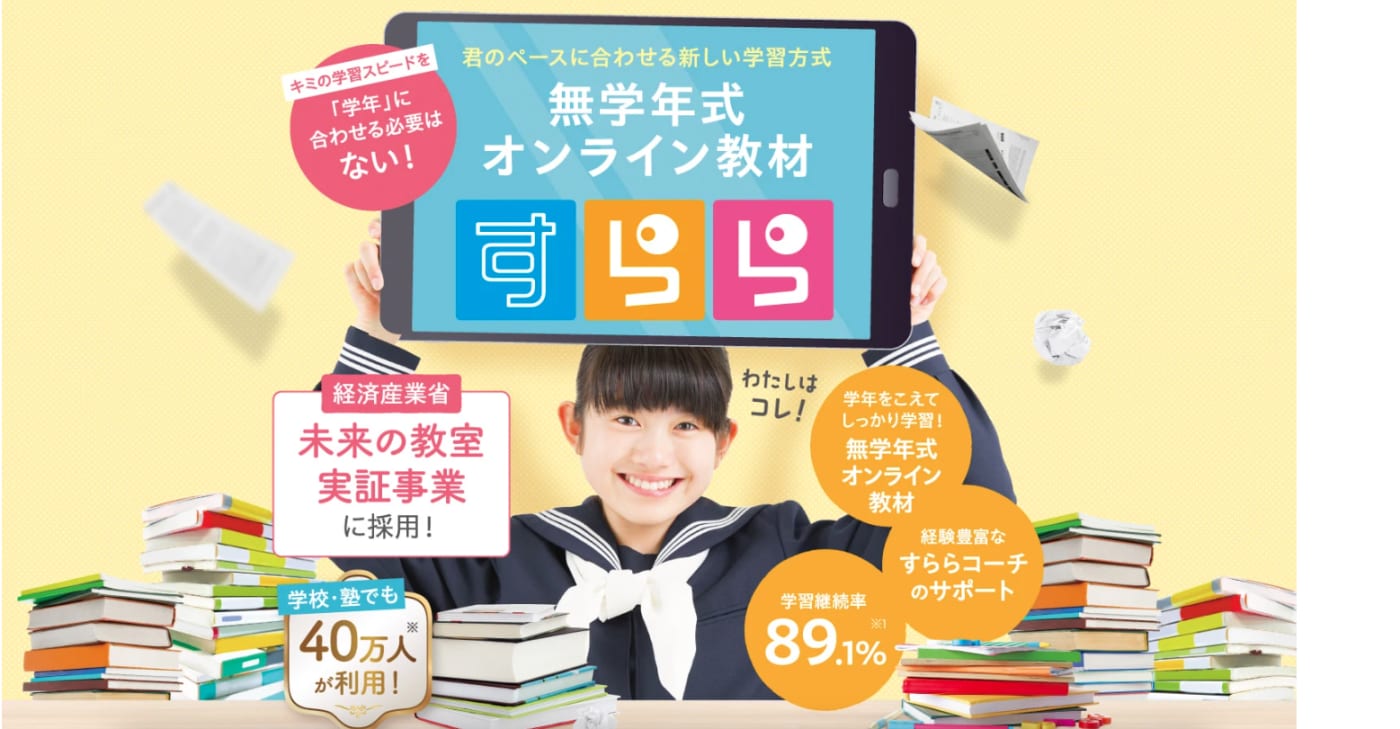
無学年式のカリキュラムを採用しているため、お子さんが自分のペースで学習を進めたり、必要に応じて過去の内容に戻ったり、あるいは先に進んだりといった柔軟な学び方ができます。
理解が遅れている部分をしっかりと補いながら、自信を持って次のステップに進めるでしょう。
AIを活用した対話型のドリルは、一人でもスムーズに進められる設計で、子どもたちの「わかった!」という達成感を引き出します。
またゲーミフィケーションの要素を取り入れているため、学習がゲーム感覚で進行し、学習意欲を高める効果があります。
自らのペースで、楽しく確実に算数の力をつけたいお子さんにとって、すららは最適な学習パートナーとなるでしょう。
「うんこドリル」算数シリーズ(文響社)
うんこを擬人化した可愛いキャラクターやうんこ型の空欄などとともに数字になじんでいく人気シリーズです。種類も様々なものがあります。1ページ取り組むごとに「できたねシール」を1枚貼っていったり、付属のカスタマイズシールを使ってがんばりに応じて自分だけのスペシャルなキャラクターを作ったりと、楽しみながら算数に向き合えるのが特色です。
「うんこドリル 九九 5・6さい」1078円
「うんこドリル すう・たんい・ずけい 小学1年生」1078円
「うんこドリル 数・たんい・図形 小学2年生」1078円
「うんこドリル たし算・ひき算 小学3年生」858円
ほか
「陰山英男の徹底反復 百ます計算」(小学館)
2002年に発売されてから高い人気を続けるロングセラー教材で、立命館小学校副校長や立命館大学教授を務めた経験のある陰山英男氏が手がけています。たし算、ひき算、かけ算、わり算で、百ますを埋める各プリントが2週間分セットになっており、同じ問題を毎日解き、2週間続けることで算数の基礎力を着実に養います。
定価は660円です。
学年ごとに算数力をつけるのであれば、同じ著者による「陰山メソッド 徹底反復 新版 算数プリント 小学校1~6年」や「陰山メソッド 徹底反復 新版 計算プリント 小学校1~6年」などもおすすめ。
「早ね早おき朝5分ドリル」計算シリーズ(学研プラス)
前述の陰山英男氏が監修した教材で、「学習習慣がなかなか身につかない」「毎日ドリルをやるのは大変で続かない」といった悩みに応えるべく、「負担にならず,毎日続けられること」を重視して作られたシリーズです。表のページで5分で解ける問題に向き合い、裏のページで復習に挑戦。
裏のページには前日の出来事を記録する「生活チェック」のスペースが設けられており、自分の生活を振り返ることで、規則正しい生活習慣が身につくようになります。
小学1年生から6年生まで学年別にドリルが出ており、価格はそれぞれ660円。
同じ「早ね早おき朝5分ドリル」シリーズでは小学1年生から3年生までを対象とした「算数 文章題」もあります。
「きらめき算数脳」シリーズ(主婦と生活社)
中学受験をサポートする進学教室「SAPIX(サピックス)小学部」が監修した問題集。中学受験塾おすすめ17選!面倒見の良い塾ランキング徹底解説
キャラクターと一緒に数字や計算・図形を使い、さまざまな方法で問題を解いていくスタイルで、楽しみながら算数に親しんでいけます。
オールカラーでイラストが豊富な構成で、読みやすく取り組みやすいレイアウトも特色。SAPIXオリジナルの思考力問題が収録されており、読解力、論理的思考力、問題解決力も身につきます。
「きらめき算数脳 入学準備〜小学1年生 かず・りょう」2090円
「きらめき算数脳 入学準備〜小学1年生 ずけい・いち」2178円
「きらめき算数脳 小学1・2年生」2090円
など
5年生まで各学年の学習に対応した問題集が出ています。
「小学特訓ドリル 算数」シリーズ(増進堂・受験研究社)
小学1年生から6年生まで各学年の算数の授業で算数で取り上げられる計算問題、図形問題、文章題などをまとめた問題集です。書き込み式のドリルとなっており、1枚ずつはがしてテストすることができます。
2年生からは巻頭に全学年の復習が掲載、単元ごとに「まとめテスト」、巻末に「仕上げテスト」があり、これまでの学日が身についているか確認できる構成となっています。
解答編には答えだけでなく、解説として「解き方」も掲載されており、答え合わせ時の理解も促してくれます。価格は792円。
そのほかにも、国語や社会、全科など、目的別にドリルを選ぶことができます。
算数では「計算」シリーズと「文章題・図形」シリーズも792円で販売されています。
「ハイレベル算数ドリル」シリーズ(文理)
「ハイレベル算数ドリル」シリーズは、学校で習う算数よりも難易度が高いレベルの問題に挑戦したい小学生向けの算数ドリルです。問題数は合計500題で、1日約30分でできる切り取り式のドリルとなっており、無理なく算数力を上げていくことができます。
「標準レベル」→「ハイレベル」→「トップレベルにトライ! 」と、取り組みやすい3段階構成で、自分に合った難易度で問題を解いていけるところも特色です。
解答の手引きが充実しているうえ、巻末にドリルで習ったことが身についているかを確認できる「総仕上げテスト」がついており、しっかりと学習の定着が図れます。
「算数ラボ」シリーズ(好学出版)
「考える力のトレーニング」という副題がついており、計算などのように反射的に解ける問題ではなく、よく考えないと解けない問題に向き合うことで、考える力のトレーニングを行うドリルです。簡単な問題から難しい問題へという3ステージに分かれており、同じ類題を繰り返し解くのではなく、様々なパターンの問題に取り組む構成のため、算数的な思考力が着実に伸びていきます。
級ごとに問題集が分かれており、それぞれ特定の学年に対応したものとなっています。
10級 小学1、2年生 880円
9級 小学3年生 880円
8級 小学4年生 880円
7級 小学5年生 996円
6級 小学6年生 996円
5級 中学1年生 1100円
そのほか、空間認識力を高める「算数ラボ 図形」シリーズもあります。
「算数あそび101」(学陽書房)
「算数あそび101」は、遊ぶ感覚で算数的な見方や考え方が育まれる教材で、全5章101題が掲載されています。「魔方陣パズル」
「足し算メイロ」
「足したら同じ三角形」
「数のクロスワード」
「ボタンを5回押して20にしよう」
「的当てゲームの点数」
「デジタル数字パズル」
「真ん中に入る数字」
などなど
バラエティに富んだ出題で、算数に必要な数感覚や図形感覚、論理的な思考を養えます。
全136ページで、コピーして印刷すればワークシートとして活用できる点が特色です。価格は2090円。
「 [よく出る!中学受験 算数] イメージde暗記!根本原理ポイント365 基礎編100」(幻冬舎)
首都圏を中心に中学受験専門の個別指導塾を展開、家庭教師派遣も行う「中学受験ドクター」が手がけた1冊です。小学生向けオンライン算数塾おすすめ9選!中学受験対策も
書名のとおり中学受験を見据えた教材で、小学4年生、5年生、基礎を確認したい6年生に向けて作られています。
正解を導き出すための「原理原則」をイメージとして身につければ様々な問題が解きやすくなるという考えのもと、各ページともまず「根本原理カード」で視覚的に「根本原理」を確認し、例題の解説を読んだあとに問題演習を行うという構成になっています。
価格は1650円。
入試問題対応実践編として、「 [よく出る!中学受験 算数] イメージde暗記!根本原理ポイント365 実践編265」も出版されています。
「出る順[中学受験算数]覚えて合格(うか)る30の必須解」(大和出版)
指導歴30年以上の著者が受験対策用に制作した1冊。中学入試でよく出題される1から3行からなる問題文の、いわゆる「一行問題」に特化した教材で、分野別に問題を解いていきます。
例)
「割合と比に関する問題」
「平面図形の面積に関する問題」
「速さに関する問題」
「平面図形の角に関する問題」
著者の橋本和彦氏は「よほどの超難関校でないかぎり、計算問題と一行問題をきちんと正解しさえすれば合格ラインに到達できる」と述べており、必須解法を覚えれば、1行問題が解けるような構成になっている点が特色です。
通常の塾やテキストでは扱っていない「公式」も掲載されています。定価は1650円です。
算数の力を伸ばしたい小学生におすすめの習い事6選【ハイレベルも可能】
算数ドリルを使った自宅学習以外で、算数の力を伸ばしたいときには習い事がおすすめです。ここで紹介する教室や通信教育はいずれも月謝が1万円以下。
しっかりと指導を受けられる環境であれば、わが子の計算力も着実にアップしていくはずです。
参考:算数塾
トライのオンライン個別指導塾
トライのオンライン個別指導塾は、完全マンツーマンで指導を行っているオンライン塾です。
1対1の授業なので、無理して周りに合わせる必要がなく、自分のペース・学力に合わせて算数の学習に取り組めます。
双方向型の授業で、分からない箇所はその場ですぐに質問でき、苦手が残りにくいのもおすすめポイントの一つです。
算数特化ではありませんが、オーダーメイドカリキュラムが提供されているため、算数を重点的に学べます。
小学生がオンライン指導を受ける場合、親としては「きちんと授業を受けられているか」「授業の進度はどうか」など、気になることが多いかもしれません。
しかし、トライのオンライン個別指導塾なら、教師が授業をサポートし、教育プランナーが学習をサポートしてくれて心強いでしょう。
定期的な学習面談もあり、気軽に相談できるLINE窓口も用意されています。
授業の様子や教師からのコメントがスマートフォンに届くのも、安心できるポイントです。
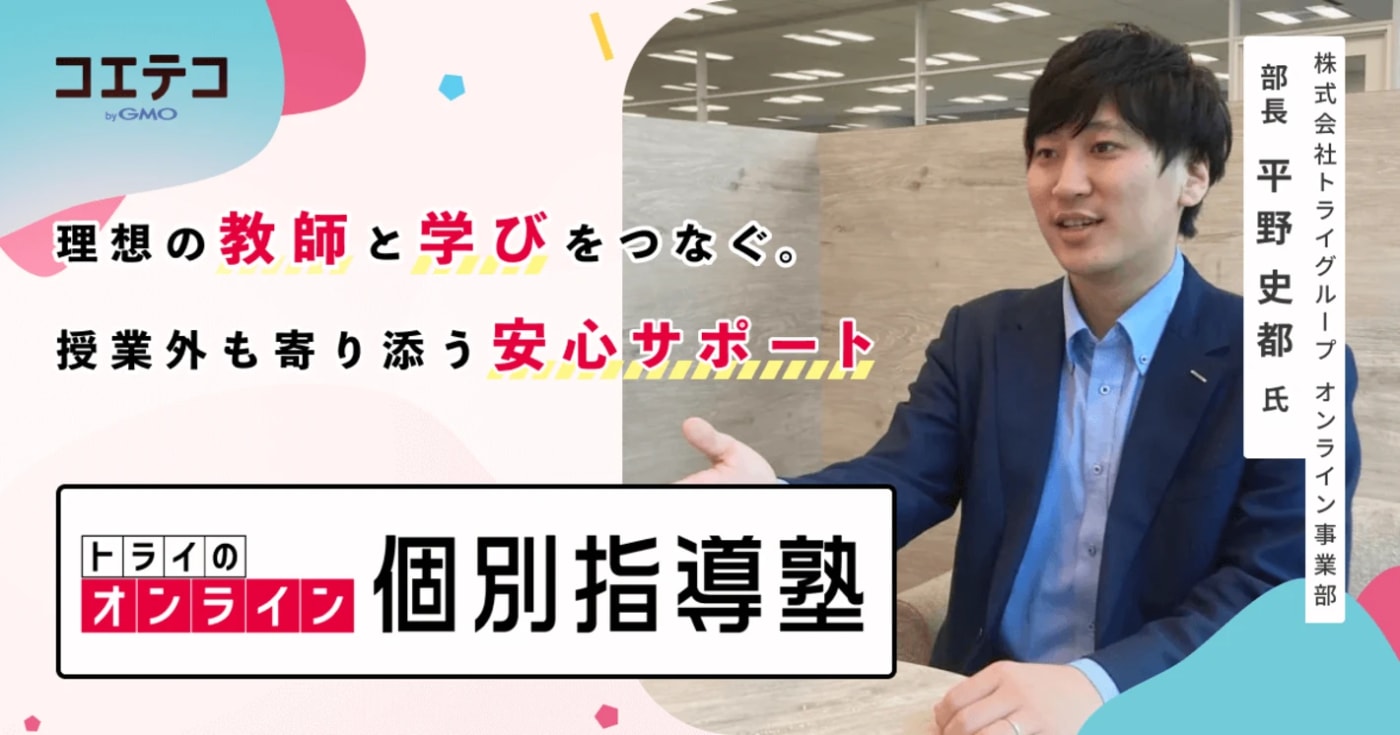
塾の目的は「成績を上げること」だと思うので、本当の意味で目的を達成できる塾を検討することが最も大切です。成績を上げられる塾を見極めるためには、授業日だけではなく、授業がない日にどのようなサポートを受けられるかを重視すべきだと考えています。
授業が行われない時間の方が圧倒的に多いわけですから、授業日以外のサポートが充実していない塾では、成績を上げるのは難しいでしょう。トライのオンライン個別指導塾は、授業日以外も意欲的に勉強できるような環境が整っており、「本当の意味での目的を達成できる塾」に当てはまると自負しています。
引用:トライのオンライン個別指導塾|プロ教師の指導力と手厚いサポートで目的達成へと導く
東進オンライン学校

受講できる教科は、算数、国語、理科、社会(1~2年生は算数、国語)です。
2学年分の授業をいつでも見られるため、得意な教科はどんどん先に進めますし、苦手な教科は繰り返し復習できます。
算数は教科書レベルの基礎知識を定着させるための「標準講座」と、応用レベルの「演習充実講座」が用意されているのが特徴。
月4回の授業と確認テストは徐々に内容がレベルアップしていく構成で、1ヶ月受講すると目標問題を解けるようになる内容です。
スマイルゼミ
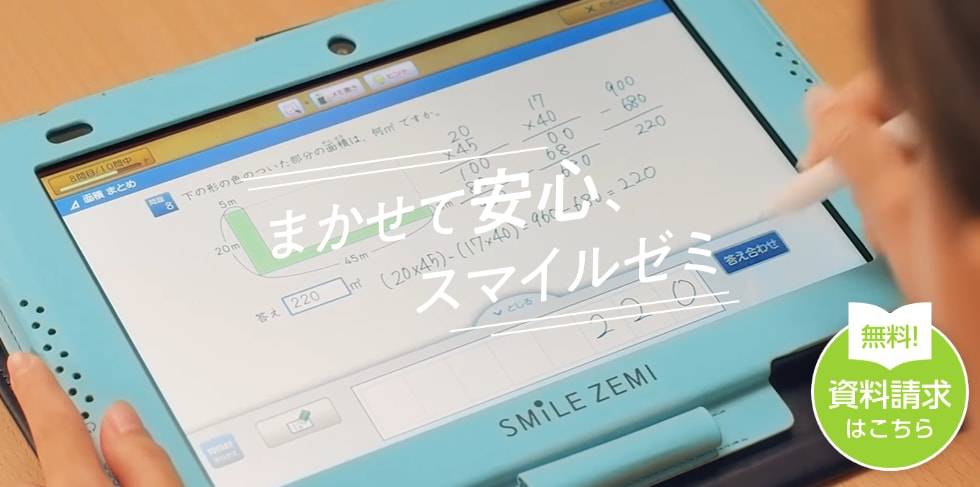
計算ドリルもあり、繰り返し取り組むことで計算力アップも期待できます。
専用のタブレットを開くと、今日取り組むべき課題が提案されるため、「何をすればいいんだろう?」と迷うことがありません。
答え合わせも自動で行われるため、子どもが1人で学習習慣を身につけられる仕組みが整っています。
競争しながら勉強できる「みんトレ」や、学習して獲得したパーツで作れる「マイキャラ」など、モチベーションにつながる要素も豊富。
トーク機能を使うと、メッセージやスタンプで保護者から応援コメントもできます。
そろタッチ ウィズダムアカデミー
習い事つきの民間学童保育の「ウィズダムアカデミー」は、そろばんの仕組みをiPadで応用した暗算学習法「そろタッチ」で学べる時間も設けています。対象校舎は目白校、恵比寿校、市ヶ谷飯田橋校、池尻三軒茶屋校、駒沢桜新町校、二子玉川校、杉並阿佐ヶ谷校となっています。
「そろタッチ」のアプリには、歌やゲーム、ランキングなど子どもを夢中にする要素が豊富に搭載されており、自分のペースで楽しみながら、効率的に暗算力を身につけることができます。
タイムスケジュールはSTEP1の「1〜9までの足し算・引き算」からSTEP10の「暗算で足し算・引き算の基礎をマスター!」までの10段階。
自宅学習も含め、約2年間毎日学習を行うことで、2桁8個の加減算や3桁×1桁、4桁÷1桁の計算を暗算で解けるイメージ暗算能力がつき、算数が得意になります。
珠算教室 ウィズダムアカデミー
東京・神奈川・千葉・埼玉エリアで民間学童保育を展開している「ウィズダムアカデミー」は習い事の一つとして珠算教室も運営しています。対象は年長から小学6年生までで、目白校、恵比寿校、自由が丘校、横浜上大岡校などを含め、約15の校舎でそろばんを学ぶことができます。
初心者は15級からスタートし、先生のアドバイスを受けながらそれぞれのペースでテキストをこなしていきます。
15級から9級までは「基礎編あたらしいしゅざん(暁出版)」、8級以上は全国に普及している全国珠算教育連盟(全珠連)の検定用テキストを教材として使用。
タイムスケジュールの最終段階には「頭の中のそろばんをイメージして暗算する」という目標が設定されています。
レッスン時間は1時間で、算数の直感力だけでなく、粘り強くコツコツ続ける集中力も養われます。
未来こども教室 そろばん教室
2008年に設立された「未来こども教室」が運営するそろばん教室は、東京都内に約50教室を展開しています。未来こども教室はかきかた書道教室とプログラミング教室も運営しており、すべてのスクールにおいて「日本人としての礼儀作法」「集中力」「正しい姿勢」「自己肯定観」「自ら考え学ぶ力」といった要素の指導に力を入れています。
対象は年中から小学6年生まで。
年中・年長を対象とした「キッズコース」の月謝が2420円、「小学生コース」の月謝が4070円と、リーズナブルな価格設定は特色の一つです。
レッスンでは一人ひとりを個別に指導。
先生が数字を読み上げて全員が一斉にそろばんを弾読み上げ算は行わず、それぞれが自分の級のテキストを開いて問題を解き、間違えた箇所を講師がピンポイントで教える指導スタイルを採用しています。
小学生はドリルや通信教材で算数の力を伸ばそう!
自宅で勉強するための算数ドリルの選び方、特色のある算数ドリル、算数の力を伸ばしたい小学生におすすめの習い事を紹介しました。小学校の6年間において算数はつまずきやすい教科だという指摘は少なくありません。
一度苦手意識を持つと、克服するには一定の時間と労力が必要になってしまいます。
「算数の壁」に直面するのを未然に防ぐためにも、学習目的を明確にしたうえで、今回の記事を参考に、わが子が楽しんで取り組める算数ドリルや習い事を見つけ、算数を得意教科にしてあげてください。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

WRITERこの記事を書いた人
塾・家庭教師ガイド
-
おすすめの塾・家庭教師一覧
-
小学生におすすめの塾・家庭教師・通信教育
-
中学生におすすめの塾・家庭教師・通信教育
-
高校生におすすめの塾・家庭教師・通信教育
-
不登校の子どもにおすすめの塾・家庭教師・通信教育
RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
小学生向け学習サイトおすすめ14選!無料・タブレット利用も可能
就学前からタブレットやスマホを使いこなす子どもたちにとって、学習・勉強でもオンラインを活用することは、一般的になりました。では、インターネットで検索できる情報や膨大なコンテンツからどの...
2025.11.17|コエテコ教育コラム
-
タブレット学習はデメリットがある?脳への影響はあるのか解説
タブレット教材は、子どもが自主的に学習に取り組めるよう様々な工夫が凝らされていたり、外出先でも場所を選ばずに学習に取り組めたりと、テキスト教材にはないメリットが得られる学習法です。 ...
2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部
-
進研ゼミ中学講座(チャレンジタッチ)の評判・口コミを徹底解説
小学校と中学校は同じ義務教育ですが「中学生になったら勉強がわからなくなった」「部活との両立が難しい」と感じる学生も多いでしょう。あっという間に受験期を迎えてしまうため、中学校入学前から...
2026.01.11|コエテコ byGMO 編集部
-
高校生向け通信教育おすすめランキング11選【2026年最新】自宅学習比較
高校生向けの通信教育はさまざまな種類があるため「どれが良いのか分からない」という人も多いのではないでしょうか。本記事では、自宅学習にもおすすめの高校生向け通信教育ランキングを紹介します...
2026.01.02|コエテコ byGMO 編集部
-
学習ドリルとは?小学生向けタブレット学習と比較
小学生の家庭学習用の教材として注目されているのが、タブレット学習向けの教材。タブレット学習のメリット・デメリットや、紙のドリルでの学習との比較、小学生におすすめのタブレット学習教材など...
2025.10.29|コエテコ教育コラム