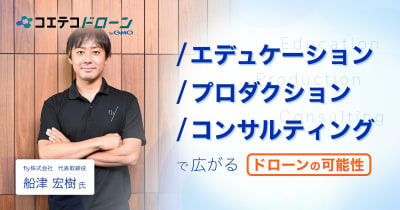(取材)特許の数は130!高い技術力を誇るベンチャー、プロドローンが目指す「空のスタンダード」

「産業を創るおもしろさ」からドローンの世界へ

株式会社プロドローン 代表取締役 戸谷 俊介氏
――プロドローンに興味を持たれたきっかけを教えてください。
もともと私は愛知の鉄道会社に就職したのですが、すぐに広告会社に出向となり、そのままDMC(電通名鉄コミュニケーションズ)に転籍になりました。その中で1980年代の終わりごろからずっとモータースポーツを担当していたんです。
2017年に東京支社長に就任し、世界ラリー選手権(WRC)といった大きなレースの仕事を担当。そんな中でドローンを知り、「ドローンもレースでイノベーションを起こせるはず」と考えるようになりました。
自動車がいまのように広く活用されるまでには、「もっと早く」「もっと安全に」を追求するレースの存在が大きな役割を果たしました。そこで日本でのドローンレース開催を模索するうちに、どんどんドローンの世界にはまっていったんです。
実際に2019年の東京モーターショーでは、日本初のFAI(国際航空連盟)公認となるDTRC2019ドローンワールドカップを開催することができました。
――ドローンレースの推進からかかわりを持たれたんですね。そこからプロドローンの社長就任に至った経緯を教えてください。
プロドローンの副社長がDTRC2019の審査委員長を務めていた関係で仲を深めていくうちに誘われた形です。それでDMCを退職し、ドローンの世界で挑戦することを決めました。現在僕が60歳で副社長が67歳。二人合わせて127歳のキラキラベンチャーです(笑)。
ドローンは、ブルーオーシャンと言えば聞こえはいいですが、成功するか失敗するかが不透明な領域です。でも我々は、むしろそこに魅力を感じました。自分の手で産業を創っていく面白さに惹かれたんです。
――会社は名古屋にありますが、地方にあることのデメリットを感じたことはないのでしょうか。
あまりないですね。実は、日本の航空機の約5割が愛知を中心とした中京で作られており、航空機産業では愛知が日本の中心地と言えます。必然的に人材も豊富なので、むしろ地理的に有利だと考えています。
当社が高機能なドローンを世に送り出せるのは、優れた人材のおかげです。当社の副社長兼CTOは非常に高い技術力と発想力を持つスーパーマンですし、常務はソフトウェアの領域ですごく活躍してくれています。この2人によってほかの社員たちも磨かれるので、粒ぞろいの人材が育っています。
それに、昔であれば対面での顧客折衝が必要でしたが、最近はオンラインがデフォルトになりました。地方にいることのデメリットはますますなくなりましたね。
130の特許!高い技術力でドローン開発

――御社のドローンの特徴を教えてください。
まず一般的なドローンに比べて大きいことが挙げられます。他社の産業用ドローンは空撮や点検用に使われるケースが多いのですが、これらは“目”となるカメラさえあればいいので、小さくても問題ありません。
一方、私たちは物資輸送と測量を主な対象としています。物資輸送ではより多くのものを運べた方がいいですから、どうしても大型化の必要があります。いま実際に長野県伊那市で物資輸送に使われている機体は大きさが2mを超え、重さも20kgほど。最大30kgの荷物を積載することが可能です。※推奨は20kg
荒天に強い測量用の機体でも最大10kgの荷物を積載でき、レーザー測量機の搭載が可能です。たとえば熱海の土砂災害のような事例が起こってしまったとき、これまでだと夜間に土砂崩れが発生したとしても被害状況を確認するのは朝になってからしかできませんでした。そのような事態でも弊社のドローンにレーザー測量機を搭載して測量することで、夜のうちに現状を把握することもできます。

ほかにも、着水・離水が可能な防水型ドローンでは特許を持っています。現在、KDDI、KDDI総合研究所と共同で開発を進めているドローンがあり、ドローンが着水するとそこから海の中を潜れる水中ドローンが出てくるというもの。これにより、たとえば東京にいながら沖縄のサンゴ礁の観察を行うことも可能になります。これまでは潜水夫が実際に潜って行っていた船底の点検や漁場の管理をドローンが担えるようになるので、省人化や安全の確保につながります。

――高い技術力をお持ちなんですね。現在いくつくらいの特許をお持ちなのでしょうか。
2023年1月末時点で130ほどの特許を取得しています。すべての特許が使われているわけではないですが、アーム付きのドローンや水空合体のドローンは活用されていますね。
これから使っていきたいのは、ドローンで地上の人物を特定し、その情報をクラウド上で共有できるシステムです。たとえば大規模なイベント会場などの上空にドローンを飛ばし、テロを起こす可能性のある人を見分けるといった用途で活用してほしいと考えています。そのようなドローンがあるだけで、犯罪の抑止にもなるはずです。
――ドローンの開発にあたり、そのような技術力をもってしても苦労した点をぜひお聞かせください。
まだまだ苦労の途中ですが、やはり安全性をいかに担保するかが一番の課題ですね。どれだけ安全性の高い機体を作ったとしても、墜落リスクをゼロにはできません。飛行中に不具合が発生した場合にはまずホバリングし、先に進めそうになければ出発点に戻る仕組みにしていますが、どうしても落ちそうなときは不時着させる必要があります。
実現不可能な「絶対に落ちないもの」を作ろうとするより、「いかに安全に着陸するか」を考える方が安全の確保のためには重要です。人がいない安全な場所をドローンが自分で探し、その緊急着陸ポイント(ラリーポイント)めがけて下りていく機能を磨いていくことが求められます。
そのほか、ソフト面では大きなドローンを運用するパイロットの育成も課題です。たとえば自動車の免許を持っていて、軽自動車を運転できるからといって「大型トラックを運転してくれ」と言われても難しいですよね。ドローンの操縦もこれと同じで、大型ドローンのように質量が大きい機体だと、なかなか急には止まれません。小回りのきく小型ドローンとは操縦の勝手が違います。

たとえば今後50キロの荷物を運んである地点でリリースするとなると、それだけの重量が一気になくなることで瞬間的に機体が不安定になります。プロペラの回転数が半分以下になりますから、前から強い風が吹くと落ちそうになるんです。
急いでプロペラを回そうとしても、プロペラは1枚1メートルくらいあるので急には回らない。そのような状況で機体をコントロールするのは大変難しいんです。こうした機体の特性をしっかりと理解し、安全に運航できるパイロットをどのように育成していくかが、今後の大きな課題といえます。
50kgの荷物を運ぶ「空飛ぶ軽トラ」へ
――いま取り組みを進められていることを教えてください。僕たちがいま取り組むべきだと感じているのは、「中山間部」「離島間」「河川」「災害」でのドローンを使った社会課題・地域課題の解決です。
その前提にあるのが、いま政府が進めている「デジタル田園都市国家構想」です。この構想では、都市部と地方に住む人たちの生活格差を極力なくすことを謳っています。それを実現するためには、ドローンが大変役に立つはずだと考えています。
デジタル田園都市国家構想は、デジタルの力で、地方の個性を活かしながら社会課題の解決と魅力の向上を図ります。そして、「地方に都市の利便性を、都市に地方の豊かさを」を実現して、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指します。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/index.html >
その中でもまず取り組もうとしているのが、統合型医療DXの推進です。これは、中山間部や離島に住む人たちに対して、オンラインの診療・服薬指導と合わせて、ドローンで医薬品や経口補水液などを輸送するサービスです。ゆくゆくは劇薬指定されているインスリンや血液製剤まで運びたいですね。

さらに災害時には、医薬品と併せて生活物資やガスコンロといった日用品も運びたいと考えています。ただ、そのためには、天候に左右されずに多くの物資を安全に運べる大型の機体が必要です。そのためいまは、精力的に機体開発を進めています。

――どれくらい大型のものが必要になるのでしょうか。
具体的には、50kgの荷物を運ぶことができるドローンが必要になります。私たちはこれを「空飛ぶ軽トラ」と呼び、なるべく早く社会実装するべく開発に取り組んでいます。
その中で、1月には中日本航空、コハタと共同で「群制御ドローン」を用いた実証実験を日本で初めて成功させました。これは隊長機1機を操作することで別のドローン2機も自動で追従するというものです。
今回の実験では最大積載量が10kgほどのドローンを使用しましたが、これが50kgの荷物を運べる機体を飛ばせるようになれば、一回に150kgの物資を運べるようになるわけです。これだけの荷物が運べれば、災害時に集落が孤立してしまった場合でもたくさんのものを運ぶことができます。

平時でも、たとえば新潟や長野といった雪が降り積もる地域では、車のない人たちが冬の間コンビニに行けなくなることがあります。そこでドローンが大量の荷物を運び、QRコードを使って電子マネーで決済し、買い物が終われば自動で帰っていく環境を構築できれば、ドローンがコンビニの役割を果たすことになります。

――地方に住む人たちにとって、すごく便利になりそうですね!
そうですね。加えて別の観点からも災害時での活用に向けた実験を進めています。いまKDDIと一緒に行っているのは、携帯の基地局の機能をドローンに担わせる実験です。
基地局を上げるために必要な電気は、たとえば提携しているトヨタの販売店舗が保有している水素カーから確保することができます。場合によっては、その店舗を拠点に孤立集落に物資を届けるケースもあるかもしれません。
加えて測量機能を使えば、要救助者がどの地点にいるかといった情報を災害対策本部に報告することも可能です。今後はその要救助者の情報をマイナンバーカードと紐づけ、すみやかに基礎疾患まで把握した上で病院に運ぶ体制をつくっていきたい。まだ課題はありますが、なんとか数年以内には構築したいと思っています。
目指すは「空のスタンダード」。空はみんなで使うもの
――50kgの荷物を積んだドローンが世に出てくるのはものすごく便利な反面、「もし落ちてきたら怖い」と思う人が出てきそうです。もちろん、そんな大型ドローンが街中を飛んでいたら怖いですよね。ですから僕は、ドローンが街の中を飛び交う想定はしていません。街の中は自動車で十分まかなえますから、やはり山間部や離島、災害時といった場面でこそドローンを活用すべきです。
空にはまだ鳥と航空機やヘリコプター、ロケットぐらいしか飛んでおらず、多くの人は空を“特別なもの、一部の人が使うもの”だと考えています。僕たちの目標は、空が普段の生活の中で当たり前のように使われるようになること。それが「空のスタンダード」だと思っています。
僕たちはいずれ、田舎に住んでいても「ドローンが物資を運んでくれるから不便を感じない」社会をつくりたいんです。それには「空飛ぶ軽トラ」であるドローンの社会実装が一つのマイルストーンになるはずです。
――「空飛ぶ軽トラ」が社会実装すれば、ドローンに対する社会の目も変わってきそうですね。
そうですね。まずは一人ひとりに「ドローンを使えばこんなに生活が便利になるんだ」と自分事として実感してもらうことが大切です。
高齢になれば、2Lの水を2本買うだけでも大変です。そんなときに、ドローンで家で届けてくれたら楽じゃないですか。高齢者が「便利だ」と実感してくれるようになれば、ドローンは一気に支持を得て広がるはずです。
最後に、特に若い人たちに伝えたいのですが、空はもっと自由に使えるはずなんです。ぜひ空を見上げて、一つでも二つでもアイディアを出してみてください。みんなでどんどん空を使い、「空のスタンダード」をつくり上げていきましょう!
日本発 産業用ドローン専門メーカーProdrone(プロドローン)。高安全、高機能、高安定の各種産業用ドローンを製造販売いたします。

https://www.prodrone.com/jp/ >
RECOMMEND
この記事を読んだ方へおすすめ-
(取材)ドローン仏から小豆島のエリアマネジメント事業まで。fly代表・船津氏に聞く、ドローン活用の可能性
浄土宗龍岸寺のイベント「ドローン仏」を企画したのは、ドローンを活用した映像制作事業、教育事業、そしてコンサルティング事業を展開するfly株式会社。代表取締役である船津宏樹さんに、その豊...
2024.08.26|宮﨑まきこ
-
そらいいな株式会社が見据える物流の未来|五島列島の空をドローンが飛ぶ!
豊田通商株式会社の100%子会社として誕生した「そらいいな株式会社」は2022年、長崎県南西部に浮かぶ五島列島でドローンによる日用品・医薬品の配送を開始しました。試験飛行開始から約1年...
2024.10.29|まつだ
-
(取材)ビデオグラファーからドローン業界に参入。ドローン空撮のスペシャリスト・上村哲平氏に聞く
ドローン空撮業界の第一線で活躍するスペシャリストたちは、どのような経歴や経験、考え方を持って撮影にあたっているのでしょうか。今回は、さまざまな映画やCMなどのドローン空撮に携わってきた...
2024.08.26|徳川詩織
-
(取材)カシワバラ・コーポレーション|足場不要、人の入れないエリアのサビも点検!ドローン×AIで実現する次世代の修...
産業インフラ・大規模建造物の維持・保全分野で建設業界を牽引してきた株式会社カシワバラ・コーポレーション。 同社は保守的な傾向が強い建設業界でいち早くDX化に取り組み、ドローンとAI分...
2025.05.30|大橋礼