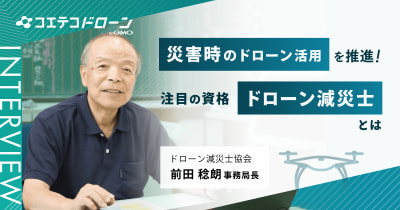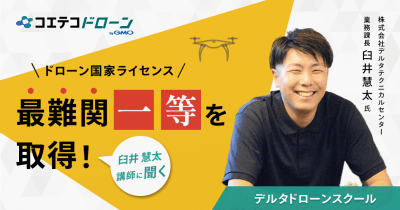(取材)最先端科学技術のドローンで障がいを持つ人の未来を支援!ユニバーサル・ドローン協会「ナミねぇ」こと竹中ナミさんの取り組みとは

事務局長の竹中ナミさん(ナミねぇ)は、30年前より最先端のICTを活用したチャレンジドへの支援を第一線で続けています。この記事では同氏に、ユニバーサル・ドローン協会を設立したきっかけや、チャレンジドがドローン操縦するにあたっての課題や工夫、今後の展望について伺いました。
障がいを持つ方の可能性を広げたい。最先端科学技術のドローンでチャレンジドを支援

ユニバーサル・ドローン協会(UDrA)事務局長の竹中ナミさん(ナミねぇ)
―ユニバーサル・ドローン協会の設立のきっかけを教えて下さい。
ユニバーサル・ドローン協会(UDrA)は、就労支援など障がいを持つ方の未来の可能性をドローンで広げることを目的として、2019年に設立した協会です。私たちは障がいのある方を「Challenged(チャレンジド)」という可能性に着目した言葉で呼んでおり、その方たちを支援する活動を、社会福祉法人PROP STATION(プロップ・ステーション)で丸30年行ってきました。
プロップ・ステーションを立ち上げたきっかけは、重症心身障がいを持つ今年50歳になる私の娘を通して、たくさんのチャレンジドと出会ったことです。彼らは、人間として当たり前のやりたいことや目標も持ち、それを実現できる可能性も十分にあります。しかし、「かわいそう」「気の毒」というような社会通念によって、それが当たり前とは思われません。そのことに違和感を持ち、本当の福祉は、一人ひとりの目標が実現できるようスキルアップの機会を提供したり、道筋を作ったりすることができる社会であるという考えにたどり着きました。
その後、「これからはコンピュータの時代だ」というチャレンジドたちの話から、一流のコンピュータの先生と学びを希望するチャレンジドを結びつける、プロップ・ステーションの活動をはじめました。ボランティアとしてご協力くださる先生方のおかげで、今ではベッド上でコンピュータを使って会社を興し、社長となる人まで出てきています。
そして、3〜4年ほどまえにドローンと出会いました。コンピュータの経験から、「チャレンジドの力を本当に引き出せるものは、最高の最先端の科学技術だ」という思いがあり、ドローンを見つけた瞬間に「これだ!」と感じましたね。

―素晴らしいご活動です。ドローンのどのような部分に大きな可能性を感じられたのでしょうか。
人間は空を飛べませんが、ドローンが自分の目や体の代わりとなって空中に上がると、いろんなものを俯瞰できるようになり、調査や研究などに結びつきます。つまり、ドローンを操縦できれば、新たな自分の道を発見することができるんです。
ドローンを初めて見たときは、30年前にコンピュータに出会ったときと同じような感覚を持ちました。まさに「ビビッときた」としか表現できない感覚でしたね。
一等国家ライセンス取得を目指す「プロジェクトみゆう」とは

ドローンを操縦するみゆうさんと、講師の榎本 幸太郎さん(国際ドローン協会)
―ドローンと出会われた後は、どのようなご活動をされたのでしょう?
まず、ドローンで新しい職域開拓ができないかと考えました。そこで協力いただける方を探し、国際ドローン協会の榎本幸太郎さんと出会いました。そこから、チャレンジドのドローン講習会を開始することができました。
榎本さんはそれ以来、ボランティア講師としてご参加くださり、「プロジェクトみゆう」などの活動にも繋がっています。「プロジェクトみゆう」とはチャレンジドの一人、現在高校1年生のみゆうさんが、将来の可能性を広げるための取り組みの一つとしてドローンパイロットを目指すプロジェクトです。彼女は両手が使えませんが、足で器用にドローンを操縦するんですよ。
みゆうさんは、もともとプロップ・ステーションでコンピュータを勉強しに来られていて、強い熱意と素晴らしい足技を見せてくれていました。そこで、新たな挑戦としてドローンを提案したところ「やってみたい!」と強い意欲を示してくれて、榎本先生からドローンを教わることとなったんです。そこから3年間練習を重ねて、今では榎本先生が驚くほど難易度の高い技もできるように。現在は、一等の国家資格取得を目指しているところです。
いまではみゆうさんだけでなく、聴覚障がいを持つはるとさんという青年も、半年ほど前から榎本先生から直接教わっていて、めきめき上達しています。やはり、みゆうさんの飛ばす姿は大きな刺激となっているようで、練習にも熱心です。

ドローンを操縦するはるとさん
―みゆうさんが最初にドローン操縦に取り組むとき、どのような工夫をされましたか?
みゆうさん自身は、足を使ってなんでもできますので、これといった工夫はしていません。私たち自身にも、足でコンピュータを操作する方をサポートした経験もあったため、不安はありませんでした。みゆうさんのためにしたのは、彼女が座る椅子と操縦機を置く椅子を向かい合わせに置き、素足で操縦できるようにしたくらいです。
みゆうさんが最初に足でドローンを操縦したときは、榎本先生も驚いていましたよ。実際に榎本先生が足で操縦しようとしたところ、足がつってしまったそうです(笑)。
障がいを持つお子さんにやりたいことをやらせるのか、それとも、障がいがあるから無理だと言い聞かせるのか。ご両親次第でチャレンジドの生きる意欲は大きく変わってきます。みゆうさんは赤ちゃんのときから、なんでも足でやってきて、ご両親もそれを応援してきました。それこそが、彼女の自信や自覚に繋がっているのだと思います。
―そのほか、チャレンジドの方がドローン操縦に挑戦する上で、課題や障壁を感じたことはなかったのでしょうか。
課題だと感じたのは、むしろ制度面ですね。例えば試験には、「ドローンの試験は手で操縦すること」などの規定がありました。これでは、手に障がいを持っている方は受験することすらできません。
そのため、チャレンジドが個々に合った飛ばし方で試験ができるように、話し合いを国交省と重ねているところです。これは、みゆうさんのように向学心のある方がいなければ、実現しなかったかもしれません。いまでは様々な障がいを持つ方が試験を受けられるような体制も整えられてきたと思います。
ただ、ドローン以外でもなんでも、課題はあると感じています。むしろ、国より一般の場所の方がハードルが高いかもしれません。
みゆうさんが高校に入るときも、偏見によって大変苦労した話を聞きました。今後、大学、社会人と進む中で、高い壁を感じることもあるかもしれません。そのときに「他の人にはないスキルを持っている」ことが、彼女に限らず、チャレンジド全員にとって非常に大切なことだと改めて思いました。そのためにも、まずは彼女がドローンで未来を切り開いていくことを、全力で応援したいと考えています。
実績も実力も指導経験もある超一流の講師から学べる環境を提供

IDAドローンスクールが運営する「東庄町ドローンパーク」開校式の様子
―少し話は戻りますが、チャレンジドのドローン操縦を指導する講師として、IDAドローンスクールの榎本幸太郎さんにオファーされた理由を教えて下さい。
一流になるために学ぶなら、超一流の、しかも稼げている講師から学ぶことが私の信念です。ですから、コンピュータのときも超一流のエンジニアやプログラマーの方々にお願いをしてきました。ドローンでもやはり超一流の講師を、と思いインターネット中を必死に探したんです。
そこで、榎本先生が代表理事を務める国際ドローン協会のサイトを見つけました。榎本さんは日本におけるドローンの先駆者で、国際的なご活躍もされており、さらにはNHKでもドローンを飛ばす仕事をされていた方です。また、榎本先生自身が、もともと聴覚障がいのある方にドローンを教えていて、他の障がい者にも希望があれば指導したい、という気持ちもお持ちでした。つまり、実績も実力も指導経験も、全て兼ね備えている方だったんです。このような方は、榎本先生以外にいらっしゃいません。
その後はすぐに連絡を取り、翌日には榎本先生のオフィスに向かいました。ボランティア講師の依頼をすると、「僕にできることなら、なんでもやりますよ!」と二つ返事で引き受けてくださり、以来毎月神戸まで講習に来てくださっています。
みゆうさんが国家試験の目標を持ってからは、国際ドローン協会の方で彼女の身辺をサポートできるような環境を整えた上で合宿させてくださったり、千葉東庄町の新校舎でも勉強できるようにしていただいたり……。榎本先生に出会えたこと、そして、講師になっていただけたことは、非常に幸運だったと思いますね。

「東庄町ドローンパーク」の外観
チャレンジドがドローン産業・業界を支える存在となることを目指す

―チャレンジドのドローン業界でのご活躍について、ナミねぇの今後の展望を教えて下さい。
具体的なところでは、榎本先生が作られたスクールで、みゆうさんが講師としてドローン操縦を指導する方向性を固めています。あとは、国家試験のあり方について国交省との話し合いも続けています。
今やドローン市場にはJALやANAなどの航空業界、その他物流業界など、多くの業界からの参入が相次いでいます。つまり、ドローンがビジネスに必要な時代が目の前まで来ていて、ドローンパイロットもそれだけ求められているということです。
私はそのことをチャレンジドに伝え、チャレンジドがさまざまな業界で活躍できるよう、ドローン技術を獲得できる場を提供していきたい。それが目下の目標ですね。
ただ、この流れをつくるためには、まずは成功事例を出さなければいけません。チャレンジドが本当にドローン業界に参入できることを世間に知ってもらうためにも、まずはみゆうさんが道を切り拓くファーストペンギンになってくれたらと願っています。
―素晴らしいお考えです。そうすると、ナミねぇのおっしゃっていた「職域の広がり」にも繋がりそうですね。
そうですね。30年前のコンピューターへの挑戦のときには、世間だけでなく、福祉業界からも非難を受けることもありました。ですが5年、10年と続けるうちに、障がいのある方にとってコンピュータこそが新しい道を切り拓くための道具であると多くの人に理解いただけるようになりました。そこからパソコンを使ってお仕事をするチャレンジドの方が増えてきて、今日に至っています。
障がいのある方がコンピュータを使うのが当たり前となったように、ドローンも同じ道をたどると考えています。はじめは理解されない方がいても、ドローンをやりたいチャレンジドが増えれば道も広がり、榎本先生のような心ある指導者の方も増えてくださると思っています。ドローン業界やドローン産業をチャレンジドたちが支える人になっていくと確信していますし、またそうしなければならないと強く思っているところです。
とはいえ、「障がい者だからコンピュータ」「障がいがあるからドローン」という義務的なものではなく、それをやりたいというチャレンジドたちを後押ししていきたいんです。
私は関西人なので、自分のことは、お好み焼きの具と具をつなぐメリケン粉(小麦粉)だと思っています。楽しみながら夢や目標を持てるチャレンジドと、可能性のある市場をつなぐメリケン粉になれたら嬉しい。いつかドローン市場がおいしいお好み焼きになるまで、これからもたくさんの人と人をつないでいくつもりです。
障がい者からチャレンジドへ。コンピュータ、インターネットなどのICT(情報とコミュニケーション技術)は、チャレンジド(the ...

https://www.prop.or.jp/ >
RECOMMEND
この記事を読んだ方へおすすめ-
SKY BIRD 東日本ドローン航行技術教習校卒業生インタビュー|未経験から一等ライセンス獲得!体験会で魅せられた...
医薬品卸売業に勤める宮下さんはSKY BIRD 東日本ドローン航行技術教習校の体験会をきっかけにドローンに魅了され、同校に入学。まったくの未経験から一等無人航空機操縦士を取得しました。...
2025.02.28|白波弥生
-
災害時の新たな救世主?ドローンがつなぐ防災の輪:ドローン減災士協会 前田稔朗事務局長
災害時のドローン活用を推進する一般社団法人ドローン減災士協会(DEO)。全国各地にあるスクールを通じて、救助や物資輸送の効率化を図るための訓練を提供しています。 この記事ではドローン...
2025.05.21|夏野かおる
-
(取材)デジタルハリウッドロボティクスアカデミー卒業生インタビュー|デジハリ全コースをコンプリート!コースごとの違...
デジタルハリウッドロボティクスアカデミーは、質の高い独自カリキュラムとオリジナル教材によって、ドローンの国家ライセンス取得と実践的なスキル習得を目指せるスクール。現場経験と実績を持つプ...
2025.09.10|水無瀬あずさ
-
(取材)デルタドローンスクール 臼井慧太氏|京都で60年以上の指導実績を誇る!デルタ自動車教習所運営のスクール
京都で60年以上の実績を誇る「デルタ自動車教習所」が運営する「デルタドローンスクール」。同校を家業とする臼井慧太さんは、他業種からドローン産業に参入し、現在では講師として参画しています...
2025.05.30|宮﨑まきこ