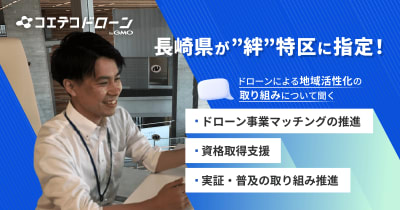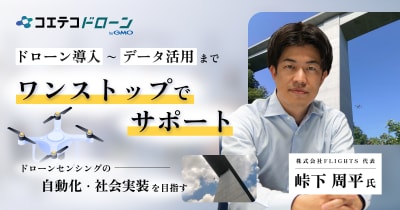(取材)センシンロボティクス代表・北村卓也氏|ドローンを活用したインフラ整備のDXで、子どもに誇れる仕事を
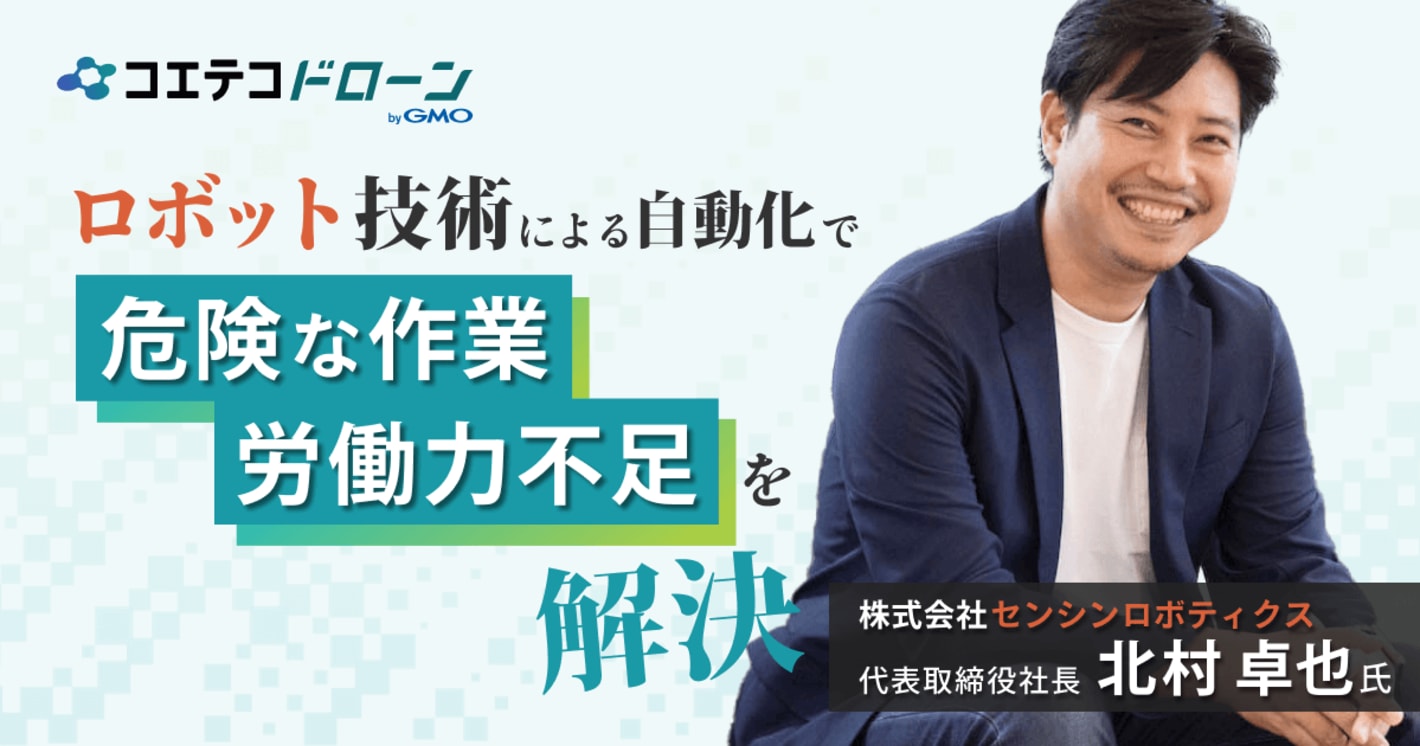
この記事では、株式会社センシンロボティクス 代表取締役社長の北村卓也氏に、ドローンを用いた設備点検自動化の意義や導入事例、課題感などについてお聞きしました。

株式会社センシンロボティクス 代表取締役社長 北村卓也氏
「社会的意義×IT」でイノベーションを起こしたいと考えセンシンロボティクスに参画
ーーセンシンロボティクスは2015年10月に創業されたとのことですが、当時のビジョンや市場の雰囲気について教えてください。最初は、取締役の間下が運営するV-CUBEという会社の一事業としてスタートしました。V-CUBEはリアルタイムコミュニケーションや音声配信などを扱っていて、ドローンの映像を多拠点に配信することで災害時の有用性やビジネスチャンスがあるのではないかと考えて事業を起こしたのが始まりです。
当時は法律も厳しくはなく安全管理の縛りも緩かったので、さまざまな操作を試せました。現在のようなレギュレーションがない中で、トライ&エラーを繰り返していた時代です。市街地やお城の周りを飛ばすケースもよく見られましたが、事故やトラブルが相次ぎ、法整備が必要だという流れに変わっていったんです。
一方、機体に関して言えば、当初のドローンは高級品で、とても一般人に手の出る価格ではありませんでした。普及するようになったのは、実はスマートフォンのおかげです。というのも、スマートフォンに用いられているセンサー技術とドローンに使われている技術はほとんど一緒なんです。
パソコンやスマートフォン、ドローンなど、ハードウェアが絡む市場が成長するときには一定のパターンがあります。まず注目が集まるのはキャッチーなハードウェアです。スマートフォンであれば、iPhoneですね。iPhoneというエポックメイキングなハードウェアが生まれ、需要が爆発的に増えたことで、小型化されたセンサーやチップが大量に製造されました。
通常、部品を小型化するにはものすごい投資が必要になり、そのコストは販売価格に転嫁されます。しかしドローンの場合は、スマートフォンの普及によって、その部分をショートカットできた。このことがドローンの価格を押し下げ、企業努力も合わさって優秀なドローンが次々と生まれるようになったのです。
ーー北村社長は2018年10月にセンシンロボティクスに参画されたということですが、それまでのご経歴や参画に至った思いをお聞かせください。
僕はずっと外資系のIT企業に身を置いていて、最先端の仕事やエキサイティングな仕事をたくさん経験しました。ただ、外資系の日本の支社では、さまざまな戦略やプロダクトのロードマップなど、全ての物事を決定するのは本社です。日本の社会を良くしたい、日本でイノベーションを起こしたいと考えていたので、いつか日本発のプロダクトサービスにチャレンジしたいという思いはずっとありました。
そんな思いを抱えながら、僕は40歳になりました。ちょうどその頃、2人目の子どもも授かりました。人生は1回しかないので、父ちゃんのやっている仕事が子どもにどう見えるか、自分がどう説明できるかは、今後の社会人人生においてとても大切だと感じました。給料とか会社の看板とかじゃないな、と。
自分自身はもちろんですが、子どもに僕の仕事を誇りに思ってほしいという気持ちが芽生えたんですよね。それで「社会的意義のあること×自分がやってきたIT」が合致することをしようと思いました。安定した組織を飛び出すわけですから、リスクはありましたけどね。

“人にとってリスクの高い仕事”にこそロボット技術を活用すべき
ーーセンシンロボティクスでは、現在どのような事業を展開されているのでしょうか。まず強調したいのですが、僕らはドローンの会社ではなく、ソフトウェアの会社です。僕らがアウトプットしたソフトウェアを動かすために、パソコンやスマートフォンを使う。それと横並びでドローンを使っているんです。そのうえで事業内容を端的に言うと、ロボットを制御して自動で動かすためのプラットフォームと、その上で動く業務アプリケーションを作っています。
物流や農業など多くの業種を扱ってきた中で、一番インパクトが出て、なおかつマネタイズできるのが社会インフラ・産業インフラの分野でした。
ビジネスですから、人が困っているところにミートするのが最も重要なポイントです。マネタイズができなければ産業は育ちません。ボランティアでは続かないんです。僕たちの事業はCSV(Creating Shared Value)経営。「社会的に良いことをしながら、経済的にも成立させる」ことを重視しています。
ーー設備点検の自動化にロボット技術を使う意義について教えてください。
設備点検は人間にとってリスクが高いフィールドで、怪我をしたり亡くなったりするケースもあります。そのような人がやりたくない仕事や、やらない方がいい仕事こそロボット技術などのデジタルに置き換えるべきだと思っています。
点検を自動化することで、リスクを下げたり再現性の高いデータを取れたりするだけでなく、人口減少による労働力不足にも対応できます。例えばドローンのオペレーターを連れてきたり誰かを派遣してもらったりしても、結局人が動く以上、労働力不足の対抗措置になっていません。だからこそ自動化が大切なんです。
点検精度の標準化の問題もあります。これまではマイスターと呼ばれる職人の方を中心に、人が設備をチェックして判断していました。ただ、人によって判断が分かれることもあり、隠れたリスクとなっていました。マイスター自体も減っていますし、インフラ業界は30~40代が極端に少なく、技術を継承する人があまりいません。標準化の観点でも人手不足の観点でも、テクノロジーを用いた手段が必要です。
設備点検や災害対策へのドローン活用の導入事例
ーー中部電力パワーグリッド株式会社と共同で実施された、送電設備の自動点検技術開発の事例について、概要を教えていただけますか。電力設備の中でキーとなる設備は、電線とそれを支える鉄塔です。従来の点検方法は作業員による昇降点検やヘリコプターを使った点検でした。高い場所での作業が中心なので、当然リスクも高まります。さらに少子高齢化も進んでいるため、生産性向上・業務効率化が求められています。
そこで僕らは、ドローンで鉄塔と電線を一括で点検できる仕組みを作りました。鉄塔はトラス構造という複雑な四角錐で、設備形状が多種多様で再現性が高いデータを取るのは難しい。なのでマニュアル(手動運転)ではなく自動化にこだわり、ドローンを飛ばして複雑な鉄塔でも同じデータを取り続けるアルゴリズムを開発しました。
また、電線は日によって弛み具合が変わります。そこで、データを取りたい電線が常に中央に来るようなアルゴリズムを開発して、再現性が高いデータを取ることに成功しました。すると、点検のパフォーマンスが一気に変わりました。一例ですが、これまでは5人1組で1日2本の点検作業を行っていたところ、作業員は2人程度に減り、1日あたり5、6本ほど確認できるように。単純に生産性が2倍、3倍になったのです。
社会インフラDXのリーディングカンパニーである株式会社センシンロボティクスは、ドローンを活用した送電設備点検アプリケーション『POWER GRID Check』に,中部電力パワーグリッド株式会社と共同で開発した技術を活用し,送電線自動追跡撮影モードと多導体送電線スペーサ点検撮影飛行モードを実装しました。

https://www.sensyn-robotics.com/news/power-grid-check-02 >
ーー実装した効果については、どのように感じていらっしゃいますか。
人が高いところに昇ったり、場合によっては電線にぶら下がって点検したりしていましたが、そのような機会が減るので、圧倒的にリスクを最小化・作業を効率化できます。データ自体もデジタルなので、実際に検査に回したり修繕したりするときに同じデータを共有できますし、時間が経ってからデータを比較する際も役立ちます。
なおかつ、将来的には予兆保全につなげていきたいですね。データが集まれば「このような事象が起きている所は先に対処した方が良い」と判断ができるので、計画的な運用が実現でき、お金や人手を削減することができると思います。
いま、業界は、時間の経過に合わせて保全作業するTBM(Time Based Maintenance)から、状況に応じてメンテナンスするCBM(Condition Based Maintenance)へと変化しています。これを進めれば、メンテナンスの頻度を実態に応じて調整できるようになります。
ーードローンを活用した災害対策にも取り組まれているそうですが、導入事例はありますか。
愛媛県の伊方原発では、すでに社会実装されている事例があります。半島の突端に位置する原発で、災害発生時には海側と陸側のどちらに避難するか判断が求められますが、その判断は地上からでは難しいんです。なので複数機のドローンを編隊させて上空から数十キロ四方をカバーし、災害対策本部にリアルタイムで映像を飛ばす仕組みを作りました。幸い災害が発生していないので目にする機会はないのですが、毎年防災訓練を行なっています。
2020年10月22日、愛媛県にて行われた原子力防災訓練にて、自動航行プラットフォーム「SENSYN FLIGHT CORE」、「SENSYN DC」が使われました。

https://www.sensyn-robotics.com/news/announcement-06 >
ーー導入を通して得られた知見や課題などがあれば教えてください。
導入先がインフラに近ければ近いほど、スピード感は遅くなります。新しい技術を導入したり、仕事のやり方を抜本的に変えたりする場合には、現場レベルの判断ではなく上層部の意思決定が必要です。積極的なケースと消極的なケースで判断が真っ二つに分かれることも多く、そこに向き合わなければならないのが一番のハードルです。「何かあったら誰が責任を取るんだ」という議論が出ると、うまくいきません。
当然イノベーションでは失敗もあるし、そこから学ぶこともたくさんある。なので、ENEOSさんと一緒に「ENEOSカワサキラボ」を作っています。いきなりお客さんのところで試すと、万が一事故があった場合のリスクが大きいですし、お客さんの心配ももっともです。なので、使われていない石油プラント施設をラボとして使わせてもらって、テストしたものを実際の設備に持ち込み、課題をラボに持ち帰ってブラッシュアップする形で開発を進めています。
ーー現時点で技術的な課題は何かあるのでしょうか。
僕たちの仕事はソフトウェア開発が中心ですが、業務を行ううえでは必ずハードウェアが必要です。なので、自分たちだけではどうにもならない問題が必ずあります。例えばドローンでいうと、他のメーカーと比べてDJI社が頭一つ抜けている状況です。ただ、DJI社のドローンを使えないケースもあり、そのときにどの機体を使うかという難しさがあります。また、ハードウェアに変更を加えてもらう必要がある場合に、どのくらいの期間が必要なのか、そもそも対応が可能なのかどうか、といった問題もあります。こういった点に僕らのビジネスが左右されてしまうのは大きな課題です。
ドローンは外部依存性が非常に高くて、ビジネスの観点でサステナブルとはいえません。先ほどのような外部要因に加えて、天候などによる環境依存もあります。あとは法律の部分も厳しくて、僕たちが相対しているプラントや電力設備には独自のレギュレーションがあります。やはり自分たちではどうにもならない壁はとても多いですね。

目指すのは圧倒的な1番。最初に想起してもらう会社になりたい
ーー今後の展望についてお聞かせください。僕らは、ドローンなどのロボットを産業利用して人にとってリスクの高い仕事を無くす分野で、課題を持ったユーザーから最初に想起してもらう会社になりたいと思っています。目指しているのは圧倒的な1番です。
ドローンでいうと、昔はメーカーに最初に声がかかっていました。それが変わってきていて、僕たちみたいにサービスやソフトウェアを持っている会社に声をかけてもらえるようになってきたんです。狙い通りの展開ですね。ハードウェアメーカーは自分たちのハードが売れないと仕事にならない。でも僕たちはドローンがもしフィットしなければ「やめましょう」と言えます。ドローンにこだわらずにソリューションを提供できる点は、ソフトウェア会社としての強みです。

RECOMMEND
この記事を読んだ方へおすすめ-
(取材)アイ・ロボティクス代表 安藤嘉康|"課題先進国"日本におけるドローンの最新ソリューションとは
自然災害やインフラ老朽化などの課題に、アイデア×ロボティクスで解決策を提案するアイ・ロボティクス。老朽化施設の設備点検など、ドローンを活用したソリューションも数多く手がけています。代表...
2024.04.01|宮﨑まきこ
-
長崎県が”絆”特区に指定、ドローン技術で描く離島の物流革命と地域活性化
長崎県は、その先進的な取り組みを背景に、福島県とともに新技術実装連携”絆”特区に指定されました。人口減少や高齢化が進む中、地域社会を持続可能にするための鍵として、ドローンの活用が期待さ...
2025.06.11|夏野かおる
-
「空から挑むデータ革命」|株式会社FLIGHTS 峠下周平が描くドローン前提社会のビジョン
いま、ドローン市場で圧倒的な存在感を放つのが株式会社FLIGHTSです。同社はとくに、橋梁やインフラの点検・測量分野において、高精度なデータ取得と自動化された業務プロセスにより、業界で...
2024.10.09|夏野かおる
-
FINDi|水道から発電所まで!水中設備点検のDX化をドローンで実現
高齢化するインフラ設備の維持管理が社会課題となるなか、ドローンを活用した点検手法の開発が進んでいます。水中設備の点検調査サービスを展開している株式会社FINDiでは、水中点検に特化した...
2025.05.30|Yuma Nakashima