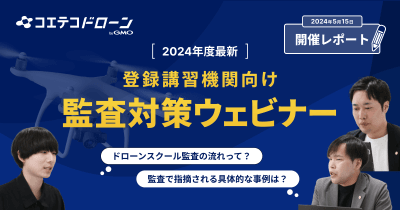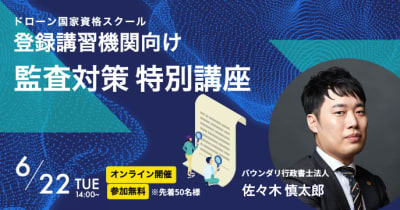(レポート)監査の実際と今後を展望する『ドローン登録講習機関監査の現状と課題点に関する勉強会ウェビナー』

ドローンの国家ライセンス制度に対応する登録講習機関に義務付けられている「外部監査制度」。まだ制度運用が開始されたばかりということもあり、登録講習機関のスクールの皆さまの中には、まだこの監査制度になじみがない方も多くいらっしゃるかもしれません。
今回のウェビナーでは、ドローン登録講習機関監査に関係する3団体、国土交通省、JUIDA(一般社団法人日本UAS産業振興協議会)、バウンダリ行政書士法人の皆さまを登壇者として迎え、登録講習機関監査の現状と制度改正の概要、現状の監査実施状況、所感と今後の展望を伺いました。

■登壇者
・国土交通省 航空局 安全部 無人航空機安全課 専門官 藤井 秀基 氏
・国土交通省航空局 安全部 無人航空機安全課 無人航空機企画調整官 櫻井 一孝氏
・JUIDA(一般社団法人日本UAS産業振興協議会)理事・事務局長 熊田 知之 氏
・JUIDA(一般社団法人日本UAS産業振興協議会)経営企画室 室長 田口 直樹 氏
・バウンダリ行政書士法人 代表行政書士 佐々木 慎太郎 氏
・バウンダリ行政書士法人 登録講習機関等監査実施団体管理者 許認可法務部マネージャー
行政書士 橋本 拓人 氏
■司会
GMOメディア株式会社 事業開発本部 柴垣 泰
■協力
一般社団法人日本UAS産業振興協議会
https://uas-japan.org/
バウンダリ行政書士法人
https://boundary.or.jp/lp_drone-kansa/
■後援
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/
登録講習機関監査の現状と制度改正の概要(国交省 藤井氏)

国土交通省 航空局 安全部 無人航空機安全課 専門官 藤井 秀基 氏
ウェビナーの前半では、国土交通省 航空局 安全部 無人航空機安全課 専門官 藤井 秀基 氏より、登録講習機関監査の現状と制度改正の概要について説明いただきました。
- 新制度の運用状況
- 監査制度の概要
- 登録講習機関の登録及び監査関係通達の改正概要
1. 新制度の運用状況
2022年12月、レベル4飛行を可能とするライセンスや機体認証制度が導入され運用を開始しています。これにより、機体認証と操縦ライセンスを得て、運航ルールに従っていれば、レベル4の飛行が可能になりました。機体認証には、メーカー等が設計・製造する量産機を対象とする「型式認証」と、無人航空機の使用者が所有する一機ごとの機体を対象とする「機体認証」があります。制度が開始してから現時点までの認証数は、型式認証、機体認証ともに低く推移している状況のため、認証の数を増やす政策を検討しています。なお、登録講習機関の登録件数、一等・二等のライセンス交付数も予想より低い数での推移となっており、ライセンスの取得を促す政策が必要だと感じています。

そのような課題はある状況ですが、新制度の効果も現れてきています。
レベル4飛行については、2023年3月に日本郵便が奥多摩で配送の実証実験を実施しています。そして、11月にはANAが物資輸送、12月にはKDDIが医薬品の輸送に関する実証実験も行われました。
いずれの飛行もまだ人口密度の低い地域の第三者上空での実証ですが、将来的な人口密度の高い地域での飛行に向けた大きな試金石となったのではないかと考えています。
2. 監査制度の概要
登録講習機関の外部監査制度は、無人航空機の利用促進のために非常に重要な意味があります。無人航空機の利用促進を図っていくためには、無人航空機が安全かつ社会的に非常に重要なインフラだと一般の皆さまにも認知いただくことが不可欠です。そのためには、事故等なく安全に無人航空機を操縦できる優良な操縦士の育成が必要となります。
外部監査を通して、登録講習機関における講習事務の実施状況、法令の遵守状況などが的確であることを確認することにより、適切な講習水準の確保や向上、ひいては技能証明の水準・信頼性を確保することが重要です。
監査を受検するメリット
監査を受検するメリットとしては、下記の点が挙げられます。- 法令及び事務規程に違反した講習の防止又は是正につながる
- 一定の無人航空機習の水準が担保されれば、受講者による事故の防止等により業界全体の信頼性にもつながりうる
- 監査に係る対応を適切に終了した登録講習機関は社会的な信頼性を得ることができ、当該の登録講習機関の受講者も安心して講習を受けることができる
なお、この外部監査制度は、受けていただくことが義務付けられており、もし受けていただかなかった場合は行政処分等の対象になる可能性があります。
監査を受けていただく際には、監査に向けて帳尻を合わせるのではなく、ご自身の作成された事務規程や国の基準をよく確認していただいた上で、日頃から適切な講習を実施し、その上で監査を受けていただければと考えております。
監査の流れ
監査の流れは下記の通りです。-
1.国土交通省のホームページに掲載している監査実施団体を選定し、契約
(※監査実施団体は、2024年1月末時点で19団体) - 2. 監査実施団体からの必要書類の送付依頼に沿って、必要書類を送付
- 3.オンライン監査、または実地監査を実施
- 4.監査終了後、監査実施団体より監査報告書が発行
- 5.報告書の写しを監査受検後1ヶ月以内に航空局に提出
不適切事項が認められた場合は、監査実施団体とともに是正対応し、是正が終わりましたら監査実施団体から通知される不適切事項に関する報告書を航空局に提出いただきます。

国土交通省航空局 安全部 無人航空機安全課 無人航空機企画調整官 櫻井 一孝氏
監査の種類
監査実施団体が行う外部監査には、「計画的監査」と「随時監査」の2種類があります。先ほど述べた流れは、毎事業年度に行っていただく計画的監査の流れです。随時監査は、計画的監査において是正措置報告を求められた場合や、講習において事故もしくは重大インシデントが発生した場合、航空局または監査実施団体が必要と認めた場合に行われます。
また、重大な不適切事項が見つかった場合は、航空局が直接立入検査を行う場合もあります。立入検査の拒否や、立入検査中に虚偽の申告があった場合には罰則が適用される厳しい検査となりますので、なるべく立入検査を行わなくて良いよう、適切な方式で実施していただきたいと考えています。
監査に係る課題と今後の対応
運用を始めてみるとさまざまな課題が出てきていますが、主に感じている課題は以下の3つです。- 監査制度、監査の必要性及び重要性の認知不足
- 不適切事案の増加(当局としても随時立入検査を実施)
- 監査制度の規定通りに監査することが難しい場合がある
一つ目は、そもそも監査制度や監査受検の必要性についてまだ十分な理解を得られていない点です。この点については、今後も周知活動を進めていきます。
二つ目は、監査の数が増加してくるにしたがって、不適切事項が報告される数も増加している点です。不適切事項の数を減らすためにも、監査基準の中で曖昧な記載がある点は今後改善していきます。また、登録講習機関の皆さまも今一度、事務規程や国の基準を確認していただき、適切な講習の運営を心がけていただくような、関係者が一丸となった取り組みが必要だと考えています。
三つ目は、当初作った制度が実際の運用に適していないところがあるという点です。今後、随時基準をアップデートし、運用に即した形での基準制定をしていきたいと考えております。
3. 登録講習機関の登録及び監査関係通達の改正概要
制度のアップデートについて、国交省では登録講習機関の登録に関する通達、そして監査関係の三つの通達について改正を進めています。- 「登録講習機関の登録に関する取扱要領」関係
- 「登録講習機関等監査実施要領」関係
- 「登録講習機関等監査実施細則」関係
- 「登録講習機関等監査実施団体について」関係
各通達の改正ポイントは下記の通りです。(登録講習機関に関係のある箇所は赤文字)

①登録講習機関の登録に関する取扱要領では、事務規程の変更の際に提出が必要となる書類について明確化します。さらに、管理者および講師研修の記録方法を明記し、講習の記録簿、他の書類につきましても必要な記載事項および保管方法について明確に記載したいと考えています。
②登録講習機関等監査実施要領での変更点は、実地監査の要件緩和です。現行の通達の中では、実地監査は登録講習機関の事業期間の最終年度、3年目に絶対行わなければなりません。しかし、実際の運用では現実的ではないため、3年間の中で1回は実地監査をすればいいと要件を緩和しようと考えております。
監査実施団体の2社も交えて現状の監査実施状況、所感と今後の展望
講習機関監査は、制度設計から運用まで比較的短い期間で実装されたこともあり、登録講習機関であるスクールの皆さまも「情報が少ない」など、いろいろとお困りのことも多いかと思います。後半は、監査実施団体のJUIDA(一般社団法人日本UAS産業振興協議会)、バウンダリ行政書士法人の方々も交えて現状の監査実施状況、所感と今後の展望をお話いただきました。
まずは取扱要領や告示をしっかり読むことが重要(JUIDA 田口氏)

JUIDA(一般社団法人日本UAS産業振興協議会)経営企画室 室長 田口 直樹 氏
田口氏:JUIDAでは、75の登録講習機関に監査を実施させていただいていますが、その中で、やはり多くのスクールで混乱があったのではないかと感じています。実際に監査を受検していただくと「思っていたより厳しい」というコメントをいただくこともありました。
これは、航空法で定められた法定監査になりますので、今までのような民間スクールでの認証とはやはり違います。国家資格ですので高い水準で質を保っていく必要があり、かなり厳しいと感じられると思います。そうでなければ、資格の価値自体が失われてしまうことになりかねません。その点をぜひご理解いただきたいと思います。
課題として感じているのは、登録講習機関のみなさんがまだ慣れていない部分があり、「監査をクリアするために何をしなければいけないのか」について把握が難しいのではないかという点です。
この点については、国から出ている取扱要領や告示、ガイドラインなどを、登録講習機関の皆さまにも読んでいただくことが重要だと思います。「これはどうするのか」という部分があれば、一つひとつドキュメントに立ち返っていただく必要があるからです。しかし、この点はなかなか慣れないことですので、どう解釈すればいいのかも含めて、皆さん混乱されているのかなというのが率直な感想です。
JUIDAでは引き続きさまざまな解説を行い、解釈に余地がある部分については国土交通省と緊密にコミュニケーションを取りながら確認をしていきたいと思います。

JUIDA(一般社団法人日本UAS産業振興協議会)理事・事務局長 熊田 知之 氏
藤井氏:おっしゃる通り、そもそもこれまで民間の認証として営まれていた制度と、国家ライセンスの制度にギャップがあったというのは事実かと思います。
国交省としては、通達の中で曖昧な解釈ができてしまう点は今後もアップデートしていきます。また、通達では書ききれない点については国土交通省のホームページにFAQを掲載しています。今後はこのFAQの充実を図り、情報をわかりやすく提供していきたいと考えています。
不適切事項を指摘された場合の措置に不安を感じる方が多い(バウンダリ行政書士法人 佐々木氏)

バウンダリ行政書士法人 代表行政書士 佐々木 慎太郎 氏
佐々木氏:田口様と同感で、やはり航空法などのそもそも基本的な法令をまだあまり理解されていない方が受講生も含めて多くいらっしゃると感じております。例えば、準備しておかなければならない書類を把握されていなかったり、講習の記録簿などに記載されるべき事項が漏れていたりなどです。
よくご相談いただく点としては、動画の提出についてです。講習や修了審査の動画撮影について、受講生の撮影の同意がなかなかいただけないという声も聞きます。受講生の方に対しても、なぜ監査を受けるのかといった制度説明をなるべく事前に申し込みの段階でしていただきたいと感じています。
また、不適切事項について、どのような措置が取られるのか、そもそも処分があるのかないのかも分からないことから、コミュニケーションが多少荒くなってしまうケースも散見されています。監査後の是正措置報告書を提出させていただく際に、不適切の原因や再発防止の分析をどうすれば良いか分からず、スムーズに進まないこともございます。

バウンダリ行政書士法人 登録講習機関等監査実施団体管理者 許認可法務部マネージャー 行政書士 橋本 拓人 氏
藤井氏:不適切事項があった場合どうなるのかという点は、登録講習機関の皆さまが心配されている点だと思います。制度がまだ開始したばかりということもあり、不適切事項を受けて即ペナルティを発動したいという意向ではありません。そうではなく、適切な講習を実施していただくために不適切事項を明らかにし、是正を行っていただくための監査制度だと考えています。悪意のある重大な不適切事項の場合は別ですが、講習の中で少し至らない点があって不適切事項を指摘された場合は、監査実施団体の指示に従って是正をしていただけたらと思います。
質疑応答

セミナーで参加者の皆さまからは多くの質問をいただきました。ここでは、質疑応答の内容をまとめます。
ーー解釈の違いや誤解を生じるような記述を直してほしいです。講師条件についても「資格を得てから6ヶ月経過した者」等の記述にしてください。
藤井氏:まさに今回の改正の中で、この点についても明確にする予定です。
ーー教則第3版は4月から試験に反映されるのでしょうか?
藤井氏:試験に関する内容は、公平性担保の観点から公表しておりません。試験に反映されるかされないかにかかわらず、教則の最新情報を受講者の方達に教えていただいて、結果的に学科試験に出るフェーズはいつか来るかもしれないという心づもりでいていただければと思います。
※4/14から試験問題の変更が決まったので、こちらのリンクを追加
ーー国家資格を取得するメリットが少なく、受講を躊躇してしまうという声を多く聞きます。今後、取得者のメリットを拡大していくことは検討されていますか?
藤井氏:検討中の段階です。一つの検討の結果としては、昨年12月よりレベル3.5飛行というものが開始されております。これにより、操縦ライセンスを保有していること、飛行リスクに応じた保険に加入していること、機上カメラによって第三者の有無を確認できること、の条件を満たしていただくことで、従来の立入管理措置がを撤廃するような飛行となっています。なお、現在は民間ライセンスを保有されている方でも許可承認の際の申請の免除が認められていますが、今後は民間の資格については免除が廃止される予定です。
ーー真面目に講習業務、事務を行っているつもりでも何か不備が見つかった場合、受講者様のライセンスが取り消しになるような事案はあり得るのでしょうか?
藤井氏:理論的な可能性としてはあり得ますが、影響が大きいと思いますので、事態の重大性や悪質性を総合的に判断し、なるべく社会的に妥当と考えられる対応をしたいと考えています。
ーー監査の際に動画の提出ができない場合は、今後撮影を行うことを是正の際に報告すればよいでしょうか?
藤井氏:年度をまたいだとしても、動画の撮影ができた際に提出していただき、監査を受けていただければいいかなと考えております。ただし、次年度の監査が迫っているようなフェーズだと2回続けて動画を撮影して監査を受けることは厳しい状況もあると思います。そういった場合は、監査実施団体と話しながら都度対応しています。
ーー告示に定められている講習科目に則り、実地講習のカリキュラムを作成・運営しています。こちらは告示と事務規程の時間を厳守したものになりますが、各登録講習機関の実地講習カリキュラムは、実地監査での監査対象になるのでしょうか。
藤井氏:実地監査だけではなくオンライン監査でも監査対象になるという認識です。書類の確認の際に、事務規程に記載されている実地講習カリキュラムが告示の内容や時間数と合っているかということは、監査実施団体に確認をお願いしています。
ーー修了審査や講習内容の解釈が難しい(曖昧な部分がある)部分に関しては、正式な内容をわかりやすく再掲示していただけますか。
藤井氏:できるだけ分かりやすい形で通達、あるいは別の資料等で掲示させていただきたいと考えています。
ーー日常点検記録や飛行記録などの記入欄が小さい、順番がバラバラであるなど、使用しにくいのですが、内容は変えずに順番を変えるなど独自に作成することは良いのでしょうか。
藤井氏:現状は、なるべくその指定試験機関から配布されているものをお使いいただきたいと考えています。
ーー登録講習機関監査実施団体になるには法人の実績は問われますか。実施団体になるために立ち上げる法人でも可能なのでしょうか。
藤井氏:現状の基準では、法人である必要があります。監査実施団体になる際には、基本的には法人としての監査実績が定められた要件を満たしているということが必要になります。監査実施団体になるために法人を立ち上げることも可能ですが、その際は願い出の際にすでに法人が立ち上がっている必要があり、登記簿等を提出をしていただきます。また、そのような団体に対しての監査実績の確認は、その監査実施団体の管理者など個人に要件に定められた監査実績があれば認める場合もあります。
ドローンの安全な利活用促進のために

将来的な無人航空機業界の発展のためには、操縦士の技能水準の向上が大きなポイントとなります。そして、そうした優良な操縦士の育成には、登録講習期間での講習水準の向上が欠かせません。
外部監査を通じて適切な講習水準の確保や向上が実現するということは、つまり技能証明の水準、信頼性の確保、ひいては無人航空機の利用の促進、そして業界全体の発展にも繋がります。その意義を再確認できたウェビナーとなりました。
登壇者の皆さま、ありがとうございました。
RECOMMEND
この記事を読んだ方へおすすめ-
(レポート)『2024年度最新 登録講習機関向け監査対策ウェビナー』ー登録講習機関の現状と課題とは?
2024年5月15日、ドローン情報サイト「コエテコドローン」は『2024年度最新 登録講習機関向け監査対策ウェビナー』を開催。バウンダリ行政書士法人の佐々木氏、橋本氏には登録講習機関の...
2025.05.26|大森ろまん
-
(レポート)ドローン国家ライセンス登録講習機関向け「監査対策」セミナー(バウンダリ行政書士法人)
ドローンの国家ライセンス制度に対応する「登録講習機関」には、年に一度の「外部監査」が義務付けられています。そこで2023年6月22日、ドローン関連業務に特化したバウンダリ行政書士法人代...
2025.09.10|宮﨑まきこ
-
「コエテコドローンスクールEXPO2023(2日目)」レポート|ドローン産業発展に必要なこと、操縦士が心がけること...
ドローン市場の現状やドローンスクール立ち上げ・運営の課題解決などのノウハウが集結するオンライン展示会「コエテコドローンスクールEXPO2023」(2023/7/20、21開催)。ドロー...
2023.09.08|大森ろまん
-
「コエテコドローンスクールEXPO2023(1日目)」レポート|ドローンのレベル4飛行で何が変わる?ドローンスクー...
ドローン市場の現状やドローンスクール立ち上げ・運営の課題解決などのノウハウが集結するオンライン展示会「コエテコドローンスクールEXPO 2023」(2023/7/20・21開催)。ドロ...
2025.05.26|大森ろまん