(取材)『ロボット検定®』に挑戦してみよう!小学生から受けられるロボットプログラミング検定・ロボ検を詳しく解説

-
今回お話を伺った方
-
一般社団法人ロボット技術検定機構事務局長
近藤敬洋氏長年ロボット・プログラミング教育の普及推進に注力し、2017年より一般社団法人ロボット技術検定機構事務局長・NPO法人青少年科学技術振興会(英語名:FIRST Japan)事務局長を兼任。学習成果を“社会的なスキル”として証明する「ロボット検定」制度の構築・運営に尽力。ロボット分野の知識・組み立て・課題解決能力を測る実技試験による評価モデルは、全国の教室や教育現場で高く評価され、次世代エンジニアの裾野拡大に大きく貢献。STEAM系教育イベント講師としても登壇、『Crefus』等業界メディア・教育団体で教育観インタビュー多数。“才能が正当に評価される社会”の実現を掲げて活動を続けている。
-


ロボット検定®、通称「ロボ検®」は、小学生から受けられるロボット・プログラミング検定です。小学生のうちから検定を受けることで自信もつき、モチベーションアップにもつながります。
受験でもロボット検定の認定を記入できますし、面接などでロボティクス工学に触れてきたことをアピールできるメリットもあります。
今回は一般社団法人ロボット技術検定機構の事務局長 近藤敬洋さんに、ロボ検®について詳しくお話を伺いました。実際の試験会場での様子も写真と共にご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
ロボット検定®とは?

ロボット検定®は、ロボット工学とプログラミングを学ぶ子どもたちの学習成果を評価するための試験です。知識問題だけでなく、ロボットの組み立てやロボットを用いた課題解決などを含む実技試験もあります。
| 種類 | ロボット検定ジュニア |
| ロボット検定 | |
| 対象キット 対象年齢 |
▼ロボット検定ジュニア レゴ®SPIKEベーシック使用・WeDo2.0使用 小学1年生~3年生 |
| ▼ロボット検定 レゴ®SPIKEプライム使用・EV3使用 小学3年~高校生 | |
| 級 受験料 |
▼ロボット検定ジュニア 3級/2,900円(税抜) 2級/3,900円 1級/4,900円 |
| ▼ロボット検定 3級/3,300円(税抜) 準2級/3,800円 2級/4,800円 準1級/5,800円 1級/6,800円 | |
| 受験資格 | 検定会場に指定のロボットキットを持参できる方 |
| 合格基準 | 100 点満点とし、70 点以上 |
| 試験会場 | 24都道府県・ベトナム 北海道・宮城・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京 神奈川・新潟・富山・静岡・愛知・大阪・兵庫・奈良 広島・山口・福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 |
| 合格認定後 | 合格証明書 認定バッジ |
| 主催 | 一般社団法人ロボット技術検定機構(横浜市) |
ロボット検定®で「企業に力を、人に技術を、子どもに夢を」

一般社団法人ロボット技術検定機構の事務局長 近藤敬洋さん
2010年に神奈川県の「かながわ次世代ロボット検定事業」として設立されたのが、ロボット検定®です。
神奈川県の担当者の方々や大学関係者、ロボット工学の専門家などによるチームで、技術者育成を第一の目的としてスタートしました。
自治体事業としての期間は満了しましたが、その後も検定は必要であると考え、実験的にお子さま向けの検定も行いました。この検定は、想像以上に大きな反響がありました。
ロボットやプログラミングは学んだ成果、身についた技術力がわかりづらい面があります。検定に合格し級をもらうことで、学びつづけるモチベーションを維持できますし、もっとがんばろうという意欲につながる大きなメリットがあります。
また、お子さまのがんばった結果、学んでいるレベルがわかるので、保護者の方にもとても好評でした。
そこで、よりお子さまに特化したロボット検定®を行うようになったという背景があります。
ロボット検定®の『ねらい』について教えていただけますか?
ロボット検定®は、2つの理念を掲げています。

- ロボット技術者を育成する。
- 企業に力を、人に技術を、子どもに夢を。
特に「子どもたちに夢を与える」ことは、ロボット産業の発展や人材育成に非常に大切です。たくさんの小学生や中高生の皆さんがロボット検定®を受けて、テクノロジーへの関心を高め、目標に向かって進んでほしいと思います。
そしてテクノロジー社会での“ものづくり”に大きな夢をもって挑んでもらいたい。「ねらい」というよりも、そのような「願い」を込めて運営しています。
ロボット検定®の内容とは

実際のロボット検定®ではどんなことを行うのかを具体的に知りたいです!
ロボット検定®ジュニアの試験時間は40分。筆記と実技があります。ロボット検定®は小学校3年生以上で、準2級までの試験時間は60分、2級から1級までは90分で、やはり筆記と実技があります。
筆記試験は、いわゆる知識問題です。その後、実技の問題を行います。
実技がある試験は、なかなか珍しいですね!
はい。まさに、ロボ検®の特徴は実技があることです。知識だけでなく、実践する力があるかどうかをロボ検®では重視しています。
具体的な内容は、まず「ロボットを組み立てる」実技。
さらに、そのロボットに指定されたプログラミングを行い、試験官に実際にロボットの動作を判定してもらう実技もあります。たとえば、ロボット検定®では「ロボットカーを組み立て、壁から25cm以上離れるまで後進し、1秒停止する」といったような問題があります。
今日はちょうどロボ検®を実施していますので、そちらをご覧いただきましょう。
実際のロボット検定®を見学しました!
こちらが、ロボット検定®の試験会場の様子です。
試験会場には受験者の人数によって、1〜2名の試験官がつく。
最初に、試験官から「検定」の流れについて解説があります。
試験中の私語は禁止であることや、得点に関する質問には答えられないことなど、注意事項についても説明がありました。

試験官の指示にしたがって、問題をパソコンに表示。配布される解答用紙に鉛筆かシャープペンシルで答えを記入する。

試験で何より重要なのは、最初にしっかり名前を記入すること!
試験問題は、それぞれのパソコンに表示され、解答用紙に答えを記入していきます。

試験会場はピリッとした雰囲気。

どの子の真剣な表情で集中している。
級によって違いますが、たとえば準2級では、第1問から第4問までが、いわゆる知識問題になります。
知識問題では、実際にキットを使用してモデルを組み立て、プログラムを作成して確認することができます。「手を動かし、実際につくる」プロセスを重視しているロボ検®の特徴でもありますね。
そろそろ、みんなロボットの組み立てを始めたようです。
レベルによって違いますが、組み立て書を見て作るパターンもあれば、完成されたロボットをいくつかの角度から撮影した写真を見て、組み立て方法から考えて製作するパターンもあります。

組み立て書を見ながら製作中。

さらにプログラムを組んでいく。

実技問題に奮闘中。パーツが多いので大変!

子どもたちの集中力には驚かされる。見ているこちらも力が入る。

思ったとおりにできたかな?がんばれ!
ロボットの組み立てができたら、試験官に見せます。

試験官はすみずみまでチェック。
ロボットの組み立てが確認されたら、次は試験問題に示されたプログラムを作ります。
できたプログラムは、解答用紙に記入します。さらにプログラムをロボットにダウンロードし、実際の実技試験スペースで「検証」します。この日の試験でも、何人かがスペースで検証をしては席に戻り、プログラムを修正していました。

思ったとおりに動かなくても、粘り強く修正する。
ロボット検定®では、たとえば準2級の実技問題は4つ。そのうち3つは指示どおりにプログラムを組んで解答用紙に記入します。
最後の1問はロボットがプログラムどおりに動作するかを試験官に見せます。
ロボットの組み立てと指定されたプログラムを組んだら、手を挙げて試験官に「実技テストをお願いします」と伝えます。
試験官は実技問題の指示どおりにロボットがプログラムされ、動作するかを確認します。
一回でうまくいかなくても制限時間内でしたら、プログラム等を修正して再度、実技試験を受けられます。最初は緊張してうまくいかないこともありますが、あきらめずにがんばってほしいですね。

試験会場には、実技を行うためのスペースが設置されています。

緊張の一瞬!

合格しているといいですね!
受験者の皆さんはとても真剣な表情!1分1秒を無駄にしない意気込みで集中力を発揮していました。
レベルが上がるにつれて難易度も高くなるので、1度では合格しないことも珍しくありません。
試験の雰囲気に慣れることも必要なので、初回の検定でうまくいかなくても落ち込まず、次のチャレンジに向かってさらに力を磨いてください!
ロボット検定®の受験者について

ロボット検定®を受けているのは、主にどんなお子さまですか?
ロボット検定®には、レゴ®エデュケーションのキットを使います。
認定校であるCrefus(クレファス)では、試験に出題されるようなロボット製作も行っていますので、やはりクレファスの生徒さんが多いですね。
ただ、クレファス以外にも認定校はありますし、他のロボットプログラミングスクールからロボ検®を受けにくる生徒さんもいます。また、独学であっても、問題の傾向や実技の感覚をつかめば充分に対応は可能でしょう。
年長から高校生まで、理数系の知識を体系的に学べる「ロボット科学教育Crefus(クレファス)」。多くの習い事が小学生を対象とするなか、小学生からスタートして中学・高校と10年近くスクールに通い続け、理系の大学院に進んだ卒業生もいる実力派スクールです。今回は新百合ヶ丘校で学ぶ中高生の皆さんを突撃取材。クレファスでの学びについて、たっぷりお話を聞いてきました。


2025/05/30

設立から21周年目を迎え1万人以上の修了生を輩出する「Crefus(クレファス)」。毎年1回開催される全国大会「Crefus Cup(クレファスカップ)」は、各コースごとにエントリーした選手たちが学んだ成果を競います。本記事では大会の様子を、たくさんの写真と共にご紹介します。


2025/09/10

近藤さん:
あとは、WRO(World Robot Olympiad:自律型ロボットによる国際的なロボットコンテスト)やFLL(FIRST LEGO League Challenge:米国のNPO法人「FIRST」とレゴ社による世界最大規模の国際的なロボット競技会)の参加経験者もいます。
この記事ではFLL東日本大会で1位を獲得し、世界大会への切符を手にしたクレファス青葉台校チーム「OWL陸(オウルシックス)」に密着! きっと「通わせてよかった!」と感じられるCrefusの教育をライブ感満載でお伝えします。


2024/11/06

FLL(ファースト・レゴ・リーグ)のプラチナスクールにも認定され、ロボット教育を通して理数系の能力向上に貢献してきたCrefus(クレファス)。今回はクレファスを卒業し、名古屋大学で物理学の研究に励む増倉さんに、クレファスで学んだことと現在の進路についてお話を伺いました。今、親が子どもに与えられるベストな環境は何なのか?クレファス卒業生の増倉さんの言葉がきっと参考になるでしょう。
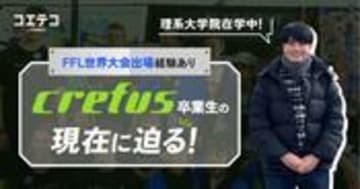

2025/05/30

近藤さん:
年齢的には小学校4年生〜中学生が多いです。中学生は、高校受験でのアピールにしたいと検定を受けるケースもありますね。
なるほど、クレファスはロボット検定®の認定校なのですね。
現在、ロボット検定®の試験会場は多くがクレファスの教室です。
クレファスでは、ロボット検定®で用いるレゴ®エデュケーションSPIKE™ベーシックやEV3を使ったカリキュラムを実施しているので、試験内容に即した知識と実践的なスキルが身につくメリットがありますよ。
Crefus(クレファスとは?)

Crefus(クレファス)は、年長・小1からの「ロボット製作×プログラミング×STEM」を学べるロボットプログラミングスクールです。
段階的にステップアップし、最終的にはPython(本格的なプログラミング言語)でロボットプログラミングを行うレベルまで到達します。ロボット製作を通じて、クレファスでは次のような力も育みます。
- 自発力
- 夢中力
- 創造力
- 問題解決力
- コミュニケーション力
クレファスは、ロボット検定®認定校であり、またFLLの最上級認定校でもあります。
検定を受ける、大きな大会に出場する、そんな目標も叶えられるスクールです。
設立から21周年目を迎え1万人以上の修了生を輩出する「Crefus(クレファス)」。毎年1回開催される全国大会「Crefus Cup(クレファスカップ)」は、各コースごとにエントリーした選手たちが学んだ成果を競います。本記事では大会の様子を、たくさんの写真と共にご紹介します。


2025/09/10

Crefus(クレファス)はブロックでプログラミングを学べる人気の教室。Crefus武蔵小杉校は生徒が増えたことから武蔵小杉駅前に2つ目の教室をオープンしました。今回はCrefusの人気の理由を探るべく、保護者の方とお子さま、さらに中学受験をしながらCrefusに通い高校生になった生徒さん、Crefusの先生にもお話を伺いました。


2025/09/10

AI・ロボット時代を担う人材を育むために

これから、ロボット検定®はどのように広がっていくのでしょうか?機構としてめざしている点についてもお聞かせください。
ロボット検定®の認定校をもっともっと増やし、受験しやすい環境を整えて、たくさんの小中学生、高校生の皆さんにロボ検®を受けていただきたいと思っています。
さらにロボティクス工学やロボット産業の発展に向けて、小学生や中学生のうちから、ものづくりとテクノロジーの両方を体験できるロボットプログラミングに触れる機会を提供したいと活動しています。
最近では公立校への出張授業なども行っています。一定期間、ロボットの授業を行った後にロボット検定®を確認テストのように行ってもらう取り組みもしています。
SDGsなどの課題をテーマにして、ロボットとテクノロジーで課題解決をしていく力を育み、やがては優秀なロボット技術者として、AI・ロボット時代を担う人材がたくさん誕生することを願っています。
未来のロボット技術者をめざして「ロボ検®」にチャレンジしてみよう!
ロボット検定®は、年に2回開催されています。まずは受けてみることで「自分に何が足りないか」がわかります。そして次のチャレンジにつながります。
ぜひ、あなたもロボット検定®を受けてみませんか?


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
(レポート)JAXA研究者とロボティクスベンチャーが語るSTREAM教育の可能性と新しい検定制度「創ロボ検定」
子どもたちに学びの機会を提供するため2023年6月に設立された、一般社団法人未来創生STREAM教育総合研究所(以下、RISE)。同法人が展開する新しいロボットプログラミング検定「創ロ...
2025.05.30|大橋礼
-
全国小学生プログラミング大会「ゼログラ」開幕! 企画者に聞くバトル戦の魅力
2021年12月、小学館が運営する新しいプログラミング大会「ゼロワングランドスラム(略称:ゼログラ)」が開幕します。プログラミング大会には個人のコンテスト形式が多いなか、ゼログラはなぜ...
2024.11.06|原 由希奈
-
(詳細インタビュー)「プログラミング能力検定」とは?新学習指導要領に準拠、大学入試対策にも
今回、新たにスタートする「プログラミング能力検定」。文科省公表の「情報Ⅰ」に基づく設計で、大学受験対策にもなるのが魅力の検定試験です。 第1回検定は2020年12月7日~12月13日...
2025.06.24|夏野かおる
-
(取材)フランス発のエンジニア養成機関「42 Tokyo」にキッズドアから合格者が誕生!合格率4%の難関突破までの...
子どもたちへの学習支援・居場所提供などの事業を展開する「NPO認定法人キッズドア」。そんなキッズドアから、この度フランス発のエンジニア養成機関「42 Tokyo」へ見事合格を果たした生...
2025.09.10|ちとせとも
-
(取材)Mind Renderで3Dゲーム制作、高度なプログラミングに挑戦|聖光学院・特別授業のようすをお届け
プログラミング教育の高度化が進むなかで、「拡張性があり、中高生の興味を引く教材」として注目されているのがMind Render(マインドレンダー)です。この記事では、Mind Rend...
2025.09.10|大橋礼



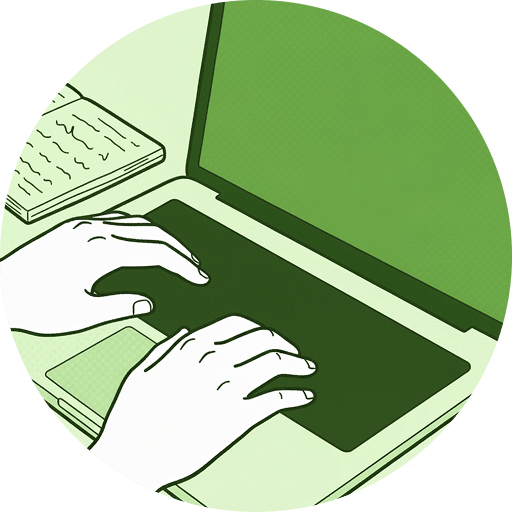




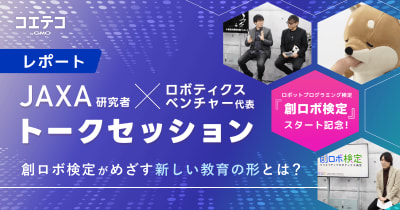
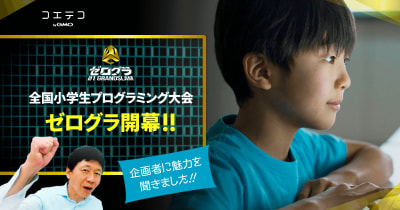



最初に、ロボット検定®が誕生した背景について教えてください。