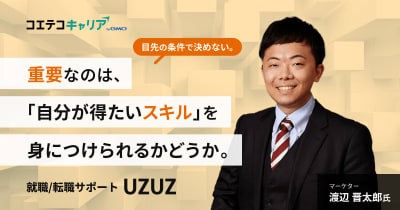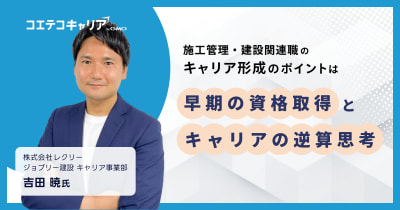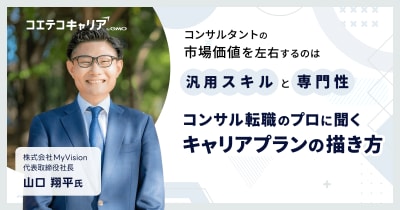※ 当サイトは、有料職業紹介(許可番号13-ユ-316281)の厚生労働大臣許可を受けたGMOメディア株式会社が運営しています。
-
今回お話を伺った方
-
株式会社ファンオブライフ 代表取締役
糸岡 樹慧氏教育業界出身、不登校児支援や家庭教師派遣事業を手掛ける。2016年ファンオブライフ参画、2020年アガルートグループ参画後は代表としてグループ各社経営・採用全般にも参画。HR領域での業界特化型転職エージェント・育成案件多数。『YOU TRUST』『アガルート公式』『LINE WORKS』『日本組織内弁護士協会』等でインタビューやリーガル・教育人材領域での取組み解説・キャリア対談経験多数。教育×人材領域の架け橋とサービス拡張に取り組む。
-
弁護士や法務職は、その専門性の高さから多岐にわたるキャリアパスを選択できる魅力があります。しかし、選択肢が多いがゆえに、自身に最適な進路を見極めることに悩む方も少なくありません。
そんな中、弁護士や法務職に特化した転職支援サービスを提供する「アガルートキャリア」は、高い専門性を活かしたサポートで、多くの求職者のキャリア形成を支援しています。
今回は、「アガルートキャリア」を運営する株式会社ファンオブライフ 代表取締役 糸岡 樹慧氏に、リーガル領域の転職市場の動向やキャリア構築のポイント、さらには転職活動における注意点について詳しくお話を伺いました。
弁護士・法務職の転職市場とは?「アガルートキャリア」の立ち上げに携わった糸岡氏に聞く
ー早速ですが、糸岡さんのご経歴について教えてください。私のキャリアは教育業界からスタートしましたが、2015年に弊社の創業者と出会ったことが大きな転機になりました。当時、彼は教育業界に特化した転職エージェント事業を立ち上げたばかり。教育業界専門の転職エージェントはまだ少なく、この分野の可能性に大きな魅力を感じて、最初の従業員として事業に参画することを決めたのです。
教育業界での勤務経験を持つ私にとって、「教育×人材」というビジネスモデルは非常に魅力的でした。事業の成長を支える中で、幅広い経験を積む機会にも恵まれました。
2020年には弊社がアガルートグループに加わり、新たにリーガル領域でのキャリア支援事業を展開することとなりました。この新事業の立ち上げにも携わり、弁護士や法律事務所、企業法務部門の方々とのやり取りを通じて、コンサルタント業務も経験しました。
そして、2022年6月には代表取締役に就任。現在は経営全般に携わりながら、さらなる事業成長を目指しています。
ーアガルートキャリアでは、弁護士や法務職に特化した転職サービスを展開していますね。この領域におられる方々の転職市場の動向を教えていただけますか?
総論として申し上げると、中途採用市場における弁護士や法務職の需要は非常に高い状況です。理由は以下の3点です。
1. 新規事業における法務チェックの重要性
新規事業を立ち上げる企業が増える中で、「新しいビジネスが法的に問題ないか」「グレーゾーンに該当しないか」といった法務チェックの重要性が高まっています。このような課題を解決するには、法務的な専門知識を持つ人材が欠かせません。
2. 海外展開に伴うリスク評価の需要
国内市場の成長が鈍化する中で、海外展開を目指す企業が増加。これに伴い、「海外の法律面からビジネスリスクを評価してほしい」といった相談が寄せられるケースが増えています。そのため、海外法務に精通した人材の需要が拡大しています。
3. コンプライアンス意識の向上
企業全体でコンプライアンス意識が向上していることも、リーガル人材の需要を押し上げる要因です。たとえば、従業員教育の一環としてコンプライアンス研修を強化する動きが広がっており、その推進役として法務人材が重視されています。適切な対策がなされない場合、経営リスクに直結する可能性があるため、企業にとっては見過ごせない課題です。
一方で、新卒採用でこれらの専門性を備えた人材を確保するのは困難です。そのため、多くの企業が中途採用に頼り、即戦力となるリーガル人材を外部から迎え入れています。この背景から、転職市場におけるリーガル人材の需要は今後も増加が続くと考えられます。
ー法律事務所における中途採用の場合はどうでしょうか?
法律事務所における中途採用は、事務所の規模や成長度合いによる部分が大きいです。例えば、Webサービスのようなモデルでは人員を増やさずとも売上を倍増させることができますが、弁護士の場合はクライアントワークで知的労働を集約するモデルなので、弁護士の人数を増やさなければ事業拡大が難しいという特徴があります。そのため、成長している事務所ほど積極的に採用を進めている傾向があります。
弁護士や法務職が市場価値を高めるためのキャリアパス戦略とは
—弁護士や法務職の方々がキャリアプランを描くにあたっては、どういったところを意識すべきでしょうか?弁護士や法務職の方がキャリアプランを描く際には、「自分の専門性をどこに置くか」を意識することが重要です。キャリアに正解はありませんが、このポイントを明確にすることで、より戦略的な道筋を描けるようになります。
たとえば弁護士であれば、離婚裁判や債務整理に強い方もいれば、企業のM&Aや企業間訴訟、ファイナンスに特化している方もいます。法律が関わる分野は非常に広いため、まずは自分がどの分野に興味があり、どこで強みを発揮できるかを見極めることが大切です。
また、キャリアが進むにつれて「何でもできる人」が「器用貧乏」と見なされるリスクも生じます。特にキャリアが上に行けば行くほど、採用においては「この分野に強い」という専門性が求められることが増えます。そのため、自分の専門性を深めるとともに、市場のニーズと一致しているかを意識することが、キャリア成功の鍵となるでしょう。
ー弁護士や法務職の市場価値を左右する要因は何でしょうか?
法律事務所と事業会社で異なる部分もありますが、共通して重要なのはリーガルの専門性を活かして課題を解決できる能力です。
以前は「この解釈はこうなります」と答えるだけの弁護士像が一般的だったように感じます。しかし、現在求められているのは、「法的リスクはあるがこうすれば実現可能」「このスキームでは難しいが、この方法なら達成できる」といった、ビジネスに寄り添った提案ができる人材です。
採用担当者からも、「法律の専門性を活かしてビジネスを前進させる提案力を持つ人はまだ少ない」という声をよく耳にします。そのため、課題解決力や提案力を兼ね備えたリーガル人材の市場価値は、今後ますます高まるでしょう。
ービジネスに寄り添った提案スキルを身につけるのは難しいですよね。どのようにすればよいでしょうか?
確かに簡単ではありませんが、重要なのは実践経験を積むことです。ビジネスに寄り添った提案スキルを身につけるためには、若いうちから自分が主体的に顧客と向き合える環境を選ぶことが大切だと考えます。
たとえば、法律事務所の場合、大規模な事務所よりも比較的小規模な事務所のほうが、クライアントと直接関わる機会が多い傾向があります。大規模事務所では上司やパートナーの指示を受けて作業することが中心となりがちですが、小規模事務所では顧客の課題解決に最前線で携わる機会が増えます。このような場面を通じて、顧客折衝や意思決定に関わる経験を積むことで、提案スキルは自然と磨かれていくでしょう。
もちろん、大規模事務所にも多くのメリットがあります。大規模案件に携わる経験や、優秀な弁護士から知識を吸収する機会は、大手ならではの魅力です。
どちらを選ぶべきかは、「若いうちに何を優先して経験したいのか」によります。この優先順位を明確にしたうえで、自分の目指すキャリアに適した進路を選ぶことが重要です。
転職成功のカギ!弁護士や法務職の転職は難しいのか
ー弁護士や法務職の方が転職サービスを選ぶ際には、どういったポイントを重視すべきでしょうか?専門性の高い職種の場合は、特化した転職エージェントを利用することをおすすめします。一般的な総合エージェントでは、弁護士や法務職特有の業界背景や用語が十分に理解されず、ミスマッチが起きるリスクがあるためです。
たとえば、弁護士が「ワークライフバランスを整えたい」という転職理由を話した場合、業界に詳しくないアドバイザーは「定時で上がれる職場を探す」といった的外れな提案をすることがあります。しかし、弁護士の「ワークライフバランス」のニーズは、単に労働時間を短縮するだけではなく、業務内容や負担の調整を求めるケースが多いのです。
また、弁護士業界では「ビラブルアワー」(課金可能時間)や「プラクティス」(専門分野)などの専門用語が頻繁に使われます。これらを理解していないアドバイザーでは、求職者との意思疎通が難しくなり、転職理由やキャリアビジョンを正確に把握することができません。また、キャリアアップのために「留学」を検討する場合も、業界知識が乏しいアドバイザーでは適切な提案が難しいでしょう。
専門性の理解が不足しているアドバイザーの場合、求職者の転職理由やキャリアビジョンを十分に把握できず、結果的に手持ちの求人をただ提示するだけの対応になることもあります。そのため、「このエージェントでは転職活動が思うように進まなかった」と感じて再相談に訪れる方も少なくありません。
関連記事:弁護士転職に強いエージェント
ー転職サービスを最大限活用するためには、どのような努力や意識が必要だと思いますか?
転職サービスを活用して成功するためには、求職者自身の努力や意識も重要です。以下の3つのポイントを押さえることで、転職活動をより有意義なものにすることができます。
1.自分の情報をしっかり開示する
転職エージェントを有効活用するには、自分の情報を正確に、かつ具体的に伝えることが大切です。現在の年収、興味のある分野、重視する条件などを率直に共有することで、エージェントは求職者の希望に合った提案をしやすくなります。情報を開示することに抵抗を感じる場合もありますが、適切な情報がなければエージェントは最善のサポートを提供できません。具体的な情報を伝えることは、より精度の高いマッチングにつながる重要なステップです。
2.柔軟な姿勢で視野を広げる
転職活動では、業界や職種にこだわりすぎず、柔軟な姿勢で可能性を探ることが大切です。「この業界でしか働けない」という固定観念を捨て、自分のスキルや経験を異なる分野でどう活かせるかを考えると、新たなキャリアの道が見えてくることがあります。
特に弁護士などの専門職に多いリファラル(紹介)転職は安心感がある一方で、条件交渉の難しさや紹介者への配慮から断りにくいといったデメリットがあります。また、リファラル求人は全体の1〜2%程度と非常に限られているため、それだけに頼るのは危険です。
そのため、リファラルがあった場合でも転職エージェントを併用することをおすすめします。エージェントを活用することで、非公開求人や詳細な企業情報にアクセスでき、自分に適したポジションをより広い視点で探せます。
3.日常的に情報収集を習慣化する
転職活動は、突発的な状況で始まることも珍しくありません。たとえば、上司の異動や会社の方針変更など、外的要因がきっかけになる場合があります。このような予期せぬ変化に備えるためには、普段から求人情報や市場動向を確認し、自分の市場価値を把握しておくことが大切です。求人情報を日常的にチェックすることで、自分のスキルがどの程度評価されているかを把握し、適切なタイミングで冷静な判断ができるようになります。また、エージェントと定期的に情報交換を行うことも有効です。エージェントは、客観的な意見や市場の最新情報を提供してくれるため、いざというときに頼れる存在となります。
依頼者の権利や利益、人権などを守るべく、各種法律事務を担う「弁護士」。独占業務を持つ士業の一つであることから需要は高い一方で、高度な法律知識が求められるため、転職は簡単ではありません。少しでも効率よくキャリアアップを図りたいなら「転職エージェント」を利用するのがおすすめです。この記事では、転職を考えている弁護士にぜひ活用いただきたいおすすめ転職エージェントを、数ある中から厳選してご紹介します。
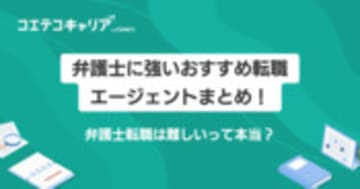

2026/02/09

プロフェッショナル領域専門の転職エージェント「アガルートキャリア」の魅力

ーではいよいよ、弁護士や法務職などのプロフェッショナル領域専門の転職エージェント「アガルートキャリア」について教えて下さい。御社のサービスの強みや特徴、他社と比べて優れている点とは?
「アガルート」ブランドの高い認知度は、当社の大きな強みです。特に若手弁護士層では、「アガルートアカデミー」で司法試験を突破した方が、そのまま自然に「アガルートキャリア」を利用する流れができています。
関連記事:司法書士通信講座・予備校おすすめランキング5選
また、予備校運営を通じて構築した法律事務所や企業との強固なネットワークも、他社にはない特徴です。
例えば、採用の現場で「どの予備校で学びましたか?」という話題になると、「アガルートアカデミー」の名前が頻繁に挙がります。この信頼感が、採用活動を円滑に進めるだけでなく、卒業生がキャリア相談に戻ってくる好循環を生み出しています。
さらに、当社のコンサルタントは人材紹介業での豊富な経験を持ち、弁護士や管理部門などの専門領域に特化したメンバーが揃っています。一人ひとりの求職者に寄り添い、個々のニーズに合ったアドバイスを提供することが、私たちのサービスの大きな特徴です。
ー御社が大切にしている価値観や思いについて教えていただけますか?
転職の主役はエージェントではなく、あくまで求職者の方々自身です。私たちはその伴走者として、求職者が最適な意思決定をできるようサポートすることを使命としています。
キャリア相談では、ご本人以上にその方のキャリアについて真剣に考えることを心がけています。求職者の方と真摯に向き合い、信頼できるパートナーシップを築くことを大切にしているため、短期的な利益を優先して転職を促すようなことは決してありません。
長期的な信頼関係を築き、まっとうなキャリア支援を行うことを最も大切にしています。
ー最後に、キャリアに悩む方々に向けてメッセージをお願いします。
リーガル人材の需要は高まり続け、選択肢が多様化しています。これは喜ばしいことですが、選択肢が増えることで迷いも増え、より一層難しくなっているのも事実です。
そこでおすすめしたいのが、キャリアの「かかりつけ医」のような存在を見つけることです。普段、キャリアについて深く考える機会は少ないかもしれません。しかし、定期的に相談できる相手がいることで、キャリアを見直すきっかけが生まれ、効率的な情報収集が可能になります。
私たちがその役割を担わせていただけるなら、全力でお力になります。ご相談いただいた結果、「今は転職しない」という選択に至ることもあるでしょう。それでも問題ありません。重要なのは、情報収集を続け、適切なタイミングで行動できる準備を整えることです。
転職は短期的な決断ではなく、長期的なキャリア構築の一環です。ぜひお気軽にご相談ください。一緒に、最適な未来を見つけていきましょう。