※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
※ 当サイトは、有料職業紹介(許可番号13-ユ-316281)の厚生労働大臣許可を受けたGMOメディア株式会社が運営しています。
2025年、育児休業制度が変わりました。小学校就学前のお子さんがいる方の働き方がより柔軟になり、看護休暇の対象も広がります。
このコラムでは、2025年の育児休業制度における改正内容をわかりやすく解説します。
実際に育休を取得した、あるいは諦めた先輩ママたちの体験談も掲載。ぜひ参考にしてください。
また、下記記事では、保育士から異業種転職を目指す際に活かせるスキルや、おすすめの仕事を紹介しています。
保育士だけに限らず、異業種転職を目指す方にも有益な情報が記載されているため、ぜひ参考にしてみてください。
保育士から異業種や違う仕事への転職は可能!資格を活かせる高収入な仕事を解説
育休制度の改正2025「一発でわかる一覧表」
育休制度の施行前・後はスクロールしてご覧ください!| 2025年4月1日から施行 | ||
| 子の看護休暇の見直し【義務/就業規則等の見直し】 | ||
| 改正内容 | 施工前 | 施工後 |
| 対象となる子の範囲の拡大 | 小学校入学に達するまで |
小学校3年生修了まで ■Point!■ 学童対象として多い小3の修了まで、 拡大された。 |
| 取得する事由の拡大 | ①病気・けが ②予防接種・健康診断 |
①病気・けが ②予防接種・健康診断 ③感染症に伴う学級閉鎖 ④入園(入学)式、卒業式 ■Point!■ 学級閉鎖や入学式も対象に! |
| 対象外となるケース | ①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6ヶ月未満 |
①週の所定労働日数が2日以下 ※②を撤廃 |
| 名称変更 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |
| 残業免除の対象拡大【義務/就業規則等の見直し】 | ||
| 請求可能となる労働者の範囲の拡大 | 3歳未満の子を養育する労働者 | 小学校就学前の子を養育する労働者 |
|
短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 ※時短の代わりとなる措置の選択肢が増える | ||
| 代替措置の追加 | ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等 |
①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等 ③テレワーク ■Point!■ 3歳未満の子がいる場合は、テレワークを 選択できるようにすることが「努力義務化」 された! |
| 育児休業取得状況の公表義務適用拡大 | ||
| 公表義務の適用となる企業の拡大 | 従業員1,000人超の企業 | 従業員数300人超の企業 |
|
2025年10月1日から施行 | ||
| 柔軟な働き方を実現するための措置 | 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、 2つ以上の措置を選択して講ずる必要がある。 ①始業時刻等の変更 ・フレックスタイム制度や始業または就業の時刻を繰り下げ、繰り上げる制度 ②テレワーク等 ・月に10日以上利用できる ③保育施設の設置等 ・保育施設の設置や、ベビーシッターの手配および費用負担など ④働きながら子を養育することを容易にするための休暇 ・1日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの ⑤短時間勤務制度 ・1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの ■Point!■ 全部ではなくて、最低でも上記のうち2つはやろうねってこと。 たとえば、時短+フレックス+必要に応じてテレワーク、みたいなことで 子育てと仕事の両立をしやすくしようという試み。 |
|
|
柔軟な働き方を実現するため 個別の周知・意向の確認 ■Point!■ うちの会社では子育てと仕事の 両立がしやすいように こんな制度があるよ!と知らせる、 伝えなくてはいけないってこと! |
周知時期 | 子が3際の誕生日の1ヶ月前までの1年間 |
| 周知するべきこと | ①事業主が選択した対象措置(2つ以上)の内容 ②対象措置の申出先(人事部など) ③残業免除などに関する制度 |
|
| 周知・意向確認の方法 | 面談・書面交付・FAX・電子メールのどれか | |
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内/厚生労働省をもとに作成
2025年育休制度の改正!4つのポイントをわかりやすく解説

- 柔軟な働き方が義務化に
- テレワーク導入を企業に促進
- 看護休暇の拡大
- 育休取得状況の公表義務拡大
働き方改革の本格始動!柔軟な働き方が義務化に
2025年から、事業主には小学校就学前の子どもを育てる労働者に対して、柔軟な働き方を提供することが義務付けられます。- 短時間勤務制度の導入
- フレックスタイム制の実施
- 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
- 所定外労働の制限
改正により、保育園などへの送り迎えや急な発熱にも対応しやすくなります。育児中の方々の働き方の選択肢が広がることで、より充実した仕事と育児の両立が期待できます。
近年需要が高まる職種では、労働力不足を解消するために働き方改革が進みつつあります。
下記記事では相談援助や福祉サービスの提案・調整を行う専門職である社会福祉士に強い転職支援サービスを紹介しています。
働き方改革が進む業界や職種への転職を検討している方は、下記記事もチェックしてみてください。
社会福祉士に強い転職サイト・エージェントおすすめ!
在宅勤務で育児との両立を!テレワーク導入を企業に促進

3歳未満のお子さんがいる労働者向けに、企業にテレワーク導入の努力義務が課されます。通勤時間の削減や急な子どもの体調不良にも対応しやすくなり、育児中の方々の負担軽減が期待されます。
※努力義務とは:努力義務とは、法律や規則において「〜するよう努めなければならない」と定められた義務のことです。法的拘束力は弱く、違反しても直接的な罰則はありません。
看護休暇の拡大で子育ての不安を解消
2025年4月1日からは、子の看護休暇の対象が大きく広がります。- 対象年齢が小学3年生まで拡大
- 学級閉鎖への対応が可能に
- 入園式や卒園式などの行事参加も対象に
これまで悩みの種だった学級閉鎖時の対応や、大切な行事への参加がしやすくなります。
対象年齢も小3まで拡大されます。
企業の取り組みを可視化!育休取得状況の公表義務拡大
育児休業の取得状況の公表義務が、より多くの企業に拡大されます。公表する=この会社は男性も育休けっこう取っているんだな、とか、女性の取得は多いな、とわかるわけです。「名ばかり制度」を減らす効果が期待できますね。この公表義務は、従業員数300人以上の企業が対象となりました。
これまでは育休取得の公表義務は、従業員1,000人以上が対象だったから、それこそ超大手企業で、ほんの一部だった。でも、300人以上っていうのも、かなりの規模ですねぇ。
300人超でも、まだまだ……というところですが、それでも公表義務が拡大したことは大きいですね。
育休制度は上昇はしているけれど「課題もある」
厚生労働省の最新データによると、育児休業取得率は以下の通りとなっています。
| 女性 | 84,1% |
| 男性 | 30.1% |
女性の取得率は横ばいのようですが、特に男性の取得率は年々上昇傾向にあります。これを見ると多くの女性が育休を活用しています。
育休は多くの企業に制度として導入はされていますが、実際にそれを利用できる・利用しやすい環境にあるかは、また別の問題です。
企業規模による格差は依然として課題
大手企業と中小企業では、育休制度の充実度に大きな差が見られます。大企業:制度が充実し、取得率も比較的高い
中小企業:人員不足などにより、取得が困難な場合も
この格差解消が、今後の重要な課題となっています。では、実際に育休制度を利用しなかった、できなかった、あきらめた人の体験談から見ていきましょう。
続いて、育休制度を利用した先輩ママ達の声もピックアップしたので、参考にしてくださいね。
体験談「先輩ママたちが語る育休制度の実態」

育休制度の取得を諦めた人々の声
育休制度はあるものの名ばかり制度。というか、会社全体で20名程度、育休取得で1年も休むとなると、同部署の人にかかる負担が大きすぎて。
社長自らに「1年間休んでもらって、その間に派遣社員さんを入れるのも考えたけど、けっこうお金がかかるんだよ。かといって、誰かがあなたの分を働くというのも無理があるし、分担できるような仕事でもないし。いったん辞めてもらって、子育てが落ち着いたら、たとえばパートとかでフルタイムに近い形で採用するよ」と言われました。
けっこう厳しそうだったから、結局はここで人を減らして、入れるにしてもパートさんにして、と思ったみたいです。小さい会社だし、育休なんて無理だよなと早々に諦めました。(Rさん/当時の勤務先:製造業)
昭和の社長ががんばっている零細企業で、育休なんて「なにそれ」状態ですよ。
「育休を取って復帰しようかと」と一応話したけど、「あ〜、そういうのがあるみたいね、ウチじゃ無理」とけんもほろろ。
人数が少ない会社では、ひとり欠けたらカバーしきれないのが現実でもあるし、会社の事情もわかるところはあるし。
77歳で現場にも出ている現役社長に、『労働基準局がー』『法的にはー』とか、話したところで何になる……。悪気がなくて、「よかったじゃないか、子どもができて。出産したらお祝いを奮発するぞ」なんて言うんですから。(Tさん/当時の勤務先:小売業)
育休取得者の体験談から学ぼう

育休の制度も定着し、何人もの先輩女性が取得しているので、特に手続き等も面倒ではなかった。
ただ、直属の上司への相談時期や、たとえば育休を取る前に部署の人達に菓子折りをわたして挨拶したほうがいいのか、みたいな細かいことはよくわからなくて困ったかな(Sさん/大手メーカー)
39歳の出産で、子育てに全力投球したい気持ちが強かったので、育休制度はありがたかったですね。
中堅企業ですがフレキシブルに対応してくれて、通常は1年の育休ですが、わたしは約3年とりました。
かなり特殊ですが、おかげで子どもが立って歩く、話し出すといった日々の成長を見られて良かったです。
ただし、当時は育休の給付金は少なく期限もあったから、収入面での不安はありました。高齢出産だった分、共働きで貯蓄もあったのでなんとかなった記憶があります。
あとは、子どもが2歳になって保育所を探したのですが、なかなか入れなかった(保育園は0歳児で入所して、そのまま持ち上がるので2歳児以降の枠があかない)です。(Aさん/不動産デベロッパー)
ベンチャーで多様性やらワークライフバランスとか派手に宣伝しているわりには、育休が取りづらい雰囲気があって、ビックリした。現職を辞めて新たな業界や業種でキャリアをスタートする人も少なくありません。
「あー、育休、うん、そうだね。どうしようか」みたいな感じ。
でもダメとは言われなかったし、自分で申請とか確認して会社任せにはしなかった。
部署の同じグループのメンバーには丁寧に相談して、引き継ぎも私が扱っている資料などもわかりやすく整理して、産後すぐでもわからなかったら普通に連絡してね、と伝えて安心してもらうよう根回しもした。
約10ヶ月の育休を取得はしたけど、半年目くらいからはリモートで会議やプロジェクトの壁打ちに参加させてもらうことができたのは、復職後、比較的スムーズに戻れたので良かったことかな。
誰かがこうして育休を使って、その後は復職して以前同様に働くっていうのをやっていかないと、「それが当たり前」にならないから、頑張りました。(Mさん/IT企業)
下記記事では、保育士から異業種転職を目指す方におすすめの転職先や失敗しない仕事の選び方を解説しています。
今の仕事を継続するか悩んでいる人は、下記記事にも目を通しておきましょう。
保育士を辞める人の次の仕事は?おすすめの転職先と選び方を紹介
新制度で変わる育児と仕事の両立
学級閉鎖問題にも対応可能に
新制度では、小学生の子どもを持つ親の大きな悩みであった学級閉鎖への対応が可能になります。看護休暇の拡大により、突然の学級閉鎖にも柔軟に対応できるようになります。これは大きいですね。学級閉鎖になると、学童にも行けないので、小1の子をひとりで留守番もさせられず、夫婦が交代で有給取る、キッズシッターを頼む、とか、けっこう大変ですから。
多様な働き方で実現する仕事と育児の両立
リモートワークや短時間勤務など、いろいろな選択肢を組み合わせることで、より柔軟な働き方が実現できます。職種によるところはありそうだけど、在宅勤務がある程度できれば、それこそ子どもの体調が悪い時も対応しやすいですよね。
下記記事では、認可保育園・認可外保育園・認証保育園など各保育園形態の違いや自己分析の方法について解説しています。
自分らしい働き方を実現したいと考える方は、下記記事も併せて一読しておきましょう。
ゼロから始める保育士への道:第2回 就職先選びで迷わない!自分に合う働き方とは
ゼロから始める保育士への道:第3回 ミスマッチを防げ!保育士就活を成功に導く自己分析とは
これからの育休制度
体験談にもありましたが、大企業では育休制度の導入も実施率も伸びていますが、小さな会社や現場の多い職種ではどうでしょうか。従業員数が少ない職場では、育休を実施しようにも、その間の「ひとり分」の業務をどう割り振ればいいのか。人手不足の上に体力のない会社では、その期間だけ別の人を雇用するのが難しいことも実際にあるでしょう。
企業も助成金などをうまく活用してほしいですね。
今回の改正後も、以下のような課題は残されています。
- 中小企業での取得率向上
- 男性の育休取得促進
- 収入面でのサポート強化
小さい会社なりに工夫して、育休が取れるようにしているところもあります。こうした事例を多く広げて、企業の規模・業界・職種にかかわらず、育休を取得しやすくなるといいですね。
人手不足が叫ばれる保育士は、近年働き方改革が進む業界の一つです。
下記記事では保育士になるまでのロードマップについて解説しています。
保育士就職を目指す方は、下記記事もチェックしてみてください。
保育士になるには?やりがいや必要なことを徹底解説
働きたい女性が出産・子育てのハードルを軽々と乗り越えていけるように
2025年の育休制度改正は、働く親たちの生活を大きく変える可能性を秘めています。柔軟な働き方の実現、看護休暇の拡大など、具体的な改善策が導入されることで、より多くの方が育児と仕事を両立できる環境が整います。この改正を機に、育児に参加しやすい職場環境づくりが進み、誰もが自分らしく働ける社会の実現に一歩近づくことが期待されます。まずは自分の職場の制度を確認し、新しい制度を積極的に活用していきましょう!

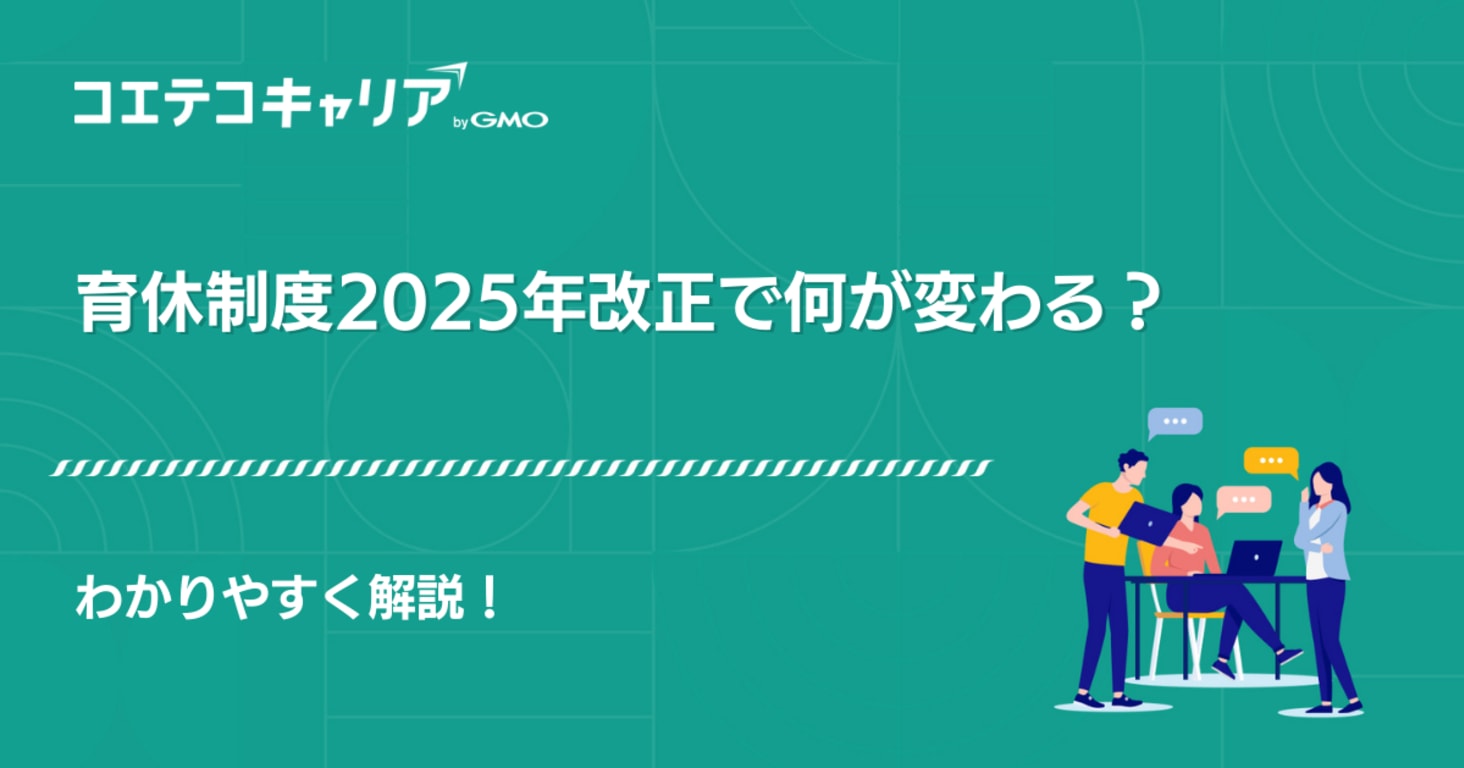




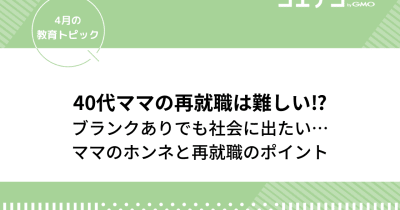

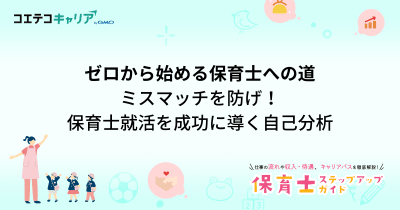


会社はできるだけ努力しなさいよ〜、というわけで、コンプラに厳しい企業だとか子育て世代に手厚い会社以外だと、「努力してるんだけどね〜」で終わってしまう可能性もあるのかな。