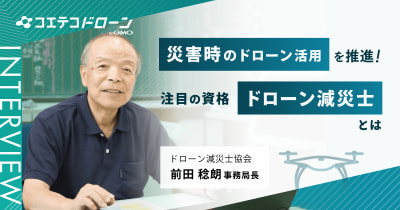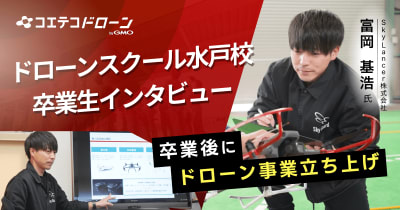ドローン減災士協会×ドローン教習所福岡校:災害対策に新たな風「ドローン減災士」が拓く未来

今回お話を伺ったのは、ドローン減災士協会理事であり、株式会社T&Tドローン事業部部長の中田耀介氏と、ドローン教習所福岡校の西耀一朗氏。西氏はドローン減災士資格を取得し、自身が運営するスクールでもドローン減災士コースを開講しました。ドローン減災士資格とはどのような資格なのか、災害対策にどのように役立てられるのかを詳しく伺いました。

防災・減災の知識&ドローンの知識・技術を兼ね備えたプロ人材
——ドローン減災士とは一体どのような資格なのでしょうか。中田:
ドローン減災士とは、防災減災の知識とドローンの知識・技術を兼ね備えたプロフェッショナル人材を育成するために設立した資格制度です。
近年、日本では多くの災害が発生しており、防災が重要視されていますが、完全に防ぐことは難しい状況です。そのため、どうやって被害を抑えるかが注目されています。減災のシーンでドローンの利活用が進んでおり、災害時にドローンをどう使うか、その可能性までを掘り下げて学ぶのが、この講習の趣旨です。

ドローン減災士協会理事・株式会社T&Tドローン事業部部長 中田耀介氏
——ドローン減災士資格のカリキュラムでは、どういった内容を学べるのでしょうか。
中田:
講習ではまず「自助」の考え方、つまり自分がどうすれば被害に遭わないかを学んでいただきます。どれだけドローンの扱いに長けていても、自分が被災者になってしまっては本末転倒だからです。そのため講習では、まず自助を学んだ上で、災害のメカニズムや地震の種類、豪雨災害の傾向、地域での防災活動や過去の災害事例などを学び、ドローンがどのような場面で活用できるかを掘り下げていきます。
また、ドローンをただ飛ばすだけでなく、平時から各自治体や消防機関と連携することで、ドローンの効果を最大限に発揮する方法も学びます。これを踏まえて、最後にやっとドローンの知識・技術を学ぶ流れです。
——コースの種類や受講日数について教えてください。
中田:
主なコースは「2日間コース」です。国土交通省認定団体資格のフライト基礎資格を持っている方が対象で、2日間のカリキュラムの中で資格試験を行い、合格すればドローン減災士を取得できます。このほか、「フライト基礎資格」と「ドローン減災士」の両方を取得できる「5日間コース」も展開しています。
ただし、スクール独自のカリキュラムを組み、日程を短縮したコースを提供しているケースもあります。コースの詳細は、お近くのスクールにお問い合わせください。
——ドローン減災士資格を受講されるのは、どのような方が多いのでしょうか?
中田:
加盟校全体では、防災士資格を持っている方や、すでにドローン事業を行っている方が事業拡大を目指して受講することが多いです。
一方で本部校では、自治体職員や消防士、消防団員の方が多く受講されています。また、大学生や高校生が、将来の就職を見据えてスキルアップのために受講するケースも増えてきています。消防士を目指す高校生が「面接でアピールするために」と来られたこともありました。高校生から社会人まで、幅広い年代の方を随時受け入れていますのでお気軽におたずねください。
なぜ今、ドローン減災士に?資格取得者に聞く
——ここからは、ドローン減災士資格を取得された西様に詳しくお話を伺っていきたいと思います。資格を取得しようと思ったきっかけをお聞かせいただけますか。西:
もともと、当スクール(ドローン教習所 福岡校)の受講生向けに新たなコースを展開したいと考えていました。そんな中、ドローン減災士協会の理事兼事務局長である前田稔朗さんが、兵庫県から福岡の弊社に来てくださり、ドローン減災士について詳しくお話を伺う機会があったんです。
ドローン減災士のお話を聞くまで、「減災」という言葉はあまり聞いたことはありませんでした。また、防災や減災に関するドローンの講習を提供しているスクールも近隣では見かけませんでした。
しかし、九州では近年大雨による災害が度々発生しております。九州全体で防災意識が高まるなか、防災・減災に活かせるドローン減災士資格を取得できるコースを新設すれば、社会的な意義も大きいと考えました。そこでまずは、自分自身がドローン減災士の資格を取ることにしたんです。

ドローン教習所福岡校 西耀一朗氏
——実際に受講されてみて、いかがでしたか?
西:
中田さんからもお話があったとおり、学科では、自助・共助・公助の講義が中心で、ドローンの話はほぼ出ませんでした。「自助」は、一人ひとりが自ら取り組むこと。「共助」は、地域や身近にいる人どうしが一緒に取り組むこと。「公助」は、国や地方公共団体などが取り組むことであり、災害の被害を軽減するためには、この3つを意識することが重要だと教わりました。
中でも印象に残ったのは、自分が助からなければ、他の人を助けられないというお言葉です。たとえば、僕は視力が悪いためコンタクトを使っていますが、災害時にはコンタクトは使えません。目が見えなければ、救援活動に参加するどころか、自分自身が被災者になってしまうんです。
このようなお話を伺ったことで、メガネを買い替えるなど、自分自身の防災意識も高まりました。最近は講習をする立場にもなっているので、受講生たちに範を垂れるためにも、気をゆるめずに備えていきたいですね。

——実技の講習はいかがでしたか?
西:
実技では、スピーカーを搭載した災害対策用のドローン、スピーカードローンを見せていただきました。これを使えば、赤外線カメラを使ってがれきの中に埋もれている人を探したり、その人たちに呼びかけたりできるそうです。こんな使い方ができるのか、と驚きました。
そして、自らもドローン減災士を育てる立場へ
——ドローン教習所 福岡校ではドローン減災士のコースがありますが、こちらのコースを開設された背景を改めて伺えますか。西:
弊社は2017年以前からドローン事業を展開しており、開校以来2,500名以上の受講者を輩出しています。しかし受講者の多くは、講習を受けて資格を取って終わってしまうケースが多く、そこに課題を感じていました。
資格を取得された受講生の方々が、「資格をどのように活かせばいいのか」といったビジョンを描けるような、付加価値を提供できる講習を作りたい。そう考えていた時に、ドローン減災士協会の前田さんのお話を聞いたことで、ドローン減災士コースを新設しようと決めました。
今年の春頃からスタートしたので受講生はまだ少ないものの、防災士の資格を取得した方や、防災や減災に興味があり、自分にできることを模索したいと考えている方が多くお越しになっています。福岡県の防災体制を強化するためにも、これから受講生が増えてくれると嬉しいですね。

——皆さん強い思いを持って受講されているのですね。受講生の反応はいかがですか。
西:
私自身もそうだったように、自助・共助・公助の講義内容に驚き、気を引き締めたという方が多いです。例えば自助について、「家具を固定したり、レイアウトを工夫したりすることで災害時の被害を抑えられる」と伝えると、8〜9割の方が「そうだったのか、うちはやっていないので危ないな」と反応されます。
講習の内容を受けて、実際に家に帰ってから教わった内容を実行しようとする方も多いですね。救援活動に加わるためには、まずは自助に務めるのが大事だということを、講座を通してしっかりとお伝えしています。

西:
そうはいっても、実際に地震が起きたときに、個人で救助活動を行うのは難しいです。そもそも、スピーカードローンを個人で所有するのは非現実的ですし、自治体と連携しなければ現地の迷惑になってしまう可能性もあります。
九州地方は、南海トラフ地震で大きな被害を受けるリスクがあります。災害自体は避けられませんが、少しでも被害を軽減するためにドローン減災士を派遣し、救助活動を行えるシステムを作れれば嬉しいですね。
ちなみに、私は兵庫の株式会社T & Tさんのスクール(JUAVACドローンエキスパートアカデミー兵庫校)でドローン減災士講座を受講したのですが、T & Tさんはいろいろな市町村と、災害時の対応に関する協定を結ばれているんです。
ただドローン減災士を育成するだけでなく、有事の際に実際に貢献できる体制があるのは素晴らしいと感じました。同じことができるかは不明ですが、今後当スクールでもそのような協力体制を築いていけるのが理想です。
災害大国日本では「ドローン減災が当たり前」に
——中田様にお伺いします。西様のここまでのお話を聞いた感想や、本部として考えている支援策などはありますか?中田:
ドローン教習所 福岡校の皆さんは本当に真面目で、受講生の人数の伸び率も、パートナースクールの中では断トツで高いです。素晴らしい講習をされている結果かと思います。
そんな福岡校を支援するために、現在、本部では実技をメインとしたコースも開講準備中です。これまでの座学の内容は当然キープしつつ、実技を手厚くすることにより、防災・減災現場で即戦力として活躍できる人材を増やしていけたら嬉しいですね。
さらには、ドローン減災士という資格の知名度をアップさせることも急務です。各種営業支援はもちろん、「ぼうさいこくたい」への出展などを通じて、全国にアピールしていきます。

中田:
それから、あくまでも一案ですが、スピーカードローンを福岡校に置き、有事の際には福岡県に貸し出すといった運用も可能かもしれません。そうすれば自然と自治体との連携が生まれますし、ドローン減災士の活動もスムーズになります。受講生が増えてくればこうした対応も実現しやすくなるので、本部としてさまざまな方向から福岡校を応援していくつもりです。
——最後に、今後の展望をお聞かせください。
西:
九州でのドローン減災については、九州連合が発足し、九州地方全体として防災・減災に対する意識が高まっている時期だと思います。南海トラフ地震への警戒も高まるなか、九州一丸となって減災に務める体制を早急に整えたいですね。
当校のドローン減災士コースは開講して数ヶ月であり、まだ力及ばないところもあります。ですが私たちの力が少しでも役立つよう、まずは受講者を増やし、環境作りをしっかりと進めていきたいです。
中田:
今後、日本における防災減災シーンで、ドローンの活用は当たり前になっていくでしょう。能登半島地震では、災害時のドローン活用について多くの知見を得ることができました。これを踏まえ、ドローンの活用をスムーズに自治体に提供できる土台作りや、現場での運用面など、本部として全国規模でサポートしていきたいと考えています。
災害が発生した際だけでなく、平時から「ドローン防災・減災といえば、ドローン減災士協会」と言っていただけるような団体を目指して、今後も頑張っていきます。

RECOMMEND
この記事を読んだ方へおすすめ-
(取材)日本無人航空機免許センター(JULC)|全国で高品質な教育を提供。現場で活躍できる人材を育成する講習内容とは
日本無人航空機免許センター(JULC)は、「現場で活躍できる人材を育成する」という思いのもと、全国に教習所を展開している団体です。ドローンの基本的な知識・技能の講習から業務活用のための...
2025.05.30|安藤さやか
-
災害時の新たな救世主?ドローンがつなぐ防災の輪:ドローン減災士協会 前田稔朗事務局長
災害時のドローン活用を推進する一般社団法人ドローン減災士協会(DEO)。全国各地にあるスクールを通じて、救助や物資輸送の効率化を図るための訓練を提供しています。 この記事ではドローン...
2025.05.21|夏野かおる
-
(取材)一般社団法人無人航空機操縦士養成協会(DPTA)代表理事 志村伊織氏|スマート農業・ハンティングドローンに...
ドローン産業の発展のため、高い専門性を持つドローンオペレーターの養成を目的として設立されたのが一般社団法人無人航空機操縦士養成協会(DPTA)です。 同協会はドローンスクールの管理団...
2025.05.30|大橋礼
-
ドローンスクール水戸校|国家ライセンスコース卒業後にドローン事業立ち上げ!卒業生インタビュー
今回取材したのは、SkyLancer株式会社の富岡基浩代表。茨城県のドローンスクール水戸校(運営:一般社団法人スカイガード)で、民間資格と国家ライセンスを取得しました。現在はドローン空...
2025.05.30|徳川詩織