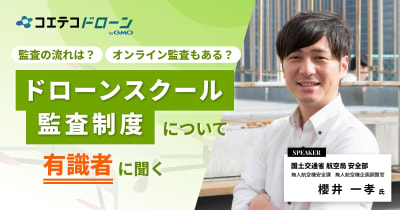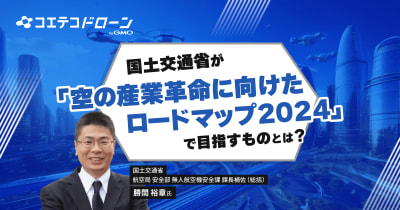(取材)国土交通省|大阪・関西万博も迫る。安心安全な「空飛ぶクルマ」実現に向けた制度設計とは

私たちの移動手段を大きく変えるかもしれない存在だからこそ、気になるのが安全面。「空飛ぶクルマ」の社会実装において、安全を守るためのルール作りを担うのは国土交通省です。
この記事では、国土交通省航空局 課長補佐の保坂達也氏に、「空飛ぶクルマ」実現における国土交通省の役割や今後の課題、未来への展望について聞きました。

国土交通省航空局 課長補佐 保坂達也氏
「空飛ぶクルマ(空クル)」実現に向けた取り組み
ーー「空飛ぶクルマ(空クル)」実現に向けて、国土交通省が担う役割を教えてください。空飛ぶクルマについては、都市部の送迎サービスや離島や山間部の移動手段、そして災害対応などの場面での活用が期待されており、国としても実装に向けて進めているところです。
国交省のなかには空を飛ぶ機体を取り仕切る航空局という部署があり、航空法や安全確保、交通管理などを管轄しています。空飛ぶクルマの実現に向けても重要な役割を持っているといえるでしょう。
ーー空飛ぶクルマの産業化にあたり、安全面ではどのような課題があるのでしょうか。
課題をわかりやすくするには、すでに運航している航空機との違いをクリアにすることで、必然的に空飛ぶクルマの課題が見えてきます。大きな違いとしては、垂直離着陸をする点と、電動である点が挙げられますね。
まず「垂直離着陸」についてです。「ヘリコプターも垂直離着陸ではないか」と思う方もいるかもしれませんが、実はヘリコプターの場合は浮いてからすぐに斜め上方向に離陸するんです。空飛ぶクルマの垂直離着陸は、垂直方向により精密になると想定されています。
そして垂直離着陸は、航空力学の分野では難しい技術であると位置づけられています。難易度の高い技術を空飛ぶクルマに新しく取り入れることになるので、当然基準も新しいものをしっかりと練らなければなりません。まずはこれが一つ目の課題です。
もう一つの課題である「電動」については、まだ機体性能についての詳細がわからない状況です。例えばバッテリー充電ひとつとっても、充電用プラグを機体に挿す形なのか、機体からバッテリーを抜き取って充電する形なのか、さまざまな形が考えられます。普通の航空機はこのような仕組みをしていませんから、まだ国際的なルールなどもありません。今後は機体メーカーなどの意見を聞きながらルールを作っていく必要がありますね。
また、運航形態も既存の航空機よりも低い高度を高頻度で飛ぶことになると見込まれています。それぞれの違いを明確にして、一つひとつの安全基準を確認していくことが重要です。考え方としては、既存の航空機並みの安全基準が必要だと認識しています。
ーー操縦者の技能証明や機体の安全性担保に向けて、どのような規制・制度が必要ですか。
まず技能証明については、航空法のなかに既存のルールがあるので、そのなかで空飛ぶクルマの操縦に関する資格を新しく作る形になります。資格を作らなければ、航空法上のパイロットとして操縦することはできませんからね。そのための制度作りを検討している段階です。
具体的には、学科試験と実地試験という2つの観点が基本です。例えば学科試験であればどのような科目を課すのか、実地試験であればどのような項目で審査をするのか、そのような点をゼロに近い状況から考えなければなりません。
機体の安全性についても、航空法上で安全が担保された航空機でないと空を飛ぶことはできません。その安全性の証明を「耐空証明」と呼びますが、それを取得するにあたっての基準について議論しています。
基本的には小型機のようなものなので、小型機の基準がベースになってきます。そのうえで、先ほど話したような垂直離着陸や電動といった差分を一つひとつチェックして基準化する作業が必要です。
ーードローンの離発着場(バーティポート)についての議論はどうなっていますか。
現在、具体的にどこに置くかという点については更なる検討が必要です。例えば駅前などの街中に置くということになると、環境アセスメントなどの別の検討が必要になります。これは経済産業省が中心となり、議論が始まったところです。
2025年に開催される大阪・関西万博での空飛ぶクルマ実現を目指し、今まさに官民一体の取り組みが行われています。今はまだ夢のような空飛ぶクルマが実用化されることで、日本の産業はどのように変わるのでしょうか。 この記事では、経済産業省 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 次世代空モビリティ政策室 室長補佐の石尾拓也氏に、空飛ぶクルマの実現に向けた取り組みや、産業化の展望などをお聞きしました。


2025/05/21

ただ、離着陸場自体の強度や広さなどについては、かなり具体的に見えてきました。2025年の万博に向け、官民協議会で2023年度中に制度整備を完了しようと進めてきたなかで、2022年度末には離着陸場の基準の方向性について表形式で示しています。
加えて、具体的な検討の場である「離着陸場ワーキンググループ」で、今年度に入って空飛ぶクルマ専用の離着陸場の整備指針や場外離着陸場の基準などについての議論を進めてきました。それらのテーマについては、パブリックコメントも公表しました。
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000086.html >
ーーまさに制度整備が進んでいるところですが、諸外国と比較して日本の「空飛ぶクルマ」の制度設計はどのような状況にあるのでしょうか。
欧米でも機体を開発中の段階なので、日本と同様に制度設計と機体開発を同時並行で進めている状況です。そういった意味ではスタンスに差はありません。
ただ、日本では2025年の大阪・関西万博での実用化という直近の目標があります。そのための検討を早めに進めているという違いはありますね。
「空飛ぶクルマ」と「ドローン」の違い
ーーいわゆるドローンと「空飛ぶクルマ」の違いは、どのような点でしょうか。航空法上の違いとしては、ドローンは無人航空機、空飛ぶクルマは航空機という扱いで区分されます。空飛ぶクルマにおいては既存の航空機がベースとなるので、基準や試験においても既存のものを念頭に置いた形になるでしょう。一方でドローンは有人の航空機とは全く別の枠組みになるので、内容もより新たな観点が導入されています。

官民協議会や2025年大阪・関西万博での役割
ーー「空の移動革命に向けた官民協議会」の概要と、協議会における国土交通省の役割についてお聞かせください。官民協議会は、2018年に政府が打ち出した「未来投資戦略2018」という文書に基づいて設置され、国土交通省と経済産業省が事務局となって進めています。これまでに9回実施されました。国土交通省は制度整備をおもに担当しており、官民協議会の下部に機体、運航、ライセンス、事業、離着陸場などに関する5つのワーキンググループを取りまとめています。
これまでの官民協議会の最も大きな成果は、ロードマップを作った点ですね。メーカーや有識者などの民間の方も含めた議論の中で、共通の目標となる道筋をビシッと決めたのは大きな意義があったと思います。
ーー官民協議会で、民間側からはどのような要望や議論があったのでしょうか。
例えば、無人航空機であるドローンと航空機である空飛ぶクルマにおいて、「基準の連続性を考慮してほしい」という意見はけっこうありますね。ドローンが大型化して人が乗れるサイズになると、空飛ぶクルマになるわけです。その境目で一気に安全基準やライセンス基準のハードルが上がると困るという指摘をよく受けます。
また、「既存の設備を空飛ぶクルマに活用できるようにしてほしい」という話も挙がります。例えば、既存のヘリポートなどに離着陸できるようにするということですね。
ーー大阪・関西万博での「空飛ぶクルマ」実現においては、国土交通省はどのような役割を担当していますか。
いざ飛行する段階になると、やはりまずは機体の安全性をきちんと審査する必要があります。すでに万博で飛行する4社は決まっているので、事業者から機体の安全性審査の申請を受け付け、審査を進めているところです。引き続き着実に進めていきたいですね。
また、運航する際には交通管理の問題も出てきます。そのために空飛ぶクルマの位置情報を地上側で把握するための設備などのさまざまなインフラを整えなければいけないので、まずは万博に特化した整備を集中的に進めています。

「空飛ぶクルマ」の未来への展望
ーー個人として、「空飛ぶクルマ」実現に向けた期待感はありますか。そうですね。2022年度末に基準の方向性を示し、2023年度中に制度整備をするという形で進んでいるんですが、現段階でかなり具体的な機体の詳細や離着陸場の概要など、図面レベルのものを目にする機会が増えました。それを見ると、これまで机上で進めてきた制度整備の議論が、具体的な形に変わりつつあるんだなという実感が湧きますね。
ーー今後は「空飛ぶクルマ」の実用化に向けて、どのような制度を設計していく予定ですか。
現在は万博に向けた議論を進めている段階ですが、今後は万博の後を見据えた制度整備も進めていかなければなりません。運航規模が拡大すれば日本全国で飛ぶようになりますし、頻度・密度を上げて運航することも考えられるので、そこに向けた一歩先の議論が必要です。
また、機体についても、これから新しい機体が次々に出てくるのではないでしょうか。例えば現在想定されている機体はパイロットが搭乗する形が基本的なコンセプトですが、自律飛行や遠隔操縦などのパターンもあり得ます。そのような新しい形の機体の安全設計など、引き続き検討しなければならないことがまだありますね。
ーー「空飛ぶクルマ」が広く普及した場合、交通インフラや都市設計にどのような影響が表れるのでしょうか。
バスやタクシーなどの都市部の道路交通に空飛ぶクルマが入り込むことで、都市としての最適化が図られていくのではないかと思います。単純な移動速度においては、おそらく車や鉄道より速いでしょう。そのため、都市が外に向けて広がっていく可能性は考えられますね。海外の方からは「日本は離島や山が多いから、普及する環境が整っている」という意見を多くもらいますよ。
ただ、輸送需要において、人の数には限りがありますよね。需要を奪い合う形では意味がないように思うので、そのあたりは都市計画という目線で検討する必要があるのではないでしょうか。

RECOMMEND
この記事を読んだ方へおすすめ-
(取材)経済産業省|2025年大阪・関西万博の「空飛ぶクルマ」実用化で産業・経済はどう変わる?
2025年に開催される大阪・関西万博での空飛ぶクルマ実現を目指し、今まさに官民一体の取り組みが行われています。今はまだ夢のような空飛ぶクルマが実用化されることで、日本の産業はどのように...
2025.05.21|徳川詩織
-
(取材)国土交通省航空局 勝間裕章氏|無人航空機(ドローン)の国家ライセンス制度と機体認証制度の現状
2022年12月、ドローンの国家ライセンス制度が始まりました。レベル4飛行が解禁し、許可申請も一部免除されたことにより、今後ますますドローン活用の幅が広がることが予想されます。 ...
2023.07.22|徳川詩織
-
(取材)国土交通省 航空局 櫻井一孝氏|ドローン登録講習機関の監査制度の現状
ドローンの国家ライセンス取得の講習が受けられる、国土交通省の認定を受けた「登録講習機関」。登録講習機関では、一定の水準を保つために外部機関の監査を受けることが義務付けられています。今回...
2023.11.21|徳川詩織
-
国土交通省航空局 勝間裕章氏|「ドローンが当たり前な社会」を官民で推進。担当者に聞く「空の産業革命」の現在地
2022年12月に国家資格の「無人航空機操縦者技能証明」制度がスタートし、今後もさらなる発展が見込まれるドローンですが、持続可能な発展に向けた課題も存在しています。今回は国土交通省の勝...
2025.02.27|Yuma Nakashima