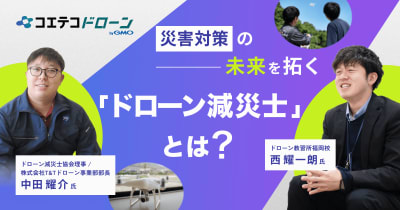災害時の新たな救世主?ドローンがつなぐ防災の輪:ドローン減災士協会 前田稔朗事務局長

一般社団法人ドローン減災士協会(DEO)は、ドローンを活用して減災に取り組むため、ドローンの知識と技術を兼ね備えた「ドローン減災士」を育成し、その資格を認定します。

https://deo-dronegensai.com/ >
この記事ではドローン減災士協会 前田稔朗事務局長にインタビュー。同協会の設立背景やこれまでの歩み、およびドローン減災士の育成機関としての活動内容に焦点を当て、その成果と地域社会への貢献に迫ります。

ドローン減災士協会 前田稔朗事務局長
地域防災の核となる「ドローン減災士」を育成
——一般社団法人ドローン減災士協会(DEO)とは、どのような団体なのでしょうか?我々一般社団法人ドローン減災士協会(DEO)では、各種スクールにおける育成プログラムを通じ、地域防災ネットワークの核を担うドローン減災士の育成を行なっています。また、防災訓練や各種イベントへの参加を通じて、災害時におけるドローン活用の認知拡大を図っています。
——ドローン減災士とはどのような存在なのでしょうか。
ドローン減災士の役割は、官と民の橋渡し役として、災害対応の質を向上させることです。
災害時の被害を最小化するには、対応を自治体任せにせず、自助・共助を尽くすことが欠かせません。迅速かつ安全な避難・救助活動を実現するためには、民間の力を社会的な協力体制に組み込む必要があるのです。
ここの接続をスムーズにするのがドローン減災士です。災害時という特殊な環境においては、普段のドローン活用とは異なるスキルが求められます。たとえば自衛隊や消防のヘリが飛び交うなか、どのようにして安全にドローンを飛ばせば良いのか。自衛隊、警察、消防、行政などとどのように連携すれば良いのかは、専門的な訓練なくして判断できません。
ドローン減災士の資格を取得することで、たとえば被災地の状況確認や撮影、記録などの業務のほか、スピーカードローンによる避難誘導などが行えるようになります。必要な情報を行政へ提供し、人々の安全を確保するうえで、ドローン減災士は大きな役割を果たすのです。
——現状、どのような方々がドローン減災士の資格を取得しているのでしょうか。
資格取得者は非常に多岐にわたります。一般の社会人はもちろん、ドローンスクールの卒業生、学生、消防士さんなど、幅広い方がいらっしゃいますね。近隣の市町村の職員や賛同企業の関係者が参加してくださることもあり、地域全体でこの資格に対する関心が高まっているのを感じます。多様な参加者を迎えることで、ドローン減災士のネットワークがさらに拡大し、災害時における即応力も増していくことを期待しています。
神戸大学・兵庫県立大学とともに数々の取り組み、兵庫県も後援
——DEOを設立したきっかけ・背景について教えてください。兵庫県はこれまで、阪神・淡路大震災や佐用町の水害など、歴史に残る大規模災害に見舞われてきました。
身近な地域が大きな被害に遭うなか、何かできることはないかと考えていたところ、減災にドローンが活用できることを知り、関心を持つようになりました。
この思いが具体的な形になったのは、廃校となった江川小学校を利用してドローンスクール(JUAVACドローンエキスパートアカデミー兵庫校)を開設してからです。
JUAVACドローンエキスパートアカデミー兵庫校(運営:株式会社T&T)のカリキュラム(座学・知識、対象(受講資格・条件))、料金(受講料・諸費用)、取得できる免許・資格や特徴など解説。

https://coeteco.jp/drone-school/schools/kk-tt >
一般社団法人日本UAV利用促進協議会(JUAVAC)の代表理事から「ドローンスクールを運営してくれる人を紹介してほしい」と相談されました。
そこで青年会議所のOB会員に声をかけたところ、「前田さんがやればいいじゃないか」と。70歳(当時)という年齢もあって迷いましたが、生きているうちに新たな産業が誕生する瞬間に立ち会える感動もあり、自分でチャレンジすることにしました。

スクールを開校したあとは、受講生を募るのに加えて地域への貢献も行ってきました。
代表的な取り組みとしては、赤穂市、佐用町、たつの市と災害協定を締結したことです。
協定を結んだからには実際の災害活用に役立ててほしいと思いPhantom4を寄贈し、受講生2名を無料招待しました。
この取り組みは神戸新聞に取り上げられ、ドローンスクールの受講生が増えるきっかけになりました。
その後、他の地域とも積極的に協定を結んでいます。
リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

http://www.sebec.co.jp/news/news162.html >
もう一つ、大きな転機もありました。それが、神戸大学の鈴木広隆教授とのご縁です。
鈴木教授が同大学で防災学を手がける槻橋修教授を紹介してくださったことで、本格的に防災関係の活動を進めていくことができたんです。
槻橋教授と初めに取り組んだのは、2018年に行われた「078神戸」でした。自助努力と自己防衛の重要性を訴えるこのイベントには3000名以上が参加し、私たちはそこで「こいのぼりドローン」による避難誘導実験を行いました。ただこれは、ドローンの機体にビニール製のこいのぼりを結びつけただけの簡易なものだったので、結果は振るわず。終了後のアンケートでは「ドローンの存在に気付かなかった」と答える人が多数で、これは改良の余地があるぞと奮い立ちました。
リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://2019.078kobe.jp/events/11626/index.html >
その後はさらに精力的に活動すべく、鈴木教授、槻橋教授と「減災ドローン研究会」を立ち上げ、兵庫防災連携フォーラム、赤穂市防災訓練に参加しました。
この防災訓練では「こいのぼりドローン」の反省を生かし、スピーカーを積んだドローンで避難呼びかけを実施。今度はほとんどの人にドローンを認知してもらうことができました。加えて物資輸送ドローンも活用し、災害時のドローン活用についての知見を蓄えました。
活動にあたっては、同県が令和元年より実施している公募事業、「ドローン先行的利活用事業」に槻橋教授の勧めで申し込み、採択されたことが大きいです。
また、「ひょうごクリエイティブビジネスグランプリ2020」でも奨励賞を受賞しました。
リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

http://www.sebec.co.jp/news/news327.html >
このようなやりとりを通じて、ドローンへの期待が官民ともに高まっていることを感じました。
リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://juavac-droneschool.jp/juavac%E5%85%B5%E5%BA%AB%E6%A0%A1%E3%81%AE%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%8C%E7%A5%9E%E6%88%B8%E6%96%B0%E8%81%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%81%AB%E6%8E%B2%E8%BC%89%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97/ >
こうして各種実験での知見を得た我々は、次なるステップ、すなわち人材育成へと踏み出すことにしました。そのためにはマニュアルが必要です。そこで槻橋教授を中心に、ゼミ生たちの協力を得て生み出されたのがドローン活用減災士の育成マニュアルでした。
次は、学べる場所づくりです。人材の確保と育成には公的な組織が必要だと考え、一般社団法人ドローン減災士協会(DEO)を設立することに。兵庫県立大学で長年減災に取り組んでこられた木村玲欧教授(DEOの代表理事でもあります)、兵庫県防災士会の室﨑友輔氏も理事として参加してくださり、「ドローン減災士」の教本の作成もスタートしました。そして2021年4月、ついに協会を発足させることができました。

なお、DEOでは今後の展開として、より実践的な内容を含んだコースも開発中です。
このコースでは、座学だけでなく実際の操作訓練を行い、大型機体を含む様々なドローンを使って具体的なシナリオに基づいた訓練を行う見込みです。
たとえば洪水時の救助ロープ搬送などは消防からの強い要望があり、コースへの組み込みを本格的に検討しています。
このように教本・カリキュラムは、随時アップデートを続けていく予定です。
1県1校でネットワーク拡大、中国・四国地方が課題
——協会発足後はどのように活動を拡大していったのでしょうか。全国各地にDEOのネットワークを広げるため、1都道府県に1校ずつのパートナー企業を募集しました。まずはJUAVACドローンエキスパートアカデミーのスクールを通じてDEOを紹介し、協力校を募集。参加スクールがない県には、登録講習機関のリストをもとに直接DEOの紹介資料を送付するなどしてネットワークを広げていきました。これにより、現在では39都道府県においてDEOのスクールが設置されています。
1都道府県に1校の方針を採るのは、災害時の効率的な対応と統一された行動を可能にするためです。災害発生時に適切な対応をとるには、平時から行政機関の危機管理部署と連携し、共同で訓練を行うなどして役割分担や対応計画を固めておくことが欠かせません。もしも1つの県に複数のDEOスクールや企業が存在すれば、情報の錯綜や混乱が生じる恐れがあります。対応のスタンダードを定めるには、1都道府県に1校という制限がふさわしいのです。
さらに言えば、各スクールが「〇〇県のスタンダード」を担う体制は、責任ある教育の保持にもつながります。それぞれのスクールが地域社会において信頼される防災の中心地になってくれるよう、協会としてもサポートしていきたいです。
——全国展開するなかで、各地域の温度感はどのような状況でしょうか。
特筆すべき動きとしては、熊本県が中心となり、九州地方全体で防災訓練や災害時の支援体制を整える動きが加速したことが挙げられます。九州連合会には、沖縄県を除く九州すべての県が加盟したほか、隣県である山口県も加わってくれました。ちょうど今年の「ぼうさいこくたい」も熊本県開催で、九州地方におけるドローン減災の盛り上がりが期待されています。
一方で課題としては、いくつかの県に加盟校がないことが挙げられます。これらの地域は比較的災害が少なく、防災の機運が高まりきっていないようです。しかしながら災害はいつ、どこで起こるか予測できません。今後はこれらの地域にも積極的にアプローチし、全国規模でのネットワークをさらに強化していきたいと考えています。
行政任せにせず、一人一人が減災を担う自覚を持とう
——今後の減災のために、私たちができることは。何度か強調したとおり、迅速な災害対応を可能にするには、地域のコミュニティ・企業・行政がネットワークを築くことが欠かせません。専門的な知識と技術を身につけた存在であるドローン減災士は、その連携の核となる存在です。より多くの命を守るため、企業や自治体、学校等においても資格取得の推進を検討していただきたいです。
災害は誰もが直面する可能性があるものです。自分自身や家族を守るためには、行政だけでなく、私たち一人一人が災害対応の主体となる必要があります。一人でも多くの方がこの動きに加わることで、強固な防災ネットワークが形成され、地域社会全体の安全が守られるのです。
準備は今からでも遅くありません。ぜひともご自身の能力を災害対策に活かし、地域の安全と安心を守るために力を尽くしていただければと願っています。
RECOMMEND
この記事を読んだ方へおすすめ-
(取材)一般社団法人無人航空機操縦士養成協会(DPTA)代表理事 志村伊織氏|スマート農業・ハンティングドローンに...
ドローン産業の発展のため、高い専門性を持つドローンオペレーターの養成を目的として設立されたのが一般社団法人無人航空機操縦士養成協会(DPTA)です。 同協会はドローンスクールの管理団...
2025.05.30|大橋礼
-
(取材)神奈川県知事 黒岩 祐治|国産ドローンを活用した災害時物資輸送の実証事業を実施
近年、ドローンの活躍が期待されている分野の一つが、防災です。小型で無人飛行が可能、場所を選ばないなどの利点から、多くの自治体が災害時の物資輸送や被災者捜索などにドローンの活用を検討して...
2023.07.11|徳川詩織
-
(取材)最先端科学技術のドローンで障がいを持つ人の未来を支援!ユニバーサル・ドローン協会「ナミねぇ」こと竹中ナミさ...
障がいを持つ方の将来の可能性を広げるために、ドローンを学ぶ場を提供している、ユニバーサル・ドローン協会(UDrA)。現在、チャレンジドの一人で足を使いドローンを操縦する高校一年生のみゆ...
2024.04.01|安藤さやか
-
ドローン減災士協会×ドローン教習所福岡校:災害対策に新たな風「ドローン減災士」が拓く未来
ドローン減災士協会(DEO)は「ドローン減災士」の育成や災害支援活動などに取り組んでいます。今回お話を伺ったのは、ドローン減災士協会理事・T&Tドローン事業部部長の中田氏と、ドローン教...
2024.09.25|中村英里