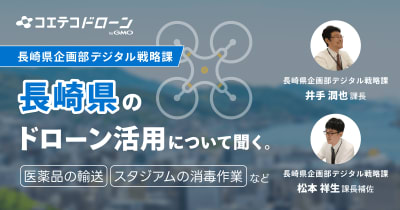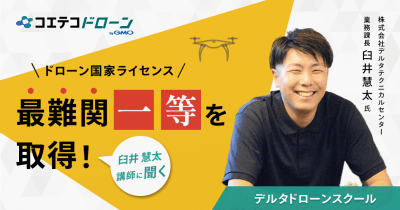(取材)京都唯一の村・南山城村|人口2500人の村で進む、ドローンの利活用



京都府南山城村(同村提供)
ドローン活用で費用削減
――まずは南山城村のご紹介をお願いします。井上(浩):南山城村は、京都府の東南端に位置する「京都府唯一の村」です。 山々に囲まれ、中央には木津川が流れる自然豊かな環境が自慢。ものづくりにもこだわっており、日本三大銘茶の一つである「宇治茶」の主産地としても有名です。
――御村がドローンを導入した理由を教えてください。
井上(浩):2020年、村内に点在する公共施設を点検する際、調査項目の一つに「屋根の劣化具合」の項目があったんです。当初は職員が施設の屋根に登るつもりでいましたが、危険だということでストップがかかりました。
そこで業者に委託しようしたところ、数百万円が必要との試算になりました。年度途中に数百万円規模の予算を確保するのは非常に難しい。やむなく再度自力で点検する方法を考えたときに、ドローンが候補として上がってきたんです。
企画政策課内で検討した結果、飛行許可や技術認証の取得、機体の購入など、ドローンの導入はそこまでハードルの高いものではないと判断。幸いなことに村の中にドローンスクールもあったので、いろいろと相談しながら導入を進めました。

南山城村役場 企画政策課課長 井上浩樹氏
――スムーズに導入できたのでしょうか。
井上(浩):そうですね。結論から言えば、大きな問題はありませんでした。
ただし、運用に当たってはまず規則を整備しました。というのは、当初の目的である施設の点検のためだけであれば必要なかったのですが、今後「ドローンを使用したい」との要望があちこちの課から出てくると確信していたのですね。そうすると自治体としては、管理者がすみやかに承認できる制度を作っておいた方がいいだろうと考えたのです。
第1条 この規程は、南山城村が所有するドローンの運用に当たり、航空法(昭和27年法律第231号)、電波法(昭和25年法律第131号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、民法(明治29年法律第89号)その他関係法令に定めるもののほか、管理運用に関し必要な事項を定めることにより、ドローンの安全で効果的な利用を図ることを目的とする。

https://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k124RG00000699.html >
規則の整備から導入開始までは1ヶ月ほど。対象施設の調査は2日間で終わり、費用も50万円程度に収まりました。これまで計30回ほどドローンを使用していますが、特にトラブルもありません。費用面・効率面の両面から効果を実感しています。
――現在はどのような場面でドローンを活用しているのでしょうか。
井上(浩):いまは四つの場面で活用しています。①施設調査、②不法投棄現場確認、③ホームページ・ふるさと納税サイト用の写真撮影、④サルの行動確認です。
①施設点検に関しては、屋根など自力で確認するのが困難な場所で使用しています。
②不法投棄では、これまで山林で不法投棄があるとの通報を受けても、まずその場所を特定するのに時間がかかっていました。ドローンを使えば、1分もあれば広範囲を確認できます。発見率も上がりましたし、非常に楽になりましたね。
③写真撮影では、ホームページやふるさと納税の商品紹介で、ドローンが撮影した写真を載せています。そのような自治体はまだ少ないので、当村に興味を持ってもらうきっかけになればと思っています。


④サルの行動確認は、農作物が食い荒らされるのを防ぐ試みの一環です。まだ実験段階ですが、ドローンが赤外線で猿の体温を感知し、ドローンのスピーカーからサルの嫌がる周波数の音や鳴き声を流す手法を取る予定です。
夏に実験したところ、サルの体温と道路の表面温度が同じくらいだったため赤外線で区別できずに失敗。冬になれば道路の温度が下がるので、うまく活用できるのではと期待しています。

ドローンを活用した文化財調査(同村提供)
――多岐に渡り活用していらっしゃるんですね。今後もさらに展開していく予定はあるんでしょうか?
井上(浩):まだまだ活用を進めていく予定です。具体的には、①山林火災時における鎮圧状況の確認、②災害時、被災者に対する情報収集、③固定資産調査、④道路・橋梁などのインフラ点検、⑤南山城村紹介動画の撮影です。
①山林火災時の鎮圧状況の確認、②災害時、被災者に対する情報収集は山林火災や災害が起こった際の出動となるので、出番はない方がいいのですが、備えは必要です。山林火災では、煙や灰の影響でよく見えない状態でも、温度感知できるドローンを使えばどこでまだ火が消えていないかがピンポイントで一目瞭然になるはず。これまでは消防団員が山の中を駆け回っていたわけですから、効果は抜群です。
③固定資産調査は、たとえば課税な必要な太陽光パネルを調査する際に活用していく予定です。④インフラ点検と⑤動画撮影は、職員のドローン操縦技術にもよるため、現段階では確実に実施するとは言い切れませんが、定期的に操縦する機会を設けており、今後も技術の向上に務めていきます。
――いま村には何台のドローンがあり、何人の職員が操縦できるのでしょうか?
井上(浩):3台あります。うち2台が業務用、1台が価格の安い練習用の機体です。ドローンを操縦するための技術認証資格を持っているのは6人で、ドローン活用に関わる部署すべてにドローンを操縦できる職員を配置しています。
ありがたいことに、2022年度は京都市内の会社が当村のドローン利活用を応援するため、企業版ふるさと納税の制度を活用して100万円を寄付してくれました。そのおかげで新しい機体の購入と講習の受講ができましたが、2023年度も予算が付けば操縦できる職員の人数を増やしていくつもりです。
南山城村は「ドローンにぴったりの環境」
――職員の方々は、村の中にあるドローンスクールで講習を受けたと伺いました。そこでドローンスクールの代表者である井上さんにお聞きしたいのですが、そもそもどうして南山城村でスクールを始めようと思われたのでしょうか。井上(博):僕は南山城村で生まれ育ち、一旦大阪に出たもののまた戻ってきて山荘経営を始めました。そんな中、2014年に興味を惹かれてドローンを買ってみたところ、すぐにハマってしまったんです。

童仙房山荘 井上博文氏(DPCA 公認マスターインストラクター)
既製品に飽き足らず、自分でも中国から部品を取り寄せて作っていたのですが、DJI社のPhantom4が発売されて「これ以上のものは作れない」と判断。いちから作るよりも、「この機体を活用していこう」と思いました。
そこで、南山城村はドローンスクールを開くのに適した場所だと閃いたんです。元々スノーボードのインストラクターといった仕事もしていたので、指導の技術もあります。いまは一般社団法人「地域再生・防災ドローン利活用推進協会(RUSEA)」の京都南山城支部として、操縦の基本から応用まで教えています。

座学講習の様子(井上さん提供)
――「ドローンスクールに適した場所」とは、具体的にどのような環境を指すのでしょうか。
井上(博):南山城村の方には廃校になった小学校や体育館など、利用できる施設が複数あります。人口がそれほど多くもなく、茶畑も絵になります。また、屋外と屋内の施設の距離が近いのもスクールとしては利点です。一日の中でも外に出たり中で飛ばしたり、受講者の目的や天候に合わせて柔軟に対応しています。
――どういった方が受講されるのでしょうか?
井上(博):関西圏にお住まいの方を中心に、ご紹介で受講される方が多いですね。年代は30~60代までと幅広く、業務目的で来られる方と趣味で来られる方では前者の方が多くて8:2くらいの割合です。
――スクールで力を入れているのはどのような点でしょうか。
井上(博):基本の徹底ですね。やはり操縦している内に、どうしても個人ごとの癖が出てきます。その癖を認識してもらった上で、個人ごとに適切なアドバイスをすることを重視しています。基本的な動作ができないと、とても応用には進めません。
僕自身が最初にドローンの操縦を学んだとき、「右に行ってください」「左に行ってください」と画一的な指導しか受けられず、挙句の果てに「頑張ってください」と言われたんですね。「頑張って」と言われても、何を頑張っていいかもわからないじゃないですか(笑)。この経験を反面教師に、抽象的な声かけをするのではなく、「何をすべきか」をしっかりと言葉にして伝える必要があると常に意識しています。

実技講習の様子(井上さん提供)
村の価値を高めるドローン
――スクール運営者の立場から見て、南山城村役場のみなさんの操縦技術はいかがですか。井上(博):確実に基本を理解されていて、危険回避もしっかりできます。全く問題ありません。また操縦技術に加え、ここにいる井上さんは課長ですが、幹部職員が率先してドローンの技術を取得している自治体は少ないんですよ。これは非常に重要なポイントです。
講習には実際に作業に当たる方だけが来られるケースも多いのですが、管理者がドローンの性能をしっかり理解していないと、「あれをやってほしい」「これを撮ってほしい」と無茶な要求をしてしまうんですね。そのようなミスコミュニケーションが続くと、操縦者がストレスを感じてしまい、プロジェクトを円滑に進めることが難しくなります。ですから、「幹部に理解がある」というのは、とにかく心強いことです。
――井上課長にお聞きしますが、実際に作業をするわけではない管理職が技術認証を取得しているのはなぜでしょうか?
井上(浩):実は、最初は実際に作業する若い職員だけに技術があればいいのかなとも考えました。しかし、申請を承認する立場の人間がドローンの知識を持っていないと、いつか必ず大きな事故につながります。そのような考えから、いまは管理職2名が技術認証を取得しています。
――最後に、行政がドローンを活用していくことに対する価値をお伺いしてもいいでしょうか。
井上(浩):2020年には、ジャパン・インフラ・ ウェイマーク(JIW)やドローン撮影クリエイターズ協会らと「災害時等を始めとする無人航空機の運用に係る包括連携協定」を締結しました。
これは災害時に加え、村民の生命や身体、財産に重大な被害が生じる可能性がある事態が発生した際に、ドローンを活用して情報収集や被災者支援活動を行っていくというものです。住民の安全にかかわるところでドローンを活用できるのは、行政ならではですよね。
費用面でも非常にメリットが大きいです。委託するより断然安く、できることも多い。操縦のハードルもそこまで高くはありません。まだバッテリーの稼働時間の短さなど改良の余地はありますが、今後機体の性能がさらに向上し、ドローン活用の機運が高まっていけば、ほかの自治体でも活用が進むだろうと期待をしています。
ドローン活用を進める先駆的な自治体として、南山城村の宣伝もしていきたいですね。

南山城村の様子(同村提供)
――「南山城村のドローンスクール」が考える今後についてもお聞かせください。
井上(博):ドローンスクールで言えば、いまは基本的な操縦技術を取得する講習が主ですが、今後は業務に活用するための指導にも力を入れていきたいですね。たとえばいまは農薬散布ができるコースの開講を検討しています。
また、南山城村はダム湖や河川、山林や鉄道など、ドローンを飛行させる際に配慮すべきインフラも揃っており、企業がドローンソリューションを検討する上で非常に適した立地条件だと考えています。いまはDJI社がドローン業界のメインストリームですが、ぜひ国内企業も村を活用してくれたらと希望しています。
南山城村は人口が少ない分、住民のみなさんの団結力がとても強い。みなさんにドローン活用の意義を理解してもらい、多くの人や企業を呼び込んでいくことで、南山城村全体を盛り上げ、村の価値の向上につなげていきたいと思います。

RECOMMEND
この記事を読んだ方へおすすめ-
(取材)都ドローンスクール| 廃校を利用し、マンツーマンで手厚く指導!
京都府南丹市にスクールを構える都ドローンスクールは、一人一人のレベルに合わせ、レッスンの日程も個々のスケジュールに対応してもらえるパーソナル指導が魅力のスクールです。「新しく趣味を始め...
2022.10.14|藤田
-
(取材)長崎県企画部デジタル戦略課|全国から事業者・自治体が集まる長崎県の取り組みについて聞く
長崎県は、すでに民間企業による離島での物流支援が社会実装されているなど、ドローンの活用に力を入れている自治体の一つです。2023年9月には第2回ドローンサミットも開催され、全国から事業...
2025.05.21|徳川詩織
-
(取材)サイポート株式会社 中西 淳さん|「ニーズありき」で提供するドローンソリューションで日本の市場を盛り上げていく
テクノロジーと技術がすさまじいスピードで進化する今、あらゆる産業でドローンの利活用が進んでいます。 そんな中、「『ドローンの性能ありき』で事業のあり方が決まるようではいけない。あ...
2025.05.30|大橋礼
-
(取材)デルタドローンスクール 臼井慧太氏|京都で60年以上の指導実績を誇る!デルタ自動車教習所運営のスクール
京都で60年以上の実績を誇る「デルタ自動車教習所」が運営する「デルタドローンスクール」。同校を家業とする臼井慧太さんは、他業種からドローン産業に参入し、現在では講師として参画しています...
2025.05.30|宮﨑まきこ