(取材)実質「ほぼ義務化」?注目の『ドローン保険』について東京海上日動に聞いてみた
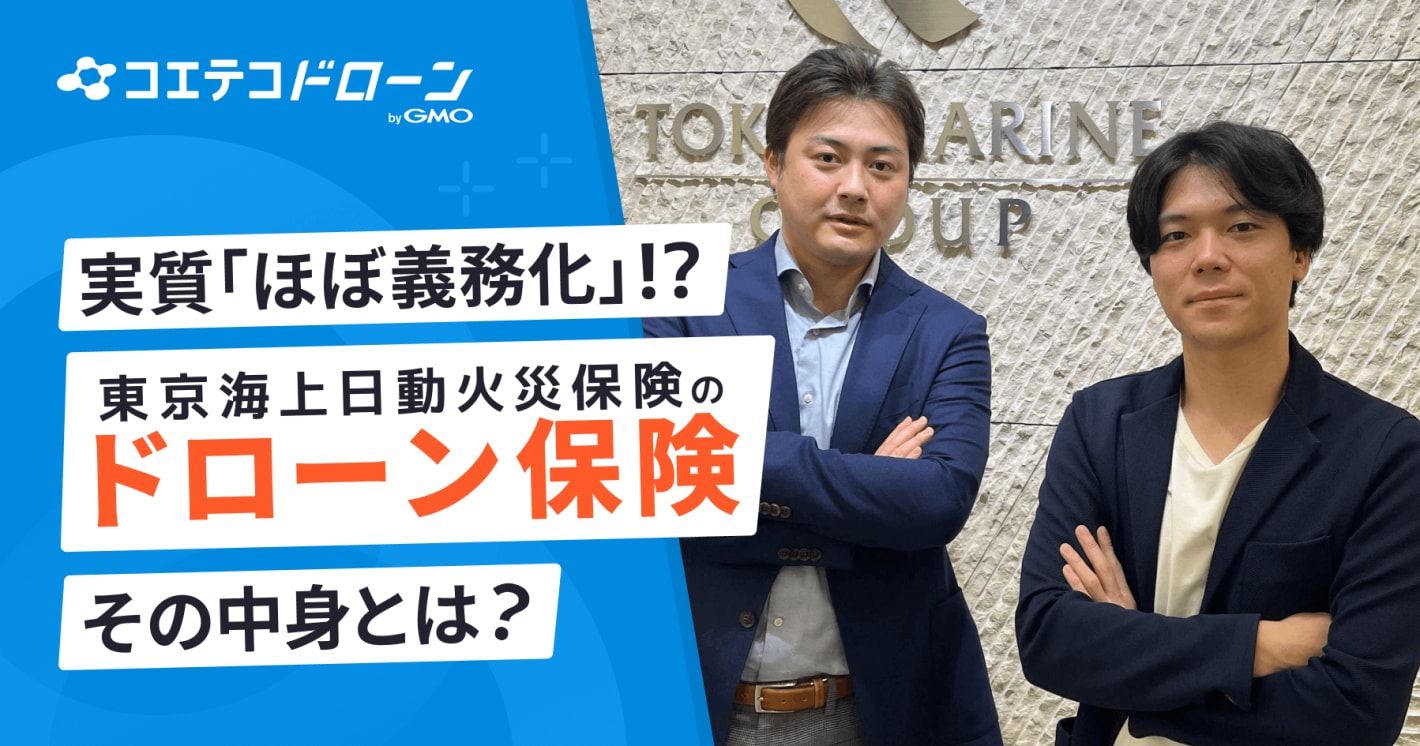

同社提供
実質ほぼ義務化?!ドローン保険とは
――まずは、ドローン保険が生まれた経緯を教えてください。吉村:私たちは2015年7月、日本で最初にドローンを対象とした幅広いリスクを補償する保険の提供を開始しました。一般的には「ドローン保険」と言われていますが、正確には「無人ヘリコプター総合保険」といい、動産総合保険と賠償責任保険のパッケージ商品でドローンに関する事故の補償を行っています。
ドローン保険の販売に至ったのには二つの理由がありました。一つは航空法が改正されてドローンの飛行に関するルールが定まるほど、ドローン業界が盛り上がってきていたこと。もう一つが、ドローンは事故を起こす危険性が極めて高いことです。
従来は、ラジコンやドローンは事故のリスクが高いことから、保険会社としては積極的に商品を展開していく領域ではありませんでした。ただ、今後世の中でドローンが広まっていくことは間違いない。そんな中で複数の事業者からの要望もあり、「何かあったときの安心安全を守ることは私たちの使命」と判断し、販売を決めました。
――そもそも、ドローン保険はなぜ必要なのでしょうか。
吉村:やはり、火災や地震などと比べ、事故が起こる可能性が非常に高いことが一番の理由です。地上にあるものと異なり、空中では停止することも難しく、何かあれば墜落に直結してしまうことから、空を飛ぶことでリスクが格段に高まります。
――ドローン保険の具体的な内容を教えてください。
吉村:当社のドローン保険は、総重量150㎏未満の無人ヘリコプターを対象として、機体にかかる損害を補償する「動産総合保険」と、他人にケガを負わせるなどした場合に発生する法律上の賠償責任を補償する 「施設賠償責任保険」の2つの保険から成り立っています。

同社提供
――「動産総合保険」と「施設賠償責任保険」はそれぞれどのような保険なのでしょうか。
吉村:動産総合保険からお話します。ドローンの操縦に関して発生する機体の損壊については、通常の火災保険では補償対象外となっています。一方で、風や操作ミスによる墜落事例は非常に多いため、動産総合保険を別途手配する必要があります。
具体例としては、「ドローンでの撮影中に建物により電波が遮断され、制御不能となり落下」「ドローンでの撮影中に突風にあおられ、電柱に接触し、落下」といったケースを想定しています。ドローン保険ではこれらの事故による修理や再購入の費用を補償します。
そのほかドローンならではの補償として、落下したドローンの捜索費用や再発防止のための操縦訓練費用を補償するオプションもご用意しています。
宮澤:施設賠償責任保険は、第三者に損害を与えてしまい、それによって被る法律上の損害賠償責任を補償するものです。賠償責任を負うケースは主に①対人事故②対物事故③人格権侵害にわかれます。
①対人事故は他人にケガをさせること、②対物事故は他人の所有物を壊してしまうこと。具体的にはドローン部品が落下して他人の車を壊したり、街灯に接触して壊してしまうといった事例が考えられます。
③人格権侵害事故はドローンならではのリスクと言えます。たとえばドローンで撮影した映像に他人の家の中が映り込んでいて、それに気付かないままネット上にアップロードしたところ、プライバシー侵害で訴えられてしまったケースなどを想定しています。

企業商品業務部企業新種保険グループマネージャー吉村佳佑氏(左)
同部責任保険グループ主任宮澤拓也氏
――イメージとしては自動車の自賠責保険のようなものでしょうか。
宮澤:そうですね。賠償責任に備える保険という意味では同種の保険です。自賠責保険の加入が法令上義務付けられている自動車と異なり、ドローンではまだ保険の加入は法令上の義務化に至っていませんが、高速で飛行するものを遠隔で操縦するわけですから、ミスをゼロにするのは難しい。墜落した場合は第三者に危害をおよぼす可能性があるため、何かあった場合に備えて賠償責任保険をかけておくのは自然なことかと思います。
国土交通省が公表している「無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン」でも、賠償責任保険の加入を推奨しています。
――今後、自動車のように保険が義務化される流れになるのでしょうか。
吉村:現在、ルール上は義務化されていません。しかし、国土交通省への飛行許可申請を行う際、賠償責任保険への加入状況を記載する欄があります。つまり、保険への加入またはそれと同等の賠償資力の確保が求められている、ということです。
飛行の安全性を高めることが最も重要ですが、もし、「事故を起こしたのにお金がなくて賠償できません」となればそれは大きな問題と考えています。ドローンの社会需要性に影響を与え、日本のドローン産業の発展を阻害してしまうかもしれません。このような事態を防ぐためにも、保険を広く行きわたらせることの重要性を感じています。
“国内損保初”Web完結のシステムを構築
――今後、ドローン保険の必要性はどのように変化していくとお考えでしょうか。宮澤:これまでは物を壊すケースが中心でしたが、有人地帯における目視外飛行の解禁により人にケガをさせてしまう事故が増加すると考えています。また、当然ですが、目視外飛行は目に見える範囲での飛行より操縦が難しい場面が多いですから、事件の件数自体も増加し、保険の必要性もより高まると考えています。
――保険各社がドローン保険を販売する中、御社の保険が選ばれるポイントはどこにあるのでしょうか。
吉村:ドローン保険を日本で初めて提供し、お客様やメーカー・販売店の皆さまのニーズに対応してきたことによって、選んでいただいているのかもしれません。
熊耳:現在は、ドローン販売の流れの中でスムーズに保険にご加入いただけるシステムの構築を行っているところです。2022年度内のサービス提供を目指し、ドローンメーカーや販売店と対話を重ねています。
ドローンに限った話ではありませんが、保険に加入するのはモノを購入したり、イベントが起こったりしたタイミングが一番多いですよね。これはそのようなタイミングでWebを通じて手軽に申し込みができるシステムです。
このシステムを通してドローン保険の加入率を高めることで、よりドローンの安心安全な活用が進むよう推進していきたいと考えています。

企業営業開発部企業営業グループ課長代理 熊耳俊太郎氏
――このシステムはどのような点で便利なのでしょうか。
熊耳:これまでの保険加入は紙でやり取りする必要がありました。それがこのシステムではWebで保険に加入できるだけでなく、事故後の保険金請求まで行えます。このようなWebで完結する仕組みのご提供は国内損保初と言えます。
――より利便性が高まるのですね。
熊耳:より多くの方に保険に加入していただくためには、保険に加入しやすい動線を構築し、チャネルをしっかり広げていくことが必要だと考えています。より使い勝手の良いシステムとなるよう、鋭意努力中です。
保険を通じ「安心安全な社会づくり」を目指す
――ドローンとドローンにまつわる保険は今後、どのようになっていくと想定しているのでしょうか。吉村:ドローンは市場の伸びが大きいですが、それに呼応するように私たちの保険も毎年150%程度の成長を見せています。目視外飛行の解禁により、ドローンも保険も今後ますます伸びていくと予測しています。
小林:ドローン自体の今後としては、物流や点検、農業分野などさまざまな分野で展開されていくと考えています。スマートシティやSDGsといった観点からも、ドローンは大きな役割を担うはずです。
保険会社が関係するところでは、災害時の迅速な支援や保険金の査定の場面でもドローンの活用が期待できると考えています。
一方、細かいルールやガイドラインについてはまだこれから煮詰まっていく段階です。各事業者は事故のリスクを完全に排除できない中で、社会実装を進めることが求められています。
そんな中で、保険があれば何かあったときに経済的なサポートを提供できます。それが結果的にドローンの活用を進め、ひいては安心安全な社会づくりにつながっていくと考えています。

営業企画部マーケティング室課長代理 小林隼人氏
――そのような状況の中、御社はどのような役割を担っていくお考えでしょうか。
宮澤:賠償責任保険は自分が相手に損害を与えた場合に役立つだけではなく、被害者にとっても、「ケガをさせられたのに相手にお金がなくて賠償してもらえない」といった状態を防ぐ効果があります。つまり、ドローンを操縦する人にとっても、ドローンが操縦される地域に住む人にとっても必要な保険だと言えます。
自動車が発展するためには、自動車保険の存在が欠かせませんでした。私たちがよりお客様と社会のニーズに合致した保険を作ることが、ドローンの発展のためになると信じています。
吉村:保険の観点からドローンの活用を促進するには、二つのことが必要だと考えています。一つは、被害を受けた側も事故を起こした側も守られること。もう一つは業界ごとに合った保険を提供することです。たとえば農業と物流では異なるリスクがあり、適切な補償内容は異なります。抜け漏れなく、加入者に合った保険の提供に努めていきます。
熊耳:いままさに、ドローンメーカーやドローンの販売店と、ドローンの発展に向けた対話を始めたところです。その一つの成果がWebのシステムになりますが、保険だけではなくお客様の事業に寄り添って、プラスアルファで何ができるのか保険以外の文脈でも考えていきたいと思っています。
この「保険だけではなくお客様の事業に寄り添う」という姿勢を通じて、お客様から選ばれる存在である事を目指しています。お客様の事業発展の貢献や既存ビジネスからの発展に向けた価値提供にこれからも取り組んでいきたいと思います。
小林:保険を通じ、ドローン産業の発展にも貢献していきたいですね。改正航空法も施行され、ドローンはいま社会実装が進むかどうかの瀬戸際にいます。この過渡期に、万一重大な事故が起これば、社会実装のせっかくの勢いが減速してしまうかもしれません。
もちろん、「保険があるから大丈夫」というわけではありませんが、安心安全の提供にはつながります。行政やほかの企業と一緒になって草の根活動を行い、より人々が快適に過ごせる社会をつくっていくことが必要だと感じています。
RECOMMEND
この記事を読んだ方へおすすめ-
(取材)ドローンのための気象予報サービスって何ですか?ウェザーニューズさんに聞きました!
気象分野で世界をけん引する株式会社ウェザーニューズは、いまや陸・海・空すべての領域の気象予測サービスを世界中で展開しています。 そんなウェザーニューズは2016年、「ドローンビジネス...
2024.04.01|まつだ
-
(取材)楽天グループ株式会社 ドローン事業課 シニアマネージャー 宰務 正|「ドローンのエコシステムを作る」楽天が...
2016年に日本で初めてドローン配達サービスの実験を行なった楽天グループは、2022年、ドローン産業のリーディングカンパニーだったスカイエステート株式会社を子会社化し、本格的に『空の産...
2023.05.24|宮﨑まきこ
-
(取材)パーソルグループが業界初の「ドローンキャリアマップ」を公開。企業・働き手の双方を支援する
パーソルクロステクノロジー株式会社は2022年7月、企業と個人のドローン人材のマッチングを促進する「ドローンキャリアマップ」を策定しました。 現状のドローン人材に関する課題とドローン...
2024.04.01|まつだ
-
(取材)一般社団法人日本マルチコプター協会(JMA)|全員が“親方”だからこそ生まれる事業シナジーでドローン市場を...
ドローンの普及とドローン飛行による安全な社会を目指し、2018年に設立された一般社団法人日本マルチコプター協会(JMA)。JMAの特徴は、もともと商工会議所に所属していた経営者らによっ...
2022.12.03|まつだ







