(取材)福島ロボットテストフィールド|陸海空、あらゆるテストを一箇所で。ドローン開発について副所長 細田慶信氏に聞く
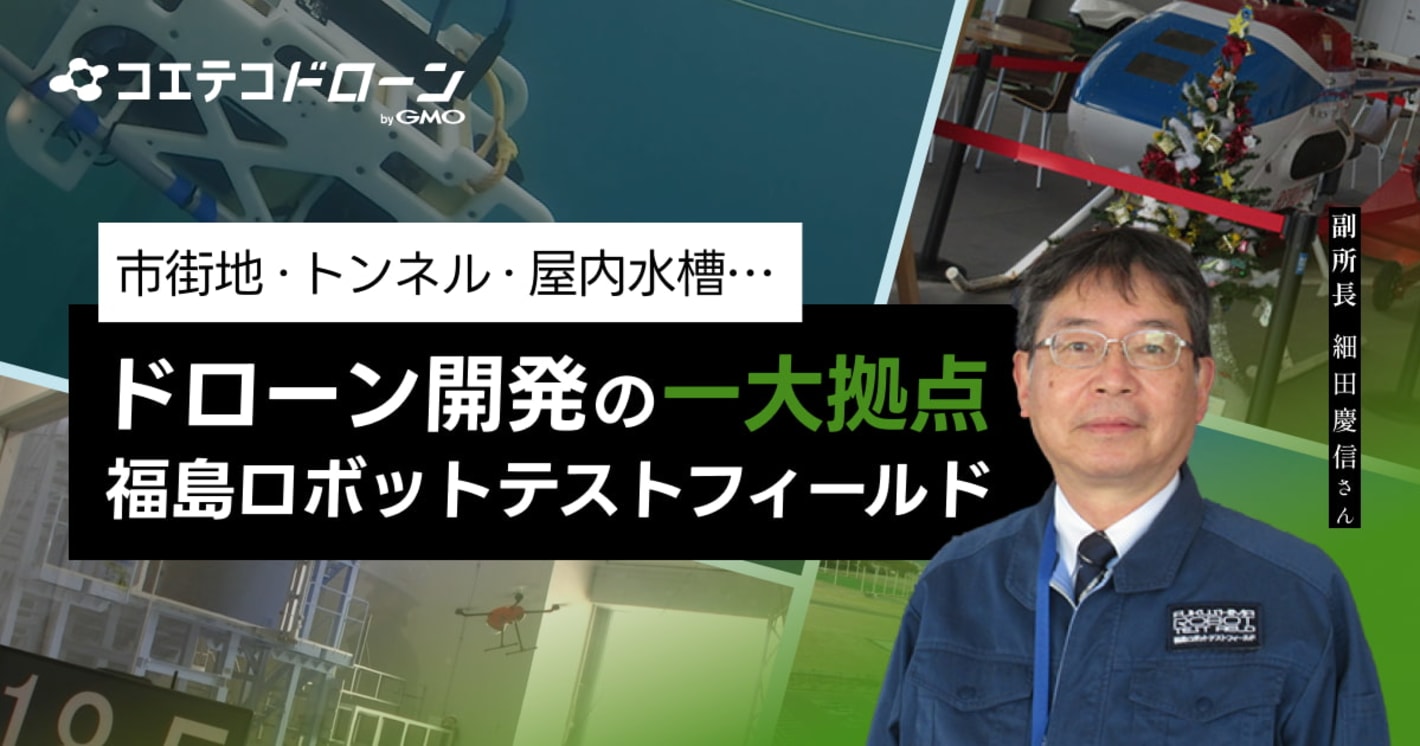

広大な敷地には長い滑走路が伸び、そのわきにはネットで覆われた飛行場が並びます。またある場所には家やビルを模した建物が並び、トンネルがあり、大きな橋があり、がれきの山もあれば水に半分浸かった建物もあります。滑走路わきには緩衝ネット付飛行場があります。
これらはすべて実際の使用環境を再現したもので、ドローンの機能を確認したり、安全性の実験をしたり、操縦訓練などを行ったりする設備だそう。この記事では福島ロボットテストフィールド副所長 細田 慶信さんに、施設の内容やドローンにおける今後の展望について伺いました。
「ドローン/ロボットの開発拠点」として、福島に新しい産業創出を

福島ロボットテストフィールド副所長 細田 慶信さん
―福島ロボットテストフィールドは、「福島イノベーション・コースト構想」のもと設立されたと伺っております。まずはその構想について教えていただけますでしょうか?
福島イノベーション・コースト構想のおこりは、東日本大震災です。震災で津波や原子力災害が起こった後、原子力災害現地対策本部の本部長であった赤羽経済産業副大臣(当時)がこちらに来られ、「単なる『復興』にとどまらない、未来につながる新しい産業を起こしましょう」とプロジェクト構想を立ち上げられたと伺っています。
では、その「産業」とはなにか。有識者によるディスカッションが行われた結果、ドローンやロボットの開発、そして開発に必要な試験場が良いのではないかという意見が出され、福島ロボットテストフィールドの設立へとつながっていきました。
―復興において希望の灯となるような新しい産業として、ドローンをはじめとするフィールドロボット開発が選ばれたのですね。
はい、そう聞いています。そして具体的な中身については、次に挙げる6つの重点分野が選択されました。
- ロボット/ドローン
- 廃炉
- エネルギー/環境/リサイクル
- 農林水産業
- 医療関連
- 航空宇宙
福島ロボットテストフィールド「4つのエリア」

①無人航空機(ドローン)の開発拠点「無人航空機エリア」
―福島ロボットテストフィールドにある4つのエリアと、実際の活用例を教えてください。では、最初に無人航空機エリアについてご紹介しましょう。
このエリアには、緩衝ネット付飛行場や500mの滑走路があります。滑走路を長い道路に見たてて、自動車の事故処理訓練などにも利用されています。
なお、緩衝ネット付飛行場は天井までネットが張られており、屋内扱いになりますから、安全性を確認するテストや改造したドローンの実験などによく使用されています。

ここではテトラ・アビエーション株式会社さまが、大型ドローンの形をした、いわゆる「空飛ぶクルマ」の飛行テストを行っています。

また、最近では無人航空機の認証制度が始まるにあたり、NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)さまが、事業者に向けて安全対策や飛行試験実施を模擬的に行うプロジェクトが実施されました。
不時着、落下、衝突回避といった試験も安全に行えるテストフィールドの良さを活かし、無人航空機(ドローン)の開発拠点としてご利用いただいております。
②トンネルや橋もある「インフラ点検・災害対応エリア」
次にご紹介するのは、インフラ点検、災害対応エリアです。このエリアには実物さながらの橋やトンネルが備えられています。
最近ではドローンによる橋梁点検が進んでいますが、点検業務を行う前には、ドローンの安全性や性能を確認する実証実験を行う必要があります。しかしトンネルや橋を実際に使用してテストを行うのは難しく、通行止めをしなくてはならないなど、費用も時間もかかります。そこで、本物同様のトンネルや橋を備えた福島ロボットテストフィールドの出番というわけです。
たとえば、橋を使った事例では、ドローンで橋を撮影してAI解析をし、修理が必要な箇所を判別するような研究が行われています。

ドローンだけでなく、事故対応の訓練などにも使用されています。両側のシャッターが閉まるので、煙が充満した状況など、さまざまなシチュエーションを再現することが可能です。
他にも、住宅地を模した市街地フィールドもあります。このフィールドもなかなかの完成度で、歩道ひとつをとっても、縁石がある・ないとか、縁石と建物の間がアスファルトで埋まっているとか、実際の道路であり得るさまざまなパターンが再現されています。ですから、走行ロボットの実験などに非常に適していますね。
なお、市街地フィールドの裏手にはがれきが山積みになっており、救助犬の訓練や、ビルの上に取り残された人を救助する消防訓練なども行われています。
―インフラ点検・災害対応エリアにある背の高いビルはどういった施設でしょうか?

これは試験用プラントです。試験用プラントは科学用プラントを模したものですが、クローラー型ロボットやドローンを使った点検の飛行訓練やテストがよく行われています。
私達は、テストフィールドとして場所を提供するだけでなく、プロジェクトにも積極的に携わりたいと思っています。ここではJUIDA(一般社団法人日本UAS産業振興協議会)さまがドローンの「プラント点検上級操縦技能証明証」講習を定期的に開催していますが、講習の内容については、経済産業省・消防庁・厚生労働省がまとめたガイドラインをベースにして、福島ロボットテストフィールドがJUIDAさまに委託して独自のガイドラインを作成しました。
―ドローンをプラントや住宅街でテスト飛行をしたり飛行訓練をしたりするのは、現実問題として非常に難しいだろうと思います。でも、実際の現場と同じ環境で飛ばしてみないとわからないわけですし、テストフィールドの重要性はとても大きいですね。
普通の空き地はあっても、ユースケースに合わせた模擬的な試験場はなかなかありません。その点からも福島ロボットテストフィールドは社会実装にも非常に役立っているのではないでしょうか。
③水中のインフラ点検や災害対応の実証試験を行える試験場「水中・水上ロボットエリア」
続いては水中ロボットエリアです。水中ロボットエリアは大きく分けて、水没市街地フィールドと、屋内水槽試験棟の2つがあります。水没市街地は主に訓練に使用されるほか、JAXAさまが「水が溜まっているときと無いときでは、衛星からの市街地の見え方がどう変わるか」という実験をされた事例があります。いっぽう屋内水槽は、水中ドローンの開発などによく利用されています。こちらの写真は、大水槽の側面をダムの壁面に見立て、コンクリートダム堤体を水中ドローンで点検検証できるかの事前確認をしているところです。水槽にテストピースを貼って水中ドローンで見えるかどうかをテストするなど、搭載する観測機器の性能を調査することができます。

屋内水槽は深さが7メートルもあるだけでなく、スクリューをとりつけられるため、中で水流を起こせます。水流がある状態でも水中ドローンがその場にとどまれるかどうかをテストできます。
たとえば東京電力の関連会社さまは、原子力発電所の燃料保管プールの状況確認に水中ロボットを使用していますが、その訓練もここで行っています。他にも、廃炉のデブリ(溶けて固まった原子炉内の燃料)を取り出す機械の実験が行われたケースもあります。
それからここには風洞棟があります。人工的な風なので、風速を少しずつ上げながらドローンの耐風性や性能を段階的に確認するようなこともできますよ。

④福島ロボットテストフィールドの本館「開発基盤エリア」

最後にご紹介する開発基盤エリアには、試験・研究室があります。福島ロボットテストフィールドの本館でもあり、会議室や展示場としての利用も可能です。

エントランスにはSUBARUの大型無人ヘリコプターが展示されています

本館会議室は展示場などにも活用できます。
ここには各種の装置が設置されており、福島県ハイテクプラザ南相馬技術支援センターのご協力を得て、設備の利用支援等も行っています。
たとえば、3次元でデジタイズする計測器では、昔に制作された部品で図面がない場合でも、部品をステレオカメラで撮影することで、外形を高精度でデータ化できます。
こうした装置は、どなたでも借りることができます。一般的に自治体の公設試験場は利用にあたり諸条件がありますが、福島ロボットテストフィールドは全国どこの研究者・事業者でも利用できるのが特徴です。これまでに実績はありませんが、海外の方でも利用可能ですよ。
誰でも研究に利用でき、陸・海・空すべての環境をテストできる。ここまで大型のテストフィールドは世界を見渡してもここにしかないと自負しています。
無人航空機ドローンの未来と課題

―今後、無人航空機(ドローン)は社会でどのように活用されていくと考えられますか?
近いところで大きく発展が見込めるのは、ドローンが唯一無二となる分野です。たとえば空撮などは、今やドローンがもっとも手軽な撮影手段ですから、今後もさらに広がっていくと思います。
さらには農薬散布などを含む、いわゆるスマート農業分野も期待大ですね。今でも、リモートセンシングを使用して衛星から農作物の育成状態を見ることはできますが、かなりのコストがかかります。それに比べてドローンはより手軽ですから、今後さらに需要が伸びていくはずです。
―一方で、課題は?
いかにビジネスモデルを構築するかです。
たとえば、ドローンは物流でも活躍すると期待されていますが、現状ではドローン1機に対して2~3人のサポートが必要です。これではコストが見合わないので、1人でも配送が可能なように技術開発をするか、コストを許容できるほどの利益が出るビジネスモデルを確立するか、どちらかの対応が必要です。
そのうえで、私はドローンによるビジネスが成立する環境を作っていくことが大切だと考えます。なぜならビジネスが成り立たないと、技術開発に資本を投入する価値がなくなってしまうからです。
ビジネスモデルを構築し、その利益で技術開発が進む。このサイクルをいかに回すかがドローン普及の鍵を握ると考えています。
福島ロボットテストフィールドが担う「これからの役割」

―福島テストフィールドは今後、ドローンの開発においてどのような役割を担っていくでしょうか?
無人航空機に関しては、2022年12月5日より認証制度が始まりました。この制度に対応するための訓練や練習、あるいはフライトの実験などに福島ロボットテストフィールドは最適です。
加えて、今後の展望としては、南相馬市と浪江町の両拠点間(約13Km)を結ぶ長距離飛行試験コースをさらに充実させていきたいですね。通常、ドローンを長距離にわたって飛行させるには地権者や地元の皆さまの合意が必要で、万全な対策を取っていたとしても、心理的な抵抗感からトラブルにつながってしまうこともあります。ドローン専用の長距離コースがあればこうしたトラブルも避けられ、ドローンの社会実装にまた一歩近づくことができるのではと考えています。
—最後に、ドローンやロボット開発に携わる方々に向けてメッセージをお願いします。
ドローンに限らず、機械は「作ったら終わり」ではありません。社会普及をめざすには、実証実験でのデータ収集や、膨大な回数のテストが欠かせません。
福島ロボットテストフィールドは公的機関ですから、使用料金もリーズナブルです。研究開発施設の拠点として、ぜひたくさん活用してください。皆さんと一緒に新しい産業を創出していけたらと願っています。
RECOMMEND
この記事を読んだ方へおすすめ-
(取材)ドローンのための気象予報サービスって何ですか?ウェザーニューズさんに聞きました!
気象分野で世界をけん引する株式会社ウェザーニューズは、いまや陸・海・空すべての領域の気象予測サービスを世界中で展開しています。 そんなウェザーニューズは2016年、「ドローンビジネス...
2024.04.01|まつだ
-
MFLP・LOGIFRONT東京板橋内に「板橋ドローンフィールド」が誕生!ドローン産業の未来を担う新たな拠点
板橋ドローンフィールドが2024年10月2日に盛大に竣工し、ドローン産業の発展を担う新たな拠点が誕生しました。 東京23区内最大級の物流施設であるMFLP・LOGIFRONT東京板橋...
2025.05.30|大橋礼
-
(取材)神奈川県知事 黒岩 祐治|国産ドローンを活用した災害時物資輸送の実証事業を実施
近年、ドローンの活躍が期待されている分野の一つが、防災です。小型で無人飛行が可能、場所を選ばないなどの利点から、多くの自治体が災害時の物資輸送や被災者捜索などにドローンの活用を検討して...
2023.07.11|徳川詩織
-
(取材)エアロセンス株式会社代表・佐部浩太郎|国産機初のVTOL型ドローンで災害対策のDXに挑む
エアロセンス株式会社代表・佐部浩太郎氏は、かつてソニーでエンターテインメントロボット「アイボ」を開発した、AIやロボティクスの第一人者です。 技術開発への情熱をもう一度呼び起こし...
2025.05.21|宮﨑まきこ







