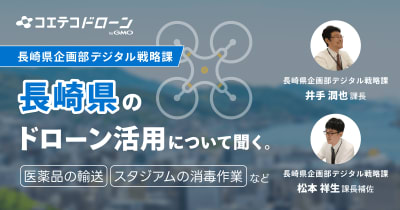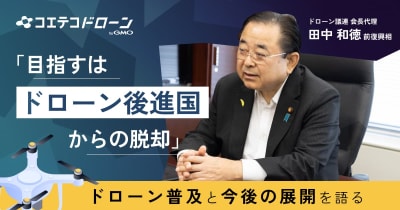(取材)ANAホールディングス・ドローンプロジェクトディレクター信田光寿氏|空のプロ集団が、日本の物流を変える

しかし、私たちの便利な生活を支えてくれている宅配業への負担は大きく、物流業界の人手不足は年々深刻化しています。
そこで期待されているのが、ドローンによる物流改革です。ドローンを利用すれば、離島や山間部、被災地へも、安全かつ迅速に物資輸送を実現できます。
航空運送事業を幅広く展開するANAホールディングスは、2016年よりドローン事業に着手し、社会実装に向けて挑戦を続けています。
同社が新事業・新サービスの創造をミッションに設立したデジタル・デザイン・ラボで、ドローンプロジェクトディレクターを務める信田さんに、ドローン物流の社会実装に向けた課題や今後の展望などについてお話をうかがいました。

ANAホールディングス デジタル・デザイン・ラボ ドローンプロジェクトディレクター信田光寿さん
航空会社の知見を活かし、ドローン物流に挑戦
ーANAがデジタル・デザイン・ラボを立ち上げ、ドローン領域への挑戦を始めた経緯について教えてください。デジタル・デザイン・ラボは、ANAホールディングスが航空会社のノウハウやスキルを活かして、新規の事業やサービスを生み出すために立ち上げられた組織です。
ドローン以外にもアバターや宇宙におけるモビリティなど、幅広い領域に挑戦しています。

その中でも私がディレクターを務めるドローンプロジェクトでは、今まで活用が少なかった低空域に注目し、ドローンを利用した物流を社会に根づかせることを目的として実証実験を重ねてきました。
離島や山間地といった、そもそも買い物に行きづらい場所に住んでいる方や、仮にネットで購入しても届くまでに時間がかかる方などに、生活に必要な物資を迅速に届けられる社会を目指しています。
ーEC市場の拡大によって配送業の人材不足が深刻だとされていますが、そういった背景もドローン配送に挑戦する理由に影響しているのでしょうか?
そのとおりです。とくに2024年4月以降は、法律によってドライバーの年間時間外労働の上限が960時間に制限されますので、今以上に人材は不足していくと考えられます。
とはいえ、これはドライバーの安全や健康を守るためにも必要な法律ですから、人材を増やすだけでは根本的な課題の解決には至りません。
将来的に自動・自律運航が可能とされているドローンを導入すれば、配送業務を効率化し、物流業界を健全に発展させていくことにも繋がります。まさに、配送業のイノベーションを起こせるのです。
ドローン市場におけるANAの優位性
ーさまざまな業界から参入が相次ぐドローン市場において、ANAの持つ優位性とは?ANAの優位性は、航空会社として培ってきた有形無形の知見だと考えています。そのうち有形のノウハウとして挙げられるのは、創業70年以上の歴史の中で作成された各種規定やマニュアル、チェックリストなどです。
こうしたノウハウを持つANAなら、ドローンという新しい領域においても、過去の事例を参考にドローンに適した規程やマニュアルを作成できます。長年の経験に基づいているぶん必要事項の抜け漏れが少なく、ゼロイチで参入するよりもスピード感を持って進められます。
いっぽう無形の資産は、いわゆるマインドセットです。ANAグループでは入社時に、ANAの過去の失敗や事故に関して学ぶ時間が必ず設けられます。失敗から学び、再発を防止し、改善していくためのフィードバックサイクルの大切さを理解するための時間なんです。

これらを経てから実際の業務にあたるため、安全への意識と責任、愚直にマニュアルを遵守するマインドが着実に培われます。このマインドこそ、空路において安全な物流を実現するために必要不可欠だと考えています。
ーANAに対しては旅客機のイメージが強いのですが、物流においても知見をお持ちなのでしょうか?
はい。ANAホールディングスのグループ企業には航空貨物事業を担うANA Cargoがあり、旅客機だけでなく物流に関する知見も持っています。
もちろん、貨物用の航空機とは規模感や事業内容も違うため、すべての知見をそのままドローンに転用できるわけではありません。しかし、ANA Cargoが請け負ってきた空港間での輸送に加えて、空港の先にあるエンドユーザーの手元まで届ける手段としてドローンを活用できれば心強いと考えています。
ANA Cargoは全国に営業拠点があるため、今後はグループ内で連携しながら、ドローン物流を全国に拡大していきたいですね。
ドローンに何ができるのか?積み重ねた実証実験
ーこれまでにおこなってきたドローン配送の実証実験について教えてください。ANAでは離島や山間部での血液検体や医薬品の輸送、レベル3飛行といった実証実験を重ねてきました。なお、レベル3飛行とは、海や山などの人の目が届かないところに、ドローンが単独で配送をする補助者なしの目視外飛行のことです。
多数の実績を重ねてきたANAですが、2016年のプロジェクト立ち上げ当初はドローンについて充分な知識を持つメンバーはほとんどいませんでした。そこで、まずはゴルフ場の空撮や設備の点検を経験することで、「ドローンに何ができるのか」を確かめるところから始めました。

そこから、補助者ありでのレベル3に挑戦したのが2018年です。補助者は飛行経路に航空機などがいないかを観察したり、操縦者にアドバイスをしたりとドローンの飛行をサポートする役割を担う存在ですが、イノベーションを起こすためには補助者を置かなくてもよい運航を目指さなければなりません。
2019年5月には補助者なしでのレベル3飛行を実現し、離島や被災地への物資輸送をこれまでに15回おこなってきました。実験においては、場所を選ばない運航を目指して都心部での運航も実施しましたが、いずれサービス化するのであれば、まずは物資の届きにくい地域への安定した配送を実現したいと考えています。

2020年12月、福岡市能古島の子供たちに見送られてドローンが離陸したときの様子
ードローンを使った点検や空撮などにも航空会社の知見は活かせると思うのですが、物流にこだわって実証実験を重ねている理由とは?
たしかにドローンは物流以外にも点検、測量、空撮など多くのユースケースがありますが、航空会社の知見を一番活用できるのは物流の領域だと考えました。
我々は定められた地点に安全かつ正確に飛ばすためのノウハウも持っていますし、ANA Cargoという既存の航空貨物事業と連携することによって、物流業界全体のグロースが期待できます。ドローンのユースケースの中で難易度が一番高い点も、空のプロフェッショナルであるANAが取り組む意義であると感じています。
空のプロフェッショナルとして、業界に貢献していく
ーそれだけの実証実験を重ねても、現時点で実用化に至っていないのはなぜでしょうか。大きな要因として、運航コストの高さが挙げられます。荷物をひとつ届けるだけで利益を得るのは難しいのが実情です。
ドローン配送の利用者が増えれば解決しそうな問題ではあるのですが、離島や山間地域での想定利用者は年配の方がメインなので、ネットを利用した注文やオンライン決済などをすぐに受け入れられないケースも多いのです。
ー心理的な抵抗感が壁になっているのですね。
はい。しかし、得体の知れないものを受け入れられない気持ちも理解できます。安全対策を講じるのはもちろん、説明責任を果たし、きちんと理解して受け入れていただける関係性を構築できなければ、社会実装は進まないでしょう。
そのうえで、ドローン配送の利用で生まれるメリットを実感できるサービスを提供できれば、社会合意の形成が進むと考えています。
たとえば、車がないと生活できない地域にドローン配送が根づけば、日用品の買い出しや薬の受け取りで遠出をする必要もなく、事故も減少するはずです。採れたての鮮魚や農作物を港や畑からダイレクトに配送できれば価値が上がり、地方創生にも繋がっていくでしょう。こうしたメリットをどのように伝えていくかが、ドローンビジネスの今後の課題です。

ードローン配送の社会実装に向けて、ANAは今後どのような取り組みをしていきたいと考えていらっしゃいますか?
航空会社として、ドローン配送における空の安全を確固たるものにする責任があると考えています。
今後は都市部や住宅街と言った人口集中地でも飛行が可能になるレベル4飛行が解禁され、これまで以上にリスクをともなう運航が増えていくでしょう。
しかし、国民に安心してドローン物流を受け入れてもらわなければ、社会実装は実現しません。
業界全体の安全に対する意識を底上げするために、私たちは空の安全対策を熟知したANAのノウハウを他社にも共有し、航空局をはじめとする政府への提言をおこなうなど、国民への説明可能な安全対策を講じる準備を進めています。
安全対策と並行して、効率的な配送経路を検討したり、関わる人員を減らしたりといった運送コストを下げるための取り組みをおこない、人々がドローン配送を気軽に利用できるよう、今後も意欲的に事業を展開していきます。
RECOMMEND
この記事を読んだ方へおすすめ-
(取材)長崎県企画部デジタル戦略課|全国から事業者・自治体が集まる長崎県の取り組みについて聞く
長崎県は、すでに民間企業による離島での物流支援が社会実装されているなど、ドローンの活用に力を入れている自治体の一つです。2023年9月には第2回ドローンサミットも開催され、全国から事業...
2025.05.21|徳川詩織
-
FINDi|水道から発電所まで!水中設備点検のDX化をドローンで実現
高齢化するインフラ設備の維持管理が社会課題となるなか、ドローンを活用した点検手法の開発が進んでいます。水中設備の点検調査サービスを展開している株式会社FINDiでは、水中点検に特化した...
2025.05.30|Yuma Nakashima
-
「目指すはドローン後進国からの脱却」ドローン議連・田中和徳前復興相に聞く
日本国内におけるドローンの技術開発や法整備、安全規制には多くの課題が残されています。これを解決するため、2016年に設立されたのが無人航空機普及利用促進議員連盟(通称:ドローン議連)で...
2025.06.24|夏野かおる
-
SKY BIRD 東日本ドローン航行技術教習校卒業生インタビュー|未経験から一等ライセンス獲得!体験会で魅せられた...
医薬品卸売業に勤める宮下さんはSKY BIRD 東日本ドローン航行技術教習校の体験会をきっかけにドローンに魅了され、同校に入学。まったくの未経験から一等無人航空機操縦士を取得しました。...
2025.02.28|白波弥生