(取材)ドローン・コンプライアンス・アドバイザー 尾関健氏|ドローンの法律面・申請をプロがサポート

今回は、ドローン・コンプライアンス・アドバイザーの尾関健氏に、業務内容や活動事例、ドローンのコンプライアンスを守るためのポイントなどをお聞きしました。

ドローン・コンプライアンス・アドバイザー 尾関健氏
きっかけはトイドローン。コンプライアンスの重要性に気づきエンジニアから転身
ーー尾関様のこれまでのご経歴をお聞かせください。日本でインターネットがはやり始めた1995~2000年ごろ、当時大学生だった僕は学生同士の集まりで、インターネットカフェの事業を始めました。この事業を5年ほど行って、インターネットやネットワークの技術を学びました。
その後は企業に就職し、25年ほどの間ネットワークエンジニアとして勤めたあと、昨年12月末に退社。そして、ドローン・コンプライアンス・アドバイザーとして独立しました。
ドローンを始めたのは2020年ごろで、きっかけは「ドローンをやってみたい」という息子に買ってあげたことでした。買ってあげたトイドローンで遊んでいたら、僕がはまってしまったんです。
ドローンを触り始めて「これはいろいろ使えるな」と思ったのですが、航空法などのコンプライアンスがとても重要かつ複雑だと気づきました。それでドローンの業務活用の可能性とコンプライアンスに興味を持つようになり、その分野に特化したドローンスクールを卒業しました。
サラリーマンとして働きながらも「ドローンを仕事にしてみよう」と思い始めていた2021年ごろ、プロのドローンカメラマンである小澤諒祐君と出会いました。彼は当時高校生でしたが、すでにドローンの空撮の仕事をしていて、日本でも指折りのドローンのレーサー・パイロットでもありました。しかし、学生であるためコンプライアンスのチェックまではなかなか手が回らないということで、一緒に仕事をすることになったのです。
仕事をしていくうちに、ドローンにまつわるコンプライアンスの大変さがどんどん顕著になってきて、小澤君だけではなくパイロットみんなが困っている状況が見えてきました。そこで、ドローンのコンプライアンス面を支援する仕事をしていこうと考え、現在に至ります。
ーードローンのコンプライアンス面に目を向けた理由やきっかけは何ですか。
ドローンのコンプライアンスとITのエンジニアとは全く関連がないようにみえるかもしれません。しかし実は、コンプライアンスというキーワードで考えると、ドローンとITは密接につながっている部分があります。
ITエンジニアにおける最も重要なポイントは、情報漏えいなどのリスクに対するセキュリティです。IT業界では10年以上前から法律とシステムとの兼ね合いが重要になっていて、僕もずっと取り組んできました。法令順守したシステムを設計するために、公文書を読み込んだ上でシステム化させ、完成したシステムに対してコンプライアンス対応ができているかを確認する作業です。
現在はドローンの分野でも法令順守が重要視されるようになりましたが、公文書を読み込んで自分の飛行計画に落とし込んだり、必要な許可承認を得たりする作業が不得意なパイロットもいます。でも僕はそのような作業に慣れているので、みんなが困っている部分で自分の能力を活かせればと考え、この仕事を始めました。

パイロットが自分の業務に集中できるよう、各種申請や調整を行うのが仕事
ーードローン・コンプライアンス・アドバイザーの業務について教えてください。IT業界では、コンプライアンス面は専門の部署が担うのが当たり前ですが、ドローン業界ではまだそこまでには至っていません。現在はパイロット個人がコンプライアンス面も対応していますが、「何が問題になるのか」「漏れはないか」など、困っている人も多いです。
そこで、パイロットから「ここで飛びたい」という相談を受けて、どんな飛ばし方をしたいのか、どのような機種で飛ばしたいのかなどをヒアリングした上で、僕が飛行計画やさまざまな法律に関わる部分を担います。一言でいうと、パイロットが自分の業務に集中できるようにするのが、ドローン・コンプライアンス・アドバイザーの仕事ですね。
ーードローン・コンプライアンス・アドバイザーの役割が特に求められる産業や業界はありますか?
業界としては、やはり空撮業界からの相談が最も多く、その中には、点検・測量などの状況空撮、工事後の空撮なども含まれます。空撮をする人は「包括申請」という、航空局へ申請し国土交通大臣の許可・承認書を得て飛行させることが多いのですが、「包括申請の範囲内でどれだけやっていいのか」という質問がけっこう多いですね。航空局への申請は行政書士にお願いするのが一般的になっていますが、行政書士は許可・承認を取得した後のパイロットのアフターフォローまでは基本的には行いません。そのため、取得した許可・承認書でどこまで飛行できるのか、パイロットもよくわかっていないんです。
ドローン・コンプライアンス・アドバイザーは、例えば、包括申請の範囲内としても繁華街の中で飛行させる際に警察との調整をしたり、包括申請の範囲内に収まらない山岳自然災害の状況空撮として、150メートル以上の超高高度での飛行に必要な支援や調整など、飛行計画にかかわる全体的な調整をパイロットに代わって担っています。
ーーこれまで、どのような案件・プロジェクトを担当されてきたのでしょうか。
小澤君との仕事で、レインボーブリッジを中心とした東京の街並みを海上から空撮したいという依頼を受けました。そばに空港があって特別な許可が必要だったり、周りの陸地が港湾会社の管理する土地で離着陸ができなかったり、船の出入りが多く20カ所に及ぶ関係企業への連絡が必要だったりと、さまざまな課題がありましたね。最終的にドローン・コンプライアンス・アドバイザーとして、船の上から離着陸する形を提案し、海上保安庁や各自治体の管理者、空港などと調整して、空撮業務を実施しました。
また、自治体からの依頼で、国道の拡幅工事中前後の比較のために国道沿いの3.6キロを飛行させるという案件もありました。道路の近くを飛ぶときには警察との調整が必要です。飛行計画を説明し、飛行させてよい時間の調整などを行った上で、航空局にも申請し、許可をもらって無事に飛ばせることができました。

ドローンのコンプライアンスのよくある誤解・問題点は?
ーードローン使用におけるコンプライアンスを考える際のポイントとして、よくある誤解や問題点は何ですか?ドローンを飛ばす際には、飛行マニュアルを用意してその通りに飛行をすることを条件に、国土交通大臣から許可・承認を取得するのですが、多くのパイロットがこの飛行マニュアルを知らない、もしくは、目を通したことがないまま、許可・承認書を取得してしまっていることが散見されます。
私が自治体や企業を相手にドローン・コンプライアンスの講習会をする中で、組織が代表して社員の許可・承認を取得していてもパイロットである社員1人1人は飛行マニュアルを知らない、読んだことがないというのはよくあることです。
マニュアルの内容をよく知らずに飛行させて法に触れてしまうケー スもあるので、しっかり読んでほしいですね。
2022年6月機体登録制度改正、同年12月国家ライセンス制度の制定など、ドローンの交通ルールはまさにいま、突貫工事中です。機体登録、国家資格、飛行許可申請や事故発生時の対応など、細かいルールが制定されれば、それに対する罰則も増えていきます。ルールに違反すれば、懲役を含む刑事罰が科されることも。 今回はバウンダリ行政書士法人代表 ...
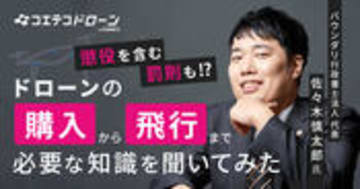

2025/05/30

また、ドローンのコンプライアンスというと航空法が注目されることが多いですが、ドローンを飛行させる際に関わる法律は航空法だけではありません。道路の上で飛ばせば道路交通法、河川の上で飛ばせば河川法、海の上なら港則法や海上交通安全法というように、もっと広く関わってきます。
ドローンはどこを飛ばすにしても、必ず誰かの管理する土地や海上、河川上の上空を飛行させることになります。河川のなかでも、管理者が自由に飛ばしてよいとしている川もあれば、届け出を求めている川もあります。また、海上でも大きなタンカーが行き来するような場所は当然さまざまな関係団体が管理しています。自分が飛ばそうとする場所は誰が管理しているのかをしっかり認識し、飛行させることが大切です。
ーードローン技術の進化や普及に伴って、コンプライアンスのニーズや課題はどのように変化してきたと感じますか。
技術の発展に伴い、制度も充実してきています。法律やガイドラインが3カ月に1回はどこかしら変わるというくらい、スピード感が速いのがドローンのコンプライアンス面における現状です。
例えば、2022年6月には航空法の規制対象となるドローンの重量が200g以上から100g以上に変更されたり、ナンバープレート制が始まったりと、大きな変化がありました。また、同年12月にはドローンの国家資格制度が始まり、罰則が強化されました。制度が変化するとともに、対応しなければならないことが増えています。ドローンのコンプライアンスにおける専門家として、常に情報収集して対応しないかなければなりません。
ーー現在のドローン関連の法規制や指針について、注目すべき変化やトレンドがあれば教えてください。
ここから先は、ドローンの物流や測量、点検がポイントになってくるのではないでしょうか。機体がどんどん優秀になっていて、今後はAIによる自動航行も増え、飛行する範囲も広がっていきます。ただ、自動航行する際にも基本となる飛行計画は人間が作ることになるため、よりいっそうコンプライアンスは重要になってくると思います。
ーーこれからドローンを導入しようと考えている事業者に、一番伝えたいアドバイスや注意点をお聞かせください。
現在はドローンが広がる前の過渡期にあたると思っています。もう数年たてば多くの人が日常的にドローンを目にする機会も増えるでしょう。とはいえ、現状は自治体や企業もドローンの導入を考えてはいらっしゃいますが、目的に合わせた個別機体の登場を待って足踏みしていると私は感じています。
例えば、自治体庁舎からドローンが自律飛行して、災害地の状況を空撮して帰還できる機体は開発段階であり、まだできません。ならば、DXと組み合わせて、災害地近くのパイロットが現地に赴き、自治体庁舎までリアルタイムで配信すれば良いでしょう。日本は、世界でも有数の通信インフラが充実した国ですので。
ドローンの機体をどうするかよりも、どう活用したら便利なのかという点に注目して専門家と話をしてほしいですね。ドローンをどう使えば有用なのかを相談してもらえると、さまざまなアイディアが生まれて面白いはずです。
パイロット一人ひとりがコンプライアンスをすべて把握しているということはあり得ません。なので、企業や自治体の中でドローンのコンプライアンスについて専門家に尋ねる体制が整っていることも大切ではないかと思います。

ドローンのコンプライアンスの専門知識を持ち、活躍できる人材を社会に増やしたい
ーーここまでのお話を踏まえて、今後、ドローン・コンプライアンス・アドバイザーとしての活動をどのように展開していきたいと考えていますか。ドローン・コンプライアンス・アドバイザーがもっと増えてほしいです。私自身1人で担当できる範囲は多くても20社くらいですから。一つ一つの案件に対して、本当に問題ないかという判断をパイロットと同じ責任で行わなければならないので、担える数には限界があります。
専門知識を持ってアドバイスできる人が増えれば、法令を遵守した形でもっと便利なドローンの発展が進むはずです。今後はドローン・コンプライアンス・アドバイザーを増やすための活動に取り組んでいきたいと思っています。まだ構想段階ですが、飛行計画や許可承認のアドバイスをする仕事につながる「ドローン安全管理士」のような資格制度を作りたいですね。ドローンのコンプライアンスの専門知識を持ち、各企業や自治体で活躍するような人材を社会に増やすことを目指します。

RECOMMEND
この記事を読んだ方へおすすめ-
(取材)防災事業からドローンビジネスへ!ブルーイノベーション株式会社代表取締役社長熊田貴之氏
ドローン業界のパイオニア的存在であるブルーイノベーション株式会社。防災事業でのドローンの活用をきっかけに、現在は複数のドローンやロボットを連携させてさまざまな業務のDX化・オートメーシ...
2024.04.01|まつだ
-
(取材)センシンロボティクス代表・北村卓也氏|ドローンを活用したインフラ整備のDXで、子どもに誇れる仕事を
社会のさまざまな場面で活躍が期待されているドローン。その分野の一つに設備点検が挙げられます。労働人口の減少やインフラ設備の老朽化などの社会的課題に対して、ドローンをはじめとするロボット...
2024.04.01|徳川詩織
-
(取材)コマンドディー代表 稲田悠樹氏|「ドローン手形」で熊本県・阿蘇の絶景を誰でも空撮可能に!
ドローン空撮で人気が高いエリアの熊本県・阿蘇で、ドローンを1日自由に飛ばせる「ドローン手形」というサービスが注目を集めています。ドローン手形を展開するのは、熊本県でドローン事業を行う株...
2024.04.01|徳川詩織
-
(取材)一般社団法人日本マルチコプター協会(JMA)|全員が“親方”だからこそ生まれる事業シナジーでドローン市場を...
ドローンの普及とドローン飛行による安全な社会を目指し、2018年に設立された一般社団法人日本マルチコプター協会(JMA)。JMAの特徴は、もともと商工会議所に所属していた経営者らによっ...
2022.12.03|まつだ







