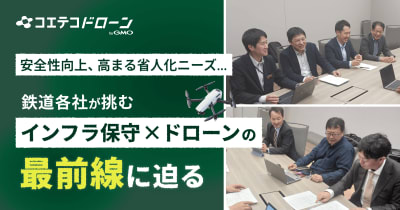首都高技術株式会社|安全性&効率性UPに貢献する、ドローンを使った橋梁点検

そんな中、ドローン人材を内製化して自社の業務に特化したパイロットの育成に取り組んでいるのが首都高技術株式会社です。首都高グループの一員として高速道路の維持管理を行う同社では、構造物の点検業務にドローンを活用して業務効率化を図っています。
首都高技術株式会社の構造管理部 点検技術課 担当課長の影澤 雅人氏と、構造管理部 構造管理課 係長の加藤 穰氏にお話を伺いました。

(左)構造管理部 構造管理課 係長 加藤 穰氏、(右)構造管理部 点検技術課 担当課長 影澤 雅人氏
現場での活用を見据えた実践的なドローン教育
――首都高速道路という都市の大動脈を支えるインフラ点検に、新技術であるドローンを導入しようと考えられた背景について教えてください。加藤:
2014年(平成26年)に橋梁の構造物点検が法令化されたことが、ドローン導入の大きな契機となりました。
これまでも首都高速道路の全構造物を点検してきましたが、海上や河川上に架かる橋や、都市部特有の周辺建造物との近接などにより、従来の点検手法では接近することが難しい現場環境が数多く存在していたんです。

高所作業車による点検が物理的に不可能な場所も多く、ロープを使ってアクセスする点検等を行っておりましたが、このような課題に対応するため、新たな点検手法としてドローンの導入を検討することになりました。人手不足も背景の一つではありましたが、それ以上に構造物へのアプローチ性の向上が重要な課題でしたね。
――最終的にドローンを選ばれた決め手は何だったのでしょうか。また、機体を選ぶ際のポイントとして意識された点を教えてください。
加藤:
1人のオペレーターで運用でき、必要な資格も少なくて済むという利点が大きかったです。2018年に本格的な検討を始め、2019年からプロジェクトとして取り組みを始めました。
また機体選定で最も重視したのが、GPS非受信環境下での安定飛行性能です。橋梁点検では基本的にGPSが使えない環境での作業となるため、これは必須の要件でした。
最終的には飛行性能に加え、上向きにカメラをチルトできたりする機体を選定しています。
課題解決のデータを蓄積し、コスト減&作業効率向上に貢献
――都市部でのドローン点検は、当時としては前例のない挑戦だったと思います。開拓者として直面された課題についてお聞かせください。影澤:
最初の検証現場として設定したのが、首都高速2号目黒線の四之橋付近(港区)です。この場所は、下には水深の浅い古川が流れ、周辺にはビルが近接するという、まさに典型的な点検困難箇所でした。
古川に架かる一之橋から四之橋までの首都高速2号目黒線の区間は、すべてが一般的な近接点検では対応が困難な「点検困難箇所」と定義されるような路線だったのです。都市部でのドローン点検事例が少なかっただけに、河川管理者との調整など、前例のない取り組みにも苦心しました。
河川管理者からも「このような事例がないため、どう判断していいかわからない」という反応があり、細かな調整を行う必要がありましたね。

影澤:
現場での実践を通じて、さまざまな技術的課題も見えてきました。たとえば、橋桁の裏側を撮影する際は手前の部材にピントが合ってしまい、見たい箇所にフォーカスが合わないというのは大きな課題でした。他にも水面からの反射光による画像のちらつきも、実証実験を経てわかった課題です。
その後の運用では、対象物からの距離を一定に保つなど撮影方法の標準化を図ったり、時間帯を考慮した撮影計画を立案したりといった工夫で対応してきました。
――3年間の運用を通じて、従来の点検方法と比較した効率性やコスト面での手応えをどのように感じていらっしゃいますか?
加藤:
導入から約3年が経過し、さまざまな現場条件での実績データを蓄積している段階です。費用対効果の正確な比較はこれからの課題ですが、従来の点検方法と比較すると大きな可能性を感じています。
とはいえ、足場を設置したり、ロープアクセスを使用したりする従来の方法と比べると、作業日数は大幅に短縮できていますね。今後は飛行実績や作業時間のデータを積み重ねることで、より正確なコスト比較が可能になると考えています。
また点検の質を維持しながら、いかに効率的なオペレーションを実現できるかという観点からも、継続的な改善を進めています。
新分野への応用でドローンへの知見とノウハウをさらに蓄積
――点検の実施体制についてですが、橋梁のプロフェッショナルが自らドローンを操縦するという御社ならではの特徴的なアプローチをとられていますね。その狙いと効果についてお聞かせください。加藤:
現場では複数人体制で作業を行い、撮影した画像や動画をその場で確認しています。1フライト目の撮影内容をその場で確認し、品質が不十分な場合は2フライト目の終了後に再度撮影を行うなど、品質管理を徹底しています。
橋梁の専門家が飛ばすのでしっかり撮影するべきポイントを押さえられますし、最終的な判断は撮影画像を事務所に持ち帰って行いますが、現場での即時判断や効率的な撮影ができるというのは当社の強みですね。

影澤:
点検では、コンクリートのひび割れや浮き、ボルトの緩み、塗装の剥がれなどを詳細に確認しています。
他社では外部ベンダーに撮影を依頼するケースも多いのですが、当社では点検のプロフェッショナルが直接ドローンを操作することで、現場での即時判断や効率的な撮影を実現しています。これにより、機密保持の観点からも安全な運用が可能となっています。
――水管橋施設の点検など、道路橋とは異なる新しい分野への挑戦も印象的でした。技術者として、このような未知の領域に取り組まれた経験から得られた気づきがありましたら、ぜひお聞かせください。
影澤:
水管橋施設は道路橋とは全く異なる構造で、細かい部材が複雑に組み合わさっているため、全く新しいアプローチが必要でした。
この経験を通じてドローン点検の可能性の広がりを実感しましたし、今後はこの分野でのドローン活用がさらに増えていくのではないかと期待しています。
加藤:
私たちにとって新鮮な挑戦であると同時に、技術者としての成長の機会にもなった取り組みでしたね。従来の点検方法にとらわれず、新しい技術を積極的に取り入れることで、より効果的なインフラ維持管理の実現を目指しています。
新たな技術が新たな取り組みの可能性を創造
――若手から40代以降まで幅広い年齢層の方々がドローン技術の習得に挑戦されていると伺いました。そこでの課題や工夫、特に通常業務との両立や技術の習得スピードの違いなどについて、具体的にお聞かせください。加藤:
社内での人材育成には特に力を入れており、現在では約20名のドローン資格保有者がいます。今年度中には総社員数の約1割が資格を持つことを目標としています。
2024年5月にドローン操縦技術の向上・継承を目的として、首都高速道路株式会社が資格保有者以外でも操縦訓練が可能な「首都高ドローントレーニングフィールド」を大橋換気所に構築し、これまでに7、8回の訓練を実施しています。

影澤:
年齢による学習速度の違いも考慮しています。40代以降から始めると、若い世代と比べて習得に約40%程度多くの時間がかかる傾向があります。
しかし、これは決して障壁ではありません。むしろ、豊富な点検経験と新しい技術を組み合わせることで、より効果的な点検が可能になると考えています。
また通常業務と並行して点検業務を行うため、特定の社員に負担が集中しないよう配慮しているのもポイントですね。多くのパイロットを育成することで業務の分散化を図るとともに、災害時などの緊急対応にも備えています。
――今後の展望についてお聞かせください。
加藤:
現在ドローンを活用した点検実施範囲は、首都高速道路全体の1%にも満たない状況です。首都高は約330キロの道路網を有しており、2車線区間は2倍、3車線区間は3倍の点検距離となるため、実際の点検対象延長は更に膨大なものとなります。
しかしながら機体の性能は日進月歩で進化していますし、我々のオペレーション技術も向上を続けています。
将来的には点検業務以外への活用も検討しています。たとえば首都高速道路の維持管理の様子をドローンで生中継し、臨場感ある形で一般の方々に伝えることができれば、インフラ管理の重要性への理解も深まるのではないかと考えています。
影澤:
法整備の面での課題もありますね。都市部での第三者上空飛行に関する規制緩和や許可取得の円滑化が進めば、さらなる展開が可能になると考えています。
若手人材の育成も重要な課題です。ドローンやDXといった先進的な取り組みは、若い世代にとって魅力的な要素になりそうです。新技術の導入は、インフラ点検という伝統的な分野に新しい可能性を開くだけでなく、若手にとって魅力的な職場づくりにもつながります。
これからも年齢や経験に関係なく、誰もが新しい技術にチャレンジできる環境を整備することで、組織全体の技術力向上を図ってまいります。
RECOMMEND
この記事を読んだ方へおすすめ-
本田技研工業株式会社(Honda)|モビリティデータを活用した道路インフラ管理でめざす「交通事故ゼロ社会」
社会インフラの老朽化に対する効率的な維持管理手法として、センシング技術とビッグデータ解析を組み合わせたアプローチを試みている本田技研工業株式会社。車両データを活用した革新的な道路管理プ...
2025.05.30|Yuma Nakashima
-
FINDi|水道から発電所まで!水中設備点検のDX化をドローンで実現
高齢化するインフラ設備の維持管理が社会課題となるなか、ドローンを活用した点検手法の開発が進んでいます。水中設備の点検調査サービスを展開している株式会社FINDiでは、水中点検に特化した...
2025.05.30|Yuma Nakashima
-
鉄道施設の安全をドローンで守る。鉄道会社が挑む、「保守×ドローン」の最前線
関西の主要電鉄会社が集まる「関西電鉄会社ドローン研究会」では、鉄道の保安・点検業務における課題解決に向けたドローン技術の活用を検討しています。各社の担当者に、鉄道会社として点検保安業務...
2025.07.31|Yuma Nakashima
-
ドローン最前線、レベル4対応新型機「PF4-CAT3」とは|未来の物流を支えるACSLの挑戦
高度な自律制御技術を基盤に、産業用ドローンの開発と社会実装を進める株式会社ACSL。同社が新たに第一種型式認証機として申請したのが、日本郵便(JP)との共同開発によって誕生した大型ドロ...
2025.05.21|夏野かおる