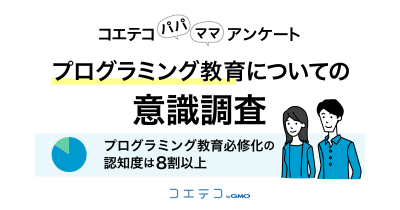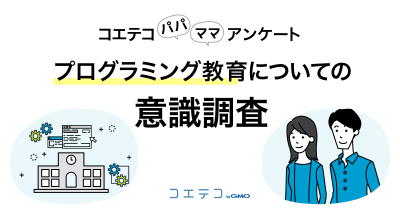保護者目線で選んだ教材…ユーキャンのロボットプログラミング、担当者インタビュー

そんなユーキャンが、今年1月からスタートさせたのが、「スタディーノ(R)ではじめるうきうきロボットプログラミングセット 」の教材販売。
ついに来年度に迫った小学校授業必修化に向けて「何をどう備えればいいのか…」と戸惑う親御さんたちに「ぜひ手にとっていただきたい」と語る、開発担当者インタビューです。
子どもの夢、『お母さん検知マシン』

さっそく見せていただいたのが、こちらのロボット。横方向に細長く、特長と言えば、コードにつながった3つの部品くらいです。
シンプルな見た目ですが、これは?と伺うと、「『お母さん検知マシン』です」とのこと。

『お母さん検知マシン』は、自分の部屋にいる子どもが、2つのセンサで「お母さんの接近」に気付けるロボットです。
まず、写真手前の「光センサ」が、お母さんが廊下の電気をつけたことを感じ取り、写真の奥にあるブザーが「ピッ、ピッ、ピッ……」と鳴り始めます
次に、ロボットの前をお母さんが通ると、写真中央にあるセンサ「フォトリフレクタ」が反応。ブザーは「ピピピピピピ!!」と激しく鳴り、もうすぐお母さんが部屋に入ってくるよ!と知らせてくれます。

「これって、子どもの夢ですよね(笑)」と語るのは、株式会社ユーキャン・教育事業部・マーケティング部係長の松本真由美さん。小学生のお子さん2人を育てるワーキングマザーです。
子どもの思考回路は「身近なもの」から広がる
--お母さん検知マシン、何というか、カワイイですね(笑)そうですね(笑)、他にも『自動ドア』や『ねらいうちゲーム』『ピカピカLEDマシン』など、完成するロボットがとても身近なのが、この教材の特長です。正解のイメージを思い浮かべながら取り組めるのが、『アーテックロボ』の良さだと思います。
--では、教材の対象は、初めてプログラミングに触れる子ども、ということになりますか?
はい、初心者向け教材です。だいたい10歳くらいからは、お子さん1人で取り組める程度の難易度になっていますが、親御さんや先生など、これから子どものプログラミング教育に関わることになる大人が「どんなものか」を知るためにやるのも良いと思っています。
私はプログラミング未経験の文系人間なのですが、まずは書いてある通りに進めるだけで、ちゃんと完成しました(笑)。自宅で試作をしていたら小学四年生の子どもが興味を持ったのでやらせてみたのですが……子どもの吸収力ってすごいですね。
自分でどんどん進めて、その後「あれって、こういう仕組みだったんだ!」という思考が広がっていました。ああいう姿は、親心にも嬉しいですね。
--子どもの成長が見える瞬間って嬉しいですよね!
子どもの思考回路って、身近なものへの理解からスタートして、そこから広がっていくものだと思います。
--お客さんの反応はどうでしょう?
2019年1月から始まったばかりですが、全国から数十件のお申込みをいただいています。
今のところ、お申込みされる方は30代後半から40代が多いです。小学生のお子さんを育てている年代ですよね。小学校での授業必修化を意識しているのだと思います。
--プログラミング教室の少ない地方からの申込みが多いのでしょうか?
そうとは限らない、という印象です。小学生くらいのお子さんだと、教室って本当に自宅のすぐ近くとかでないと、結局親の送り迎えが必要になったりして通いにくいですよね。
それに、通塾の教室は他の習い事と比べて月謝が高めで、「試しに行ってみよう」で入会するには、ちょっとハードルが高いです。
そのようにして、「何かはしたいと思っているのだけれど……」と迷っている方が多いのかもしれません。本当に、全国からまんべんなくお申込みをいただいております。
実際、どう勉強して、どんなことができるようになるのか?

--具体的に、この教材でどんなことができるようになりますか?
この教材で作れるのは『自動ドア』『リモコン式ねらいうちゲーム』『ピカピカLEDマシン』『お母さん検知マシン』『床拭きお掃除ロボット』の5種類です。
--名前がわかりやすいですね(笑)この教材以外に必要なものはあるでしょうか?
プログラミングをするためのパソコンと、プログラミングソフトをダウンロードするときにインターネット環境が必要です。
--パソコンのセットアップでつまづく、ということはなさそうでしょうか……
もともと「初めての方向け」の教材なので、テキストにはロボットを作り始める前の準備段階について、かなりページを割いて解説されています。
テキストもちょっと厚めなのは、パソコンの準備やプログラミング言語『Scratch(スクラッチ)』の使い方なども丁寧に書かれているためです。読んでみると、とても分かりやすいですよ。

--この本は、ユーキャンさんオリジナルのものですか?
基礎テキストと基本パーツは市販されているものと同じです。ユーキャンの教材では、アーテックと共同開発したオリジナルパーツで、その一歩先の学びができる「チャレンジミッション集」が追加されています。
--チャレンジミッション集ではどのようなことができるようになるのでしょうか?
基礎テキストは、本を読みながら進めるだけで何となくでも完成させられてしまいますが、チャレンジミッション集では、基礎テキストで完成させたロボットに追加パーツを付け足したり、設定を変えたりして、より深い理解や発展的な学習を促します。
「違った動きをしたこと」や「動かなくなってしまったこと」を体験して、うまくいかない理由を考え、解決に導く「問題解決能力」を育てます。
--難しそうですね……
一般的な通塾教室での1回分くらいで課題をクリアできるボリュームに区切ってありますよ。
基本のロボットを作るのに1回、チャレンジミッションがロボットごとに2つあるので、ロボット1種類あたり3回分。ロボットが5種類なので、1週間に1つとしてだいたい15週くらいで全て完成させられるイメージです。
--たしかに、「作って終わり」の先があるのは嬉しいですね
うまく動くことばかりではないですし、そんなときも、子どもには自分で考えられるようになってほしいですからね。
気構えず、一緒に楽しんでいただけたら
--現在の手応えと今後の見通しについて伺えますか?子育て世代からのお申込みが多く、興味を持っている人の多さは感じています。2020年に向けて、今年1年でさらに周知が広がると思っています。
--最後に、保護者の方へのメッセージをお願いします
2020年度から小学校でプログラミングが必修化され、続けて中学でも高校でも取り入れられていきます。
我々親世代にとっては、プログラミングは「好きな人ができる」特別なものでしたが、いまの子どもたちは必ず通る道になるでしょう。その隔たりは大きいものだと思っています。
「子どもにはできるようになってもらいたいけれど、自分は全くわからない」という方も多いと思います。親御さんもお子さんも、まったく初心者という方にぜひ手にとっていただきたい教材です。
ゼロからはじめても、ロボットづくりを通して「プログラミング」を理解できる内容になっています。個人的な差はあると思いますが、10歳くらいからは1人で学習を進められる難易度ですし、教材の内容もとても分かりやすいので、親御さんも気構えることなく、一緒に楽しんでいただければと思います。
--ありがとうございました!
おわりに
雑談のなかで、松本さんは「これからは、プログラミング的思考が『国語力』のように、全ての教科に必要な基礎能力になっていくのではないか」と話されていました。授業必修化といっても、「プログラミング」という教科があたらしく作られるわけではありません。
現在の教科学習のなかに、プログラミング的思考についての学習が盛り込まれることになるのだそう。これは、数学や理科において、問題の文章をきちんと読んで正しく理解する「長文読解」の能力が求められるのと同じではないでしょうか。
必修化まであと1年。学校や家庭の模索が続くなか、様々なタイプの教材が出てきています。ユーキャンのロボットプログラミング教材は、お子さんはもちろん、大人にとっても心強い「はじめの一歩」になりうると感じました。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
(インタビュー)iRobot|ルンバみたいなプログラミング学習ロボット「Root」でSTEM教育を実践
ルンバの開発元であるiRobot(アイロボット)が、プログラミング学習ロボットを開発しているのをご存知ですか? その名も「Root(ルート)」。てのひらサイズであるものの、非常に多機...
2025.05.30|大橋礼
-
在宅期間中におすすめ!プログラミング教育必修化!〝模擬授業〟をママライターが体験レポート!
コロナウイルスにより小中高等学校の休校が続いている地域もあります。本来であれば4月より新学期がスタートし、必修化となったプログラミング教育の授業が行われるはずでした。 保護者の皆...
2025.05.26|大橋礼
-
(インタビュー)「toio™(トイオ)」が教室にやってくる!SIE×アフレルの新カリキュラムスタート
ソニー・インタラクティブエンタテインメントの大人気ロボットトイ「toio™(トイオ)」がついにプログラミング教材・カリキュラムとしてデビューします。この記事では「toio」開発者である...
2025.07.31|夏野かおる
-
プログラミング教育必修化の認知度は8割超! プログラミング教育ポータルサービス「コエテコbyGMO」 『プログラミ...
小学生向けプログラミング・ロボット教室の掲載教室数国内No.1のプログラミング教育ポータルサービス「コエテコ byGMO(以下、コエテコ)」は、2020年4月からの「プログラミング教育...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
「プログラミング教育に関する保護者の意識調査」を実施 ~「必修化」の認知度は8割と半年で20ポイント上昇も、 「...
小学生向けのプログラミング・ロボット教室情報掲載数が業界No.1のプログラミング教育ポータルサイト「コエテコ byGMO(以下、コエテコ)」は、2020年の小学校での「プログラミング教...
2025.06.03|コエテコ byGMO 編集部