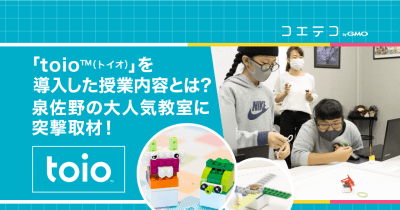(インタビュー)「toio™(トイオ)」が教室にやってくる!SIE×アフレルの新カリキュラムスタート

-
今回お話を伺った方
-
「toio」開発者
田中 章愛氏筑波大学大学院修了後、2006年ソニー入社。スタンフォード大学訪問研究員(2013 - 14)を経て、ロボティクス研究や社内起業支援プログラム「SAP(現SSAP)」の起案・運営に携わる。2016年より有志で立ち上げたtoio(トイオ)プロジェクト責任者として子どもの創造・STEAM教育ロボット商品化・事業化を実現、「Business Insider BEYOND MILLENNIALS 2019」受賞。『Unity Learning Materials』『SWITCH SCIENCE』等、本分野で複数のメディアインタビュー・教育イベント登壇歴あり。クラフトとテクノロジーの融合で新たな遊びと学びの体験を提供するプロダクトリーダー。
-
カリキュラムを開発するのは株式会社アフレルと株式会社内田洋行で、全国の小学校や民間スクールに向けて順次提供していくとのことです。
この記事では「toio」開発者である田中 章愛(たなか・あきちか)さんとアフレル社長・小林 靖英(こばやし・やすひで)さんに独占インタビュー!
「エンジニアとして、ピュアに面白いものを追求しました」(田中)
「ビジネスっていうか、面白いから一緒にやってるんだよね」(小林)
「面白い!」をトコトン重視する、お二人の描く未来についてお伺いしました。

(左)「toio」開発者 田中 章愛さん
(右)株式会社アフレル 代表取締役社長 小林 靖英さん
「toio」とは?

「toio」はソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下、SIE)開発のロボットトイ。豆腐のような形をした32mm角のロボット2台をあやつりながらあそんだり、プログラミングを楽しんだりできるエンタテインメント製品です。

「toio™ コア キューブ」はレゴ® ブロックと接続可能。思い思いの作品を作り上げられるのが魅⼒
SIEといえば「プレイステーション®︎」で有名なプラットフォーム開発からゲーム制作までを行う会社であるだけに、完成度の高い専用タイトルは各種イベントでも大人気。体験スペースには毎回行列ができる盛り上がりを見せています。

現在販売されている専用タイトルは以下の5種です。
- トイオ・コレクション
- ~みんなでもっと楽しめる~ トイオ・コレクション 拡張パック
- 工作生物 ゲズンロイド
- GoGo ロボットプログラミング ~ロジーボのひみつ~
- トイオ・ドライブ
今や子どもから大人、学校から研究所など幅広い様々な分野で、手のひらサイズのロボットを御活用いただいています。楽しみ方、使われ方自由自在。toioは多様な可能性のプラットフォームです。

https://toio.io/ >
プログラミング必修化を前に「まずはおもちゃから」というご家庭も多いのでは。今回はソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)さんにお伺いし、期待のロボットおもちゃ「toio(トイオ)」についてインタビューしました。


2025/06/24

(2020年11月追記)実際に「toio」を導入した教室を取材しました!
コエテコでは、いち早く「toio」を教室カリキュラムとして導入した大阪・泉佐野のプログラミング教室「Soft Garden」さんを突撃取材!- 教室オーナーから見た「toio」の魅力とは?
- 実際の授業内容は?
- 子ども達のリアクション
大阪弁の飛び交う、大盛り上がりの教室の様子をぜひご覧ください。
コロンと四角いフォルムでおなじみの「toio™(トイオ)」は、楽しくプログラミングに触れられるのが魅力のロボットトイです。今回、コエテコはtoioを授業に導入された教室に突撃取材!大阪・泉佐野のプログラミング教室「Soft Garden(ソフトガーデン)」さんを訪問しました。
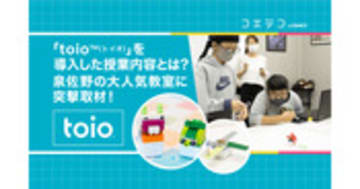

2025/05/26

「楽しい」ファーストの製品として
—本日はよろしくお願いいたします。まずは田中さんにお伺いしますが、これまでコンシューマー(一般ユーザー)向けに展開していた「toio」を全国の学校や民間スクールに向けて展開すると決めたきっかけは何だったのでしょうか。
田中:
「toio」ははじめ、教材としてではなく、遊ぶ中でひらめきや作る楽しみを感じていただくエンタテインメント製品として開発しました。
「toio」の「つくって、あそんで、ひらめいて」というキャッチコピーにも「楽しい」に重きを置く私たちの姿勢が表現されています。

ところが発売してみると、「toio」の「楽しい」コンセプトが教材にも適していると。ぜひ授業に取り入れたいとおっしゃる学校や民間スクールが増えてきました。
ユーザーの皆様からも「どこか、『toio』で学べる教室はないですか?」といった声をいただくようになっておりましたので、このたびアフレル様のような専門家のお力を借りてカリキュラム化することにいたしました。
アフレル様は教材を開発・提供するだけでなくロボコンも多数運営されており、お子さまの気持ちやエンジニアの気持ちを大変よく理解してくださるんですよ。

アフレル スプリングカップは毎年盛況となる大人気ロボコンイベント。(写真:アフレル提供)
子どもの学びを技術でアシスト
—「楽しい」コンセプト以外にはどのような点が教材として評価されているのでしょうか。「toio」はお子さまが戸惑わずにパッと使え、トライアンドエラーをストレスなく繰り返せるようにこだわっており、その点もご好評をいただいています。
具体的には「絶対位置検出」の技術が分かりやすいですね。
これは、分かりやすくいうと「ロボットが自分の位置を知る技術」です。地味な技術に聞こえますが、これがけっこうすごいんです。
たとえば、「toio」専用タイトルに「GoGo ロボットプログラミング ~ロジーボのひみつ~」という、絵本上でロボットを動かしながらプログラミング的思考を身につけるものがあります。
各ページにはコースが設定されており、「スタート」の位置にロボットを置いてプログラムを実行するのですが、お子さまがロボットを置く位置を間違えても、「toio」の場合はロボットが自動で「スタート」まで行ってくれるんです。

「GoGo ロボットプログラミング ~ロジーボのひみつ~」は絵本仕立てでプログラミング的思考が学べる人気タイトル。

小さなお子さまや、プログラミング知識のない保護者でもとっつきやすいのが魅力だ
私はロボコン(ロボットコンテスト)の審査員を務めることがあります。ロボコンだと「ロボットを最初にセッティングする位置が間違っているせいでコースアウト」なんてトラブルが起こるのですが、それは人間の設置ミスであって、本当に動かしたかったプログラム自体には関係ないですよね。
もちろん、現実のプログラムではこうしたヒューマンエラーへの対処も必要ですが、いきなりそこまでの分析や切り分けが求められるのはハードルが高すぎます。そのため、「toio」のセッティングミスに関してはコンピューターが絶対位置を使ってきちんと切り分けられるようにアシストしてくれます。
このように「toio」の絶対位置検出技術があれば、トラブルを極力なくすことができます。それにより、お子さまがプログラミングの内容だけに集中できるようにしたのです。

—ロボットでプログラミングを学ぼうとすると、セッティングの位置もそうですし、ロボット自体の性能や個体差、電池の残量……と色々な要素を考慮しなければいけないと聞いたことがあります。
低学年くらいの子だと、そうしたノイズがちょっとめんどうに感じるかもしれませんね。
「同じプログラムを書いたら常に同じ動きをする」のはプログラミング教育においてとても重要です。デバッグに集中できるのもそうですし、他の人が作ったプログラムを手元で再現したり改造したりすることもできます。
ロボットプログラミングのキットにも色々な種類がありますが、「toio」では手軽さと再現性に非常にこだわっています。これらはプログラミングに慣れ親しむだけでなく、試行錯誤と本質的理解にもつながる重要な要素だと考えているんです。
とはいえ、難しいことを考えすぎてお子さまがとっつきにくくなってしまってはいけませんので、楽しく手軽にプログラミングやトライアンドエラーを楽しんでくれるよう、そっと技術でアシストしています。

こちらは田中さんのお子さんの作品。「『toio』はお話を作るのが好きな子にも受け入れてもらいやすいロボットです。どうして3月にサンタさんなのかは分かりませんが、子どもなりのストーリーがあるみたいです」(田中さん談)
予想を超えて広がるコミュニティ
—「toio」の発売から1周年を迎え、いま感じておられることはありますか。教材として評価されたのもそうですし、大人の方にも楽しんでいただけているのが嬉しいサプライズでした。
すでにユーザーの方々の手によって、JavaScriptで動かしたりRaspberryPiとつないだり、大学の研究やメディアアート作品に取り入れてくださったりと予想を超えた受け入れられ方をしています。
「toio」の技術仕様はかなりオープンにしています。そのおかげで、現在のような予想を超えたコミュニティにつながったのではないかと感じています。
田中さんの第一印象は「変な人だな」
—次に、アフレル小林社長にお聞きします。今回、SIEと協業されるきっかけは何だったのでしょうか。
小林:
田中さんと初めにお会いしたのは3年くらい前でしょうか。ブロック好きのエンジニアの集まりでお見かけしたのが初めですね。正直なところ、第一印象は「ちょっと変な人だな」でした(笑)。とてもピュアな方でね。

その後、ビジネス上でもご縁があって今回の協業につながりました。実は「コエテコ」の事業者セミナーがきっかけだったんですよ。
2019年6月17日(月)、コエテコ×船井総研セミナー「『プログラミング教育市場』の現状と展望」が行われました。会場ではWeb非公開のトピックレポートが配布され、幅広い業界から100名近い参加者が集まりました。


2025/05/26

先ほど田中さんもおっしゃっていたように、とにかく「toio」は「楽しい」製品です。なんだか気になる、触りたくなるようなパッケージングが巧みで、クリエイティビティを刺激する工夫にあふれているでしょう。これを全国のお子さまに提供できたら、きっと素敵な世の中につながると確信できたんです。
令和は「楽しい」が牽引する
—「toio」の魅力について、より詳しく教えてください。小林:
弊社はロボコンを多数運営していますが、これまでのプログラミングは制御的な側面が強かったのではないかと思います。
言い換えれば「いかにうまくロボットを動かすか」に主眼を置いていたけれども、これからの時代を考えるとそれだけでは物足りない。
面白いものを生み出すにはSTEAM教育の「A」にあたる能力、つまり創造性が不可欠になると感じていました。
私が子ども時代を過ごした昭和といえば『巨人の星』の世界。主人公の星飛雄馬がバチーンとビンタされてね。つらいことが美徳という風潮があったように思います。
でも、令和の時代に根性論は要りません。「楽しい!」がイノベーションを牽引していくんです。「toio」はそんな新時代に適した教材と感じます。

「toio」をペン代わりにして絵を描いたり、音楽を奏でたり。子どもの「楽しい!」を引き出す仕掛けがたくさん用意されている
モノに恵まれた社会を次のステージへ
—アフレルといえばレゴ エデュケーションの製品を取り扱っておられたり、ロボコンを運営されたりとプログラミング教育業界では大きな存在感のある会社ですね。御社がロボット教育にかける思いについてお伺いできますか。
小林:
またもや自分の話をして恐縮ですが、私の小・中学生時代、つまり4、50年前にはとにかく物がありませんでした。何かを作るにも粗大ゴミからパーツを調達するしかなかった。
平成になって生活のレベルがぐんと上がり、世の中が「きちん」としてきた。それ自体は喜ばしいことですが、一方で何かを作り出す必要性は徐々に薄れてきたように感じます。
だからといって「生活のレベルを戻そう」と言っているわけではないんです。誰だって貧しい時代に戻りたくはないですから。
そうではなくて、今のレベルの上に、さらに面白いものを作り上げるにはどうしたらいいか?弊社はそれを考え続けています。

ロボコンを運営するのもその一環ですね。ロボコンでは、普段の生活とはちょっと離れたところでモノ作りに打ち込みます。すると、必ず足りないものが出てくる。大人なら時間、子どもならお金や技術でしょうか。
それらを上手にやりくりしながら面白いものを作っていく、その過程を大切にしたいんです。
学校・民間の両輪で子どもの未来を拓きたい
—4月からは小学校でプログラミング教育が必修化しますね。その一方で、民間プログラミング教育の役割はどこにあるとお考えになりますか。小林:
誤解を恐れずに言えば、学校の授業は制約が多いんですね。全員が広くあまねく理解できるレベルの内容に……となると、物足りない側面が出てくる。学校は基礎学力を育てる場ですから、これは仕方のないことです。
そうはいっても、中には協調性の輪から外れてどこまでも興味・関心を深めたい子もいるでしょう。民間教育の役割はここにある。「面白い!」とのめり込みたい子に活躍の場を提供することが我々の使命と考えています。
民間教育の事業者様とお話をしますと、「学校ではできない部分をやるぞ」と強い自負を持っておられ、我々も勇気づけられます。
指導のスペシャリストであるスクール様、教材を提供する我々、そして「toio」の魅力あるコンテンツ。これらが一体となって子ども達に「めっちゃ面白い環境」を提供できればなと考えています。
田中:
協調性の輪から外れてどこまでも興味・関心を深めたい……というのは、自分自身覚えがあります。私は小学2年生の頃から「夏休みの工作」としてロボットを作り続けてきたんですよ。
私にとってロボットは自分の分身。ロボットが動くと、まるで自分の能力が拡張されたかのような新鮮な喜びがありました。
こうした体験や感覚は原体験として今後の社会に役立つというのもあるし、純粋に楽しい(笑)。
だから「toio」ではロボットをなるべく簡単に動かせるようにして、多くの子ども達にこの楽しみを味わってもらえるよう努めました。
ポチッと押すだけでとりあえず何か動いてくれる。それを見て「こんなもんか」「意外と難しくないな」と思ってもらい、抵抗感なく受け入れてもらえたら嬉しいですね。
「作って試す」を怖がらないで
—お話を伺っていて、お二人とも純粋にものづくりがお好きなんだなというのが伝わってきました。ビジネスファーストな雰囲気ではないというか。そんなお二人が考える、未来の子ども達に身につけて欲しいスキルは何でしょうか。
田中:
私が未来を考えるとき、ある大学の先生がおっしゃったことがずっと心に残っています。
いわく、「これからの時代は不確実で、何が起きるかわからない。やってみないと分からないことが増えるだろう。どんどん作って試す力がより大切になるのではないか」と。
人の心はどんどん変わり、どんなものが愛されるか予測しづらい時代になってきました。だからこそ、「作って試す」を怖がらない姿勢が必要になるのではないかと。
小林:
「どんな人材が求められるか」も同じですよね。
今回のカリキュラムもそうですが、成長されたお子さまが「どんな時代が来ても大丈夫!」とどっしり構えられるよう支援するのが我々の役割かなと感じています。
田中:
そもそも、「toio」自体が「受けるかどうか分からなかった」一例です(笑)。
幸いにも「toio」は多くの方から支持していただけましたが、今後の製品開発は「しっかり作り込んでから出す」のではなく「出してみて、お客様と共に作り上げていく」スタイルへシフトしていくでしょう。
自分自身にも言えることですが、フットワークはなるべく軽く、試すことを怖がらずにどんどん人に見せていく姿勢が重要になってきます。

ものづくりを愛するお二人。インタビュー中も、ロボットの魅力を情熱的に語り合っておられた
小林:
私たちができるのは環境を提供することだけです。子ども達に「そうきたか!」と驚かされたい。
大人が教材を作ろうとすると、えてして「説明」しようとしますよね。でもそれは違うかなと思っていて。
「何これ!」「面白そう!」と思えば子どもはすぐにやりたがる。説明はそのあとで良いんじゃないかと。
田中:
同意見です。個人的には、仕事に必要なスキルとしてのプログラミングを教えるのはお子さまがかなり成長されたあとでも良いかなと思っています。ある程度の肌感覚があり、食わず嫌いで“触れた経験が皆無”でなければスキルは後からでも習得できます。
だから、まずは興味を持ってもらう。動いて楽しい!という感覚を持ってもらう。
少なくとも、プログラミングやロボットを「嫌いじゃない」レベルにできれば成功かなと。
小林:
ええ。そのために私たちも頑張りますし、教育のプロフェッショナルである塾やスクールの先生方もきっと、お子さまの興味をどんどん引き出してくださるのではないかと考えております。私自身、今後がとても楽しみです。

読者へのメッセージ
—本日はありがとうございました。最後に「コエテコ」読者へのメッセージをお願いいたします。田中:
私も一人の親として、自分の子どもには「食わず嫌いしない子」に育って欲しいなという思いがあります。何でもやってみることを怖がらず、広く技術やアートに親しんで欲しいなと。
様々な世界に触れる経験は、各種専門家へのリスペクトにもつながります。「すごいな」「大変だっただろうな」と相手を理解し、尊重する素地になるんです。
これまでの社会は「文系」「理系」が分かれすぎていて、お互いにどんなことをしているのか分かりづらい状況でした。でも、社会に出てみると自分ひとりで出来ることはそう多くありません。
お互いをリスペクトしあいながら、すごい人達とすごいものを作り上げて欲しい。「toio」をきっかけに一歩踏み出せる人が増えたら嬉しいです。
小林:
我々が目指すのは、ロボットや技術を特別なものと思わず、仲良く暮らす社会です。
これからの時代、ロボットは「当たり前に存在するもの」へ変わっていくでしょう。スマートスピーカーなど、すでに浸透しつつある製品も増えてきていますよね。
ロボットの存在を当たり前にするためには、「プログラミングを学ぶんだ」と身構えないくらいがちょうどいい。
「toio」は「知らない間にプログラミングを学んでいる」スタイルに適した製品です。
「toio」での学びを原体験とし、もっとロボットと自然に付き合えて、もっとうまく活用できる未来をお子さま達が作り上げてくれるんじゃないか……我々はそう願っています。
—ありがとうございました。

「toio」導入のご相談はこちら

アフレルが主催する「toio」コース開設セミナーは毎月1回、オンラインにて開催中!
参加申し込みはこちらのボタンよりどうぞ。
また、もしも日程が合わない場合は個別相談会も受付中とのこと。
個別相談会をご希望の方はこちらのボタンよりお申し込みください。
その他、ビジネス利用に関するお問い合わせは「toio」の教育関係者向け公式ページからお問い合わせください。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
「作ったものが主人公に」SIEのロボットおもちゃtoio(トイオ)
プログラミング必修化を前に「まずはおもちゃから」というご家庭も多いのでは。今回はソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)さんにお伺いし、期待のロボットおもちゃ「toio(ト...
2025.06.24|夏野かおる
-
(教室取材)「toio™(トイオ)」を導入した授業内容とは?|泉佐野の大人気教室に突撃取材!低年齢・女の子の生徒にも
コロンと四角いフォルムでおなじみの「toio™(トイオ)」は、楽しくプログラミングに触れられるのが魅力のロボットトイです。今回、コエテコはtoioを授業に導入された教室に突撃取材!大阪...
2025.05.26|夏野かおる
-
KOOVはプログラミング教育に対するメッセージ ― ソニー・グローバルエデュケーション代表 礒津政明
男女ともに人気があり、大手塾への導入も進むブロックプログラミング教材「KOOV(クーブ)」。今回は開発/運営元である株式会社ソニー・グローバルエデュケーション代表取締役社長 礒津政明氏...
2025.07.31|コエテコ byGMO 編集部
-
ITロボット塾 総合IT力育成教育教室授業をのぞいて見ました|静岡県浜松市
小学校2年生から高校生を対象としたITロボット塾。ロボットプログラミング講座の開発経緯やカリキュラムの特徴について、株式会社CAIメディアの代表取締役社長であり株式会社ITロボット塾の...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
(インタビュー)「あるくメカトロウィーゴ」一般販売スタート|人に寄り添い、共に成長するロボットとは|プログラミング...
手のひらサイズの愛嬌あるロボット、「あるくメカトロウィーゴ」。プログラミング学習でも活用でき、着せ替えを楽しむように色を塗ったりカスタマイズして、パーソナルに遊ぶこともできます。この記...
2025.05.30|大橋礼