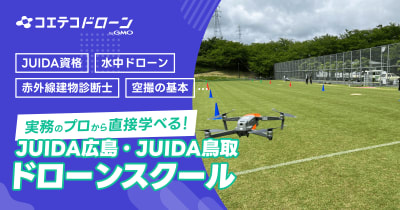SENSYN ROBOTICS ACADEMY|ドローンの現場活用を「定着」させるドローンアカデミー

こうした企業側のニーズを背景に、人材育成を担うドローンスクールには、現場で即戦力たりうるスキルを持つ「実践力」の醸成も求められているのが現状です。
安全管理や法規制への対応、データ活用まで求められる知識は多岐にわたりますが、SENSYN ROBOTICS ACADEMYではドローン導入を「スタート」と位置づけ、現場運用の定着までを支援しています。
今回お話を伺ったのは、株式会社センシンロボティクス エンタープライズ事業 フィールドサービスグループでディレクターを務める河野 健之氏と、同じくフィールドサービスグループに所属し、同グループ内のカスタマーサクセスチームにて、センシンロボティクスアカデミー運用担当を務める吉田 瑚太郎氏です。
指導内容や意識している点など、SENSYN ROBOTICS ACADEMYでの学びについて、お二人に詳しく取材しました。

(左)吉田 瑚太郎氏、(右)河野 健之氏
社会のさまざまな場面で活躍が期待されているドローン。その分野の一つに設備点検が挙げられます。労働人口の減少やインフラ設備の老朽化などの社会的課題に対して、ドローンをはじめとするロボット技術はどのように活かされるのでしょうか。センシンロボティクス代表・北村卓也氏に、ドローンを用いた設備点検自動化の意義や導入事例、課題感などについてお聞きしました。
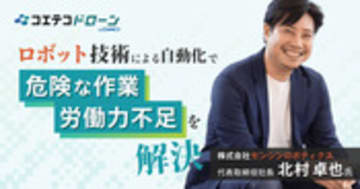

2024/04/01

点検や農業などさまざまな場面での利活用が進むドローン。センシンロボティクスと中部電力パワーグリッドは、ドローンを使った送電設備自動点検技術の共同開発に取り組んでいます。今回は、実際に現場で自動点検の様子を見せてもらい、業務の効率化や安全性の向上にドローンがどのように貢献しているのかをお聞きしました。


2024/08/26

「何を解決したいのか」から始まる教育プログラム
――数々のソリューションで知られるセンシンロボティクスが、自社でドローンスクール「SENSYN ROBOTICS ACADEMY」を立ち上げた背景について教えてください。河野:
当社は基本的にBtoBでビジネスを展開しており、プラント事業者や建設関係、電力施設設備を持つクライアントなど、エンタープライズ向けの事業を行っています。これまでも民間の講習機関として500名を超える方々に講習を提供し、そうした現場での活用を支援してきました。
2年前の法改正で国家資格制度が導入された際、お客様から「国家資格も取得できると嬉しい」というご要望を多くいただいたことで、登録講習機関の申請を行い、スクールを開設することになったのです。

――他社の事例では、ドローン導入後の運用定着に苦労されているとお聞きしますが、その点についてはいかがでしょうか。
河野:
当社の場合、そのようなミスマッチを防ぐべく、クライアントから「ドローンを導入したい」というご相談を受けたとしても、まずは「何を解決したいのか」「どのような業務課題があるのか」をしっかりヒアリングすることから始めています。
そのうえで、課題を解決する手段としてドローンが適切な場合に、当社のサービスを含めて一連の提案をさせていただきますので、「ドローンを入れたものの、うまく活用できない」というお悩みは基本的には発生しません。SENSYN ROBOTICS ACADEMYでのパイロット育成もまた、お客様が確実に課題を解決するための手段という位置付けです。
――確実に運用していくために、必要なソリューションを一気通貫で提供するイメージなのですね。その分、スクールで育成するパイロットには、高い実践力が求められそうですね。
吉田:
その通りです。たとえば当社がよく携わるプラント設備の撮影では、操縦者と点検担当者で求めているものが異なることがあります。配管のフランジ(接合部分)の撮影では、上からの角度で十分なのか、それとも下から見上げる角度が必要なのか、担当者によって要望が異なります。
この要望に応えるには、単純にルートを設計して撮影するだけではなく、現場のパイロットと画像確認者の間で十分な意思疎通を図るなど、点検対象の適切な撮影方法をその都度考えなければなりません。スクールではこうした実践的なポイントも踏まえ、丁寧に指導しています。
河野:
プラントや建設現場は常に危険と隣り合わせです。どの位置から飛行させるのが最も安全か、人員をどのように配置すべきかという安全面での知見も非常に重要です。
当社は長年の経験から、場所ごとのリスク対策やリスクマネジメントのノウハウを蓄積しています。これらを具体的な数値やガイドラインとして提供できることも、スクールの強みとなっています。
データ活用からAI解析まで、現場ニーズを満たす総合的な指導を展開
――スクールの受講者としては、どのような方を想定されていますか。吉田:
基本的には既存の契約顧客や、業務課題の解決にドローンが必要だと判断されたお客様を対象としています。実際に資料請求や問い合わせをいただくのも、ほとんどが企業の担当窓口の方々です。
年齢層については、問い合わせは上席の方からいただくことが多いものの、実際の受講者は比較的若手の方が中心です。既存の民間資格講習をすでに受講されている企業様も多く、若い方の方が、操作に適性があるという理解が浸透しているようです。
――スクールでは具体的に、どのようなコース内容を提供されているのでしょうか。
吉田:
現在は民間資格講習に加えて、国家資格の講習を提供しています。国家資格については、初学者向けと経験者向け、また目視外飛行と夜間飛行の限定変更に対応しています。

吉田:
25kg以上の機体については、現時点ではお客様からのニーズが少ないため対象としていません。さらにオリジナルコースとして、危険物のある区域での飛行方法や自動航行時の注意点など、お客様の具体的な課題やニーズに応じたカスタマイズ型の講習も用意しています。
基本的に受講は3名以上のグループで行われることが多く、会社単位でまとまって受講されるケースが一般的です。
また、ドローンの操作講習を受けただけでは、現場で飛ばして画像や動画などのデータを取得するといった「実践」は難しいので、スクールでは基本的なドローン操作に加えて、機体の組み立て方やカメラ設定など目的のデータを確実に取得するための総合的なノウハウを提供しています。
――ドローンで取得したデータの活用について、どのような指導をされていますか。
吉田:
屋内外を問わず、自動飛行でのデータ取得や3Dモデル化、そしてAI解析による錆の検出など、省人化に向けた指導を行っています。データの取得から3Dモデルの作成、その後の活用方法まで、一貫した指導を行えるのも当校の特色です。

河野:
具体的には、当社独自のアプリケーションスイート*を活用した指導を行っています。3Dモデルの生成は「SENSYN CORE Mapper」で行い、データの管理は「SENSYN CORE Datastore」で時間軸や場所軸での管理を実現するという形です。
これらのソフトにはAIによる分析アルゴリズムが組み込まれており、お客様のニーズに応じてひびの検出や錆の検出など、さまざまな分析が可能です。すべてが1つのラインで完結する形になっています。
また、お客様のご要望によっては、「ドローンを飛ばすことはできるので、アプリの使い方を教えてほしい」というニーズにも対応しています。自社アプリを活用することで、卒業後もクライアントとつながれるという関係性の構築にもつながっています。
現場経験豊富な講師陣が支える、「安全意識&技術力」を実現する指導
――指導に当たって、特に重視されている点を教えてください。
吉田:
受講者の多くは企業の看板を背負って参加される方々で、現場での安全意識が高い方が多いです。そのため、講習中も恥ずかしがらずに大きな声で確認を行うことを推奨しています。

また単に「これはしてはいけない」と伝えるだけでなく、「なぜそれが危険なのか」という理由まで丁寧に説明することを心がけています。
河野:
せっかく導入したドローンへの苦手意識を持たれないよう、安全に対する意識を徹底的に指導することも重要です。安全航行を実現するには法律面の知識も不可欠なので、航空法などの法規制についても詳しく解説しています。
――講師陣のバックグラウンドについて教えてください。
吉田:
講師を務めるのは基本的に当社の社員で、さまざまなプラントや風力発電の現場などで年間200日以上ドローンを操縦しているエンジニアたちです。
大手ドローンメーカーの元社員や大手団体のスクール元講師、プロのドローンレーサーなど、多彩な経験を持つメンバーが揃っています。
河野:
講師陣は大きく2つの特徴を持っています。1つは開発段階から現場で飛行させている特殊な操縦スキルを持つグループ、もう1つはお客様に最も近い位置で課題を理解しているCS部門のグループです。
この2視点を組み合わせることで、高度な技術指導と最新の現場情報に基づいたリアルタイムな課題解決の両方を提供できています。この「現場力」こそが、他スクールとの最大の違いだと自負しています。
――スクールの保有機材も豊富だそうですが、これも強みの一つでしょうか。
河野:
はい。保有機材を幅広く展開している理由は、お客様の選択をサポートするためです。
たとえば自動車を選ぶときは、さまざまなメーカーの車体を比較検討しますよね。それと同様に、ドローンも多様な選択肢から目的に合ったものを選べる環境を提供したいと考えています。
各メーカーの機体にはそれぞれ特徴があり、用途に応じた適材適所がありますが、最近特に注目を集めているのがDJI Dock2です。人気の背景には、人員を最小限に抑えながら長距離の場所を定期的に点検したいというニーズの高まりがあります。当社でもDJI Dock2を活用するための資格取得から運用方法まで、包括的なサポートを提供しています。
ドローン業務を確実に定着させるなら、SENSYN ROBOTICS ACADEMYへ
――最後に、今後の展望についてお聞かせください。吉田:
ドローンの活用においては自動化が進んでいますが、緊急時には人間の手による対応が必要です。そのため、現場での安全性確保がますます重要になってくると考えています。
今後は広大なエリアをカバーできる効率的な運用はもちろん、有事の際は人が対応するという体制づくりを支援していきたいと思います。
ドローンのニーズは今後さらに高まっていくと思いますが、資格を取るだけで終わらせず業務に活用したいという方や、活用法が分からないなどのお悩みを抱えた方はぜひお問い合わせいただきたいですね。

河野:
今回スクールを立ち上げて実感したのは、操縦技術の習得だけでなく、現場の管理や指揮を行う立場の人々への教育も重要だということです。
法規則も含めた安全飛行のための知識や、事業者として適切に運用するための視点など、より高度なレイヤーでのサポートを展開していきたいと考えています。
ドローン活用の出口は経営課題や業務課題の解決であり、導入はあくまでも課題解決の入口にすぎません。入り口と出口の架け橋となれるよう、今後も努めてまいります。
RECOMMEND
この記事を読んだ方へおすすめ-
DSA岐阜校|ドローンで人と人をつなぎ、人間力も育むスクール
岐阜県岐阜市に位置するDSA岐阜校は、DPAライセンス/国家ライセンスを取得できる実力派ドローンスクールです。運営するのは、ドローン運用から機体販売・保守までを幅広く手掛ける株式会社バ...
2024.08.08|夏野かおる
-
ドローン免許スクール|愛媛県で本格的な測量を学べる、産業特化のドローンスクール
橋梁や床下・屋根裏点検など、産業分野に特化した「ドローン免許スクール」を運営しているのが、株式会社イン・トラストです。同社では各種点検や農薬散布なども請け負っており、こうした実践経験を...
2025.01.16|Yuma Nakashima
-
ドローン教習所 北海道モビリティ校:初学者から屋外練習可能!実践的なドローン操縦スキルを習得できる
ドローン教習所 北海道モビリティ校は、北海道モビリティスクール株式会社が運営するドローンスクール。広大な北海道の環境を活かし、初学者でも屋外での実践的な訓練が可能。民間資格や国家資格の...
2025.05.30|中村英里
-
(取材)JUIDA広島・JUIDA鳥取ドローンスクール|講習から販売・導入サポートまで、ドローンの相談をワンストップで!
JUIDA広島・JUIDA鳥取ドローンスクールを運営するハニービーワークスは、機体のカスタマイズや製作、CMや映画の撮影、測量や点検などドローンに関する事業を多角的に展開する企業です。...
2025.05.30|大橋礼