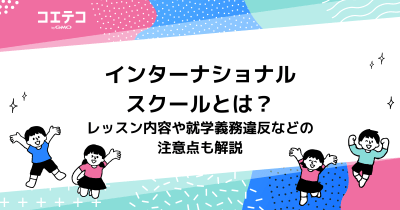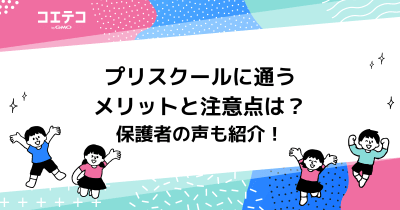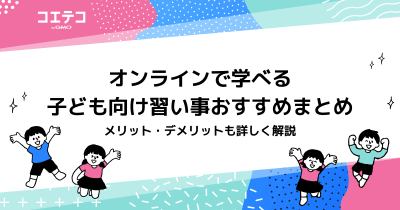インターナショナルスクールに通うメリットと注意点は?保護者や卒業生の声も紹介!
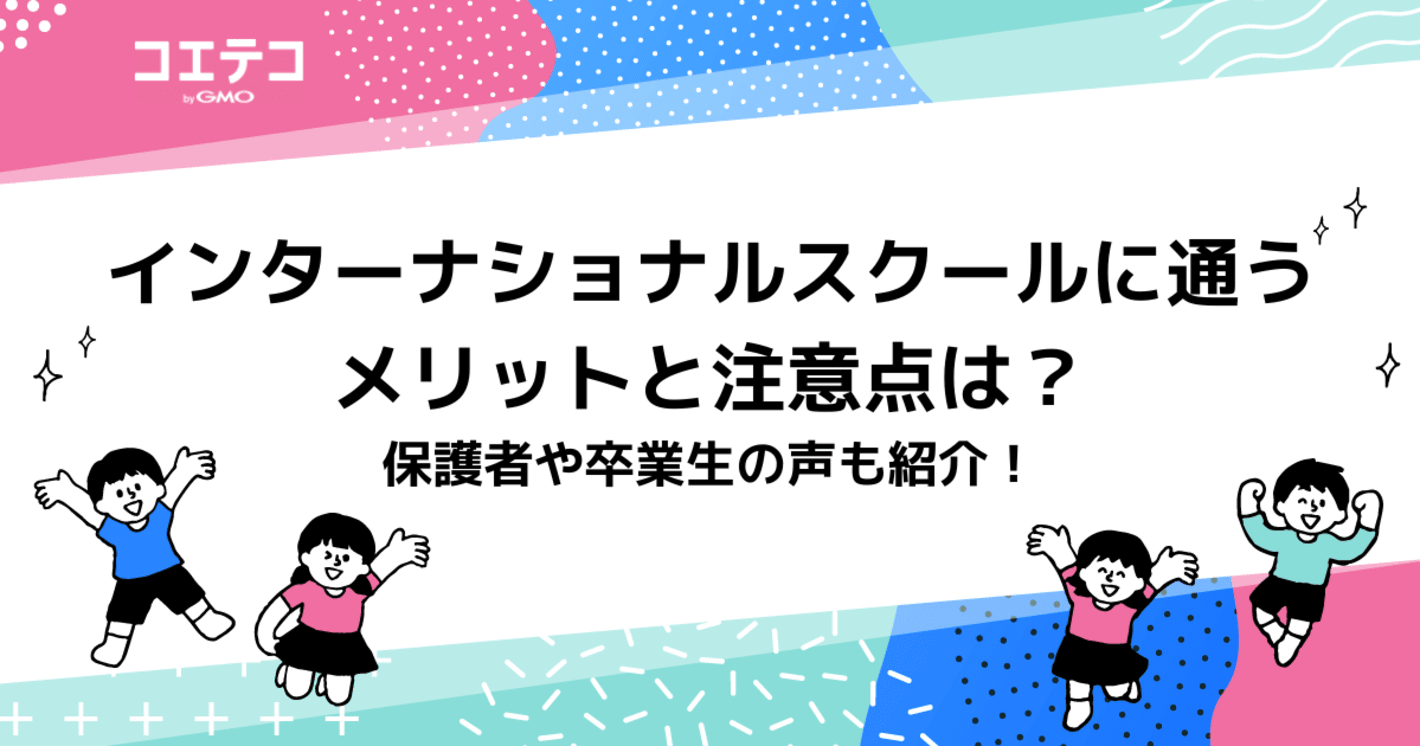
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。

外国人の子どもを対象にした 「インターナショナルスクール」。近年は子どもをバイリンガルに育てたい親も増え、日本人の子どもたちも多く通っています。スクールに通うと、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。インターナショナルスクールに通う子どもたちの進学サポートをこれまで300件以上してきた国際教育評論家・まなぼん(本名:村田学)に解説してもらいました。
<メリット>
1.高い語学力がつくので海外進学しやすい
2.多文化に触れられる
3.探究型の思考力が育つ
4.ICTスキルが身につく
5.プレゼン力がぐんと伸びる
6.音楽、演劇教育が充実
7.一人ひとりに目が行き届く少人数制
<デメリット>
1.授業費が高い
2.就学義務違反になり、中学高校受験の選択肢が狭くなる
3.日本語力が伸びにくい
4.学校行事のサポートや英語の壁…親の負担も大きい
5.地元のつながりが薄くなる
インターナショナルスクールに通って良かった!7つのメリットを紹介

インターナショナルスクールに通うメリットにはどんなことがあげられるのでしょうか。ここでは7つのメリットを、スクールに子どもを実際に通わせた保護者の声とともに紹介します。
①高い語学力がつくので海外進学しやすい
「インターナショナルスクール(小学部)を卒業後、アメリカの中高の全寮制へ。そのままアメリカの大学に進学し、英語力と自立心がついた」(大学3年生の保護者)「中国語やフランス語を週2日学べるので、第二外国語も楽しく取り組んでいる」(小学5年生の保護者)
海外の大学受験は難易度が高いため、幼いころからインターナショナルスクールに入学し、語学力を伸ばす家庭が多いです。インターナショナルスクールの公用語は基本英語です。算数や理科、社会など、すべての科目を英語で学びます。近年、小学校高学年から第二外国語が学べるスクールも増えてきました。
②多文化に触れられる
「ダンスを習っている子どもが、アメリカで開催されたダンスの大会に出場するため、1人で海外へ。『1人で行く』と聞いたときはびっくり。散歩する感覚で海外に行くとは…。英語ができるので海外がより身近に感じるようになった」(小学6年生の保護者)「これまで聞いたことがない学校行事がたくさん。愛校心を育てる『スピリットデー』やパジャマを着て学校で寝泊まりする『パジャマデー』、本の主人公になりきる『キャラクターデー』…準備も大変だけど楽しい!」(小学1年生の保護者)
お互いの文化を楽しめる学校行事はインターナショナルスクールの醍醐味で、毎日留学しているような生活を送ることができます。多国籍で様々なバックグラウンドの子どもたちや教員が集まるからこそ、一人ひとりの「違い」を自然に受け止めることができます。違うことが当たり前の世界。だからこそお互いを尊重し合い、相手を思いやる心が育ちます。
③探究型の思考力が育つ

「大学のゼミのようにテーマを深掘りするのがすごい!様々な角度から考え、論理的に仮説をたてて物事を考えられるようになった」(小学4年生の保護者)
「息子から英語の図鑑を買ってと言われるように。何でも調べることが好きになったのは探究型の学習のおかげだと思う」(小学3年生の保護者)
インターナショナルスクールの多くは、世界基準の国際バカロレアの教育プログラムなどにそった探究型の学びを取り入れています。「地球温暖化」がテーマの場合、植物園に足を運んで温室の植物を観察したり、温暖化の影響で変わる動物の生態系を調べたりします。ペットボトルで飲むのをやめて「マイボトル」を持参するなど、自分たちができることを考えて実際に行動に移します。
④ICTスキルが身につく

「パソコンがただの文房具。『校内SNS』で毎日の授業風景や動画が投稿される。子どもたちが撮影や動画編集の仕方を学ぶ授業もある」(中学1年生の保護者)
「ワードでレポートをつくったり、エクセルで科学の実験データをグラフにしたりしています」(小学5年生の保護者)
タブレットやパソコンを文房具の一つとして活用し、ICTスキルをいかに探究学習の学びに結びつけられるかが重視されています。タブレットで算数のパズルを解くことや3Dプリンターで作品をつくることもあります。街中で「鉄塔」など、三角形の構造物をタブレットで撮影し、角度と強度の関係性について学ぶ授業もあり、ICTの活用も様々です。
⑤プレゼン力がぐんと伸びる

「教室の前に立って、家族などの写真を見せてスピーチをする『Show and Tell』で場数を踏んでいるから物おじせずに話せる」(小学1年生の保護者)
「1年を振り返る発表会で、英語でスラスラ話して堂々と発表する姿に感動。プレゼン後に会場から質問が出ても論理的な根拠を示しながら躊躇せず回答していた」(小学5年生の保護者)
学んだことをパワーポイントなどにまとめてアウトプットする機会も多いです。プレゼン力だけではなく、人の発表を聞く力や、「なんで?」と質問する力も同時に身につけることができます。探究的な学びの深さは、プレゼンにも現れています。
⑥音楽、演劇教育が充実
「3歳からピアノを習っている子どもがいるが、学校行事の度にみんなの前で演奏する機会をスクール側がつくってくれている。スクールではバイオリンも習っている。デジタル音楽を使って作曲することもあり音楽教育が充実」(小学5年生の保護者)「アートも陶芸から油絵まで幅広くある。放課後に作品づくりにのめり込んでいた」(卒業生の保護者)
クリスマスの時期などに演劇の舞台があるスクールが多いです。シェイクスピアなど、文学作品に触れる機会もあります。演劇や音楽、アートなどの学びが充実しているのは、子どもたちの人格形成、感情や抽象的な考えを表現するうえで重要な教育法として位置づけているためです。
⑦一人ひとりに目が行き届く少人数制

「1クラスが16人。先生が子どもの性格や勉強の進み具合などをわかってくれるので、子どもも先生に質問や相談がしやすい」(小学5年生の保護者)
一人ひとりの心身と学びの成長をしっかりサポートする「少人数制」はインターナショナルスクールの大きな特徴です。クラスの担任の先生のほか、アシスタントも授業に入ります。生徒8人に対して先生1人という比率が一般的です。少人数でかつスクールバスもあるので、遠足や課外学習などは年間10回ほどと多め。フットワークがとにかく軽いです。
インターナショナルスクールに通って後悔!? 注意点5つ紹介

これまではインターナショナルスクールの魅力について述べてきましたが、逆にどのようなデメリットがあるのでしょうか。ここでは5つのデメリットをあげました。保護者や卒業生の声とともに紹介します。
①授業費が高い
「授業料は年間200~250万。夏休みも長いのでサマースクールに通うと別途50万かかる。合計年間300万は、高すぎ!」(小学4年生の保護者)「スクールバス代がかかる。はじめは行き帰りの通学にスクールバスを利用していたが、小学3年生からは帰りだけ電車に乗ってバス代を節約していた」(中学2年生の保護者)
外国人向けの学校として開校したインターナショナルスクールの多くは無認可の「私塾」扱いで、自治体などから財政支援を受けていません。そのため、授業料が高くなります。高い授業料を払えなくて途中でスクールを辞めるケースもあります。また、サマースクール以外にも、学校行事が盛りだくさんで、行事は保護者の寄付で成り立っています。
②就学義務違反になり、中学高校受験の選択肢が狭くなる
「何年もかけて準備してきた中学受験で第一志望が急に『インターナショナルスクールの子は志願できません』と受験条件の内容を変え、受験資格がなくなってしまった…子どもにも申し訳なくて、急遽志願校を変えることに。ショックでした」(小学6年生の保護者)日本の小学校や中学校などは学校教育法第一条で定める「一条校」ですが、インターナショナルスクールの多くは「一条校」に該当しません。一条校ではないスクールに通うと就学義務違反になる可能性があります。学校によっては「義務教育を修了していない」と判断され、受験資格を得ることができない場合も。そのため、受験にそなえるため小学5年生のころに公立の小学校に転校する家庭もいます。ただし、インターナショナルスクールに通っていた子どもを受け入れるかは、学校や自治体の判断によりますのでご注意ください。また転校後も、日本語力の問題や友達づくりで馴染めるかなど、苦労することもあります。
こんなことも…
「公立中学校に進学後、校風が違いすぎて子どもが不登校気味になった」という声が保護者から寄せられたことがあります。先輩後輩や担任の先生との距離間や人間関係など、日本独特の「縦社会」に戸惑う子もいます。また授業中に自由に質問をすると「輪を乱している」と注意を受けるなど、集団生活に慣れなくて不登校になるケースもあります。再びインターナショナルスクールに戻ったり、米国通信制の中学校・高校に進学したりする子もいます。
③日本語力が伸びにくい
「日本の公立校に通う同じ学年の子と比べると漢字や文章の力が弱いので、塾に通っています」(小学4年生の保護者)「社会人になって就職してから、ビジネスの場で使う丁寧語がわからず困りました」(30代卒業生)
1週間で日本語の授業は1コマ(45分程度)。書き初めや茶道などの日本文化の授業も取り入れています。日本語の会話を聞く力や話す力は年齢相当に育ちますが、特に読み書きが弱くなる傾向があります。状況に応じた尊敬語、丁寧語、謙譲語の使い方も社会人になって冷や汗をかくことも多いようです。日本語力を伸ばすには、日本語の本を読んだり、かるたでことわざを学んだり、自宅などで学習が必要となります。
④学校行事のサポートや英語の壁…親の負担も大きい
「遠足のサポートや食べ物を持ち寄る『ポットラック』など、保護者が協力する行事が多くて大変」(小学1年生の保護者)「英語がわからない親は子どもが高学年になると宿題のサポートができないので家庭教師を雇うことが多い。その家庭教師にスクールの外国籍の先生たちと連絡のやりとりをしてもらうケースもあります」(小学3年生の保護者)
親がイベントで食べ物を売ったり、イベントであたる景品を自ら準備してスクールに提供したり。親が科学の研究者であれば研究内容について授業で話したり、歌手であれば演奏を披露したりします。また、保護者が英語を話せないと苦労することがあります。担任の先生や保護者らが連絡するツール「校内SNS」のチャットも全て英語です。英語を学ぶため保護者が自ら英会話スクールに通うケースもあります。
⑤地元のつながりが薄くなる
「スクールに通う子は家から離れた場所に暮らす子がほとんど。地元に知り合いもいないので、成人式に出なかった」(20代の卒業生)「夏休みに地元のお祭りに行ったのですが、子どもには地元の友達がいなくて…一人で寂しそうだった」(小学2年生の保護者)
「日本史をスクールで学ぶことがないので、徳川家康や織田信長らの歴史上の人物を知らない子もいる」(中学3年生の保護者)
スクールの場所が自宅から遠く、スクールバスや電車で通学している子どもが多いので、地元の友達ができないという悩みがあります。日本の公立学校では、地元に愛着を持ってもらうために郷土の歴史や文化に触れる学習が多くあると思います。しかし、スクールでは世界史を中心に学ぶため、地元のことを深く学ぶ機会が少なく、結果的につながりが薄くなってしまうこともあります。
まなぼんからのメッセージ
たくさんの卒業生から「インターナショナルスクールで学んで良かった」と聞いてきました。社会人になった卒業生に子どもができたときに、どのような学校を選びますか?と質問すると、全員が「子どもをインターナショナルスクールに通わせたい」と断言。もちろん、通わせるためには授業費など親の負担もありますが、卒業生は日本だけでなく、世界各地で自分が興味を持った分野でたくましく生きて活躍しています。インターナショナルスクールでの経験は、国境を越えた先でも生きていきます。イラスト:カワチハルナ


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
ボーディングスクールとは?人気の理由やメリットやデメリットを解説
全国各地に英語で授業を実施する全寮制のボーディングスクールが増えています。2022年9月には、岩手県にイギリスの名門校「ハロウ校」が開校します。ほかにも愛知県や長野県などでも開校予定で...
2025.10.27|コエテコ教育コラム
-
インターナショナルスクールとは?レッスン内容や注意点も解説
インターナショナルスクールとはどのようなところでしょうか。スクールの選び方はどうしたら良いのでしょうか。入学時の注意点などについてウェブメディア「インターナショナルスクールタイムズ」の...
2023.12.03|コエテコ教育コラム
-
プリスクールに通うメリットと注意点は?保護者の声も紹介!
小学校で外国語活動がはじまり、早期英語教育と探究型学習の人気が高まったことから、英語で幼児教育をする「プリスクール」が保護者の間で人気です。元プリスクール経営者の国際評論家まなぼん(本...
2023.01.28|コエテコ教育コラム
-
オンラインで学べる子ども向け習い事おすすめランキング20選
子ども向けのオンライン受講が可能な習い事が増えてきました。この記事では、オンラインでの学習にどのようなメリットやデメリット、効果などがあり、実際にどのようなスクールがあるのかを紹介しま...
2025.11.17|コエテコ教育コラム
-
子どもに英会話は意味ない?週1で効果はあるのか徹底解説
子どもに英会話は意味ない?ネイティブ講師と日本人講師の違いを比較し、それぞれのメリット・デメリットや選び方をわかりやすく解説。
2025.11.17|コエテコ byGMO 英語編集部