(取材)42 Tokyo×NTTドコモ「X-Tech Bridge」|無料エンジニア育成プログラム「X-Tech Bridge」開幕!3ヶ月間でメタバース空間のゲーム開発に挑戦

講義に先駆けて開催された開会式では、オンライン・オフラインで参加した学生を前に、42 Tokyoとドコモの担当者が登壇。本講座の意義や目標、主催者の思いを共有するとともに、ルール説明などが行われました。
本記事では、2024年4月16日に開催されたX-Tech Bridge開会式の様子と、担当者・参加者の皆さんへのインタビューをご紹介します。
X-Tech Bridgeとは

X-Tech Bridgeは、「誰もが自身の思いと行動で学び、成長し、活躍できる世界を作りたい」という理念のもと、42 Tokyoとドコモが共同で立ち上げたエンジニア育成プログラムです。
「変わりたい、学びたい、成長したいという強い想いを持った方々が、一歩先の自分に進むための架け橋(ブリッジ)となる環境を作りたい」というイメージから命名されました。
大きな柱として掲げられているポイントは、以下の3つです。
- 参加費無料!本プログラムの参加費や教材費はすべて無料です。
- ボーダレス!本プログラムの参加には面接や試験、学歴や経験といったボーダーを設けません。意欲がある方を多く受け入れています。
- 3ヶ月間の短期集中でゲーム開発を学ぶ!
ドコモが持っているメタバースのような最先端技術と、42 Tokyoの持つ教育ノウハウを組み合わせ、新しいことに挑戦したいと考えるすべての人に、質の高い教育を提供するカリキュラムとサポート体制を実現します。
42 Tokyoとは

2020年6月に開校した42 Tokyoは、フランス発、学費無料のソフトウェアエンジニア養成機関です。
パートナー企業の支援によって運営されており、大きく3つの特徴があります。
- 経歴やプログラミングの経験にかかわらず入学試験を受けることができ、学費は完全無料
- 新宿にあるキャンパスは24時間365日オープンしており、ライフスタイルに合わせて学習可能
- 教材は常に最新の内容にアップデートされ、世界最先端の旬の技術に触れられる
また42 Tokyoは、教師がいない・授業がないという独特の学習スタイルでも知られています。
- ピアラーニング:学生同士が教え合い学び合う教育法
- プロジェクトベースラーニング:次々と出される課題を解決していく学習方法
このような手法を採用することにより、参加者同士が学び合い、レビューし合いながら、ゲーム感覚でお互いを高め合っていくことが期待されています。
X-Tech Bridgeのカリキュラムにも、これらの学習スタイルが取り入れられています。また、X-Tech Bridgeオフライン参加者は、42 Tokyoのキャンパスやdocomo R&D OPEN LAB ODAIBAで学ぶことになります。
X-Tech Bridge開会式の様子
2024年4月16日、東京お台場にあるdocomo R&D OPEN LAB ODAIBAにて、42 Tokyoとドコモによる無料エンジニア育成プログラム「X-Tech Bridge」の開会式が開催されました。
司会進行を務めたのは、42 Tokyoパートナーコミュニケーション担当でX-Tech Bridgeディレクターの佐藤奏さんです。

開会式の冒頭では、ドコモ R&D戦略部社会実装推進担当でX-Tech Bridge学長でもある鈴木邦治さんが、仮想現実を舞台にした某有名SFアクション映画のコスプレで登場!なんと自費で購入したという衣装とサングラス姿で、会場を大いに沸かせました。

某SF映画のコスプレで登場した鈴木さん。その真意は?
「なぜ私がこの姿でここに来たのか、それは『未来を作るため』です。映画の仮想現実の世界、それはまさにメタバースの未来そのものです。今回のX-Tech Bridgeもまさにメタバースの開発を行う、『未来を作る開発』であると本気で思っています。今回開催するこの企画の中から、新しい未来、新しいサービスが生まれていく。そんな『世界』を作っていきたいと思っています」と鈴木さん。
ドコモが今後展開しようとしている事業には、インフラの上につながる世界、たとえばメタバースやWeb3、エンタメ、FinTechといったさまざまなサービスが不可欠です。そしてそれらのサービスを、ドコモ単独ではなく、能力のある人と力を合わせて「一緒に作っていく」ことが大切だと鈴木さんは強調しました。
ドコモのブランドスローガンは、「あなたと世界を変えていく」。鈴木さんは「今回このX-Tech Bridgeに参加していただいている皆様も、まさにこの『あなた』に入ります。皆様と一緒に、新しい世界を変えていく、作っていく。そういったプログラムにしたいと思っています」と付け加え、挨拶を締めくくりました。
環境もバックグラウンドも異なる多様な人々が、ともに参加し、関わり合い、互いを高め合っていく。それこそが、X-Tech Bridgeの大きな目標と言えそうです。

続いて、42 Tokyoの理事長である坂之上洋子さんが参加者へ向けて挨拶しました。
「今回のプログラムは、メタバースというドコモが最新技術を持ってトライしている領域と、42 Tokyoが提供する世界最先端の教育が組み合わさってできました。
我々としても新しいことに取り組んでいるので、うまくいかないこともあると思いますが、一緒に挑戦していけたらと思います。
ドコモと42 Tokyoと参加者のみんなでカバーしあって、みんなで未来をつくっていく3ヶ月間にしましょう。終わった時に、みんなが楽しかったと言えるプログラムにできたら嬉しいです。」と坂之上さん。

X-Tech Bridgeプログラムの概要
主催者の挨拶やプロジェクトの概要に続き、X-Tech Bridgeの3ヶ月のプログラムの概要が紹介されました。まず題材となるのは、メタバースプラットフォーム「MetaMe」。参加者はゲームエンジンUnreal Engineを活用し、クラウドゲーミング方式のゲーム(Webアプリケーション)開発に取り組みます。
- 最先端の技術を学びアウトプットに挑戦し、自身のスキル強化の限界突破をする
- 仲間とともに学び、自身の視野を広げる
- どんな結果であろうとも、3ヶ月後に「有意義な学びを得て、こんな成果を作れたんだ」と自信を持って言えるような3ヶ月間を過ごす
「私たちの期待としてはぜひ、仲間同士で高め合って、切磋琢磨していって、最終的にゴールまでたどり着いていってほしいと考えています」と強い期待感をにじませました。

具体的な3ヶ月の流れ
X-Tech Bridgeの具体的な流れとしては、以下の3つのステップで進められます。- STEP1 ミニゲーム開発のための基礎学習
- STEP2 チームまたは個人で成果物を作成
- STEP3 最終報告会でプレゼンテーション
STEP1で行われる基礎学習は、Unreal Engine基礎から始まり、講義が5回、学習の振り返りが5回、交流会が5回です。
その後はSTEP2に移り、実際にチーム、または個人で成果物を作成していくフェーズに入ります。こちらは制作に時間が必要だろうということで、2ヶ月半という少し長めの期間が設定されています。
そして最後のSTEP3では、最終報告会のプレゼンテーションが行われます。審査はドコモ、42 TokyoとUnreal Engineのプロフェッショナルが、ゲーム業界のゲスト審査員を招き、厳正に行われる予定です。
優秀な作品は実際にMetaMe上でローンチされる可能性があります。また優秀だった参加者には、MetaMe専属クリエイターとして業務委託契約の相談がある可能性もあります。
X-Tech Bridgeのグランドルール
後援企業、運営メンバーの紹介に続き、司会の佐藤さんからは参加者に向けて、3つのグランドルールの説明がありました。まず1つ目が「挑戦する」こと。佐藤さんは「失敗は本当に大歓迎です。失敗が成功への近道でもありますので、たくさん失敗を重ねて、3ヶ月後にいいゲームを作れるように頑張ってください」とエールを送りました。
2つ目のルールは、「レビューする」ことです。レビューと言っても意味はたくさんありますが、たとえば「復習」「批評」「再考」などを指しています。お互いのレビューはもちろん、セルフレビューも必要になります。「きちんと3ヶ月間、自分と向き合って、他者と向き合って、敬意を持って、皆さんで素晴らしいものにしていって欲しいです」と佐藤さん。
そして3つ目が「学び合いが成長のカギ」。X-Tech Bridgeに参加する150名は、それぞれが経験もバックグラウンドも違う、実に多種多様なメンバーです。佐藤さんは「X-Tech Bridgeは刺激とアイデアの宝庫だと思います。たくさんコミュニケーションをとって、自分の成長のカギとなるアイデアを盗んだり、自分でたくさん発信をしたりして、学び合いの相乗効果を楽しんでいただけたら」と話しました。
これにより、開会式は盛大な拍手とともに終了しました。
開会式の後、同会場にてオフライン参加者による懇親会が行われました。


担当者インタビュー
開会式を終え、X-Tech Bridge担当者の皆さんにお話を伺いました。【株式会社NTTドコモ R&D戦略部 社会実装推進担当 鈴木邦治さん】

―今回のプロジェクトを立ち上げようと考えた思いや、期待することを聞かせてください。
もともとドコモの課題として、いわゆるソフトウェアに近いAIやデータ分析、メタバースといった領域をやっていることに関して認知が少ないんです。でも実はすごいエンジニアがたくさんいることを広めたい気持ちがあります。
ただそれ以上に、今回私自身がX-Tech Bridgeを立ち上げようと考えたのは、『オープンにしていきたい』という思いが強いです。たとえば今回テーマにしているメタバースは、皆が新しく暮らすバーチャルの世界です。ドコモが開発企業にお金を出して作ってもらうことはもちろんできますが、おそらく今の時代はそういう考え方ではなく、オープン化していくことが必要だと思います。クリエイターの方々が自分で作ったものがMetaMEの本当のサービスになっていく、そこで作ったものが売れて稼げる、たくさんの人に使ってもらうことで自分自身の認知を広げて有名になっていく、そういう世界。
そう考えたときに、エンジニアの方々のコミュニティをしっかりと広げて行くことが必要だと思いました。そういった方々にいろんなものを好き勝手に作ってもらって、メタバースを盛り上げてくれることが、ドコモの認知を広げるのにも繋がるだろうと思います。
―今回600名を超える方から関心が寄せられたということですが、今日オンライン・オフラインで集まった参加者様を実際に見て感じたこと、期待することはありますか。
本当に幅の広い方々がいらっしゃるなと思ったのが第一印象です。実際に前でお話ししてみて、『3ヶ月のプログラムが良いものになるかどうかは、周囲に働きかけをしたり、自分自身でアウトプットを作ったりといった取り組み次第で決まる』というところに、皆さんがすごく頷かれていたのが印象的でした。あ、本当にやる気に満ちた方々が集まっているんだなと思いました。
―では最後に、受講生に向けてのメッセージをお願いします。
一緒に未来を作ろうぜ!というところで、ぜひお願いします(笑)。
【一般社団法人42 Tokyo 副理事長 兼 事務局長 佐藤大吾さん】

―ドコモさんとの共同プロジェクトであることのメリット、期待感を教えてください。
両社とも、学歴や職業に関わらず挑戦したい人に機会を提供し、活躍できる世界をつくりたいという想いを持っていたことから、無料のエンジニア育成プログラムを提供することになりました。
本プログラムで、ドコモ様の最先端技術を扱うエンジニアの方の講義を受けられることは大変貴重な機会だと考えています。また、ゲーム開発の経験にかかわらず実践的な課題に取り組むことができ、さらにドコモ様が技術提供しているメタコミュニケーションサービス『MetaMe』上で実際に成果物を社会に発信できるチャンスがあるという点も、未経験からゲーム業界へ挑戦したいと考える方にとって大変魅力的なプログラムとなっているのではないでしょうか。
―42 Tokyoとして、X-Tech Bridgeに期待することは。
X-Tech Bridgeでは入学試験がないため参加のハードルが低く、より多くの方に機会提供ができる点に期待しています。また、42 Tokyoの特徴的な学習スタイルである『ピアラーニング』『問題解決型学習』を参加者の方に体験していただくことで、プログラミング学習の楽しさを感じていただきたいです。
―参加者への激励メッセージをお願いします。
スキルを身につけたい、磨きたいという熱意の高い方が参加されているので、『ピアラーニング』の良さが最大限発揮されると思っています。プログラミングスキルを磨くことはもちろん、さまざまなバックグラウンドを持つ仲間と刺激し合いながら学ぶ楽しさを感じていただきたいです。
参加者インタビュー
X-Tech Bridge開会式に参加した皆さんにもお話を伺いました。【42 Tokyo 受講生 堀さん・森下さん】

左:堀さん、右:森下さん
―X-Tech Bridgeに応募されたときの気持ちを聞かせてください。
堀さん:
42 Tokyoではまだ課題でメタバースを取り扱ったことがなかったので、やってみたいなという気持ちが一番でした。
森下さん:
僕も、メタバースは全然先のほうの課題なので、そういった関心がありました。あと、42 Tokyoでゲームを作る課題があり、楽しく取り組めたことからも興味を惹かれました。『42 Tokyoがやるんだったらぜひやってみよう』と思って、情報公開日くらいにそのままポチッと応募した感じですね。
―3ヶ月の講座に臨むうえで、今の気持ちを教えてください。
森下さん:
42 Tokyoもそうですが、X-Tech Bridgeにはいろんなバックグラウンドの方がいるので、たくさん関わっていきたいなと思っています。
42 Tokyoにはいろんな趣味、いろんな経歴の方々がいて、たとえば専門分野の情報とか、『これいいよ』って拡散する文化があるんです。X-Tech Bridgeでも、こういった交流ができるんじゃないかと楽しみにしています。
堀さん:
不安よりわくわくの方が強いですね。大学だとコミュニティや年代が狭いですが、42 Tokyoはいろんな方がいるので、コミュニティが広がります。X-Tech Bridgeにもいろんな方がいるので、ゼロからのスタートですが、周りと助け合いながらやっていけたらと思っています。
―最後に、意気込みをお願いします。
森下さん:
3ヶ月間、出来る限り良いものを作っていきたいです。
堀さん:
42 Tokyoのツールやピアラーニングなら、知識ゼロの状態からでもある程度のところまで行けるというのを確信しています。これを通していろいろな方と交流をして、確かな技術を身につけられたらいいなと思います。
【一般参加者 堀内さん】

―堀内さんのキャリアについて教えてください。
堀内さん:
私はもともと、Webデザイナーとして長年働いてきました。そこから習い事として陶芸に触れ、7~8年ほど取り組むなかで、陶芸作家としても活動するようになりました。
二十歳前後からいろんなことに取り組んできましたが、ベースにあったのは『ものづくり』への思い。モノでもデジタルでも関係なく、何でも作っていたい人間なんです。
―その思いがX-Tech Bridgeへの応募に繋がったのですね。
堀内さん:
はい。技術系のRSSに流れてきたのがきっかけです。私はインターネットの新しい技術がずっと好きで、『趣味も仕事もインターネット!』と言い続けてきました。最近だと、BlenderとUnityを使って3Dアバターを作って、動かして遊ぶこともあります。X-Tech Bridgeは、それと同様に、新しい“遊び“に挑戦できるチャンスだなと。いろいろ、とにかく吸収していきたいです。
―他の受講生や登壇されていた講師を見て、今の率直な気持ちを教えてください。
堀内さん:
もうすっごくわくわくしています。とくに期待しているのは、ピアラーニングによって生まれるチーム活動です。今日の懇親会だけでも、X-Tech Bridgeの皆さんはとても穏やかに交流されているので、良い化学反応が期待できそうです。とにかく積極的に行きます!
ライターコメント
X-Tech Bridgeは主催者、参加者ともに、「ともに新しい未来を作っていこう」という希望に満ち溢れているのが印象的でした。基礎学習、チームまたは個人開発を経て、3ヶ月後の最終報告会が今から楽しみです。未来を担うエンジニアたちの学びの成果に期待しましょう!
NTTドコモ×42Tokyoが共同で立ち上げた完全無料・完全ボーダレスのエンジニア育成プログラム。短期間で実践的にプログラミングスキルを学ぶことが可能です。技術の幅を広げたい、新しい技術領域にチャレンジしたい方、奮ってご参加ください。

https://42tokyo.jp/landing/x-tech_bridge/ >


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
(取材)TOYOTA×42 Tokyo|自動運転ミニカーバトル開催。学生が設計・製作した自動運転ミニカーで対決!
フランス発のエンジニア養成機関「42 Tokyo」の学生たちが、ラジコンを改造した電子制御のミニカーの速さを競う「自動運転ミニカーバトル」に挑みました。(主催:42 Tokyo、トヨタ...
2024.11.06|徳川詩織
-
CodeCampKIDS×コエテコ 「プログラミング体験ワークショップ」レポート
2018年4月にコードキャンプ株式会社とコエテコが開催した、小学生向け無料プログラミング体験ワークショップの様子をご紹介します。 MIT(マサチューセッツ工科大学)メディアラボが開発...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
(取材)ライフイズテック スプリングキャンプ2024|春休みに東大でプログラミング体験!イベントレポート
「Life is Tech!(ライフイズテック)」のキャンプは、春休みや夏休みを利用し、短期集中で学ぶプログラム。初心者も参加OKです。今回は2024年の春休みに開催したスプリングキャ...
2025.09.10|大橋礼
-
【優勝者インタビュー】全国小学生プログラミング大会「ゼログラ」決勝戦をレポート!
2021年12月に開幕した、小学館ほか3社が主催する「全国小学生プログラミング大会 ゼロワングランドスラム」。初開幕にもかかわらず1,500名の応募があったという本大会、先日とうとう決...
2025.05.30|原 由希奈
-
(取材)フランス発のエンジニア養成機関「42 Tokyo」にキッズドアから合格者が誕生!合格率4%の難関突破までの...
子どもたちへの学習支援・居場所提供などの事業を展開する「NPO認定法人キッズドア」。そんなキッズドアから、この度フランス発のエンジニア養成機関「42 Tokyo」へ見事合格を果たした生...
2025.09.10|ちとせとも


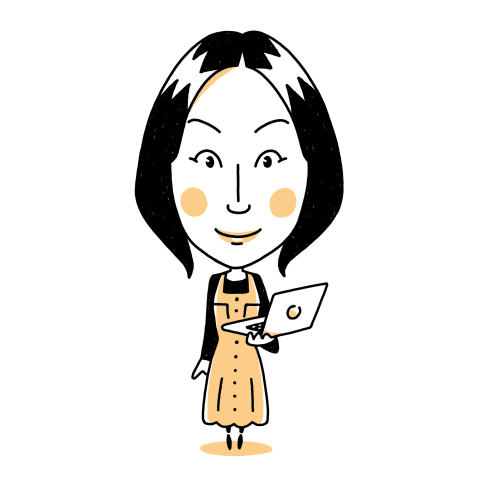





MetaMeとは、ドコモが技術提供しているメタコミュニケーションサービスです。目的や価値観に応じて他者と繋がることが可能で、“私らしさ” を表現できる「Home」と、新たな “私らしさ”の発見をサポートする「Community World」を提供しています。なんと1万人が同時接続可能!すごい。
MetaMeは2024年4月現在、β版としてすでにローンチされています。スマートフォンやPCで検索すれば利用できますので、興味のある人は触ってみてくださいね。