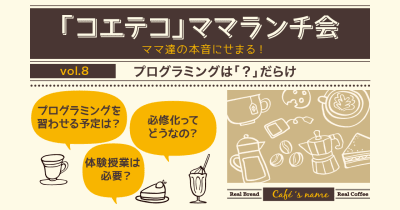非エンジニアの市民がプログラミングメンターに!地方ICT教育のウラ話と現場の声|愛知県豊橋市

小学校でプログラミング教育が必修化されて以降、中学校や高校にも広がり、子どもたちがプログラミングに触れる機会は確実に増えています。一方で、保護者の中には「何を学んでいるのか」「将来にどう役立つのか」といった関心や不安を抱く方も多いはず。本記事では、小学校におけるプログラミング教育の内容や目的をわかりやすく解説します。


2025/11/17

しかし、学校の先生と一緒にプログラミング教育の授業プランを考える「ICT支援員」が不足しているなど、現場では課題が山積みと言えます。特にIT人材が不足しがちな地方は、2020年をどう迎えたのでしょうか。
実態をさぐるべく、今回取材をしたのは人口約37万人の地方都市である愛知県豊橋市。なんでも、2020年のプログラミング教育必修化に向けて、官民学が協力して“IT 先進都市 Toyohashi !” を目指した豊橋市民総メンターによるプログラミング教育の推進(通称:とよはしプログラミング・チャレンジ2017)が行われたそう。
“豊橋市民総メンター”とはどんな取り組みなのでしょうか。事業の内容と、そこから生まれた非エンジニアの市民メンターに、事業について詳しくお話を伺いました。
とよはしプログラミング・チャレンジ2017とは

出典:CodeMonkey (コードモンキー)ブログ『「とよはしプログラミング・チャレンジ2017」はじまります!』
とよはしプログラミング・チャレンジ2017(以下、とよプロ)は、2017年に豊橋市と豊橋市教育委員会、ジャパン・トゥエンティワン株式会社が連携して、子どもから大人までプログラミングに慣れ親しめる環境を地域でつくる教育活動です。 総務省の平成28年度「若年層に対するプログラミング教育の普及推進事業」の一環として行われました。
この事業で使われたプログラミング教材は、子どもから大人まで学べるオンラインのプログラミング学習ゲーム「CodeMonkey (コードモンキー)」です。
CodeMonkey(コードモンキー)のサービス詳細・導入実績などポイントを紹介!。生徒・学校・教育機関・スクール向けサービスの無料で使えるEdTechサービス比較・紹介サイトです。WEB総合展示会!問い合わせ受付中。提供会社:ジャパン・トゥエンティワン株式会社 (J21 Corporation)
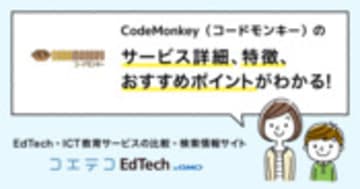
https://coeteco.jp/edtech/services/19 >
事業では、豊橋市内に在住・在勤・在学している小学生以上1000人に、無料で学習できる特別ライセンスカードが配布され、市民メンターの育成と放課後の教室を活用したプログラミング講座が開催されました。
“第二のシリコンバレー”イスラエル生まれの教材に受けた衝撃
プログラミング教育の担い手不足を解消する、画期的な「とよプロ」。この事業が生まれた舞台裏では、どのようなことが起こっていたのでしょうか?まずは、企画統括プロジェクトマネージャーである豊橋技術科学大学の高嶋先生にお話を伺いました。
取材に協力していただいた豊橋技術科学大学 高嶋教授(2021年7月取材当時)
この事業が始まる前の2015年に、豊橋に本社を移転した、海外のハイテクベンチャーの製品を日本にビジネス展開するジャパン・トゥエンティワン株式会社の創業者から、イスラエルの小学校で使われているプログラミング教材『CodeMonkey』について紹介がありましてね。これが非常に完成度が高く、「なんともよくできている。一刻も早く、地元・豊橋市の学校に知ってもらいたい。また日本中に広めたい」と思ったんです。
その後、2016年* 5月にテレビで「2020年に小学校のプログラミング教育を必修化します」と政府の産業競争力会議で安倍総理が発表しているのを見かけて。「今が若者の未来を左右する分岐点だ!」と言いながら2020年なんて、まだまだ先じゃないかと落胆しました。プログラミングを40年以上もやってきた私としては、日本はすでに世界から遅れをとっている状態だという危機意識を強く持っていたんです。
ええ。2020年なんて、待ってられないなと思いましたね。「なんとか前倒しで学校現場に導入できないか」と強く願いました。ただ、いち民間企業が販売する教材を教育現場に導入するにはさまざまな課題がありましたので、当時の市長や教育長に直談判するなど、できる範囲で奔走しました。
そんなときに、総務省から「若年層に対するプログラミング教育の普及推進事業」について話がありまして。簡単に説明すると、「2020年のプログラミング教育必修化に向けて、子どもたちを教える環境を整えるための活動に補助金を出しますよ」という事業ですね。
その2次補正予算が出て、募集がかかっていると。これを活用して波を起こそう、どうせ採択されないならダメもとで想いを一杯詰め込もう、と申請書を書き出したのが「とよプロ」の始まりです。
ーその後は、どのようにして事業の話が進んでいったのでしょうか。
もともとは教育委員会の学校教育課に打診していたのですが、あるとき、総務省のこの事業内容だったら「生涯学習課」だということでそちらに話が回されたところ、「ぜひやりましょう」と快諾してもらえました。
というのも、当時の生涯学習課では放課後子ども教室*「トヨッキースクール」 の目玉になる講座を探しており、まさに我々の「プログラミング教育の普及とメンター育成」という切り口の計画と合致したんです。

そこで、ジャパン・トゥエンティワン株式会社の創業者に「IT先進国を目指すなら、豊橋市民のみんなでプログラミングを推進しましょう」「そのためには、1000人にライセンスを無料で配りましょう」「最終的には、イスラエルと豊橋市の小学生をオンラインで繋いでプログラミング対戦をしましょう!」と熱弁をして、「若年層に対するプログラミング教育の普及推進事業」の応募書類を書き上げました。
ー「ライセンスを無料配布」のキャンペーンはいくつかありますが、せいぜい10人〜多くて100人の印象です。1000人とは、すごいですね。
私はイスラエルで使われているプログラミング教材を、本当にいいものだと感じていましたから。子どもから大人まで、どんな初心者でも操作がわかりやすいんです。これをより多くの人に使ってもらうことで、プログラミングを学ぶ機会を提供しようと思いました。事業が採択され、実際に1000人分配布できたのは、非常に良かったですね。
ーすごい情熱です。その後はどのようなスケジュールで実施されたのでしょうか。
事業自体は2017年5月から12月の約半年間でした。5月にプログラミング教材のライセンスを配布して、まずは子どもから大人まで多くの人に使ってもらうことを第一の目的としていました。
そこから11月までは、毎月オープン講座を実施して、講演会を聞いたり、プログラミングの質疑応答ができるコードモンキー広場を設けたりしました。また、講演はYouTubeとFacebookでもライブ配信を行い、来場できなかった人や市内外の人など、より多くの人が視聴できるようにしました。

出典:総務省「IT 先進都市 Toyohashi !"を目指した 豊橋市民総メンターによるプログラミング教育の推進」
それから、ライセンス配布と同時に、子どもたちにプログラミングを教えるメンター養成講座の参加希望者を募ったところ、27名が集まりました。驚いたのが、属性を見てみると、半数がプログラミング未経験者だったことです。年齢層も幅広く、学生もいれば会社員もいる。主婦の方、校長を退職された元先生など、さまざまな方が興味を持ってくださいました。
ちなみに、女性で一番多かったのは40代で、「自分の子どものために何かしたい」という動機から応募された方が多かったようです。

出典:総務省「IT 先進都市 Toyohashi !"を目指した 豊橋市民総メンターによるプログラミング教育の推進」
そこからは、その27名の市民メンターの持ち回りで、豊橋市内の小学校2校で実証講座を実施。各校のパソコンルームを利用し、放課後子ども教室「トヨッキースクール」として9月から11月のうちに全5回の連続講座をしています。またそこでは、小学校1年生から6年生が一つの教室で一緒に学びました。
ーライセンス発行から5ヶ月目でメンターとして小学校に赴くことになったのですね。指導方法や講座運営の具体的な方法は、細かく指示されていたのでしょうか。
いえ。メンター養成講座では、指導方法や綿密な講座の進め方を教えることはしていません。メンターの自主的な運営に任せるという進め方で、いわゆるリーンスタートアップ方式ですね。とにかく最低限だけを決めて進め、定期的に内容をチェックし、改善して実行する……というサイクルを短期間で繰り返すイメージです。
思い出深かったのが、実証校では、大人メンターが高学年に教えて、高学年が低学年に、低学年が「たのしかった」と自宅で幼い兄弟にに教える……といった複数レベルの市民総メンターが発生していたことです。こうした“子どもメンター”が出てきてくれたのは、プログラミングを草の根で広げる上で、とても嬉しいことでした。

出典:総務省「IT 先進都市 Toyohashi !"を目指した 豊橋市民総メンターによるプログラミング教育の推進」
あとは、12月には豊橋市とイスラエルの代表の子どもたちを国際ネット生中継で繋ぎ、プログラミング対戦をしました。イスラエルの子どもはレベルが高いので、豊橋市チームは惨敗するかなと思っていたのですが(笑)。最終結果は予想どおり1位と2位がイスラエルチームでしたが、実際にはみなさん健闘されて、途中までは1位と競り合っていました。
また賞はチーム戦の結果だったのですが、後の分析で分かったのですが、個人レベルでは豊橋の小学生がイスラエルの子どもたちを抜いてトップの成績だったのには驚きました。

出典:総務省「IT 先進都市 Toyohashi !"を目指した 豊橋市民総メンターによるプログラミング教育の推進」
ー事業を通し、まさに「草の根」でプログラミングの輪を広げてこられたのですね。
そうですね。今回の事業を通して、豊橋市内だけでなく、他の自治体や学校、企業などからも問い合わせを受けるようになりました。今後は市民メンターが豊橋内外で活躍し、より輪を広げてくれたら嬉しいです。
ー先生、ありがとうございました!
“プログラミング未経験のオカン”がメンターに⁉︎その意外なメリットと実情
このようにして始まった「とよプロ」からは、さまざまなバックグラウンドの市民メンターが誕生しました。取材後半では、現在も市民メンターの1人としてプログラミング体験教室に携わっているおぐらさんに、市民メンターになった経緯や当時の様子、その後の活動についてお伺いしました。
インタビューに協力してくださった市民メンターのおぐらさん
ーまずは、おぐらさんのご経歴について教えてください。
私は北海道出身で、大学卒業後、結婚にともない愛知県豊橋市へ移住しました。職歴は業務委託でBtoB向け商材のBtoC向けオンラインショップ展開やSNSプロモーション、講師業や創業・新規事業支援、市内のコワーキングスペースで広報やコミュニティーマネージャーなどを経験しています。
ーフリーランスとしてマルチに活動されているんですね。ちなみに、これまでプログラミングのご経験は?
この事業に参加するまで、プログラミングはまったくの未経験でした。
ーそうだったのですね。未経験だったおぐらさんが、市民メンターに応募したきっかけとは。
当時、会員として出入りしていたコワーキングスペースで、「とよプロという事業がはじまる」と知ったのがきっかけです。というのも、自分の子どもが2020年に小学校へ進学する年だったため、いち保護者として、プログラミング教育に関心を寄せていたんですね。子どもの成長に合わせて、私自身もスキルアップしながらプログラミングを教えていけたら素敵だな、と思い、参加を決意しました。
とよはしプログラミングチャレンジ、特別ライセンスカードの交付初日の朝。 「あんまりやる気満々で取りに行ったらちょっと恥ずかしいわね」と思って交付開始から30分ちょいあけていったのですが、十分に早すぎたらしくココの交付場所ではトップバッターでした。 受付のお姉さまを慌てさせて若干申し訳なかったのですが、これで晴れてコードモンキーをNO.100まで無料でトライすることができます! (追記) ...
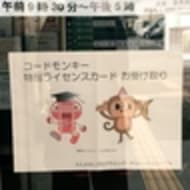
https://toyopuro-okan.hatenablog.com/entry/2017/05/26/100000 >
ー「とよプロ」では、プログラミング未経験からメンター育成講習を受け、子どもたちにプログラミングを教えることになったのですよね。実際に指導にあたった感想は。
やはり、最初は大変でしたね(笑)。
教材のおかげで、私自身がプログラミングを学ぶことに抵抗感はなかったのですが、そもそも、たくさんの子どもたちを相手に体験教室をするのに慣れていなくて。プログラミングの内容というよりも、運営や指導の面で苦労することがありました。
ただ、その点については、市民メンターの中に特別支援学校の先生や元プログラマーの方もいたので、アドバイスをもらうことができました。私たち未経験者側も気づいたことをシェアし、お互いに意見交換をしながら、運営側も成長していきました。
ーさまざまなバックボーンを持った市民メンターたちならではの相乗効果ですね。ちなみに、事業自体は2017年12月で終了していますが、その後の活動はどうなっていますか。
その後は、市民メンターを中心に結成された市民団体「とよプロ市民メンターの会」として、2021年現在もプログラミング体験会の活動は継続しています。
自主的にイベントを開催しつつ、高嶋先生経由で小学校からご依頼をいただいて「総合的な学習の時間」にプログラミング教室をメンターの皆さんと一緒に実施しています。小学校からのご依頼は、2018年と2019年が1校、2020年は2校、2021年現在は3校になりました。

学校の夏休み期間に開催された体験教室の様子
ー徐々に小学校からの依頼も増えているんですね。おぐらさんのように、非エンジニアの方が市民メンターになることのメリットを教えてください。
そもそも、この事業では「講師」ではなく「メンター」と表現をしているのがポイントなんです。いわゆる「子どもたちの“ちょっと先輩”として、一緒にプログラミングをやろう!」という位置付けで、「これ難しいよね」と初心者のわからない気持ちを共感しながら進められるのが強み。プロではないからこそ、子どもたちも抵抗感なくプログラミングを学べるのではないでしょうか。
実際に、学校の先生や保護者から必ずと言っていいほど寄せられる感想が、「子どもたちが楽しそうだった」です。子どもたち自身からも、「最初は難しそうだったけど面白かった」とコメントをもらっており、市民メンターの私たちもやりがいを感じています。
ー子どもだけでなく、大人たちも楽しんで取り組んでいるのが印象的です。これはあえて聞きますが、運営側の課題や、難しいポイントはありますか。
やはり、難易度が高いコースになると、教える人が減っていくという課題はありますね(苦笑)。あとは、プログラミングに触れてもらっても、「じゃあ、それを活かして、これからどうするの?」を充分に提示できていない。つまり、明確な形で将来につなげられていないところです。
私個人の考えとしては、市民メンターのプログラミング体験教室はいわば「プレ教室」。これをきっかけに、子どもや大人たちがプログラミングへの苦手意識をなくすことができれば、充分なゴールかなと思います。もっと学びたいと感じてもらえたら、プログラミングスクールに通ったり、独学で学びを深めたりしてもらえると、市民メンターとしてうれしいですね。
ーちなみに、おぐらさんが市民メンターとして活動するようになってからお子さんの変化はありましたか。
子どもとオープン講座に参加したり、自宅で一緒にプログラミングをやったりしているので、現在では年齢相応の単元まで進んでいます。小学校のタブレット端末に入っているプログラミング教材「Viscuit(ビスケット)」も楽しんでいるようで、抵抗感なく能動的にプログラミング学習ができるようになりました。
ー親子でプログラミングを楽しんでいるんですね!では最後に、プログラミング教育や市民メンターに興味がある方に向けてメッセージをお願いします。
小さなお子さんがいる保護者には、「自分がプログラミングを楽しみましょう!」とお伝えしたいです。
私たちのプログラミング体験教室は親子で参加を促しています。大人だからと言って「完璧にできなければ」と気負わずに、困ったことがあれば子どもたちと一緒に考えて解決することを重視しています。
今後は指導者育成にも力を入れて、大人だけでなく子どもたちもメンターとして教え合えるような取り組みにしていければと。「プログラミングは難しそう」という方ほど、私たちのプログラミング体験教室に参加してもらって、大人も子どもも苦手意識をなくしてもらいたいですね。
ーありがとうございました!
市民1人ひとりが、未来のIT人材
とよはしプログラミング・チャレンジ2017は、豊橋市と豊橋市教育委員会、ジャパン・トゥエンティワン株式会社が連携して、地方のプログラミング教育とその担い手を育成する目的で実施されました。この取り組みの特徴を総合するなら、子どもだけでなく幅広い市民にプログラミング学習のきっかけを提供したこと、と言えるでしょう。事業から生まれた非エンジニア畑の市民メンターが、不足しがちな地方の人材として、プログラミング学習の教え合いの輪を広げてくれたのは、非常にポジティブな結果だったと考えられます。
今後は、体験教室に参加した子どもたちが「子どもメンター」として活躍し、近い将来、プログラミングを本格的に学ぶようになり、未来のIT人材の1人になるかもしれません。幅広い人材がIT社会の未来を担う豊橋市に、今後も注目していきたいところです。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
自動運転を体験!小学校プログラミング教育の推進月間「みらプロ」公開授業レポート
2020年からの小学校におけるプログラミング教育の実施に向けて、さまざまな取り組みが見られます。文部科学省、総務省および経済産業省は、2019年9月を「未来の学び プログラミング教育推...
2025.06.03|小澤志穂
-
3ステップで解説!「日商プログラミング検定」の会場になるには?
2020年の小学校プログラミング教育必修化を前に、「日商簿記」などで有名な日商(日本商工会議所)が「日商プログラミング検定」をスタートしました。レベルは「ENTRY」「BASIC」「S...
2025.06.24|夏野かおる
-
「女の子が取り組みやすいプログラミング教育環境を作る」人気プログラミング教室の女性スタッフが語るAfrel ONE...
2020年11月25日の13時から、株式会社アフレルが主催するセミナー「Afrel ONE Mission!」が行われました。 女の子が取り組みやすいプログラミング教育の在り方につい...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
「コエテコ」ママランチ会 Vol.8 ~プログラミングは「?」だらけ~
2020年に小学校で必修化するプログラミング教育。「コエテコ」では読者ヒアリングを実施し、習い事に関するママ達の本音を語ってもらいました。今回は「プログラミングのイメージ」「必修化に感...
2025.09.10|夏野かおる
-
ママだってプログラミングしてみたい!ITな女子会に行ってきた!
2020年からの小学校でのプログラミング教育必修化にともない、盛り上がりを見せるロボットやプログラミング教室。でも、そんな中でなんとなく取り残されているのがお母さんたち…。「いったい何...
2025.05.26|工樂真澄