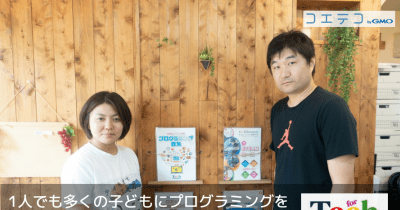中山間地域でのICT教育「木育×プログラミング教育」とは?|株式会社武田林業 代表 武田惇奨氏インタビュー

今回は、そんな「MOCKUPプログラミング教室」を運営する株式会社武田林業の代表、武田惇奨さんにお話を伺いました。

武田さんの経歴とMOCKUP立ち上げまで
ー武田さんは現在、内子町で武田林業の代表を務められていますが、MOCKUPプログラミング教室を開くまでの経歴を教えていただけますか。私は松山市の出身で、大学時代を広島と福岡で過ごしました。それから福岡の広告代理店で5年間、企画営業の仕事をしていました。その仕事を辞め、2017年4月に内子町の地域おこし協力隊に入ることになりました。
協力隊では「林業の6次産業化」をテーマに、地域の林業産品の企画開発をしていました。他にも林業や山村振興に関わるプロジェクトを数々立ち上げましたね。そして、入隊から1年半後の2018年10月に総務省の実証事業をきっかけに、町と協力しながら「MOCKUPプログラミング教室」を開くことになったのです。

木育×プログラミング教育「MOCKUPプログラミング教室」
ー林業振興をする会社が、ICTを駆使した教育活動を行っているのは非常に興味深いです。もともと、教育業界にご関心がおありだったのでしょうか?いえ、実のところは、はじめから教育に興味があったわけではありませんでした。それでも教室を立ち上げたのは、愛媛に戻って子供が生まれてから、教育関連の活動も行いたいという気持ちが強くなったためです。
林業振興の活動や林業の担い手を増やす活動は以前から行っていましたが、自分の子供が生まれるときに、「山間部で教育を受ける子供達の、将来の選択肢を増やせたら」という思いを強く抱いたのが大きなきっかけでした。

最近では「地方移住」がある種のトレンドになっていますが、現実問題として、移住先に仕事があるかどうかは大事なポイントです。実際に、地方に移住したくても、仕事に対する不安から移住の決断をできない方々が多くいます。
ただ、一次産業が盛んな地方を移住先に考えた場合、たとえ現場で木を伐採するプレイヤーでなくても、都会のIT企業で培ったスキルやノウハウを地方で活かせるチャンスは大いにあります。そういった仕事や人材が増えれば、UターンやIターンを考える若い人たちの大きな受け皿になれると考えています。
林業とICT教育を結びつけることで、地方のさらなる林業振興に貢献できる。そう考えていた時に総務省の実証事業のチャンスを掴み、「MOCKUPプログラミング教室」をスタートさせることになりました。
ー正直なところ、田舎ではICT教育そのものが広まっていない印象ですが、「中山間部で子供向けのプログラミング教室が本当にできるのか?」という疑念はなかったのですか?
周りにサポートしてくれる人が多かったので、疑念を抱くことはなかったですね。
実を言うと、私自身がバリバリにプログラミングをできるわけではなかったんです。大学の頃は研究のためにMATLABという数理系の画像や、グラフィックに強いプログラミング言語を勉強していたのですが、就職したのは広告代理店でしたし、しばらくプログラミングからは遠ざかっていました。
ただ、今の小・中学生のプログラミング学習に採用されているのは、アプリケーションを使った「ビジュアルプログラミング」だと知り、「これなら自分でも教えられる」と感じましたね。

ビジュアルプログラミングはあらかじめブロックが用意されていて、そのブロックを組み合わせるだけでプログラミングができます。MITが開発し、今では世界中で利用されている「Scratch(スクラッチ)」というプログラミング言語に触れた時、あまりにもテクニカルなハードルがないことに驚きました。
そこでまずは教室用の端末を揃え、自分や地域の講師候補がプログラミング塾へ出向いて研修を受けたり、彼らと教材開発をしながら、少しずつ教室運営の体制を整えていきました。
MOCKUPプログラミング教室の教材やカリキュラム

ー林業とプログラミングを結びつけたMOCKUPプログラミング教室は、他の産業にICTが関わっていく上でのロールモデルにもなると思います。具体的な教材やカリキュラムを教えていただけますか。
MOCKUPプログラミング教室では、ゲーム・ロボット・課外授業という3つのカテゴリーで授業を行っています。教材は、松山でプログラミング教室事業を展開するテックプログレスさんに開発を手伝ってもらいました。プログラミングを通して林業の学習ができる内容となっているのが特徴です。
例えば、教材の1つである「伐採シミュレーション」。プログラムを組みながら、画面上にランダムに生えていく木々を時間内にどれだけ多く切れるかを競うゲームです。
ロボットを使った授業に関しては、木の特性を理解してもらうことを意識しています。地域の端材を使って木工ロボットを作る授業では、レーザー加工機などのデジタルファブリケーション機器で木工ロボットのパーツを地元の木材で切り出し、組み立てる際には木目に沿って木が割れやすいことなど材料の性質について学習をしながら、作ったロボットでセンサーとプログラミングの学習をしています。
また課外授業では、ドローンなど実際の林業で使われるICT機器に触れたり、高性能林業機械の搭乗体験をしたり、現場に近い山村ならではの産業体験を提供しています。



林業には泥臭い部分もあるけれど、最先端技術も取り入れているから新しくも見える。「プログラミングを使って林業と接点を持ったらどのような変化が起きるか」ということを、子供たちが都市部ではななかなか触れることができない森林や林業、木材など一次情報に触れながら考えられる機会を作っています。
いずれのカテゴリーにせよ、まずは子供達に楽しんでもらい、林業に対して良いイメージを持ってもらうことが重要だと考えています。
私自身、小さい頃は林業を営んでいた祖父のヒノキ林が遊び場でした。山や渓谷も大好きで、そんな小学生の時の良い思い出が、林業振興をする会社を営む今に繋がっていると思います。担い手育成をするにあたっても、子供たちがそんなポジティブなイメージを持てるような工夫を心がけています。
ーまさに、林業が盛んな内子町ならではのICT教育ですね。実際の教室運営はどのように行っているのですか?
MOCKUPプログラミング教室は、1回60分・月に2回、生徒3人に対して1〜2人の講師で授業を行っています。木工を行う「内子手しごとの会」さんのご厚意により、店舗の一部をお借りして運営しています。
また通常の授業以外にも、「出前授業」として教育委員会や行政などからの依頼による授業をイベント的に行ったり、地方の特性を活かしたICT教育を教育現場に提案するような仕事もしています。
ー出前授業とは、具体的にどんなことをしているんでしょうか。
最近の出前授業では、人気ゲームの「マインクラフト」と内子町の白壁の町並みを掛け合わせた授業を行いました。
内子町には伝統的な建造物が立ち並ぶ「町並み保存地区」があります。プログラミングを始める前に、実際に並ぶ建物や展示を見て、今回のテーマである「内子町の町並み」にはどんな特徴があるのか、どのように保存されてきたのかなどを考えてもらいました。

自分たちが暮らす町並みやその建物について学んだら、次はそれをマインクラフトと融合させます。例えば、壁にはなめらかな砂岩、窓には黒樫の木の柵、屋根にはブラックストーンなど、プログラミングをしながら外観として町並みの印象に近い素材のブロックを使って仮想空間の中で家を建てていくような内容です。
このように、プログラミングを通して林業・木材業と密接な関係にある建築についても触れてもらうことで、より林業の魅力や楽しさ、将来性などを子供達に伝えていく活動も行っています。


引用元:https://mockmock.jp/event/822
【うちこ未来塾】古い町並みをマイクラで再現!?プログラミング×ゲーム建築!
新たな選択肢を得る子供と、親の心情の変化
ー2020年度より、小学校でのプログラミング教育が必須化されました。時代の流れも変わる中で、実際にプログラミング教室に通った子供や親御さんは、どのように感じているんでしょうか。初月から教室に通ってくれた子の一人は、ゲームクリエイターになりたいという新たな夢ができたみたいです。本来、こちらが望むのは林業への参画なんですが、もちろんそれが全てではありません。子供達がどんな選択をするにせよ、職業選択の幅を広げられたのは嬉しいですね。
他にも、林業を営んでいた方のお孫さんがいたのですが、その子はプログラミングが大好きで、クリスマスのプレゼントはドローンやプログラミングソフトが欲しいというくらい、ハマっていたんです。その子は「将来は林業に関連する仕事に就きたい」と言ってくれていました。プログラミングを通したITからのアプローチになるとは思いますが、林業に関わりたいと思ってもらえるのは嬉しいものです。

引用元:https://mockmock.jp/event/822
また、親御さんたちにも変化が見られます。例えば、子供のために自宅のプログラミング学習環境を整えてあげたいという親御さん。IT関連のことはあまりわからないという方でしたが、「子供のために学びの場を提供したい」という意識に変わったようです。
子供に電子機器を与えることで、教育放棄に繋がるのではないかという不安を持つ親御さんもいます。ただ、学びの提供という意識の切り替え1つで、子供は楽しみながら将来性のあるスキルや思考法を身につけられるということも、積極的に伝えていければと思います。
アウトドア視点で林業を体験する「ワンツーツリーフォレスト」
ー武田林業さんではMOCKUPプログラミン教室の他に、「ワンツーツリーフォレスト」というイベントも主催されていますね。これはどういったイベントなのでしょうか?ワンツーツリーフォレストはアウトドアイベントに参加する感覚で林業を体験するイベントで、年に一回、地元の広大なスキーゲレンデをフィールドに開催しています。当社は企画者ですが、複数ある出店者の中の1つとしてプログラミング体験も提供します。
あくまでもアウトドアイベントではありますが、木や山に関係する体験を取り揃えているのが特徴です。林業機械を操作しながら丸太を掴んだり、ノコギリで木を切ったり、プログラミングでドローンを飛ばすワークショップを行ったりなど、子供から大人まで楽しみながら林業をエンターテイメントとして楽しめるように企画しています。
2021年開催予定だったワンツーツリーフォレストは、新型コロナウイルス流行の影響で残念ながら中止となってしまいました。ただ、幸いこのイベントは毎年好評をいただいているので、今後も林業振興・中山間地域のICT教育の一環として継続的に取り組んでいきたいと思います。
MOCKUPプログラミング教室の課題とビジョン
ーMOCKUPプログラミング教室では、中山間地域ならではの手法で木育×プログラミング教育を実践されていることがわかりました。現状の課題や今後のビジョンを教えてください。大きな課題の1つとしては、運営側のマンパワー不足が挙げられます。存在を知ってくれた方からは「うちでもやってください」と声をかけられることも多いですが、さらに広めたいと思ったときに、現状のリソースではなかなかそれが難しいというジレンマがあります。
実は、MOCKUPプログラミング教室で使用している教材は全てオープンソースにしています。同一の教材を使ってもらい、「MOCKUP〇〇(地域名)」というように、各地域で木育×プログラミング教育を広めるのが狙いです。
それをきっかけとして、中山間地域における林業振興×ICT教育が、各地の山間部で同時多発的に盛り上がるのが理想的です。もちろん林業だけでなく、農業など他の産業とICT教育を結びつけることも可能でしょう。
教材は武田林業にお問い合わせいただければ、無料で提供させていただきます。興味のある事業者様や教育関係者の方がいらっしゃれば、ぜひともご連絡お待ちしております。
—武田さん、ありがとうございました!
関連リンク
株式会社武田林業は、愛媛県内子町を拠点に、まち・ひとと山の間である「梺」にたち、林業と人びととの接点をつくることで"林"業を"下"支えする「梺業」を展開しています。さまざまなサービスやプロダクトから森の入り口をつくることで、林業・山村活性を目指します。 「買える」森の入り口=オンラインストアをオープン。

https://4est.co.jp/ >


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
『MADE IN SHIBUYA』の子どもたちを育てる街づくり―渋谷区 長谷部健 区長
『ちがいを ちからに 変える街。渋谷区』をコンセプトに新たな街づくりを目指している渋谷区。これからの時代を生きる子どもたちの育成への意欲的な取組みや渋谷区ならではの事例、今後の学校教育...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
現役東大生と与那国島の子どもをつなぐ!日本最西端の島で最先端のプログラミング授業
日本の最西端・沖縄県与那国島。東京から2,000km以上も離れたこの島で、現役東大生による授業が行われているのをごぞんじですか? 現役東大生による双方向遠隔ライブ授業サービス『東...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
(取材)『STREAMチャレンジ2022』|Pepperを活用し、SDGsを実現しよう
ロボットと人間が共生する未来に向け、Pepperを活用した課題解決の方法を探るコンテスト『STREAMチャレンジ2022』。コエテコでは今回、『STREAMチャレンジ』主催者であるソフ...
2024.11.06|夏野かおる
-
「女の子が取り組みやすいプログラミング教育環境を作る」人気プログラミング教室の女性スタッフが語るAfrel ONE...
2020年11月25日の13時から、株式会社アフレルが主催するセミナー「Afrel ONE Mission!」が行われました。 女の子が取り組みやすいプログラミング教育の在り方につい...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
1人でも多くの子どもプログラミングを『Tech for elementary』代表者インタビュー
小学生向けのキッズプログラミングスクール『Tech for elementary(テックフォーエレメンタリー)』。教室は国内外をあわせて200を超えています。今回は、『Tech for...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部