Z会が中学生向けプログラミング講座をパワーアップ。ソニー・グローバルエデュケーション 礒津政明氏に聞く
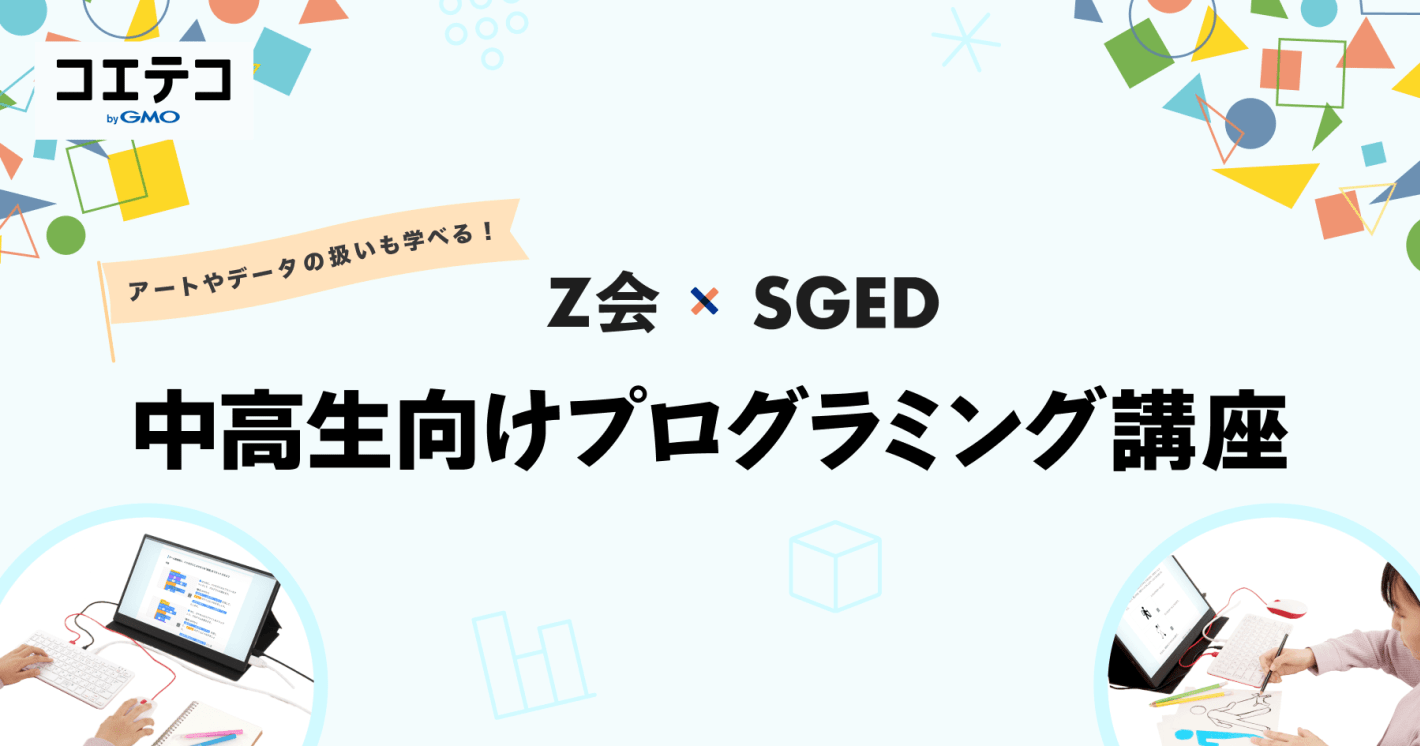
ロボットプログラミング学習キット「KOOV®」などのサービスを提供してきた同社は、2019年よりZ会との協業を開始。2020年には小学生向けの「Z会プログラミング講座 みらい with ソニー・グローバルエデュケーション」の提供を開始し、昨年には小学校高学年~中学生向けの「Z会プログラミング中学技術活用力講座 教科実践編」の提供を開始するなど、プログラミング教育の裾野を広げてきました。
さらに、今年7月には、Raspberry Pi 400を活用した中学生向け通信教育講座「Z会プログラミング中学技術活用力講座 コンピュータ活用編」を開講するそう。
さまざまな形でプログラミング教育にコミットする同社は、日本のプログラミング教育をどう捉えているのでしょうか。そして、Z会との協業により、各種の課題をどのように解決するのでしょうか?ソニー・グローバルエデュケーション 礒津政明会長にお話を伺いました。
自分専用のコンピュータを使った幅広い実践で、必要な知識を押さえつつ、今はもちろん、将来に役立つ知識・スキルをしっかり身につけます。

https://www.zkai.co.jp/z-programming/jr2/ >
習い事市場は“お墨付き”重視
ーSGED様はこれまで、ロボットプログラミング学習キット「KOOV」の開発・提供に携わられてきました。そのご経験を踏まえ、現在の日本のプログラミング教育環境をどう捉えていますか?日本の公教育の課題は、教える内容(学習指導要領の中身)を増やしすぎることです。ダンス、英語、プログラミング……時代に合わせ、新たに必要となったスキルを教えるのはもちろん良いことですが、増やすばかりで減らすことができないのは問題です。児童・生徒や教員の負担が増えていくばかりで、消化不良に陥るのではと懸念しています。
ー民間教育についてはいかがでしょうか。
やはり、必修化の波を受け、ここ数年で情報教育・プログラミング教育が盛り上がってきているのを感じます。しかし、まだ足りていない部分もある。それこそが「専門的な実践」であり、私達が注力したい領域でもあります。
日本では、検定試験への「合格」や、習い事での「級」「段」取得が重視される傾向があります。簡単に言うと、教育の目的が“誰かのお墨付きをもらうこと”になってしまっているんです。
それに対し、情報教育において私たちが大切にしたいのは、コンピュータを使って何かを作り出した経験です。子どものうちからそうした「実践」を積み重ねて引き出しを増やしておけば、生活や仕事の中で課題に直面した時、自分の力で解決することができます。
ですから、「Z会プログラミング中学技術活用力講座 コンピュータ活用編」では、実際に役立つスキルを身に着けていただくことをゴールに据えてカリキュラムを設計しています。内容はのちほど詳しくお話ししますが、決して“お墨付き”を目的とした内容ではないことを強調したいです。
ー「分かりやすい結果」といえば、「情報Ⅰ」が大学入試に新設されるなど、いわゆる受験市場との関わりも見逃せませんよね。
受験関連で私が気になっているのが、中学受験を機にプログラミング教室をやめる子どもが少なくないことです。
中学受験を視野に入れると、遅くとも高学年から塾に通う必要がありますので、そのタイミングでプログラミング教室を辞めてしまうケースが多々あるのです。ここでいったん熱が途切れてしまうためか、中高生向けのプログラミング教育はあまり活発ではありません。
しかし、コンピュータを活用するスキルは、私立中学を受験して難関大学へ行くような子ども達だけが学習するものではありません。今後の社会を生き抜くスキルとして、全ての子ども達が学ぶべきものです。
私達は、中高生がコンピュータについて学べる手段や場所をもっと増やしていきたいと考えています。そういう思いが、今回のZ会さんとの協業につながりました。
Z会に取り組まれているご家庭は、教育に対して熱心な方が非常に多いです。プログラミングが今後の社会で必須スキルとなることもはっきりと認識されています。
いずれは幅広い中高生にアプローチしようと考えておりますが、まずはこうした教育感度の高い方々に私達のサービスを使っていただき、フィードバックを得る中で、カリキュラムをより良くしていきたいと考えています。
クリエイティブな素養が幅広く身につくカリキュラム
ーでは、いよいよ新講座について教えてください。まず、学習用のコンピュータに「Raspberry Pi 400」を採用された理由は?Raspberry Piは値段のわりに性能が高く、「この価格でこれだけのことが出来るんだ」と驚くほどのプロダクトです。もちろん、大人と同じくらい本格的な作業をするのであればより高スペックなパソコンが必要になるでしょうが、入門的な講座であれば、Raspberry Piで十分です。

スペック以外には、キーボード・マウスが使えることも重視しました。GIGAスクール構想により、全国の小中学生にタブレット端末が配られましたけれども、多くはキーボードが標準装備ではなく、マウスがついていることもほとんどありません。しかし、クリエイティブな作業をするならば、これらのデバイスは必須です。その点、Raspberry Pi 400はキーボード一体型のコンピュータであり、マウスもセットで付属しているところが魅力的でした。
―カリキュラムについても教えてください。「Z会プログラミング中学技術活用力講座 コンピュータ活用編」のカリキュラム設計にあたっては、どのような点にこだわられましたか。
コンピュータで出来ることは多岐にわたります。スキルの抽象度が高いので、スポーツのように、「これができるようになった!」と習熟度を明示するのが難しいことがSGEDとしての課題でした。
そのご不安を受け止めた上で、「Z会プログラミング中学技術活用力講座 コンピュータ活用編」では、「作る」体験がたくさんできるようにこだわっています。
コンピュータには、「習うより慣れろ」の側面もあります。ツールの使い方をただ習うよりも、実際に自分で手を動かして物を作りながら、ある種の「感覚」を身につけていただいたほうが、大人になってからもスキルを活かせる可能性が高い。
分かりやすく言えば、大人になって「こういうものが作りたい」と思ったときに、「そういえば、昔こうして作ったな」「あのツールを使えば良いんじゃないかな」と考えられるような、スキルの引き出しを増やして欲しいと考えています。
ーカリキュラム内容について、詳しく教えてください。
「Z会プログラミング中学技術活用力講座 コンピュータ活用編」では、デジタル制作・探究プラットフォームPROC®を使い、学習を進めていきます。
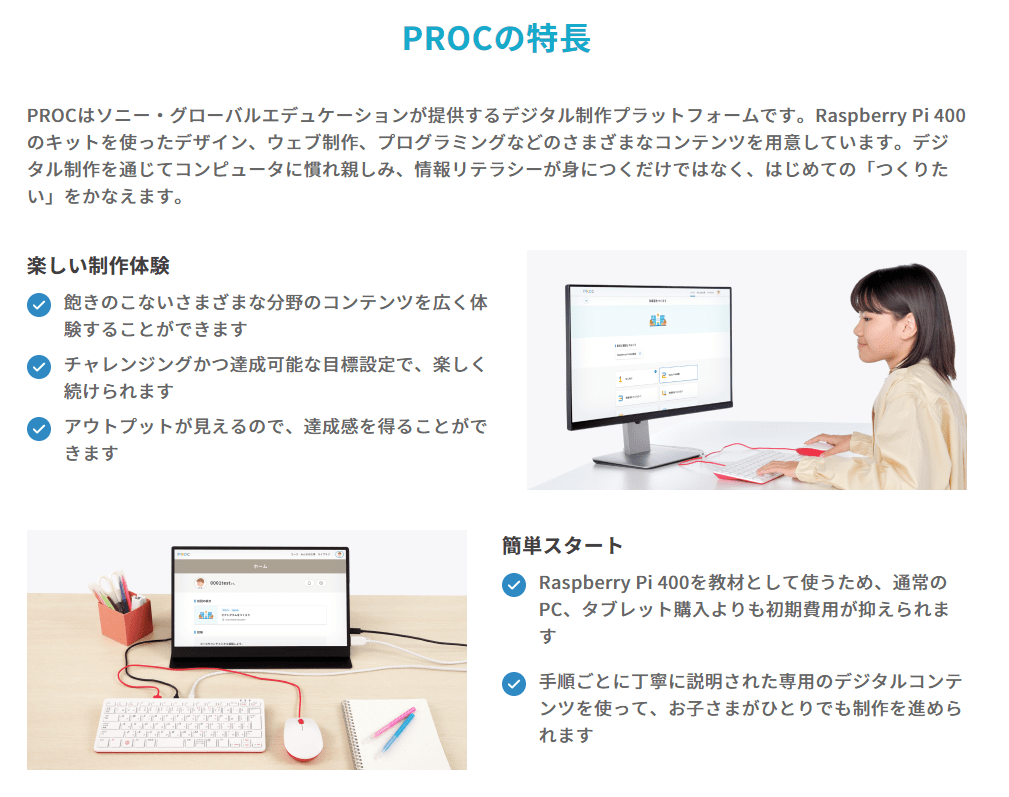
カリキュラムは大きく「マルチメディア」と「コンピュータ&データサイエンス」に分かれており、サウンド(Sonic Pi・Audacity®)やデザイン(Impress・GIMP)、プログラミング(Scratch・Python)、ウェブ制作(HTML・CSS・JavaScript)、データ分析(Calc・Mathematica®)など、ソフトウェアやプログラミング言語を活用した幅広いコンピュータ体験が盛り込まれています。
それぞれのお子さまが得意なこと、好きなことを発見し、才能を伸ばすきっかけをご提供するイメージです。

幅広い内容の中でも、子ども達からの反響が大きかった内容をひとつご紹介しますと、モニターの方々に提供したコンテンツの中でも「ピクトグラムを作ろう」という講座は人気でした。フリーソフトウェアであるImpressを使ってピクトグラムを作っていくのですが、「今まで何気なく見ていたものも、自分で作ってみると見え方が変わった」というコメントが寄せられ、とても嬉しく思っています。
もちろん、その他の内容も力作ぞろいです。くわしくご説明しましょう。
マルチメディア
マルチメディアでは、サウンドとデザインを学びます。サウンドでは主にSonic Piというオープンソースのプログラミング環境を利用します。これはコーディングによって音楽を生成できるもので、効果音やメロディを作りながらオリジナル曲を作っていきます。
実は、サウンドのカリキュラム制作には、東京藝大で作曲を学んだメンバーが携わっています。私も講座内容を見て、非常に勉強になりました。大人でも学びたいような内容に仕上がっておりますので、ぜひ一度ご覧いただきたいです。
デザインでは、画像ソフトのGIMPと、プレゼンテーションソフトのImpressを使って写真加工をしたり、アニメーションを作ったりします。先ほどご紹介した「ピクトグラム」はこの内容の一部ですね。子ども達からの反響も大きく、人気の内容となっています。
コンピュータ&データサイエンス
コンピュータ&データサイエンスでは、プログラミングとデータを学んでいきます。まず、プログラミングは、Scratch・Pythonでのゲーム制作とHTML・CSS・JavaScriptを用いたWebサイト制作を並行して学んでいくのが特徴です。
Scratchでビジュアルプログラミングに触れながらプログラミングの基礎を学び、HTML・CSSでテキストコーディングを学びながらランキングサイトを作ります。その後、Pythonでのゲーム制作やJavaScriptを用いたWebサイト制作に挑戦します。
データでは主に表計算ソフトCalcを用いたデータ処理を学びます。「合計を調べる」「順位を調べる」などの作業を通じて、データ分析に関する知見を深めていきます。中高生の間にデータを扱う素養を身につけてもらうことで、将来、仕事をする際にもデータを抵抗なく見られる人に育っていただければと考えております。
コンピュータは万人の道具。早いうちから訓練を
ー今回の取材で、「Z会プログラミング中学技術活用力講座 コンピュータ活用編」がとても魅力的な講座であることがわかりました。最後に、未来を生きる子ども達に期待することを教えてください。コンピュータを使いこなす技術は、今後ますます重要になっていくスキルです。物事を俯瞰的に見て論理的に正しい判断を下すため、もしくは、自らの手で様々なものを作り出すために、コンピュータは今以上に必要不可欠な存在になるでしょう。
とはいえ、コンピュータの良いところは、訓練さえすれば誰もが使いこなせることです。コンピュータを使いこなすのに、特別な才能は必要ありません。「Z会プログラミング中学技術活用力講座 コンピュータ活用編」を通し、21世紀半ばを生きる子ども達にぜひ、コンピュータスキルという強い武器を持っていただければと願っております。
自分専用のコンピュータを使った幅広い実践で、必要な知識を押さえつつ、今はもちろん、将来に役立つ知識・スキルをしっかり身につけます。

https://www.zkai.co.jp/z-programming/jr2/ >


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
KOOVはプログラミング教育に対するメッセージ ― ソニー・グローバルエデュケーション代表 礒津政明
男女ともに人気があり、大手塾への導入も進むブロックプログラミング教材「KOOV(クーブ)」。今回は開発/運営元である株式会社ソニー・グローバルエデュケーション代表取締役社長 礒津政明氏...
2025.07.31|コエテコ byGMO 編集部
-
Pythonが学べる!個別指導Axisロボットプログラミング講座「アドバンス」の内容とは
個別指導Axisロボットプログラミング講座がPythonを学べる新コース〈アドバンス〉を開講します。その内容とは?株式会社ワオ・コーポレーションの野々宮さん、株式会社ソニー・グローバル...
2024.11.06|夏野かおる
-
名門塾・早稲田アカデミーが、STEM教育プログラム「CREATIVE GARDEN」を開講する理由
2020年2月、中学・高校・大学受験専門進学塾として有名な「早稲田アカデミー」が、STEM教育プログラム「CREATIVE GARDEN」を開講!早稲田アカデミーと株式会社ソニー・グロ...
2024.11.06|KAWATA
-
家庭教師のトライが主催するKOOV™を使ったロボット・プログラミング教室1日体験イベントに行ってみました。
小学生向けに新設されたトライ式プログラミング教室。ソニー・グローバルエデュケーションのKOOV(クーブ)を使ったロボット・プログラミング教室の体験イベントを通して、独自のカリキュラムの...
2025.05.30|コエテコ byGMO 編集部
-
(取材)【グローバル人材の基礎となる学習カリキュラム】英語で学ぶプログラミング『Wonder Code(ワンダーコ...
今回ご紹介するのは、プログラミングと英語を学べる教育カリキュラム『Wonder Code(ワンダーコード)』。ワンダーコードは「プログラミングスキル・英語力に加えて21世紀型スキルが育...
2025.05.30|大橋礼






