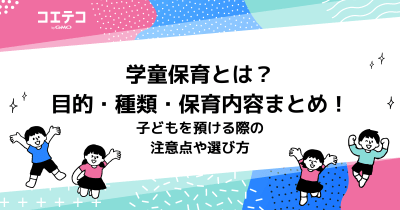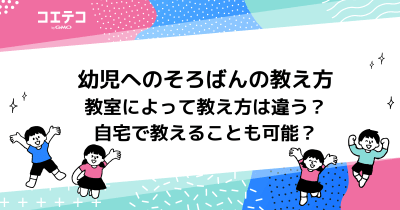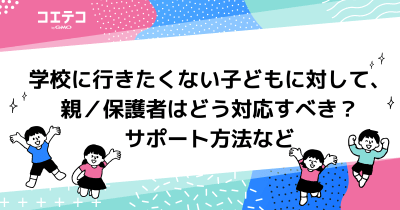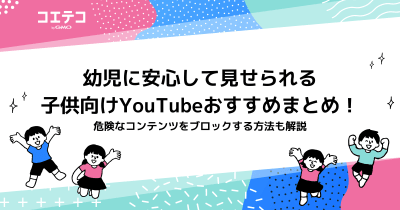小学生の作文がうまくなる書き方は?原稿用紙の使い方も解説

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
小学生のお子さんが、夏休みの宿題や授業の作文を前に「何を書けばよいの?」と固まっていませんか?
いざアドバイスしようとしても、「どう教えたらよいかわからない…」と悩む保護者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、小学生のお子さんを持つ保護者の方向けに、作文の基本的な書き方のルールから、文章がもっと上手になるコツ、そしてお子さんのやる気を引き出す声かけのポイントまで、わかりやすく解説します。
まずは基本から!小学生向け原稿用紙の正しい使い方

作文に慣れていないうちは、上手に書くことよりも、思ったことや感じたことを自分の言葉で文章にする練習が大切です。
まずは、作文の基本となる原稿用紙の使い方をしっかり確認しておきましょう。
原稿用紙の基本ルール9選

1. タイトル:行のいちばん上を2〜3マス空けて書きます。
2. 名前:姓と名の間は1マス空けます。名前の最後の文字のあと(行末)は1〜2マス空けるのが一般的です。
3. 本文の書き始め:段落の最初は、1マス空けて書き始めます。
4. 句読点(、や。): 1文字として扱い、マスの右上に書きます。
5. 句読点の位置:行のいちばん上(行頭)には書きません。行頭に来てしまう場合は、前の行の最後のマスに、文字と一緒に入れます。
6. 小さい「っ・ゃ・ゅ・ょ」:1マスを使い、マスの右側に寄せて書きます。
7. 会話文:新しい行から書き始めます。
8. かぎかっこ(「」):それぞれ1文字として扱います。「 はマスの下側に、」はマスの上側に書くと見やすいです。会話文が2行目以降に続く場合、行頭を1マス空けると、どこが会話なのか分かりやすくなります。
9. 文末のかぎかっこ:文末の句点とかぎかっこ(。」)は、1つのマスに一緒に書きましょう。
まずはこの基本ルールを意識して、どんどん書いてみる練習から始めましょう。
作文が苦手な小学生でもスラスラ書ける!書き方の3ステップ

ここでは、多くの子どもたちを指導してきた作文の専門家、岩下修先生の教えなどを参考に、具体的な書き方の手順を3つのステップで紹介します。
ステップ1:何について書くか「テーマ」を決める
いきなり文章を書き始めるのではなく、まず「何について書くか」というテーマだけを決めましょう。
岩下先生によると、最初に作文で1番伝えたいことをはっきりさせることが、書きやすさの秘訣だそうです。
たとえば、「夏休みの思い出」「好きな給食のメニュー」など、お子さんが書きたいことを一つ選ぶことから始めます。
作文全体のタイトルは、全部書き終わってから決めるとスムーズです。
ステップ2:文章の設計図「構成」を考える
テーマが決まったら、次は文章の骨組みとなる構成を考えます。
岩下先生は「はじめ・なか1・なか2・まとめ」の4段落で書くことを推奨しており、この型に当てはめるだけで、ぐっと文章が整理されます。
| はじめ | これから何について書くかを簡単に紹介します。 (例:「ぼくが1番楽しかった夏休みの思い出について書きます。」) |
| なか1 | テーマに関する具体的なエピソードを一つ書きます。 (例:家族で行った海の話) |
| なか2 | テーマに関する別のエピソードをもう一つ書きます。 (例:おじいちゃんの家でやった花火の話) |
| まとめ | 「なか1」「なか2」で書いたことを通して、自分が何を感じ、考えたのかをまとめます。 (例:「海も花火も楽しかった。来年の夏休みも楽しみだ。」) |
このように、まず簡単なメモでよいので構成を作っておくと、途中で何を書くか迷うことが少なくなるでしょう。
ステップ3:まずは書いてみる!「一文一意」を心がけよう
構成ができたら、いよいよ文章を書いていきます。
文章を書くのが苦手な小学生は、一つの文にたくさんの情報を詰め込んでしまいがちです。
そこで意識したいのが「一文一意(いちぶんいちい)」です。
これは、「一つの文では、一つのことだけを伝える」というルールです。
文を短く区切ることで、伝えたいことが明確になり、すっきりとして分かりやすい文章になります。
最初は完璧を目指さず、まずは構成に沿って最後まで書ききってみることが大切です。
もっと上手になる!作文の表現力を上げる5つのテクニック

基本的な書き方に慣れてきたら、次は文章をより魅力的にするテクニックに挑戦してみましょう。
少し工夫するだけで、読んだ人が「おもしろい!」「もっと読みたい!」と感じるような作文になります。
テクニック1:読者を惹きつける「書き出し」の工夫
作文は書き出しで印象が決まるとも言われます。
いつも「〜について書きます。」から始めるのではなく、読者が「何だろう?」と興味を持つような書き出しを試してみましょう。
簡単に真似しやすい書き出しのパターンを紹介します。
| 結論から書く | 「ぼくが1番好きな場所は、図書室だ。」 |
| 発見から書く | 「とんでもないものを見つけてしまった。」 |
| セリフや会話から書く | 「『すごい!見てみて!』と思わず叫んだ。」 |
| 疑問から書く | 「どうして、あんなことが起きたのだろう。」 |
| 音から書く | 「ザザーッ、という波の音が聞こえてきた。」 |
これらのパターンを参考に、テーマに合った書き出しを考えてみると、作文がぐっと生き生きしてきます。
テクニック2:「楽しかった」を使わずに気持ちを伝える練習
感想文では、「楽しかった」「おいしかった」などの言葉を使いがちです。
教育情報メディア「ソクラテスのたまご」で紹介された、教師の須貝誠さんのヒントに、これらの言葉を使わずに感想を書く練習があります。
たとえば、「お弁当がおいしかった」なら、「どんなお弁当だったの?」「卵焼きは甘かった?」などと保護者の方が質問してあげることで、子どもはより具体的な情景を思い出し、言葉にできます。
「ハンバーグが口の中でとろけるようだった」「キラキラした宝石みたいなゼリーが入っていた」のように、五感を使った表現ができるようになると、文章に深みが出ます。
テクニック3:単調にならない「語尾」のバリエーション
文章を書き終えたら、同じ語尾が続いていないか確認してみましょう。
「〜でした。〜でした。〜でした。」のように同じ語尾が続くと、文章が単調で幼稚な印象になってしまいます。
【修正前】
きのうは、えんそくに行きました。とてもたのしい一日でした。また行きたいと思いました。
【修正後】
きのうは、えんそくに行きました。たくさんの友だちとおしゃべりしながら歩いて、本当に楽しい一日でした。また、みんなで行きたいなと思います。
「〜でした」「〜ます」だけでなく、「〜でしょう」「〜かもしれません」「〜と思います」など、語尾に変化をつけるだけで、文章のリズムが良くなります。
テクニック4:1番伝えたいことを「深掘り」する
作文の中で、自分が1番伝えたいクライマックスの部分は、特に詳しく書いてみましょう。
【修正前】
かけっこで1番になりました。とてもうれしかったです。
【修正後】
ゴールテープを切った瞬間、心臓がドキドキして、うれしくてたまらない気持ちがこみ上げてきました。友だちの声援が聞こえて、思わずガッツポーズをしていました。
このように、その時の気持ちや周りの様子を具体的に書くことで、読者にもその場の臨場感が伝わります。
テクニック5:タイトルは最後に付ける
書き方のステップでも触れましたが、タイトルは本文をすべて書き終えてから付けるのがおすすめです。
文章全体を読み返して、1番伝えたいことが凝縮された言葉を探してみましょう。
先にタイトルを決めてしまうと内容が縛られてしまいますが、最後に付けることで、本文の内容に最もふさわしい魅力的なタイトルを考えられます。
書きっぱなしはNG!上手な作文のための見直しポイント


見直しにより、文章の質が格段に上がります。
誤字・脱字をチェックする
まずは、漢字の間違いや、ひらがなの打ち間違いがないかを確認します。
自分の間違いやすいポイントを知るよい機会にもなり、次から気をつけるようになります。
声に出して読んでみる
書いた文章を、小さな声でよいので実際に声に出して読んでみましょう。
目で追っているだけでは気づかなかった、読みにくい部分や不自然なリズムに気づきやすくなります。
また、少し時間を置いてから読み返すのも、客観的に文章を見つめ直すのに効果的です。
小学生が作文を得意になるメリット

作文を書くトレーニングを続けると、文章力が上がるだけでなく、さまざまな力が身につきます。
メリット1:自分の考えを伝える「表現力」が向上する
作文を通して、自分の気持ちや考えを言葉で表現する練習を重ねることで、豊かな表現力が身についていきます。
最初は拙い言葉でも、書くことに慣れてくると、語彙が増え、より的確で生き生きとした表現ができるようになります。
メリット2:筋道を立てて考える「論理的思考力」が身につく
よい作文を書くには、内容を整理し、筋道を立てて、主張が明確に伝わるように構成する必要があります。
このプロセスは、まさに論理的思考力そのものです。
この力は、算数の文章問題や理科の実験レポートなど、あらゆる学習の場面で必要とされる重要なスキルです。
小学生のやる気を引き出す!保護者の関わり方と声かけのコツ


大人から見れば改善点は多く見えるかもしれませんが、否定的な言葉ばかりでは、お子さんは作文そのものを嫌いになってしまいます。
大切なのは、まず「書けたこと」を褒め、内容のおもしろい点や共感した点を具体的に伝えてあげることです。
その上で、「もっとうまく書きたい」お子さんの気持ちに寄り添い、「こんな方法もあるよ」とこの記事で紹介したようなコツをいくつか提案して、本人に選ばせてあげるとよいでしょう。
「どうしてそう思ったの?」と質問を投げかけ、お子さん自身の言葉を引き出してあげるサポートが、上達への近道です。
作文の書き方をプロから学ぶ!おすすめ通信教育・オンライン教室8選

ご家庭での指導に限界を感じたり、より専門的な指導でお子さんの国語力を伸ばしたいとお考えなら、プロの力を借りるのも一つの有効な方法です。
ここでは、作文に不可欠な思考力、記述力、表現力を伸ばせる、おすすめの作文教室や国語教室をご紹介します。
独学では難しい部分も、プロの指導なら効率的に身につけられる可能性があります。
まずは無料体験などで、お子さんに合うかどうかを試してみてくださいね。
参考:読解力を鍛えるには?
東進オンライン学校小学部

各教科専門の実力講師陣が在籍しているのは、東進オンライン学校小学部です。
東進オンライン学校小学部では、苦手科目の克服だけではなく、夏休みの宿題のサポートや全国統一小学生テスト対策などを行います。
年に2回、全国統一小学生テストと同じ形式の問題が解けることで、知識が身に付いているかを確認できます。
算数の基本的な問題は、その日限りで毎日配信されることが特徴です。
そのため、基礎知識を定着させながら計算力や思考力などを伸ばすこともできます。
先取り学習や戻り学習なども可能であるため、受講生のスキルに合った学習ができることがメリット。
保護者サポートページからは、お子さまの学習状況やお知らせなどの確認が可能です。
・東進オンライン学校小学部
対象:小学1年生~小学6年生
コース&料金:小学1~2年生で月額2,178円(税込)、小学3~6年生は月額3,278円(税込)
※詳しくは教室にお問い合わせください
スマイルゼミ

スマイルゼミでは、適切なサポートを行うため、コーチングを採用。
全国の小学生の学習データやお子さまの性格や特徴、学習状況などをもとに、最適な学習リズムを解析して提案しています。
学習状況に応じた個別のアドバイスも行っており、お子さまのやる気を伸ばすことが可能です。
適切な時間管理により、毎日決まった時間に学習に取り組む習慣も身につきます。
無学年式の学びを導入しており、学年に関係なく復習や予習ができるのも魅力の1つ。お子さまの理解度に合わせて国語力を伸ばすことができます。
タブレット1台で学習が完結するシステムなので、学習が苦手なお子さまでも気軽に取り組めるでしょう。
仲間と競い合って実力を高められる「みんトレ」や学習で獲得したパーツを組み合わせて作りあげる「マイキャラ」など、学習を楽しめる要素も満載です。
すらら

学習対象範囲は小学1年生~高校3年生までですが、学年を超えて勉強できる「無学年方式」を取り入れているため、分からないところを学年をさかのぼって苦手を克服できるようになっています。
すららでは長文読解ができるようになることを目標として、文字や語彙の習得から始め、文章の構成を理解できるようになったら一文の読解へとステップアップをしていきます。
一文を正確に理解できるようになったら、次は1~2段落程度のまとまった文章の読解を行っていく形で段階を踏みながら読解力を鍛えていけます。
授業は個性豊かなキャラクターたちが先生として、生徒である子どもへ質問をしながら進める対話型となっているため、楽しみながら学習ができます。
作文に必要な理解を深められるようにしっかりと説明されているうえに、AI搭載のドリルではつまずき箇所を自動で診断し、理解するために今必要は問題を出題してくれるので、確実に理解を深めながら次へ進んでいくことが可能です。
ベネッセ文章表現教室
ベネッセ文章表現教室は、作文を通じて「国語力」や「読解力」を伸ばしたい小学生におすすめの教室です。カリキュラムは「創作」「描写」「説明」「意見」などの4つのテーマを基盤に、考える→書く→伝えるを繰り返し実践することで、自然と表現力や論理的思考力を育ててくれます。
授業では自分の意見をわかりやすく伝える練習だけでなく、相手の話を丁寧に聞き、互いの考えを尊重する力も重視。
発表の時間を通じて主体性やコミュニケーション力が養われます。
すべてのレッスンはオンラインで行われるため、全国の子どもたちと交流でき、多様な価値観に触れながら学べるのも大きな魅力です。
学年に応じてステップアップする構成で、小学2年生から6年生まで参加可能。
1回90分の授業を月2回受講するスタイルで、地元の学校や塾では得られない「言葉で考え、表現する力」をしっかりと伸ばすことができるでしょう。
ピグマキッズセレクト ウィズダムアカデミー
3歳から小学6年生までを対象とした、習い事と送迎サービスつきの民間学童として注目を集める「ウィズダムアカデミー」。30種類以上ある習い事の1つが「ピグマキッズ」です。
大手学習塾のサピックス(SAPIX)が開発した小学1年生から4年生向けの教材を使用し、まだ長い文章を読むことに慣れていない子どもたちに対しても、文中のキーワードを的確に把握する方法を専門指導員が丁寧に指導します。
子どもたちが楽しみながら考えられるような問題が多数そろっており、「論理的思考力」「記述力」を段階的に習得できます。
子どもの文章力に対する相談を保護者から持ちかけられることも少なくありません。
そのため、一人ひとりのレベルや特徴に合わせ、身近な事柄を短文で表現するような授業も実施し、文章を書くことや作文に対する苦手意識を自然と取り除いていく取り組みにも力を入れています。
KEEʼSこどもスピーチスクール オンライン
「KEEʼS(キーズ)こどもスピーチスクール」は、企業のトップの方々も話し方について学ぶKEEʼSのプログラムを子ども向けに構成した教室です。現役のアナウンサーから発声や腹式呼吸、話し方の基本的なスキルを学ぶことができる点が魅力で、スピーチにおけるさまざまなノウハウを身につけることで、人前での発表が苦手だった子どもも、堂々と発言できるようになったり、聞き取りやすい声で自分の意見を表現できるようになります。
また、ただ話をするだけでなく、ロジックツリーを用いて伝えたいことを論理的、効率的に組み立てる思考法もレクチャーします。文章作成に必要な構成力なども身につくでしょう。
未来こども教室 かきかた書道教室
「未来こども教室」は2008年に設立。「将来本当に役立つ能力」に着目し、子どもたちにさまざまな力を身につけさせることを目的としています。「かきかた書道教室」で学ぶことができるのは、鉛筆を使用する「かきかた」、毛筆を使用する「書道」の2コース 。どちらのコースでも、文字の美しさを際立たせる線の書き方を大切にしながら、オリジナルの教材を用い、お題の文字を書く練習をくり返します。
進級するにつれて漢字の難易度が高まっていく ため、チャレンジ精神ややり抜く力を育みつつ、先生からの指導を通じ、より上手に書くための課題発見力や解決力の向上も期待できます。
この「かきかた書道教室」の他にも、「そろばん教室」や「作文教室」などを運営しており、礼儀作法、集中力、正しい姿勢、自己肯定感、そして自ら考え学ぶ力の育成に注力しています 。
進研ゼミ 作文・表現力向上講座
進研ゼミの「作文・表現力講座」は、進研ゼミ小学講座の有料オプション講座です。進研ゼミ小学講座を受講していない人でも利用できるため、進研ゼミ小学講座未加入のご家庭でもピンポイントで申し込みできます。本講座では、作文作詞に必要な「論理的思考力」「豊かな語彙力」「多面的記述力」の3つの能力を伸ばす教材が用いられています。また毎回個別の添削が行われるだけではなく、分かりやすく解説が記述されているため、子ども一人でも無理なく力を伸ばしていけるでしょう。
カラフルでイラストが多い教材も魅力。
子ども自ら解き進めたくなる設計を意識しているだけあり、ワクワクする身近なテーマを中心に構成されています。
飽きることなく、文章作成力を高めていくことができるでしょう。
自宅学習に役立つ!作文が上達するおすすめ本

ここでは、ご家庭での作文練習に役立つ、おすすめのドリルや本をご紹介します。
作文力ドリル
作文力ドリルは、作文入門にぴったりの、ゲーム感覚で取り組めるドリルです。「作文を書こうとすると頭がフリーズしちゃう…。」「何から手を付けたらよいか分からない…。」そんなお子さまにピッタリの1冊。
本書の魅力は、「ことばの威力」「ことばをいじる楽しさ」を感じられる問題の数々。国語の勉強とは一味違った問題・出題形式だけあり、作文嫌い・国語嫌いのお子さまでも興味・関心を喚起されるでしょう。
高学年用の他にも低学年用・中学年用も出版されているため、お子さまの年齢やレベルに合わせて選べる点もうれしいポイントと言えるでしょう。
☆★高学年の作文入門にぴったりの、ゲーム感覚でできるドリルが登場!★☆ 「作文の本はいろいろあるけど、本当にできるかな?」 「作文を書こうとすると頭がフリーズしちゃう...。何から手を付けたらいい?」 ...
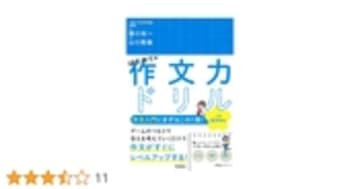
https://amzn.asia/d/hFPJGjT >
10歳からの作文力トレーニング
10歳からの「作文力」トレーニングは、子どもたちの作文力を伸ばしてきた国語指導のエキスパートである茅ヶ崎国語塾の田中弘子氏によってつまずきの要因を丁寧に取り除き、段階的に作文力を伸ばせるよう制作されたトレーニング本。ステップ1では、短い文章がスラスラ書けるよう4つのレッスンを通じて基礎力を養います。
ステップ2では、起承転結の「転」に注目し800字まで書けるように作文力向上を目指します。
最後のステップ3では、中学受験にも対応できる論理的な文章を身に付けていきます。
本書1冊で基礎から中学受験に対応できる応用力まで伸ばすことができます。書籍選びで迷った際は、まずは本書に取り組んでみてはいかがでしょうか。
「作文力」とは、言葉を使って、 自分の考えをほかの人につたえる力です。 声で自分の考えをつたえることもできますが、 声はすぐ消えてしまいます。 けれども、文字であなたの考えを書くことができれば、 遠くにいる人、未来の時代に住む人に あなたの考えをつたえることができます。 あなたの文章を読んだ人があなたに感想をつたえてくれて、 対話をすれば、新しい気づきが生まれます。 作文力があれば、時間と空間をこえて、 コミュニケーションすることができるのです。 この本では、作文を書く前に、 いろいろな文章を音読します。 音読は、目、耳、口を使い、 さらに「音読記号」を書きなが...
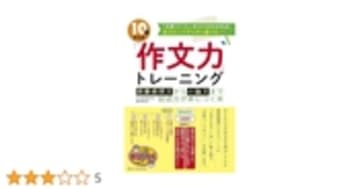
https://amzn.asia/d/hgzVhKd >
まとめ:小学生の作文は楽しむことが上達への近道

小学生向けの作文の書き方について、基本的なルールから表現力を上げるテクニック、保護者の関わり方までご紹介しました。
たくさんのコツがありますが、最も大切なのはお子さん自身が「書くことって楽しいかも」と感じることです。
最初から完璧な作文を目指す必要はありません。
まずは原稿用紙のマスを埋められたことを褒め、お子さんが書いた内容に興味を持って耳を傾けてあげましょう。
ご家庭でのサポートに加えて、必要であれば通信教育や教室などのプロの力を借りるのもよい選択肢です。
焦らず、お子さんのペースに合わせて、書く楽しさを見つけるサポートをしてあげてください。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
学童保育とは?目的・種類・保育内容まとめ!子どもを預ける際の注意点や選び方
そもそも学童保育はどんな場所?誰でも利用できるの?気になる料金はいくら?保育園卒園後の子どもの預け先となる、学童保育の種類と子どもの過ごし方、学童の選び方や実際利用する時の注意点などを...
2025.05.26|コエテコ教育コラム
-
幼児へのそろばんの教え方 教室によって教え方は違う?自宅で教えることも可能?
抽象的な数を「可視化」することができるため、幼児が数を理解するのにとても適しているといわれる 「そろばん」。この記事では、子どもに学ばせたいと思ったときにどのように始めたら良いのか迷う...
2025.04.18|コエテコ教育コラム
-
学校に行きたくない子どもに対して、親はどう対応すべき?
子どもが「学校に行きたくない」と言う理由は?親はどうすればいいの?この記事では、不登校の前兆となる可能性もある「行き渋り」の特徴や、どのようなサポートが必要なのかについてヒントになる情...
2025.12.11|コエテコ教育コラム
-
子供の英語教育はいつから習い始めるのが正解?最適な年齢も解説
小学校から英語の教育が導入されるようになり、早期からお子様に英語に触れてもらいたいと考える保護者が増えている傾向がありますが、英語教育はいつから始めればいいでしょうか。この記事では、英...
2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部
-
幼児に安心して見せられる子供向けYouTubeおすすめ6選|人気なのは?
小さな子どもに長時間見せるには、何かと不安の多いYouTube。ひとまずは見せてしまっているけれど、じつは子どもに悪影響なのでは? と、後ろめたさを感じている保護者の方も多いのではない...
2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部