(取材)天才クリエータを育成・発掘する「未踏事業」とは?|経産省主導、若者の夢とアイディアを応援するプロジェクト
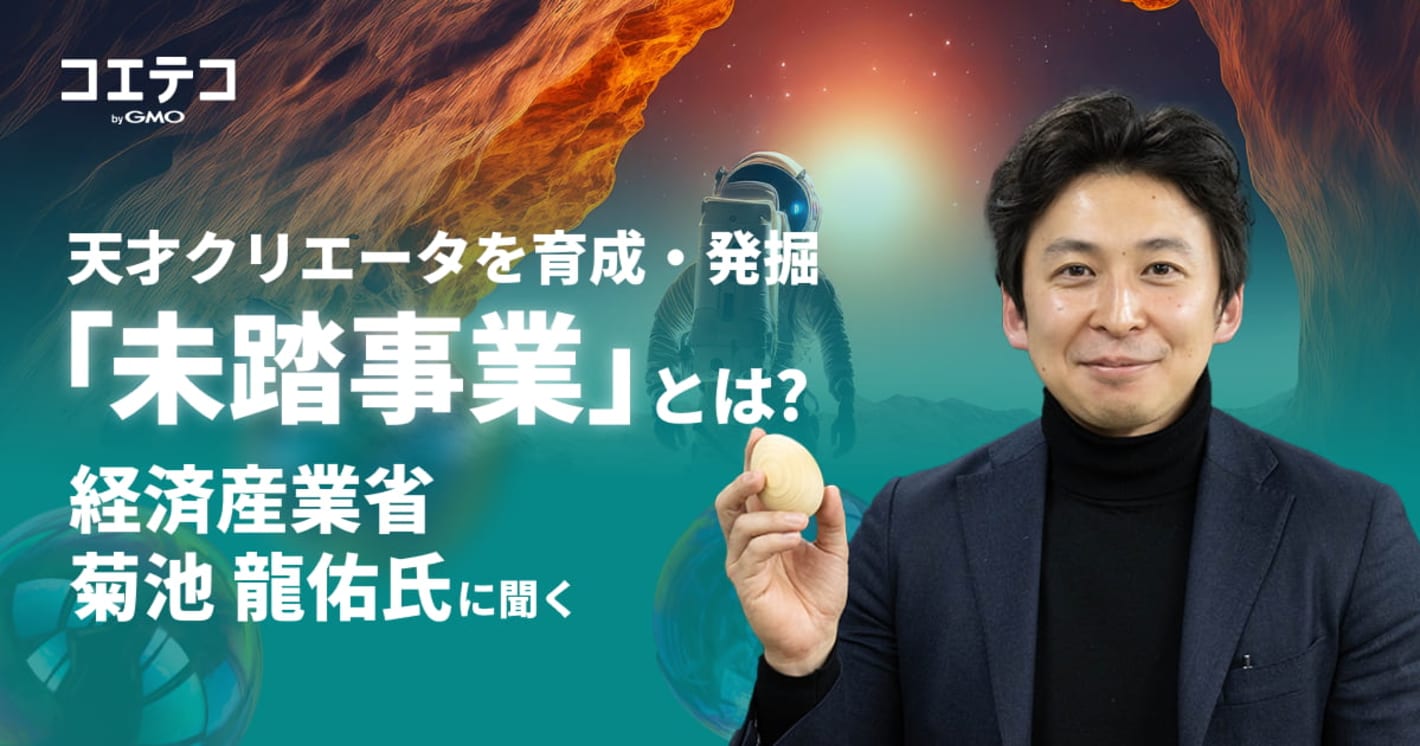

尖った人材を生み出す「未踏事業」
――そもそも「未踏事業」とはどういった事業なのでしょうか。未踏事業は優れたIT人材を育成するための事業です。経済産業省の所管である独立行政法人情報処理推進機構 (IPA)が主催する形で、2000年にスタートしました。
この事業が始まった背景には、日本経済の衰退と世界的なIT産業の興隆があります。1990年代に入るとバブル経済が崩壊して日本経済が停滞する一方、アメリカではWindows95、欧州ではSAP R/3が登場するなどインターネットの時代を欧米が主導し、切り拓いていくことになりました。
IT革命のムーブメントに日本が立ち遅れてしまったことに危機感を抱き、イノベーションを創出し得る突出した個人を発掘・育成し、その突破力をもって、日本のIT産業を世界のトップレベルまで引き上げるため、国を挙げて始めたのが未踏事業です。『日本版のビル・ゲイツ』の輩出を目指すべく、原石を掘り起こし、磨きをかけ、世界に伍するイノベーションの創出を促す狙いではじまりました。
リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/outline.html >
――「個人にフォーカスした人材育成」とは。
これまでの政策アプローチとしては、企業や地域といったある程度大きな主体に対して補助や融資を行うことが一般的でした。それに対して未踏事業では、優秀な一人ひとりの持つ独創的なアイディアを形にする人材育成の形で展開しています。
採択に当たっては、産学界の第一線で活躍されている方々が、プロジェクトマネージャー(PM)として全案件を審査し、合議制ではなくそれぞれのPMが採択するかどうかを判断。採択後もPMが8~9カ月かけて丁寧な伴走型の支援を行っています。
採択されるには、当然ある程度の技術力は必要なのですが、個人の想いも重要です。PMが「この発想は面白い」「この人を育成したい」と感じて採択することができる仕組みになっています。個人の想いや情熱をサポートできることが未踏事業の売りです。
――技術と想いの両方が必要なんですね。アウトプットとしては何を重視しているのでしょうか。
やはり「人材」そのものですね。未踏事業が始まって20年以上が経過し、これまでの修了生は約2000人に上ります。その中にはさまざまな人がいます。たとえばメディアアーティストの落合陽一さんや、一般社団法人ディープラーニング協会の理事長も務められている東京大学教授の松尾豊さん、横浜・山下ふ頭の実物大の動くガンダムのプロジェクトに参画されている吉崎航さん、スマートニュース株式会社代表取締役兼会長の鈴木健さんも未踏の修了生です。
長引くコロナ禍においてデジタル化が急激に加速している今、「社会の当たり前」が日々アップデートされています。最近ではAI(人工知能)も、画像や文章の自動生成アプリなどの登場で身近に感じる機会も増えました。そんなAI領域の技術のひとつとして、ディープラーニング(深層学習)があります。ディープラーニングは、コンピューターなどの機器やシステムが大量のデータを学習・分析し、タスクを実行する技術です。A...


2025/07/03

このように、多様なフィールドで未踏の修了生が活躍されていることが一つの成果だと思ってます。実際に修了生の進路を見てみると、民間企業に就職する方、起業する方、大学で専門家になる方がちょうど3分の1ずつくらいにわかれます。
国として未踏事業修了後の縛りをあえて設けていないところが、この事業の面白さに通じていると感じています。
――開始から20年以上が経過しましたが、未踏事業のミッションに変化はあるのでしょうか。
2022年6月、岸田文雄政権下で「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」が閣議決定されました。この中では、スタートアップの強化が重要な政策の一つとして位置づけられています。
先程ご紹介したように未踏事業修了生にもスタートアップで活躍されている方がたくさんいらっしゃいます。
このような成果からも、スタートアップの強化には未踏事業のような人材育成の強化が求められていることから、実行計画において未踏事業の拡大が定められています。
具体的には、これまでの選抜規模は年間に70人程度でしたが、これを5年後には500人程度に拡大する計画です。

この計画を実現するためには、未踏事業だけではなく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)や国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)等といったIT分野以外においても、取り組みが開始される予定です。
いかに質を落とすことなく目標を達成するかについては、この5年間、試行錯誤しながらやっていきたいと考えています。
――未踏事業の対象はどのような方でしょうか。
未踏は三つの事業にわかれます。①25歳未満を対象とした「未踏IT人材発掘・育成事業(未踏IT)」、②ビジネスや社会課題の解決につなげる「未踏アドバンスト事業」、③次世代ITを活用して世の中を抜本的に変える先進分野に挑戦する「未踏ターゲット事業」です。
3事業共通しているのは、「独創的なアイデアと情熱を持った人を発掘・育成すること」。2022年度はラップバトルをAIで返すシステムやVRを活用した筋力トレーニングシステムといったユニークな成果が生まれています。
「アドバンスト」と「ターゲット」では年齢制限は設けていません。ぜひ多くの方に挑戦してもらいたいです。
日本独自の“シリコンバレー化”に貢献
――いま感じられている課題を教えてください。実際に参加された人からは、「こういうアイディアが浮かんだけれど、日本では法律の規制があり実現できない」と言われることもあります。ところが、他国だったらできるわけです。そうすると中には自由を求めて海外に行く人も出てきますよね。 日本においてシーズをどうやって応援していくかは大きな課題です。

また日本のIT業界の発展のためには、アメリカのシリコンバレーのように新しい技術と優れた人材が育っていく文化をつくる必要があると感じています。
未踏事業は20年以上の歴史がありますので、未踏事業にかかわったPMと修了生によるネットワークの構築も進んでいます。修了後も気軽に相談に行ける環境が生まれるなど、日本でも少しずつではありますが、よい形の文化ができつつあると感じています。
――ぜひ世界で通用するような人材も出てきてほしいですね。
まさにその点も、いま課題として挙がっているところです。未踏事業の修了後、海外でのチャレンジにつなげていくためにも、省内外のさまざまなスタートアップ支援政策と連携させるなど、新しい試みに取り組む必要があります。
また、国内にいる留学生などの外国籍を持つ方のチャレンジも進めたいですね。未踏アドバンストに関しては英語での応募も受け付けており、英語で書かれた募集要項やホームページも公開しています。PMの方々も英語対応が可能ですので、外国人の方々にも挑戦してもらい、未踏事業のプレゼンスを高めていきたいと思っています。
グローバルな視点でさまざまなチャレンジを受け入れていくことは、未踏事業の進化にもつながっていくと考えています。
――どういう人材にチャレンジしてほしいとお考えでしょうか。
IT領域はますます進化を遂げています。そんな中で既存の枠にとらわれず、自分の持つアイディアや夢の実現に情熱をもってチャレンジする場として、ぜひ未踏を活用してほしいと思っています。
国内外で活躍する一流のPMが、若い世代の今まで見たことがないような独創的なアイディアに面白さを見いだし、真剣にサポートしてくれる環境はほかにあまりありません。
ひょっとしたら、それがデファクトスタンダード(市場競争を勝ち抜いた製品や規格が事実上の標準となること )になるかもしれない。自分の発想が世の中を変える可能性があるということは、若い人たちにとっても魅力的だと思います。
アイドルですと、「親が勝手に応募した」なんてよく聞く話ですが、親御さんもぜひお子さんにすすめていただけるとありがたいです。経産省としても、未踏事業の拡大と充実を図り、若い人たちがチャレンジできる環境の構築に努めます。

保護者は子どもたちに選択肢を示し、見守る役割
――子どもたちにとっても未踏は目指す先の一つですね。子どもたちで言えば、未踏事業の修了生や関係者が「一般社団法人未踏」という団体を立ち上げ、事業の一つとして17歳以下の子たちを対象にした「未踏ジュニア」を展開しています。未踏事業とほぼ同じスキームで、PMによる丁寧な伴走支援のもと、成果発表会でその成果を発表する形です。
成果はYouTubeにもアップされていますが、とても小中高生のものとは思えないアイディアや技術を使ったものが多いんです。たとえばカメラによるAI検知で障害物の位置を把握できる盲目の方のための杖や、植物の生体電位を活用して人と植物のコミュニケーションを表現するシステムなど、発想が豊かだと思いますね。
私が小さい頃はミニ四駆で遊んでた記憶しかないので、本当に大したものです。いまやパソコンやデバイスの進化により、できることがずいぶん増えました。いまの若い子たちには可能性しかないと思っています。若いうちからぜひ、未踏ジュニアにチャレンジしてほしいです。

――一方で保護者の中には、子どもがパソコンばかり触ることに不安を覚える方もいます。そのような保護者にメッセージをいただけますでしょうか。
以前、こんな相談を受けました。「夜中までバットの素振りをしていても怒られないのに、夜中までプログラミングをやっているとなぜ怒られるんだろう」。それを聞いて「確かに」と思ったんです。
野球でもプログラミングでも、好きなものに打ち込むことはその子を成長させます。保護者としては「ゲームだ」と目くじらを立てず、応援してあげることが大事なんじゃないかと個人的には思います。
私の子どももゲームを通してプログラミングに熱中していますが、大好きなゲームが題材だと、親が教えなくても勝手に学んでいくんですよね。「それどうやってやったの」と聞くと、「YouTubeで調べた」と返ってくる。すごい時代になったものだと感心します。
若い子たちは、大人よりも速いスピードで新しいテクノロジーやコンテンツに順応します。そこで子どもが「面白い」と思えるものに触れることを応援するのは、子どもが今後の社会のテクノロジーの進化に対応するためにも重要だと思います。
――興味のある分野やその子の強みを伸ばしてあげるとよいというお考えですね。
急速に変化する社会の中では、ぶっ飛んだアイディアや尖った発想こそが世の中を変える鍵になります。親としてはどうしてもできないところに目が行きがちですが、チームで動く場合には、自分ができないところは誰かがやってくれます。それを考えると自分の好きなもの、得意なものをどんどん磨いていくことは、決して無駄にはならないと思います。
保護者の方々におかれては、その上で、ぜひ「こういうものもあるよ」「こういうにイベントに出てみたら」といった選択肢を与えてあげてほしいですね(自戒もこめて)。子どもにとっては何か一つでも自分でつくったり成し遂げた成功体験があると、その経験が生涯の宝物になります。
もちろん、最終的に何を選ぶかは子どもたちの自由です。ただ、その可能性を妨げず、さまざまな選択肢を示すことが大人の使命ではないでしょうか。



Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
2月19日開催「MITOU2022 Demo Day」レポート|ITで世の中の困りごとは解決できる?未踏クリエータ...
2023年2月18・19日、経済産業省およびIPA(情報処理推進機構)が展開する「未踏プロジェクト」の成果発表会「MITOU2022 Demo Day/第29回 未踏IT人材発掘・育成...
2024.11.06|ちとせとも
-
2月18日開催「MITOU2022 Demo Day」レポート|突出したITスキルを持つ未踏クリエータたちが生み出...
2023年2月18・19日、経済産業省およびIPA(情報処理推進機構)が展開する「未踏プロジェクト」の成果発表会「MITOU2022 Demo Day/第29回 未踏IT人材発掘・育成...
2025.05.26|ちとせとも
-
(取材)経済産業省 吉倉 秀和氏|スポーツ×テクノロジーが育む、これからのAI時代に必要な論理的思考力
スポーツを経済の面から捉え、スポーツの成長産業化をテーマに取り組みを行う経済産業省のスポーツ産業室。スポーツ産業室が目指すこと、スポーツと論理的思考力の関係、ICTが拓く新たなスポーツ...
2025.04.22|大森ろまん
-
『チェンジ・メーカー』を作ろう!日本の教育現場をもっと贅沢に―経済産業省 教育産業室長 浅野大介さん
驚くべきスピードで変化し続ける現代社会において、今の日本の教育は改めてその在り方を問われている中、将来の日本を背負って立つ子どもたちの育て方や今後の教育の在り方などを経済産業省商務・サ...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
子ども達の「未来を生き抜く力」を育てるために、学習を個別最適化|株式会社COMPASS 代表 神野元基氏インタビュー
子ども達に効率的な学習を提供するAI型タブレット教材「Qubena(キュビナ)」を開発・提供している株式会社COMPASS。 開発以降、サービス導入先も年々幅広い業態に拡大、また20...
2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部






