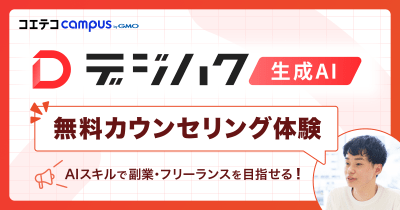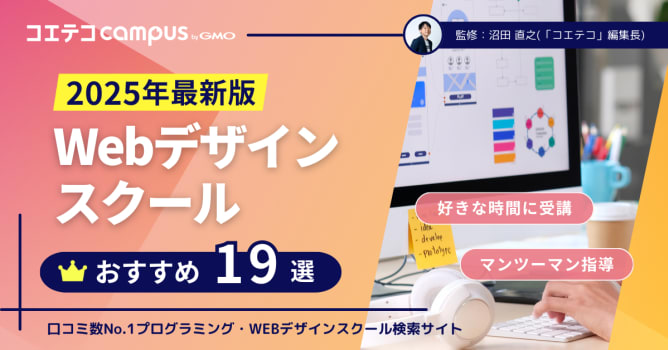(取材)AIを活用し、活躍するビジネスパーソンを育成。日本ディープラーニング協会が目指す、一億総AI人材社会

-
今回お話を伺った方
-
一般社団法人日本ディープラーニング協会 専務理事
岡田 隆太朗氏2017年から日本のディープラーニング業界を牽引し、産業活用の促進やデジタル人材教育に貢献。日本ディープラーニング協会(JDLA)事務局長(取材当時)として活動中。
-
そんなAI領域の技術のひとつとして、ディープラーニング(深層学習)があります。ディープラーニングはコンピューターが自律して大量のデータを学習し、人の手を介さずにデータ内から特徴を見つけ出す機械学習の技術的手法で、データ分析はもちろん、画像認識や音声認識、自然言語処理など様々な領域で活用が進んでいます。
仕事の効率化が進む一方で「AIが人間の仕事を奪う」なんて噂話を耳にすることもありますが、実際のところはどうなのでしょうか。AIが台頭しつつある社会において、身につけておくべき知識や心構えとは?
そんな疑問や不安を解消すべく、2017年から日本のディープラーニング業界を牽引し、産業活用の促進やデジタル人材教育に貢献してきた日本ディープラーニング協会(JDLA)事務局長の岡田さんにお話をうかがいました。

日本ディープラーニング協会(JDLA)事務局長 岡田 隆太朗さん
デジタル人材育成で、産業競争力を向上させる
ーまず、協会を設立された目的と、活動内容について教えてください。日本ディープラーニング協会は、ディープラーニング技術を活用して、日本の産業競争力を向上させることを目指して2017年6月に設立されました。日本の産業において高い生産性と収益性を実現させるために、公的機関や企業と連携して人材育成事業や産業促進活動をおこなっています。
当会の理事長であり、東京大学大学院工学系研究科の教授を務める松尾豊先生が『人工知能は人間を超えるか』という書籍を2015年に出版した当時は、ディープラーニングが圧倒的成果を出し始めていた時期でした。しかし、欧米では活用のフェーズに入っているにも関わらず、日本の産業界では導入すらあまり進んでいない状況だったのです。
そこでディープラーニングを事業の核とする企業と有識者が中心となって、世界が注目し、大きな成果が出ている技術を日本でも社会実装するために協会を設立しました。
ー社会実装するためには、具体的にどのような取り組みが必要なのでしょうか?
まずは人材育成です。ディープラーニングを日本の産業に根付かせて発展させていくには、ディープラーニング技術を事業に活用するための企画・導入スキルを持ったジェネラリストと、ディープラーニング技術を用いて開発・実装するスキルを持ったエンジニアが必要です。
そういった優秀な人材を生み出していくために、当協会ではジェネラリストを認定するG検定、エンジニアを認定するE資格という資格認定試験を実施しています。

現在までに6万人を超える有資格者が誕生し、近年では企業の団体受験も増えています。企業の代表が自ら受験するケースもあり、ディープラーニングを取り巻く世の中の流れが着実に変わってきているのを感じています。

団体受験をした企業の一部
中小企業と大企業のAI格差
ー「世の中の流れが変わってきた」とのことですが、具体的にはどのような変化が起きていると感じていますか?経済産業省によるリスキリング施策など、国を挙げてデジタル人材の育成を推進していることが、社会に大きな影響を与えていると感じています。
社会人が新たなスキルを手に入れようとする場合、これまでは個人の裁量で学習や資格取得をおこなうリカレント教育が主流でした。いっぽう現在では、企業が率先して社員に学びの機会を与え、事業の発展を促進するリスキリングが注目されています。
日本では就職や転職時に最終学歴や再就職歴が重視されるケースが多いですが、海外ではリスキリングによって習得したスキルなどの最終学習歴が大きく評価されるんです。
日本でも近年はリスキリングしたことを転職の武器にしようという取り組みが進んでいて、Googleを主幹事として設立された日本リスキリングコンソーシアムには、総務省、経済産業省、デジタル庁、地方自治体が後援・協力団体として名を連ねています。
今後は就職や転職をする際に、財務諸表に加えて、どういった教育環境を提供してくれるのかという基準でも企業を判断するようになっていくでしょう。実際に現時点でも、マネージャーなど一定以上の役職についている社員は全員G検定を受ける企業や、G検定やE資格を取得するとそれぞれ月給が数万円アップする企業も出てきています。

ーG検定やE資格の取得を推進しているかどうかは、就職先企業を判断する際のわかりやすい指標になりそうですね。受験者数も増えていくなかで、実際にディープラーニング技術が普及してきたと感じるシーンはありますか?
コロナ禍においてデジタル化が進み、政府の施策なども後押しとなって、企業のAIの導入・実装の面ではかなり普及してきた印象です。しかし、大企業の多くが導入に積極的な姿勢を見せるのに対し、中小企業においては、まだ検討も十分に進んでいない状況かと思います。
ソニービズネットワークスの2022年最新AI導入状況調査によると、「AIの導入を検討しているか」との問いに対して、「現段階で検討していない」と答えた大企業は3割未満でしたが、中小企業では7割にも及びました。日本の企業のほとんどが中小企業なので、この課題をクリアしていかないことには、日本全体の産業競争力の向上につながってこないと考えています。
「AIは仕事を奪う」は誤解。理解し、共存すれば不安はワクワクに
ー私たち一般の消費者もAIの知識を身につける必要はあるのでしょうか?これからどんどんAIが当たり前の世界になっていくと考えられますので、知識を身につけておいて損はないと思います。当協会が提供しているAIリテラシー講座「AI for Everyone」は世界で75万人が受講しており、無料で受講できますのでぜひ受けてみてください。

ただ、身につけようと構えなくても、知らず知らずのうちに理解して受け入れていると思いますよ。例えば宅配業者のクロネコヤマトでは一部のサービスでAIオペレーターが電話対応をしていますし、フリマサイト大手のメルカリでも、あらゆるシステムにAIが活用されています。すでにAIが当たり前の社会に生きていると言えるかもしれません。
ー「AIに仕事を奪われるかもしれない」と考えている方もいらっしゃいますが、本当のところ、そういった状況は有り得るのでしょうか?
いえ、確かにシングルタスクにおいては、AIは既に人間以上の成果を出していますが、それがイコールで「人間の仕事を奪う」ことにはつながりづらいと考えています。
AIは大きく分けると「特化型」の弱いAIと「汎用型」の強いAIに分類されます。一時期話題になった囲碁AIは特化型に分類され、その名のとおり特定の作業領域で力を発揮するタイプです。一方の汎用型は作業領域を特定せず、人間と同じように自分で考えて行動し、人間以上のパフォーマンスを実現するものを指します。ドラえもんをイメージしていただくとわかりやすいですね。
特化型のAIがそれなりに高い結果を残しているのに対し、汎用型の強いAIはまだ生まれていませんし、今のところ実現可能性が見えているわけではありません。
例えば、箱の中にパソコン、お茶、スマホを入れたとします。そのうえで、「お茶とスマホを取り出したら何が残る?」と問われたとき、AIは答えられません。
なぜかというと、この問いは空間を認識・理解できなければ答えられない問いだからです。人間からしてみればすごく簡単な問いですが、数式で定義できない問いにAIはうまく答えられません。ですから、現在のところAIがおこなう作業に意味を持ち込んだり、タスクとタスクをつないだりするのは、あくまでも人間。AIが人間の仕事を奪う段階ではありません。
ーAIにも不得意なことがあるんですね。
そうなんです。画像を自動生成するAIアプリが誕生して、イラストレーターの仕事を奪うんじゃないかと言われていますが、それも人間が言葉を入力しなければ生成されません。
ただ、どんな言葉を入れるかで出てくる画像が違うところに着目し、画像生成アプリを使って表現するアーティストも誕生しています。つまり、AIと人間がコラボレーションしているわけです。
一時期話題になった将棋AIもそうですが、AIには、人間の考えでは及ばないアイデアを生み出し、臆することなくチャレンジできる良さもあります。それが人間に新たな気づきを与えてくれたり、クリエイティブに影響を与えたりする可能性は十分にあると思います。

ーそのような事例を踏まえると、「AIが仕事を奪う」ことはなく、AIの導入に付随して新たな仕事が生まれる可能性もあるということでしょうか?
そうですね。AI関連の仕事というと、Pythonをはじめとするプログラミング技術を持ったエンジニアの領域だと感じる方も多いと思うのですが、AIの活用方法を企画して導入する人材も非常に求められています。
企業がAIを導入したいと考えたとき、どんなAIを導入し、どう活用すべきかを判断し、開発するエンジニアと企業の橋渡し的なポジションを担う人材は、今後のビジネスにおいて必要不可欠な存在になっていくでしょう。
G検定を持つジェネラリストは、そのために必要なスキルを保有しています。
検定合格者を100倍に!実現への課題と展望
ー今後さらにAIが当たり前になっていく社会において、企業がとるべき行動とは?事業を成長させていくには会社全体でAIを理解し、活用していく体制の構築が必要です。「デジタルやAIのことはわかりません。担当部署に任せています」という姿勢ではなく、すべての部署が連携できれば、効率化したりグロースしたり、新たな価値を生み出せる仕事がたくさんあるはずです。
部署間の連携、経営層と現場を繋ぐ役割として、G検定保有者の活躍の場は今後も広がっていくでしょう。

ー今後の協会としての展望、それに向けた課題があれば教えてください。
政府が230万人のデジタル人材を育成しようと提唱するなかで、当協会は資格認定を通して6万人以上を輩出しました。日本の産業競争率を向上させるためには、優秀な人材をさらに100倍、1,000倍と増やしていく必要があり、協会としてできること・やるべきことは、まだまだたくさんあります。
資格を取得した方にアンケートをとったところ、約半数の方が「現在の仕事にスキルを活かせていない」と回答しました。これは企業や社会の課題でもありますが、全員が活躍できれば「ディープラーニング技術を活用して、日本の産業競争力を向上させる」という協会の設立目的も達成されると考えています。
そのために協会ができることは技術や知識を常にアップデートし続け、価値ある学びを提供し続けることです。勉強した人が活躍できる社会の実現、ひいては日本の産業界の発展を目指して今後も活動していきます。
デジタル人材を育成し、日本の産業競争力を促進する!日本ディープラーニング協会
デジタル人材を育成し、日本の産業界に大きく貢献してきた日本ディープラーニング協会が認定するG検定とE資格の概要は以下のとおりです。| 資格名 | G検定 | E資格 |
| 受験資格 | 制限なし | JDLAプログラムを試験日の2年以内に修了していること |
| 実施概要 | 試験時間:120分 知識問題(多肢選択式・220問程度) |
試験時間:120分 知識問題(多岐選択肢き・100問程度) 各地の指定試験会場にて受験 |
| 試験会場 | オンライン実施(自宅受験) |
申し込み時に、希望会場を選択 |
| 出題範囲 | シラバスより出題 |
シラバスより、JDLA認定プログラム修了レベルの出題 |
| 受験費用 | 一般:13,200円(税込) 学生:5,500円(税込) ※AI For Everyone修了している場合、Coursera受講修了証を提示すると 一般:9,240円(税込)、学生:3,850円(税込)で受験可能 |
一般:33,000円(税込) 学生:22,000円(税込) JDLA会員:27,500円(税込) |
| 申し込み方法 |
「G検定」受験サイト |
一般:ピアソンVUEのE資格受験サイト JDLA会員: 会員用リデンプションバウチャーコード申請フォーム |
G検定は年3回、E資格は年2回の試験が実施されます。資格取得は、デジタル人材として社会で活躍するための第一歩となるでしょう。
試験の開催日程は開催年によって異なりますので、公式サイトをご確認ください。
WRITERこの記事を書いた人
RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
AIセミナーやスクールは怪しい?編集部がデジハクの無料カウンセリングを体験
生成AIスクールと聞いて、「怪しい」と感じる人もいるのではないでしょうか。 今回、コエテコ編集部の中庭が、副業・フリーランスをめざす受講検討者として、「デジハク」生成AIスクール...
2026.01.04|大橋礼
-
(取材)経済産業省 荒木 由布子氏|「すべての社会人にITパスポートを」。生成AIも取り入れた最新のIT国家試験で...
IT系試験の入門編にあたる国家試験として注目を集めている「ITパスポート試験」。現代社会に欠かせないITの基礎知識を身に付けようとする社会人や就活生に普及が進んでいます。 今回は、経...
2025.06.03|徳川詩織
-
【2026年最新版】生成AIスクールカオスマップを公開
2025年最新版の生成AIスクールカオスマップを公開。「仕事に役立つAIスキルを身につけたいけれど、どこで何を学べばいいかわからない」という個人の方や、社員研修を検討中の企業担当者の方...
2026.01.02|コエテコ byGMO 編集部
-
(取材)経済産業省 細川茜氏|「新しいスキルで、新しいチャンスを!」リスキリングで一人ひとりのキャリアアップを支援
2023年にスタートした経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」。なぜいま、リスキリングが必要とされているのでしょうか。 この記事では、経済産業省 経済産業政策局 ...
2025.05.26|徳川詩織
-
スクール選びの決め手は “寄り添うメンター”と“見える成長実感”!プログラミングスクール受講生の口コミ分析調査を実施
この記事では、当サイト(コエテコキャンパス byGMO)に投稿されたプログラミングスクール受講者の口コミ調査結果を詳しく解説しています。スクール受講中の満足度や学習スタイル、モチベーシ...
2025.08.27|コエテコ byGMO 編集部