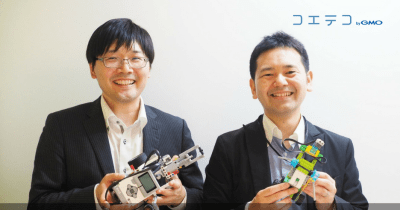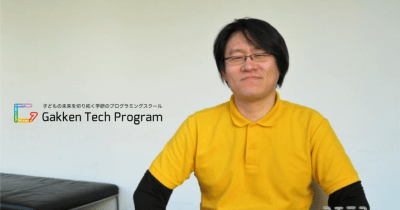勉強がもっと好きになる!学研のロボットプログラミング教室「もののしくみ研究室」

全国に学習塾を展開し、教育系分野のパイオニア的存在の学研グループ。そんな学研グループでは以前にご紹介した「Gakken Tech Program(学研テックプログラム)」(https://coeteco.jp/articles/10076)というイベント的な形態のプログラミングスクールと、子どもが定期的に教室に通うスタイルの「もののしくみ研究室」を展開しています。
今回はこちらの「もののしくみ研究室」について、学研エデュケーショナル「もののしくみ研究室」編集長の前原達也さんと、営業部コンテンツ事業室営業推進課課長の山本聡志さんにお話を伺いました。
身近にあるモノの仕組みを学ぶプログラミング教室
Q. まず「もののしくみ研究室」を立ち上げられた経緯をお伺いできますか?そもそもプログラミング教育の必要性については、兼ねてから言われていたことでしたので、学研グループ全体で企画がいくつも上がっていました。会社としても論理的思考を高める商品に注力していこうという流れがあったのですが、「”まなび”をたのしく!」というグループビジョンと今ひとつ合致しないという問題がありました。
その中でアーテック社が手がけるアーテックブロックの紹介もあり、身近にあるモノを扱うことで子どもたちの興味を引くというコンセプトであれば、心に残る学習ができるのではないか考え、スタートしたのが「もののしくみ研究室」です。
算数、理科、社会など教科を横断的に学習できるのが強み

Q. 身近なものに興味を持ってもらい、学びを楽しくするというコンセプトは素敵ですね。他のプログラミング教室との違いやおすすめポイントはありますか?
弊社自体が小学生向けの『科学と学習』という学年誌から始まった経緯があるので、そういった「身近にあるモノの仕組みを知る」という切り口でテキストを作りました。
他のスクールだと子どもたちが楽しく学べるように漫画にしたり、キャラクターを登場させることもあると思うのですが、うちではあえて算数っぽい書き方をしたり、社会科の教科書っぽい書き方をしています。これは子どもたちが「勉強って将来なんの役に立つの?」と疑問に思っている場合が多いので、プログラミングのテキストに学校で習ったような算数や社会などの知識を取り入れることで、「勉強って役に立つんだ!」と実感して欲しいという狙いもあります。
プログラミングだけでなく算数や理科、社会、さらには雑学などの知識も盛り込み、様々な教科を横断的に学習できるというのは、他スクールにはない強みだと思います。
論理的思考に加え、読解力も身につくカリキュラム

Q. 確かに勉強が実際に役立つ場を作ってあげることは大切ですよね。具体的にどのようなカリキュラムを組まれていますか?
講座は1回90分で月2回の頻度。1ヶ月に1テーマを学んでいただいて、全部で3年間用意しています。1年目はプログラミングの基礎とブロックの扱い方に慣れるプログラムが中心です。2年目はフローチャートを効果的に利用しながら、プログラミング的思考を重視するカリキュラム。3年目は論理的思考に加え、プログラムとロボットの形状から何が書かれているかを読み解く読解力を身につけることを重視したカリキュラムになっています。
講座のスタイルや進め方について「こうして欲しい」ということを強要はしておらず、基本的にそれぞれの学習塾、講師の方々のベストなスタイルでお願いしています。ただ、先生1人に生徒が4〜8人を推奨させていただいています。子どもたちには90分の授業でプログラミングを学んでもらうだけでなく、学んだことを活かしてさらによくするにはどうすればいいか?というところまでを考えてもらうようにしています。
先生も一緒に学び、子どもたちの創造性や自主性を育む

Q. 先生の育成はどうされていますか?
「もののしくみ研究室」は大手の学習塾に多く取り上げていただいているのですが、先生はプログラミングのプロではなく教育のプロにお願いしています。これはプログラミングのプロの場合、子どもたちに教えすぎてしまい、子どもたちが試行錯誤することや、想像力を働かせることをやめてしまう可能性があるからです。
講座は全てにおいて先生の予習用兼講座用の映像を用意しています。先生たちには予習してもらった上で、口頭で教えてもらったり、わかりづらい部分は映像を使ってもらったり、細かいやり方などは各学習塾の方針に合わせていますね。
ちなみに、各学習塾さんには「学習塾がやるプログラミング講座」という建てつけでお願いしており、保護者や子どもたちに向けて「もののしくみ研究室」のことを「習い事」と言わないようお願いしています。これは「もののしくみ研究室」はプログラマーになるため、ロボット工学を学ぶスクールではなく、勉強につながる、勉強が好きになる教科の一つと考えているからです。以前に保護者の方にリサーチした際「スポーツの習い事をしながらプログラミングをやりたい。そして勉強につながるようにして欲しい」という要望が多くあり、そのお声を反映しているという背景もございます。
ものづくり企業の取り組みを社会科見学しながら、プログラミングを学ぶ
Q. 勉強につながる、勉強が好きになるプログラミングというのは、保護者にとってありがたいことですよね。ちなみに講座内容でこだわっている点はありますか?
例えば、洗浄機能付きのトイレを作る回があるのですが、いきなりロボットを作るのではなく最初に洗浄機能付きトイレの仕組みを学びます。その後ロボットを組み立て、プログラミングを作るのですが、1時間目で洗浄機能が使えるトイレを作り、2時間目に座った時だけ洗浄機能が働くトイレを作るなど、ステップアップするようにしています。
さらに洗浄機能付きトイレの回ではTOTO株式会社へ取材した内容もテキストに掲載しており、洗浄機能付きトイレが普及するまでの歴史や現在に至るまでの企業の試行錯誤も学ぶことができます。他のテーマの際も同じような形で企業インタビューを載せているので、ロボットプログラミングを学びながら、社会科見学も同時にできるようにしているのはこだわっている点ですね。企業がやってきたことを後追いする形で学んで、最終的には自分たちなりに考えたものを加えて、企業が作ってきたものを超えられたらいいね、と思っています。
さらに先日、実際に子どもたちが工場見学をした後にロボットプログラミングをしたらどうなのかということを総務省のプロジェクトで実験的に実践したところ、いい効果があり、関係者からも感動のお声をいただきました。
ただロボットを作るだけでなく、子どもたちが自分で考え工夫する力をつける

Q. 企業の取り組みまで学べるとは、まさに教科を横断したプログラミング講座ですね。ちなみに「もののしくみ研究室」では教材としてアーテックブロックを採用されていますが、どんな理由があったのでしょうか?
アーテックブロックは縦・横・斜めに繋げられ、専用パーツを用意しなくても様々な形状にできます。そのため、子どもたちが自分でアレンジして作ることができ、それぞれが自由な感性で想像力と個性を発揮できるというのが選んだポイントです。
カリキュラムでは自動ドアを作る回があるのですが、作った後に余った時間で「今日は自動ドアを作ったけれど、もっと安全な自動ドアを作るにはどうしたらいいと思う?」というような課題を先生が出します。そうすると、前回の講座で信号機の仕組みを学んでいるので、自動ドアの前に信号機を設置する子がいたり、音を出す歩行者用信号機も学んでいるので、音を出す自動ドアを作る子がいたり、それぞれ創意工夫してオリジナルの自動ドアを作るんですよね。これがアーテックブロック以外の他のロボットでは難しいんです。
私たちはただロボットを作るだけでなく、さらに子どもたちに自分で考えてもらいたい。モノを作って終わりにしてしまうのは非常にもったいないと思っています。そのため、テキストで学んで、モノを作って、学習した内容をもとに自分なりにアレンジを加えて、さらに実生活の中にどのような形でプログラミングが役立っているのか、ということを子どもたちが自主的に発見・探索してくれるような講座を心がけています。
論理的思考、想像力が身につくほか、学力が向上したという声も

Q. そういう学習ですと、子どもたちの「物事をより良くしていこう」という思考も培われそうですね。実際に通われているお子さんの変化や、保護者からの感想を教えてください。
課題解決や論理的思考に加え、新しいものを生み出す想像力が身についたというお声はやはり多いですね。保護者の方からいただく感想としては「学んだことを喜んで話してくれるようになった」「今まで会話があまりなかったのに、送り迎えで子どもがたくさん話すようになった」「勉強が好きになった」「将来の職業について話すようになった」「日本の産業に興味を持つようになった」「勉強や物事を深く考えるようになった」というお声をいただいています。学習塾の先生からは「色々な教科の成績が上がっている」という意見も聞かれました。
教育的な視点で言うと、親子間で会話があればあるほど学力が伸びていくと言われています。特に会話の質が高いほど学力が伸びるんですよね。これは私たちの目指していることでもあるので、嬉しいことです。
Q. 将来の職業について話すようになったと言うのはすごいですね!最後にプログラミング教室を検討されている保護者の方や子どもたちへメッセージをお願いします。
学研のプログラミング講座は、社会に興味を持って、勉強が好きになってもらえる講座です。実生活においていろんなことに興味を持ってもらって、子どもたちには「勉強ってこういうことに役立つんだ」ということを感じてもらえればと思っています。そこから学んだことを、子どもたちには将来やりたいことへ役立ててもらえると嬉しいですね。
編集部コメント
「”まなび”をたのしく!」というグループビジョンに通じたカリキュラムを展開している「もののしくみ研究室」。ただロボットを作るのではなく、自分たちでアレンジを加え、さらにプログラミングが実生活でどのように役立っているかまで自主的に考えられるようなカリキュラムは、他にはないと感じました。また、学研グループは学年誌に受験用テキスト、参考書など教育系出版物に強みを持っていることから、わかりやすく知識をさらに広げてくれるようなテキストも魅力的です。プログラミングを学ぶことも大切ですが、それ以上に勉強が好きになること、勉強につながることを意識されているのが印象的でした。
<もののしくみ研究室>
電話:03-6431-1337(受付時間9:30〜17:00※土・日・祝は除く)
URL:http://robot.gakken.jp/
もののしくみ研究室の口コミや料金、カリキュラム情報をわかりやすく紹介!子供・小中学生向けプログラミング教室の特徴や体験レッスン情報も満載。Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン実施中!運営本部:学研メソッド
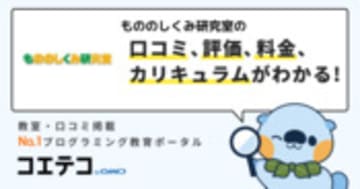
https://coeteco.jp/brand/robot-gakken >
(取材・文/中森りほ、撮影・編集/コエテコ編集部)


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
『学研・ArTec × コエテコ byGMO』 プログラミングワークショップ開催レポート
2018年10月20日、学研・アーテック×コエテコbyGMOによる【もののしくみ研究室出張版!自分だけの「ブロック運びロボット」製作にチャレンジしよう!】 が開催されました。STEAM...
2024.11.06|Amati
-
プログラミングを通じて楽しく学ぶ姿勢が身につくエデュケーショナルネットワークの「ロボットアカデミー」
Z会グループの株式会社エデュケーショナルネットワークは、2015年4月よりロボット製作&プログラミング教室「ロボットアカデミー」事業を開始。フランチャイズの教室を募り、全国に34教室を...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
1日で子どもがプログラミングできるようになる学研のプログラミング教室~その「テキスト」の秘密とは?-Gakken ...
学研ブランドのプログラミング教室は2つあり、ひとつは、子どもが定期的に教室に通う『もののしくみ研究室』、もうひとつが『Gakken Tech Program(学研テックプログラム)』で...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
夢中になれる環境と子どもを虜にするカリキュラムが「考える力」を伸ばすカギ
オリジナルロボットの組み立てから動きの制御、さらには改造まで、ロボット製作の一貫を学ぶことができる、ヒューマンアカデミーが運営するロボット作りの教室。今回は東京都多摩市にある落合教室を...
2025.06.24|KAWATA
-
Robloxでプログラミング!楽しみながら学ぶ「デジタネ」の魅力を開発者と代表が語る
小中学生向けプログラミング教材「デジタネ」のRobloxコースなら、ゲーム制作を通して楽しくプログラミングスキルを習得できます。Roblox社公式教育機関であるエデュケーショナル・デザ...
2025.09.10|大橋礼