サッカーほど知的持久力が必要な競技はない ― Jリーグ 村井満チェアマン

-
今回お話を伺った方
-
Jリーグチェアマン
村井 満氏早稲田大学卒。リクルートで執行役員・CSR推進室長等歴任、2008年Jリーグ理事に就任し、2014年から第5代Jリーグチェアマンに抜擢。財政危機にあったJリーグを「DAZN」放映権契約(2100億円)や、ネット配信/地域活性化施策等の構造改革で経営再建。“スポーツ×ビジネス”モデル推進で、日本代表・下部リーグまで基盤を拡大。2023年より公益財団法人日本バドミントン協会会長。『東洋経済』『日経ビジネス』『CPA Life Career』など経済誌解説や講演も多い。リーダーシップ、セカンドキャリア支援など人材育成にも注力する経営イノベーター。
-
小学生の習い事として人気のサッカーも、実は論理的思考力が必要とされるスポーツ。
そこで今回は、公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)の村井満チェアマンにお話を伺いました。
サッカーには数学の知識が必要?
――スポーツ系の習い事はいろいろありますが、サッカーはスイミングに次いで人気を集めています。サッカーを通じて身に着く能力には、どんなものがあるでしょうか?私も自分の子どもを少年サッカーに通わせ、6年間くらいずっと朝から晩まで土日も全部付き添っていました。
サッカーは習うことで競技そのものが上達するだけでなく、大きな声を出す訓練にもなるんです。サッカーのピッチ(フィールド)って広いじゃないですか。
キーパーやディフェンダーが前方の選手に、ものすごく大きな声を出さないと聞こえない。さらに状況が刻々と変化してゆくので、要領を得た言葉を正しく選択しないと伝わらない。
だらだら説明している間にもどんどんボールは変わってしまう。大きな声を出して一言で伝えないといけないんです。
数多くの選択肢の中からひとつのプレーを選ぶのと同じように、ひとつの言葉を選択するというのはものすごく重要ですよね。
スティーブ・ジョブスのスピーチのように人の心を打つ言葉が選択できているか、その時、その状況に合わせた言葉が選択できているか。
スクールに通っているうちに、最初はシャイで何も言えなかった子どもも大事な試合になるとはっきりと言えたりするんですよ。
そういう変化を見ると、サッカーのプレーだけを学んでいるのではなく、人間力を学んでいるんだなと感じます。
――子どもたちはやがて大人になり、社会人となっていきます。これからの社会人に必要なスキルは何だとお考えですか?

社会人に必要なスキルのひとつは、キーワードで言うと『オーナーシップ』です。営業に行く時にこの店に行きなさいとかこの資料で説明しなさいとか、ただ指示を受けて動けばいいような、単純な世の中ではなくなっています。
どんどん技術革新が進み、顧客ごと状況ごとに課題は変わります。指示を受けてやっていたのでは、とてもじゃないが解決しえない。自分で考えて判断してソリューションをその場で提供しなければダメですよね。
考えるだけではく、しっかり解決策を提供するところまで求められるようになる、と確信しています。
私の確信が深まるきっかけとなったのは、2014年のブラジルワールドカップでした。開催国であり圧倒的な強さを誇るサッカー王国ブラジルが、ドイツに1-7で圧倒的な大差で破れた試合があって、最終的にドイツは優勝しました。
ちょうどその年に私はチェアマンになったので、ドイツがいったい何をしているのかを調べてみたんです。
その過程で、国際試合に参加中のドイツU-17の宿舎風景のVTRが手に入りました。通常であれば試合開催中の宿舎ですので、フィジカルトレーニングや戦術の打ち合わせなどのメニューがあります。
不思議なことに、それらのメニューの合間に授業1と授業2というのが入っていました。ひとつは数学の授業、もうひとつは地理の授業。全選手に対してほぼマンツーマンの形で教えているんです。
「これは落ちこぼれのための補習授業ですか?」と尋ねたんですがそうではなく、サッカーで勝つためにはこういうトレーニングが必要なんだ、という答えでした。
びっくりして、その映像を何回も見ました。なぜ大会中に数学の授業をやるのか。ドイツがワールドカップで優勝するのとどういう因果関係があるのか。
考えてみれば優勝した14年前、2000年のドイツは欧州選手権の予選で1勝もできずに敗退するチームだったんですよ。14年かけて育成改革をしてきた中で、こうした物事をしっかり考える授業をプログラムに入れたんだということが分かったんです。
それが分かってから私なりにずっと整理してるんですが、サッカーという競技に起因することが実はいっぱいあるんです。
サッカーは基本、屋外でやる競技です。試合が行われる90分の間に、天候の変化ってものすごくあったりするんですよね。
たとえば急に雨が降ってきてスリップしやすくなると、ボールを使ったパス回しが今までとは違った状況になる。あるいは30度を超えるような暑さの中で、90分経ったら相手の疲労度はどのくらいになるのか、自分自身の疲労度はどうなるのか。
太陽の位置がこのあたりで日差しの角度がこのくらいだと、ゴールキーパーの目線に光が入るのか入らないのか。天候の変化ひとつひとつを読みながらプレイすることになります。
また、サッカーはきわめて選択肢の多い競技です。ボールを持ったら右に行ってもいいし左に行ってもいい、前に上がってもいいし後ろに下がってもいい。
ボールを打ったら1塁に走ると決まってるわけでもないですし、ハーフウェーラインのあちらとこちらに活動エリアが限られてるわけでもない。あの広いピッチのどこにどう走っていくかも、すべて本人の自由なんです。
先日、スペイン代表で長らく活躍したイニエスタが日本にやってきましたが、そのイニエスタはぽーんと20mくらい宙に浮かせた浮き球パスを出したりする。平面の前後左右だけでなく、空間を使うこともある。三次元すべてをどう使うかというのは、その選手の判断に委ねられているんです。
それからプレーの選択についても、ドリブルで行ってもいいし、パス出してもいいし、その場でシュートを打ってもいい。ありとあらゆる空間の利用の仕方も、どういうプレイをするのかも、全部自分で考えて判断する。常に状況を判断しながら考えることを迫られる競技です。
次に、サッカーが11人で行う競技ということにも起因しています。1対1なら相手だけを見ればいいんですが、サッカーは第二、第三の動き、変数がたくさんあります。
自由自在に相手は仕掛けてきますので、どういう動きを相手がしているのか、味方がどこのポジションにいるのか、これをすべて頭に入れながらプレイをしないといけない。11人対11人、合計22人で行う競技がゆえに、非常に多くの打ち手があるんです。
さらに、サッカーが足を使う競技であるという点にも起因しています。
たとえば、バスケットのような手を使う競技であればミスは起こりにくい。でも人間が本来苦手な足を使うことで、ミスばかり起こる。プロが90分間やっても0-0で終わってしまうような、1点も入らない試合が数多くあります。
相手の動きを予測しても、相手のプレーが予想外の展開を招いてしまうこともある。瞬時に違う展開になり、そこでまた軌道修正しないといけない。
屋外で、ものすごく行動の自由度が高い競技で、11人が、足を使ってプレーする。
刻々と状況変化が起こり、それを常に観察して考えて、何かひとつの打ち手を判断してそれを仲間に伝えて、伝えたものを統率して、一気呵成に全員でやりきって、やりきった5分後にもう1回状況を観察して打ち手を考えて判断して伝えてやりきって、考えて判断して伝えて、これをものすごく高速でグルグル回していくことができなければサッカーのプレーはできないというのがドイツの考え方だったんです。
こういうプレーを行うための指導が属人的であったり再現性がなかったりすると育成世代への指導は安定しません。ですが、育成方法をメソッドに落とし込んで、多くの人に再徹底するところまでドイツでは行われていました。
サッカーほど知的持久力が必要な競技はない
育成指導のメソッドの中に『オーナーシップ』という項目があります。あるサッカーの練習を見ている評価者がストップウオッチで計測しながら、『オーナーシップ』の項目を見ているんです。
当時の私は意味が分からなかったんですが、要は対戦相手を自ら想定し、どんなクセ・特徴があるのかをしっかり理解したうえで、コーチに「こういう練習をしませんか?」と選手が提案した練習時間が全体練習時間の何パーセントあったかというのを計測しているんですよ。
サッカーは監督がタイムアウトを取ることができない競技です。そして、大きな声で指示を出しても、観衆の声にかき消されて聞こえなかったりします。
あのピッチ上で選手は観察して考えて判断して伝えて、というサイクルを試合中、選手たちは自分たちでやらなきゃいけない。だとすれば、普段の練習時間でもそのトレーニングをさせなければ何の意味もないだろう、と。
試合の『オーナーシップ』は選手自身が持っている。だから練習の『オーナーシップ』も選手が持つ。『オーナーシップ』を持っている人が、提案をして練習をするべきである。それを毎日繰り返していれば、自然と自分で考えるようになるよね、ということなんです。
海外に行っていたある選手が言ってましたが、練習が終わると身体よりも頭がヘトヘトになって動けなくなってしまうそうです。
フィジカルが疲れるのではなく、戦況や戦術をとにかく瞬間瞬間でぐるぐる考えているので、90分練習するともうそれ以上練習できなくなってしまう。サッカーは頭が酸欠になるくらい頭脳を使うスポーツなんです。
ドイツの勝利の裏側にあったものを学び、現在我々も日本の各クラブの育成機関にそのメソッドを入れているところです。
一言で言えば、サッカーほど物を考え続ける、知的持久力が必要な競技はない、ということですね。考えることができなければ、サッカーはできません。
将棋の脳とサッカーの脳は同じ?

Jリーグにモンテディオ山形というクラブがあるんですが、そのクラブがある天童市は将棋の駒を生産している街なんです。
以前、天童に試合に行った時にある将棋関係者の方にご縁をつないでいただいて、渡辺明竜王(現・棋王)と座談会で話をさせていただいたことがあるんですよ。
将棋は9×9の81のマス目で、まっすぐしか行かないとか斜めに行っちゃうとか前後左右行けるとか、いろんなキャラクターを持っている駒を盤上で動かします。刻々と変わる状況の中でどういう手を打っていくか、という思考の将棋の脳とサッカーの脳は同じじゃないかと座談会の中で竜王が仰っていました。
確かに考えてみればサッカーにはそういう要素が多々あります。サッカーはフォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダーのゾーンを真ん中と左右の3×3=9のマス目にヒートマップを分けます。
今はJ1であれば、この選手はこのあたりのゾーンに動いているとか、スピード、加速度がどのくらいか、平均速度がどのくらいか、ダッシュする本数がどのくらいあるか、というデータをすべてデジタルトラッキングしています。データを頭に入れ、選手の特徴を読みながら相手の攻撃を止めに行く。
このやり方は、まるで将棋と同じような手だったりしますね。試合の戦法なんかもサッカーと将棋はきわめて似ていて、サッカーは考えるスポーツだというのが将棋との比較の中で改めて良く分かりました。
サッカーとビジネスに共通する『傾聴力』と『主張力』

チェアマンになってから、多くの世界で活躍している選手とそうでない選手の比較を試みたことがあるんです。
私はもともと人材開発や人事系の仕事をしていて、いわゆる職業適性検査やビジネスマンに必要なスキル、コンピテンシーの分析などをずいぶんやってきた人間なので、社会人に共通する能力とサッカー選手に共通する能力があるのかどうなのか、検証したんです。
対象となったのは、2005年にJリーグに入った100名を超える選手たちです。
その中で、10年後も活躍している人たちに共通する能力は何だろう、と。フィジカルがすごいとか、闘争心や平常心がすごいとか、心技体が人並み外れているとか仮説を立てたんですけど、ほぼほぼ全部はずれました。プロになった時点でみんなそんなのは持っていたんです。
10年活躍した選手に共通していたのは、人の話をよく聴く『傾聴力』という能力でした。
これはやはり、サッカーという競技に起因しています。サッカーはハーフウェーラインの右と左で分かれて行う競技ではありません。どこから相手が飛んでくるかも分からないし、身体的接触も激しいですよね。
自分がフェアプレーをしても相手の悪質なファウルで怪我することもある理不尽なスポーツなので、心が折れることがいっぱいあります。
自分は上手いと思っても監督が使ってくれない、監督のコンセプトに合わない選手はどんなに結果出しても使ってもらえない。人間が苦手な足を使って行うがゆえに、シュートミスがあったり、オウンゴールをしてしまうこともあります。
だから長くやっている選手は、誰もが何度も心が折れているんです。でも折れた心をリバウンドさせる、きわめて高いリバウンドメンタリティーを持ち合わせる選手がいて、そういう選手は共通してものすごく『傾聴力』が高いんですよね。
いろんなものを観察して自分で考えることに加えて、さらに人に聴くんです。どうしたらいいの、と。
2番目に必要な能力は主張力。
傾聴した選手が、観察して考えて判断して伝えてという作業をぐるぐる廻して、「俺はこう思うんだけど」というのを伝える。そしてまた相手の言うことを傾聴して、折れた心をリペアしていくんです。
資本市場で競争相手に敗れることがあったり、自社を出し抜いて新たなすごい製品が競合他社から出たり、相手のセールスがものすごくて商談を途中でひっくり返されたり、何度も何度も心が折れるビジネスのシーンの中でも、折れた心を自分でリペアする能力というのは不可欠です。そして、それはサッカーの中にあるんです。
おそらく、代表クラスで活躍している選手はビジネスの世界に行っても通用すると思います。
――スポーツより勉強してほしいという保護者の方も少なくありませんが、スポーツを通じて大事なことをたくさん学べるんですね。
サッカーに限らず、これまでの話の中にはスポーツ全般に共通する要素がたくさんあるので、子どもたちにはぜひいろんなスポーツをやってほしいなと思います。
世間的にはスポーツは体を動かすだけ、と考えられているかもしれませんが、実は脳の消費量の方が高いんじゃないかと思うときがあります。
スポーツを本気で、ものすごく頭を使い続ける練習をやったら、2時間は長すぎる。せいぜい90分が限界ですね。だらだらと勉強時間を阻害するほど長くやる必要はないんですよ。
子どもたちのサッカーだったら、せいぜい1時間。子どもたちはボールを蹴ってるだけで頭を使ってますから。それで十分だと私は思います。何かを犠牲にしてまでやる必要はありません。
サッカーは世界につながる競技
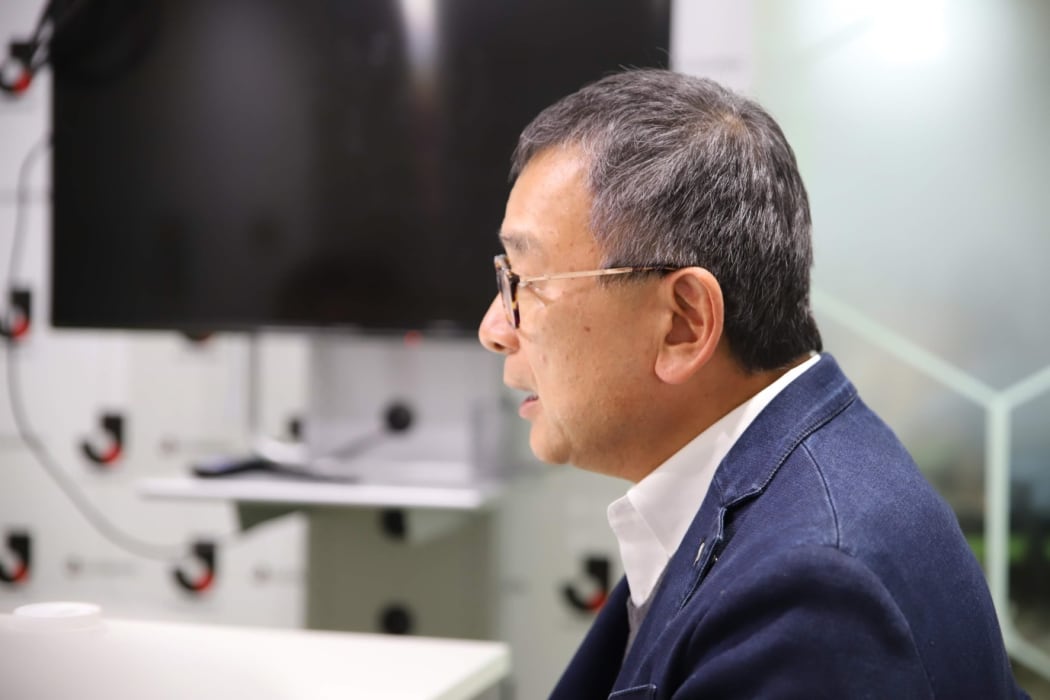
――今の若者はおとなしいと言われていますが、サッカーの世界では積極的に海外に出ていく若者がたくさんいますよね。
サッカーは世界につながる競技です。現在の国連加盟国が193、対してFIFA(国際サッカー連盟)に加盟しているのは211。国連加盟国よりもワールドカップ予選に出るFIFA(国際サッカー連盟)の登録数の方が多い。
世界中で行われている競技なので、たとえば中学生だって高校生だって頑張れば年代別の国際大会に出れますし、Jリーグで言えばAFCチャンピオンズリーグとかFIFAクラブワールドカップ、日本代表で言えばFIFAワールドカップにつながっています。
2019年のJリーグは日本国内の39都道府県にクラブがあります。いろんな地域で国際交流マッチが行われ、チームにも外国人選手がいます。
先日、北海道のコンサドーレ札幌というクラブに「タイのメッシ」と呼ばれているチャナティップというタイの選手が移籍してきました。そのチャナティップの初日練習をタイで視聴した人が300万人もいたんです!
札幌の人口は約200万人。その札幌の人口を超える人数がタイで見ている。ボール1個あれば世界中の人とつながることができるのが、サッカーのものすごく大きな特徴です。
本当にサッカーを極めたい人は最低でも英語は喋れなければいけません。選手たちも国際化していく波に乗り遅れないように、相当言語的な能力をどんどん上げていますね。
そして、さきほどお話しした『傾聴力』もすごく大事です。たとえば本田(圭佑)選手だって香川(真司)選手だって長友(佑都)選手だって、みんなひとりで海外に行ってチームメイトと食事をして一緒に練習していろんな文化を学んで、それを自分の栄養として身に着けていくわけです。
そのプロセスには英語での傾聴、ドイツ語での傾聴が欠かせません。長谷部(誠)選手はドイツ語がほとんどネイティブな状態にまでなって、チームのキャプテンも務めています。サッカーは、言語能力が磨かれる競技でもあるんです。
海外で活躍できる環境が常に身近にありますし、逆に日本にもイニエスタやフェルナンド・トーレスといった多くの外国人プレイヤーが来はじめています。
ヨーロッパに限らずタイやベトナムなどのアジアからも。数年経ったらサッカーは今よりもっと国際化しているでしょう。サッカーが国際社会に飛び出したり、語学を勉強するきっかけになる可能性は十分にあると思います。
――最後に子育ての先輩として、『コエテコ』の読者にひとことお願いします。
子育てには、親の見えていないところが実はいっぱいあります。親のいないところで学校生活がありますし、子どもに自分で考えて自分で行動するという習慣を早く身につけさせるというのが大事だと思います。
思い切って子どもをピッチに突き放してみるといいんじゃないでしょうか。
――ありがとうございました。

プロフィール
公益社団法人日本プロサッカーリーグ チェアマン
村井 満(むらい みつる)
略歴
1959年8月2日、埼玉県生まれ。
県立浦和高校ではサッカー部に所属。
早稲田大学法学部卒業後、1983年に日本リクルートセンター(現リクルートホールディングス)に入社。
同社執行役員、リクルートエージェント(現リクルートキャリア)社長などを歴任。
2008年よりJリーグ理事を務め、2014年1月31日に第5代チェアマンに就任。
公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)
https://www.jleague.jp/
(インタビュアー/GMOメディア株式会社 代表取締役社長 森 輝幸)
(文/冨岡美穂、撮影/コエテコ編集部)


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
(取材)経済産業省 吉倉 秀和氏|スポーツ×テクノロジーが育む、これからのAI時代に必要な論理的思考力
スポーツを経済の面から捉え、スポーツの成長産業化をテーマに取り組みを行う経済産業省のスポーツ産業室。スポーツ産業室が目指すこと、スポーツと論理的思考力の関係、ICTが拓く新たなスポーツ...
2025.04.22|大森ろまん
-
パソコンもタブレットも使わないプログラミング学習?『未来実現IT教室』出張授業レポート
『未来実現IT教室~Children's Technology Challenge~』は、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(以下、CTC)が開発した、小学生向けのIT教育コンテンツ...
2024.11.06|コエテコ byGMO 編集部
-
これからKIDS 築地口教室|名古屋市・慶和幼稚園内に開校!ロボット&マイクラでプログラミング!
「これからKIDS」は4歳から楽しく、自走力や論理的思考力を育むプログラミングスクールです。この度、名古屋市の慶和幼稚園内に、新たに「これからKIDS 築地口教室」を開校!教室は幼稚園...
2025.05.30|大橋礼
-
「思考力ってどう育つ? 生成AI時代の"考える力"を育む方法とは」〜Sony Global Educationの『...
生成AIの時代、小学生に求められるのは“考える力”。ソニーの学習アプリ『ロジックラボ』は、家庭で楽しく思考力や理数脳を育てられます。注目の学び方について、ロジックラボ事業責任者・池長さ...
2025.08.05|鳥井美奈
-
子どもたちにドキドキわくわくしてほしい!「夢を実現するチカラ」を育む『プログラボ』
幼稚園年長~中学生までが対象の「プログラボ」。プログラミング教室なのにプログラミングの習得以上に大切なものを学べるプログラミング教室です。そんな「プログラボ」の論理的思考力や、最後まで...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部







