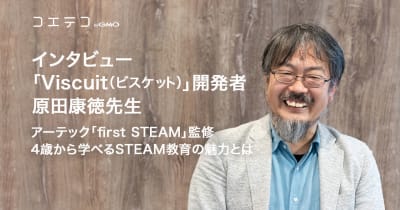「ソードアート・オンライン」がプログラミング教育に与える影響とは?川原礫先生インタビュー

-
今回お話を伺った方
-
ソードアート・オンライン作者
川原礫氏青山学院大学卒業。2002年より自作小説を個人サイトに連載開始、ライトノベル『ソードアート・オンライン』(通称SAO)を2009年に電撃文庫で刊行、以降『アクセル・ワールド』『絶対ナル孤独者』など電撃小説大賞大賞受賞作家として著作40冊超。「ソードアート・オンライン」「アクセル・ワールド」両シリーズともTVアニメ化され、国内外で累計3,000万部以上発行、グローバルに大ヒットとなる。執筆の舞台裏や教育観は『電撃文庫公式』『ASCII.jp』『湯けむりフォーラム』などで度々紹介。次世代型クリエイターとしての発信も目立つ。
-
オンラインゲームという仮想空間を舞台に魅力的なキャラクター達が戦いを繰り広げる本作は、日本の小中高生だけでなく海外のファンも魅了しています。
10月からはTVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』も始まり、ますます人気が加速する「SAO」の世界。
今回はなんと、原作者である川原 礫(かわはら・れき)先生にインタビューする機会をいただきました!
SAOの構想が出来上がった経緯、最近のVRについて思うこと、プログラミング必修化について……など、ここでしか聞けないお話をぜひお楽しみください。

============
「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」
10月12日(土)より各局にて放送開始!
10月5日(土) には、前半戦総集編#0「リフレクション」も放送決定!
TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」最終章(2ndクール)Blu-ray&DVDシリーズ発売中。各配信プラットホームにて配信中。
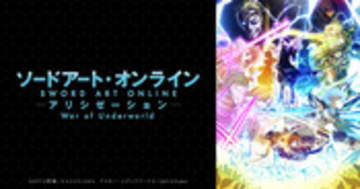
https://sao-alicization.net/ >
============
「SAO」がイメージキャラクターを務める「日商プログラミング検定」紹介記事へはこちら
「日商プログラミング検定」がスタートしました。学習効果を成績化しにくいプログラミング学習において、到達度をはかるのにピッタリの資格と言えるでしょう。日商プログラミング検定の会場となるための手続きを分かりやすく解説しました。
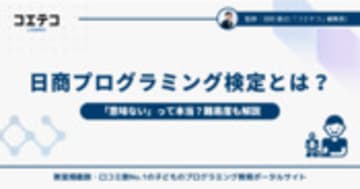

2025/06/24

元々は「応募を諦めた作品」だった

—「ソードアート・オンライン」はオンラインゲームや仮想世界を舞台とされていますが、影響を受けた作品などはありますか?
いわゆる「仮想世界」と出会ったのはSF小説や映画でした。アメリカにはかなり昔から仮想世界をテーマとしたSF作品があり、強く惹かれていたんです。
その後、2000年ごろに「ウルティマオンライン」というMMORPG* と出会いまして。この二つを融合させて「SAO」の構想が出来上がりました。
—「SAO」にはITやプログラミングの知識や用語が多く登場しますね。川原先生ご自身もお詳しいのですか?
いえいえ!私はバリバリの文系で。自分にないものを持った主人公を描きたいという、憧れの表れでしょうね。
一応プログラミングらしきものといえば、同人活動でノベルゲームのスクリプトを書いたくらいでしょうか。プログラミングとはとても言えないレベルかもしれませんが、それでも大変苦労しました。
リファレンスに首っ引きでスクリプトを書いて、失敗して……だけど、楽しさは感じて。小説を書ききったときとはまた違った感動がありました。とはいえ大変だったので、2作目をやろうとは思えませんでしたが(笑)。
—初めは個人ホームページで連載されていたそうですね。どうしてオンライン小説の形をとったのですか?
「ソードアート・オンライン」を書き始めたのは2001年の秋頃で、翌年(2002年)4月の「電撃小説大賞」に応募するために書きました。ところが、規定枚数をかなりオーバーしてしまいまして。内容を削りきれず応募を諦めたんです。
完成した原稿が手元に残され、さあどうしようかな、と。それならホームページに載せてみようか、というのがきっかけでした。
—今でこそWeb発の作品づくりもメジャーですが、当時はまだマイナーだったのでは?
そうですね。出版社の編集者さんも、ネット小説はチェックしていなかったのではないかと思います。
でも、個人のホームページやそれを紹介するポータルサイト、ランキングサイトはあって。知る人ぞ知るメディアのような立ち位置でしたね。
「SAO」がきっかけで理系の進路をとる読者も
—「ソードアート・オンライン」は中高生だけでなく、「Oculus」* の創業者であるパルマー・ラッキー氏など多くの人に影響を与えていますね。今やVRといえば「SAO」を思い浮かべる人も多いのではないかと思います。どうしてここまで大きな反響を得られたのでしょうか。「SAO」を書き始めたとき「ゲーム世界に入っていく」理屈をどう設定するか迷いました。
「魂が吸い込まれる」など半オカルトな設定も検討したのですが、なんとか現在の技術の延長線で説明がつくラインに踏みとどまりたいなと。
ああでもない、こうでもないと頭を絞って……多少強引ではありますが「脳に電波を照射することで色々な感覚を与えつつ、運動命令を回収する」という設定にしました。ちょうどファンタジーとSFの境界線ですね。
ここでなんとかSFに踏みとどまったおかげで、読者の皆さんに「将来、《SAO》は実現可能なんじゃないか」と思っていただけたんじゃないかな。

—影響を受けた中高生の中には、将来のIT技術者をめざす方もおられるのでは。
中高生の読者さんから「《ナーヴギア》* を実現するために理系の大学を目指しています」と言っていただくことがあります。ただ、それに関してはちょっと申し訳ないなと思っていて。
というのも、ブレイン・マシーン・インターフェースを実現するには何十年もかかると思うんですね。脳に直接信号を伝える技術には人体実験が必要不可欠ですが、倫理的にできませんから。
読者が現実にがっかりするかも……と思うと心苦しいのですが、ギャップをなんとか乗り越えていただきたい。
ヘッドマウント型の機器は日進月歩で進化していますし、先日は「テスラ」のイーロン・マスク氏が「ニューラリンク」という会社を立ち上げ、脳埋め込み式のインターフェースに関する発表を行いました。
「SAO」の世界をすぐに実現できなくても、ぜひそうした機器の開発に力を注いでいただければと願うところです。
「VR元年」から3年、映像体験は大きく変わった
—最近はVR教材など、VRを活用したコンテンツも増えてきました。先生もいくつか体験されたと思うのですが、ご感想はいかがでしょうか。2016年は「VR元年」と言われた年で、僕もいろいろなデモを体験しました。すごい技術ですし、感動もしたのですが、求めていたものとはまだ少し差がありました。
たとえば、映像の粗さ。VRでは液晶パネルをレンズで拡大して見るので、液晶の網目が見えてしまうんです。スクリーンドア効果と呼ぶらしいのですが、これが目の疲れにつながっていました。
そこから3年経ち、2019年現在では網目の見えなくらい解像度の高いディスプレイが出てきたり、接続ケーブルのない機器が出てきたりと大きく体験が変わったように感じます。
装着感もずいぶん快適になりましたので、5時間、6時間使っても疲れない機器が近い将来に出てくるんじゃないかと期待しています。
—とはいえ、まだ物足りない部分もあるのでは。
そうですね。まだ解決しなければいけない問題はあると思います。
たとえば、体の動き。全身を動かそうとすると現実の部屋にも広い空間が必要なので、家庭ではなかなか難しいですよね。それに、現状では手の動きしか反映されません。ゆくゆくは足の動きも拾ってもらいたい。
機器自体は省スペースでありながらも、広大なVR空間をどこまでも歩いていけるような仕組みをなんとか私が生きているうちに実現してほしい。そしたら老後はVR廃人になって帰ってこないでしょうね(笑)。
《SAO》は2022年に発売されたという設定で、気づけばもうすぐなんですよ。各企業さんにも希望は伝えているのですが……皆さん、ニヤニヤするばかりです(笑)。

プログラミング必修化はフォローアップが大事
—いよいよ来年度から小学校でプログラミング教育が必修化します。何か感じられていることはありますか?壁を感じたり、全くわからない!とつまずいてしまった子をふるい落とさない仕組みが必要だなと思います。
僕、「センス」って言葉がすごく嫌いなんですよ。僕自身がセンスを持たない側の人間なので。ただ、現実的にセンスを問われる場面というのもあるなと思っていて。
大人だったらいろいろな知識・経験でカバーできますが、子どもはまだ何も訓練されていない。次々に襲いかかってくる未知なる試練にセンスだけで立ち向かっていく必要があるんです。
だから、小学生の段階でプログラミングに触れて「僕・私には無理だ」と思ってしまった子をふるい落とさないで欲しい。「センスがない」と感じてしまった子をフォローアップする仕組みが欲しいですね。
「ゲームは日本」の時代をもう一度
—最後に、「コエテコ」読者へ向けてメッセージをお願いいたします。
現代のIT技術はアメリカの大企業に支配されていると言っても過言ではありません。プラットフォームを抑えた企業が勝者となる。実際、WindowsもMac OSもアメリカ製ですよね。
ゲームも昔は日本がリードしていましたが、今や海外の巨大スタジオが作るようになっていて、対抗できるメーカーといえばソニーや任天堂など大手の会社ばかりです。
日本にも独自のOSを作ろうという時代はあったので、もう一度その流れが来てくれたら嬉しい。「ゲームといえば日本」の時代を若い方々にもう一度作っていただきたい。
「SAO」から興味を持ってくださった方がプログラミングにチャレンジし、今後の社会の経済活動において大きな位置を占めるAIやVRの技術を背負って立ってくださると嬉しいです。
—ありがとうございました。
アニメ最新作は2019年10月〜放映開始!
TVアニメ最新作『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』は10月放送開始!第一弾PVはこちらから。8月18日にはアプリゲーム最新作『ソードアート・オンライン アリシゼーション・ブレイディング』も公開されました!
「SAO」とコラボ!「日商プログラミング検定」はこちら
「日商プログラミング検定」がスタートしました。学習効果を成績化しにくいプログラミング学習において、到達度をはかるのにピッタリの資格と言えるでしょう。日商プログラミング検定の会場となるための手続きを分かりやすく解説しました。
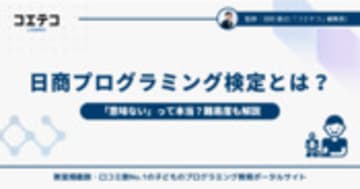

2025/06/24

日商プログラミング検定について日商プログラミング検定は、IT人材の育成を応援します。特徴 1初学者をはじめ幅広い方が対象IT技術者(志望者)の方のみならず、学生・社会...
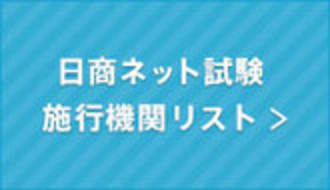
https://www.kentei.ne.jp/pg-special >
リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://twitter.com/sao_anime >


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
12月23日開催「リモロボライブホームルーム(Xmas1時間スペシャル)」イベントレポート|をご紹介
リモロボでは、ロボット講座だけでなくオンライン上で先生や他の子どもたちと一緒に楽しめる面白いイベントが定期的に開催されているのだとか。 今回は、リモロボで開催されたオンラインイベント...
2025.05.21|コエテコ教育コラム
-
「Viscuit(ビスケット)」開発者・原田康徳先生 | アーテック「first STEAM」監修
株式会社アーテックが4歳から学べるSTEAM教育スクール「first STEAM(ファーストスティーム)」を新規開講します。今回は「デジタルアート」のカリキュラムを完全監修された「Vi...
2025.06.24|夏野かおる
-
『embot(エムボット)』開発者・額田さん独占インタビュー|スクール向けカリキュラム開発中、テストマーケティングを予定
「プログラミングってなに?」そんな子どもの問いに優しく答えてくれるのが「私にも作れる!」楽しさを教えてくれる、ダンボールプログラミングロボットのembot(エムボット)です。 今回は...
2025.07.31|小春
-
ほぼ満点!「ジュニア・プログラミング検定」Entry合格者にインタビュー
サーティファイ「ジュニア・プログラミング検定」。Scratchの知識を問うだけでなく、制限時間内に1つの作品を作り上げるという実践的な試験内容が特長です。今回はEntryレベル(4級)...
2024.11.06|夏野かおる
-
(取材)e-Crefus在籍中の親子に聞いてみた!満足度はズバリ◎、中学受験との両立もしやすい!
名門プログラミングスクール・Crefus(クレファス)が2021年4月から始めたのは、なんと!対面授業とまったく同じカリキュラムで学べるオンラインコースe-Crefus(イークレファス...
2025.05.21|夏野かおる