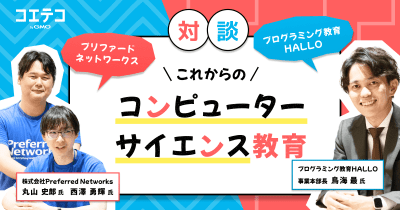(インタビュー)「天才の集まる企業」PFNのプログラミング教育とは?代表取締役CEO西川徹氏

国内屈指のAIスタートアップであり、”天才が憧れるAI企業”と名高いPFNが今回発表したのは、小学生から始めるプログラミング教材「Playgram™」。
なぜ今、PFNがプログラミング教育を手がけるのか?
今回は代表取締役 最高経営責任者である西川徹氏と、開発担当の西澤勇輝氏にお話を伺いました。

代表取締役 最高経営責任者 西川徹氏
Playgram™(プレイグラム)とは?

2020年7月6日(月)、株式会社Preferred Networks(略称:PFN)は小学生から始めるプログラミング教材「Playgram™(プレイグラム)」を発表しました。ソフトウェアが世界を動かす時代に向け、IT人材を育むための入り口を設けるのがねらいです。西川氏は会見で、CSR(社会貢献)としてはもちろん、PFNの新たな事業柱として注力していく決意を語りました。

Playgramにはプログラムを書いて課題をクリアする「ミッション」と、自由自在に自分の空間をデザインする「クリエイト」という2つのモードがあります。ゲームのような見た目と操作感で、子どもが楽しく取り組めるよう設計されています。
教材としての特長はビジュアルプログラミングからテキストコーディングへと段階的に移行できること。"入り口は親しみやすく、奥行きは実践レベル"な教材といえます。今後は株式会社やる気スイッチグループと協業し、プログラミング教室パッケージとして2020年8月より順次導入*される予定です。

Playgramでは同じステージを3パターンでクリアできる。ビジュアルプログラミングからより実践的なテキストコーディングへと徐々に移行していけるのが特長
きっかけは「そこそこの教育」への懸念
—さっそくですが、なぜ御社がプログラミング教育を手がけることを決めたのでしょうか。西川:
やはり、大きなきっかけは小学校でのプログラミング教育の必修化ですね。
それも「マーケットが広がるから」というビジネス上の理由というより、むしろ「大丈夫なのかな?」と心配に思ったことの方が大きいです。
—心配、というのは?
僕は初め、ゲームを作る手段としてプログラミングに触れました。PC-9801とかFM-7の時代です。当時はほとんど誰もパソコンを使っていなくて、憧れの世界でした。周りと違ったことをしている特別感。そんなワクワク感があったんです。

プログラミング教育を広く行うことは重要ですが、その一方で「みんなでそこそこの勉強」となってしまわないか、プログラミングが勉強になってしまうことでワクワク感が無くならないか、子どもたちが「面白い」と感じてくれるんだろうかと。
学校だと「もっとやりたい!」と思っても時間割の都合で止められてしまうかもしれない。その結果、消化不良で「なんかつまらないなあ」と離れてしまう子が出るんじゃないか。そんな懸念が浮かびました。
個人的な経験から言えば、プログラミングのスキルは「1日に1時間」「週に○時間」のようなスタイルで学んでもなかなか向上しないと思います。
寝る間も惜しんで没頭するような体験、作りたいものに向かってどこまでも熱中できることが大切だと思うんです。
—確かに、限られた授業時間でどこまでできるか?は大きな課題となっていますね。
コンピュータサイエンスは急速に発展しており、多くの知見が積み重ねられてきました。どんどん複雑なものを動かせるようになり、表現の幅は広がり続けています。
一方で、学校で「みんな」に一律に教えられるレベルとなると、簡単なものにならざるを得ない。
子どもが実際に触れているのはNintendo Switchとかスマホゲームのようなコンテンツでしょう。子どもの中で、学校で習ったプログラミングとゲームなどの高度なコンテンツがうまく繋がらないんじゃないかと。
もっと高度なものが作りたいのに、授業の内容と大きなギャップがある。このギャップを埋めたいなというのが中心的な問題意識です。

算数にも同じことが言えますね。小学校の算数と中学校の数学って切り離されているでしょう。代数なら代数、と連続して学べばいいと思うのですが、実際は知識がこまめにリセットされてしまう。
義務教育での学びは、人間が学習するしくみと隔たりがあるように感じることがあります。子どもたちが興味を持てないような教え方で教わることにより、パソコンを嫌いになって終わる子どもが出るんじゃないかと。
—体育の授業にも同じ指摘がありますよね。「学校でやるのはイヤだったけど、自分のペースでする運動は楽しい」とか。
プログラミングだと機器の問題もありますよね。本来は全小学校にこの(オフィスで使っている)くらいの端末は配ったほうがいい。
解像度の低い画面で、キーボードも打ちにくくて、何かしようとするたびにモッサリ画面が止まってしまう。それではつまらないでしょう?
—確かに。プログラミングの本質とは関係ないところで、パソコンがイヤになってしまうかもしれません。
今の子にファミコンを与えたら?と考えてみて欲しいんです。
僕たち大人は盛り上がるけど、彼らにとっては「何これ?しょぼい」ですよ。Nintendo Switchで「スプラトゥーン」を遊んでいるほうがよほど楽しいでしょうね。
スターを育てて全体人口を増やしたい
—義務教育化は「国民全体の底上げをはかる上で大切だ」という声もあります。まさに「全員にそこそこの教育」方針を評価する意見ですが、どう思われますか。そのような意見を否定するわけではありませんが、我々としてはできる子、やりたい子をどこまでも育てたいと考えています。
スポーツの世界と同じですね。スター選手がいると競技人口が増えていくでしょう。
すごいものを作っている人を見て「自分も作りたい!」と感じてもらえれば、結果的に全体のプログラミング人口も増えていくのではないかという考え方です。
—プログラミング人口が増加すれば、御社が携わっている製品やサービスにも好影響がありそうですね。
プログラミング教育においては、僕がコンピュータを大好きなように純粋にプログラミングが好きな人を増やせたらいいなと思っています。若い世代にプログラミング好きの優秀な人を増やして、僕たちの会社にどんどん入ってきてもらいたい。
学校でつまらないプログラミング体験をして嫌いになってしまう人が増えてしまったら非常にまずいのは事実ですね。

新しい表現力を得るツールとして
—「プログラミングが好きな人を増やしたい」とのことですが、西川さんの考えるプログラミングの魅力とは何でしょうか。コンピュータさえあれば、物理的な制約を離れてなんでもできるところです。
現実世界でロボットを作って動かそうと思うとお金もかかるし、なかなか難しい。一方でプログラムは、創造力さえあれば音楽も作れるしゲームも作れます。唯一の制約といえば、パソコンのスペックや通信速度の問題ですかね。
スキルと創造力があれば、好きなものを無限に作れる。プログラミングは、イマジネーションを飛躍的に爆発させる手段なんです。
—イマジネーションといえば、御社は本当にさまざまな分野で活躍されていますよね。自動運転、医療、イラストの自動生成など業界の枠に捉われない印象があります。
僕たちが製品やサービスを通して取り組んでいるのは、人の能力をどこまで置き換えられるのか真剣に考えることだと思っています。
世間では「コンピュータが仕事を奪う」など煽情的な意見が目立ちますが、むしろ「コンピュータで置き換えられない人の仕事って、何なんだろう」と考えたい。
弊社にはCrypko™(クリプコ)という、深層学習を利用してアニメの顔画像を自動生成するサービスがあります。リリース当初は「イラストレーターの仕事を奪う」論につながるんじゃないかと不安でした。
ところが蓋を開けてみると、もっとも好意的だったのはイラストレーターさん達自身だったんですよ。
自分の作業を効率化させるために取り入れてみたり、「こういうパターンもアリだな!」と刺激を受けたり。
Crypkoが生成したキャラクターのディテールを磨いて新キャラにしたりと、新しい表現力を得るツールとして受け入れられたのです。
コンピュータと人がインタラクション(交流)しながらお互いの能力を高めていく光景がそこにはありました。非常に印象的でしたね。
「ミッション」「クリエイト」で楽しく学ぶ
—ここまで、PFNが教育にかける思いをお聞きしました。いよいよ「Playgram」についてお話を伺えますでしょうか。西澤:
現状のプログラミング教育の課題は「Scratchなどのビジュアルプログラミングのあと、どうすれば良いのか見えてこない」ことです。
無料で使えるサービスやアプリが増え、入り口の環境は整って来ました。でも「その先」が見えない。一歩踏み込もうとすると非常に高いハードルがある。

「Playgram™」開発担当 西澤勇輝氏
弊社はここに問題意識を抱き「Playgram」を開発しました。画面をご覧ください。

アプリは「ミッション」「クリエイト」など、学習の進捗に合わせたいくつかのステージに分かれています。
「ミッション」では画面上のロボットを動かし、与えられたミッションをクリアしながら基礎的なプログラミングの知識を身につけます。
障害物を避けたり、ループの概念を学んだり。左に曲がるミッションなのに「右に曲がるブロック」しかないなど、子ども達に考えさせるステージも用意しています。

「クリエイト」では、庭の各所に配置されたロボットに命令(プログラム)することで好きな庭をデザインできます。
決められた課題をクリアするゲーム的な要素の強い「ミッション」に対し、「クリエイト」は創作にのめり込めるフィールドです。女の子からも評判が良いですね。

「Playgram」ではビジュアルプログラミングからテキストプログラミングへスムーズに移行できるようになっています。
入り口を広くするため、初めのほうのステージでは慣れ親しんだビジュアルプログラミングで学びます。そこから徐々にテキストプログラミングへステップアップしていくイメージです。
お子さんがテキストプログラミングに親しむ際、大きな壁となるのは「タイピング」「アルファベット(英単語)」なので、ここで詰まらないよう、両者を比較しながらプログラムを書けるようなインターフェースに仕上げました。

子ども達がとっつきやすいビジュアルプログラミング

ビジュアルプログラミングの骨格は残したまま、ブロックの中身がテキストプログラミングのコードに

最終的には完全なテキストプログラミングになる
—全体的にやわらかい印象でとっつきやすいですね。チュートリアルも充実していて、これなら私でもできそうだと感じました。
「先生にとって負担の小さい教材にする」は強く意識しました。プログラミング経験のない先生が、「わからない」「怖い」などネガティブな感情を持っていると、子ども達にも伝わってしまいます。
先生が知っていることしか教えられない教材ではなく、子ども達が自分のペースで好きなだけ進んでいけるよう、チュートリアルはかなり充実させています。
—御社ならではのこだわりポイントはどこですか。
ゲームでも使われている3Dのグラフィックにはこだわりました。今のお子さん達が触れているコンテンツは3Dがほとんどですので、「つまらない」「貧相」と感じないようにと。
この夏から、やる気スイッチグループに提供し、教室での対面授業や家庭でのオンライン学習に使っていただきます。子ども達の反応を見ながら追加アセットやAI技術も組み込んでいって、どんどん複雑な表現ができるプラットフォームに育てていけたらと考えています。
子ども達に色々な方法を知ってほしい
—PFNは「みらプロ」にコンテンツ提供を行っていますね。教育を通じて、子ども達に何を伝えたいですか。リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://mirapro.miraino-manabi.jp/lp_pfn.html >
ひとつは、深層学習(ディープラーニング)がどういうものか小学生のうちから知ってもらうことです。
プログラミングの歴史においては、何度もパラダイムシフトが起きてきました。機械語を書いていた時代からアセンブラ、高級言語、オブジェクト指向、関数型言語、論理型言語、すぐれた型システムの登場……この流れは今後も止まらないでしょう。
そしてこれまで以上に、大きなパラダイムシフトをおこしつつあるのが深層学習です。
—深層学習についてより具体的に教えていただけますか?
これまでのプログラミングは、ルールを積み重ねてコードを書く演繹的な手法でした。
簡単に言うと、深層学習や機械学習はその逆で、コンピュータに大量の訓練データを与えることでその中のルールを見出させ、プログラムを自動で作る手法です。
たとえば、手書きの「1」を認識させるケースを考えてみましょう。これまでの手法だと、「1」と認識させるルール(線の傾きや長さ)をあらかじめ人間が設定し、それに沿ってコンピュータが判断していました。
一方、機械学習や深層学習では、手書きの「1」を訓練データとして大量に与える。そうするとコンピュータが「1」と見なすための特徴を見出してくれるのです。
—そんなことが可能なのですね。一般にイメージする「プログラミング」とは大きく異なっています。
僕たちが伝えたいのはプログラミング=コードを書く作業ではない、ということです。
プログラミングには色々な方法があるし、好きな方法をとっていい。コンピュータサイエンスには色んなチャンスがあるんだよ、と伝えたいですね。
「正しい」の定義をともに考えよう
—「みらプロ」の指導案を拝見して「AIは、本当に私たちの生活を豊かにしてくれるものなのだろうか」と問いかけているのに驚きました。御社の基幹技術にも関わらず、その存在意義に疑問を投げかけるのはなぜですか?ものづくりに正解がないように、プログラミングにも正解はありません。コンピュータサイエンスは今ものすごいスピードで進化し、その領域を広げています。何を「正しい」と考えるかは議論によっても変化しうる。ある意味でカオスな世界ですが、”考える余地がたくさんある”と捉えると面白いですよね。
詳しくない方にとっては、コンピュータ=怖い印象かもしれません。そんな方にもぜひ議論に加わっていただき、何を「正しい」とするのか、ともに考えていただけたらと願っています。
さらにコンピュータが進化した時代において、その進化を脅威ではなく、大きなチャンスとして捉えられるような社会の実現を目指していきたいです。
—ありがとうございました。



Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
(対談)プログラミング教育 HALLO powered by Playgram x やる気スイッチ™ 始動!プロ...
トヨタをはじめ、名だたる企業と提携・共同研究を行うPreferred Networks(プリファードネットワークス、略称PFN)が開発したプログラミング教材「Playgram™(プレイ...
2025.05.26|夏野かおる
-
(取材)「Omega Crafter」|PFNが贈る、自動化が楽しいクラフトゲームの魅力に迫る
株式会社Preferred Networks(以下、PFN)は3月29日、オープンワールドサバイバルクラフトゲーム「Omega Crafter」(オメガクラフター)の早期アクセス版をP...
2025.05.26|夏野かおる
-
(対談)プログラミング教育 HALLOとプリファードネットワークスが語る、これからのコンピューターサイエンス教育
2020年のスタート以来、ハイレベルな授業内容で保護者さまからの支持を集めてきたプログラミングスクールHALLO。今回はHALLOの魅力、スクールで使用するプログラミング教材「Play...
2024.11.06|宮﨑まきこ
-
毎月100万人以上が利用!「プレイグラムタイピング」超人気タイピング練習教材のすごさに迫る
タイピング教材として圧倒的な支持を受けているのが「PlaygramTyping(プレイグラムタイピング)」です。その利用者数は月間100万人以上!なぜ、これほどプレイグラムタイピングが...
2025.05.30|大橋礼
-
(取材)プログラミング教育HALLO|プログラミングで読解力・成績がアップ?!生徒・保護者インタビュー
「プログラミング教育HALLO」は年長〜中学生まで通えるプログラミングスクールです。ゲーム感覚で楽しく学び実用レベルのコーディングまで身につけられる教材「Playgram」を使用。今回...
2025.09.10|大橋礼