【体験・取材レポート】オンラインでも深く学べる|これからKIDSの「探究型学習」の魅力とは

これからKIDSの口コミや料金、カリキュラム情報をわかりやすく紹介!子供・小中学生向けプログラミング教室の特徴や体験レッスン情報も満載。Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン実施中!運営本部:株式会社これから
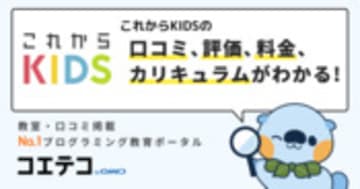
https://coeteco.jp/brand/c-kids >
そんなこれからKIDSが、2022年7月にオンライン教室を開校!これからKIDSオンラインでは、私たちの身近にあるモノ/コトを探究しながら、プログラミングについても学べる、探究型のプログラミング学習ができます。
そこで今回は、これからKIDSオンラインの探究型学習を、コエテコライターが小学5年生の娘と体験!更にオンライン校の校長である「なーりー」先生と、授業のサブファシリテーターの「宮さん」にお話をうかがいました。
「いろんなことに興味を持ってもらいたい」「これからの時代に備えて、プログラミングも気になる」そう考えている保護者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
これからKIDSオンラインの概要・特徴 (現在募集停止中)
| 学習方法 | オンラインレッスン(現在募集停止中) |
| 対象年齢 | 小学1〜4年生(初心者の方や興味がある方は学年問わず受講可能) |
| レッスン日程 |
水曜日クラス:月4回 第1〜4週 水曜日 19:00〜20:00 日曜日クラス:月4回 第1〜4週 水曜日 17:00〜18:00 (どちらのコースも第5週はお休み) |
| 料金 | 入会金:0円 レッスン料金:8,800円(税込み)/月 |
| 運営会社 | 株式会社これから |
これからKIDSオンラインは、身近なモノ/コトをテーマに、探究学習×プログラミングを学べる、新しいスタイルのスクールです。
※現在募集停止中です。
1ヶ月・全4回の授業を通して、1つのテーマの探究学習に取り組みます。例えば開校した2022年7月のテーマは「交通安全」で、本記事でご紹介する8月のテーマは「打ち上げ花火」。以降9月「回転寿司」、10月「ゲーム」、11月「コンビニ」の予定です。月ごとにテーマを深く探究し、プログラミングとの関係を紐解いていきます。
なお、これからKIDSオンラインでは、2022年9月まで1ヶ月の探究学習をまるっと無料体験できるキャンペーンを実施しています。「探究授業ってどんなもの?」を1ヶ月かけてじっくりと体験でき、お子さまとの相性をしっかりと確かめた上で入会を決められるのが嬉しいですね。
10月以降は第1回目のレッスンのみの体験となる予定ですが、そちらは毎月でも参加OK!2回目以降の授業に参加する場合のみ、レッスン料金(税込み・8,800円)が必要となります。
今後のテーマを知りたい方や、探究学習を体験したい方は、ぜひこちらのボタンからチェックしてみてください。
【体験レポート】オンライン授業を体験!8月のテーマは「打ち上げ花火」
ここからは、2022年8月の「打ち上げ花火」の授業1〜3回目をレポートしていきます!
1回目・2回目の授業をダイジェストでお届け!
1回目・2回目の授業では、どちらかというと花火の歴史や仕組みに関わる内容が多い印象でした。

例えば……
- 日本で一番最初に打ち上げ花火を見た人は?誰が持ってきたの?
- 花火大会はどうして行われるようになったの?
- 日本と世界の打ち上げ花火の違いは?
- 打ち上げ花火の中の仕組みはどうなっているの?光る仕組みは?
- そもそも花火に使われている火薬は、どのようにして始まったの?
- 花火の色は、どうやって変えている?
- 打ち上げ花火で、音が遅く聞こえるのはなぜ?
(ちょっとだけ中身の例をお伝えすると、日本で一番最初に打ち上げ花火を見たと言われているのは、徳川家康だそう!1613年に、イギリス国王の使者が徳川家康に献上したと記録が残っているようです。)

子どもたちもびっくりしたり、笑顔がこぼれたり、深くうなずいたりと楽しく集中している様子でしたよ!
「間違えても、とにかく楽しむ!」がルール!

授業の開始時間になると、メインファシリテーターのなーりー先生が元気に登場!ZOOMに入ってきたお子さんのお名前を呼んだり声をかけたり、またお子さん側もスタンプなどで答えたりしながらコミュニケーションを取ります。

授業で大切なのは「間違えてもいい!」「とにかく楽しむ!」こと!
今日も楽しく、一緒に勉強していこう!
今日の授業は「プログラミングの内容もたっぷり!」なのだそう!打ち上げ花火とプログラミングの関係性とは、どのようなものなのでしょうか。
クイズで楽しく!花火とプログラミングの関係性を探究
3回目となる今回は、いよいよ打ち上げ花火とプログラミングの関係性が明らかに!実は打ち上げ花火の点火とプログラミングに、重要なつながりがあったのです。まずは、以前は打ち上げ花火を入れる筒に、直接火の塊を入れて点火していたこと。そして、その方法は危険であったことが説明されます。


人間だと完璧にやろうと思ってがんばっても、ミス(=ヒューマンエラー)しちゃうこともあるし、危険だよね。
どうしたら安全に花火が打ち上げられるかな?

このように電気によって、打ち上げ花火を離れたところから点火でき、安全に打ち上げられるようになったこと。また、プログラミングによって、複雑な演出もできるようになったことまで、探究学習によって打ち上げ花火とプログラミングの関係が学べました。
花火を打ち上げる花火師さんは「プログラマー」、とも言われています!

一見あまり関係のなさそうな、打ち上げ花火とプログラミング。ですが深く探究することによって話がどんどんつながっていき、実は花火を打ち上げるために、プログラミングが欠かせないことがわかりました!
途中少々難しい単語や内容も出てきますが、なーりー先生の問いかけにうなずくなど、子どもたちもしっかりと画面に集中している様子です。そして、授業中に最も盛り上がりを見せていたのが、テーマに関連するクイズタイム!



これからKIDSオンラインの授業では、テーマ・授業に関するクイズ大会が行われます。答えは2〜4択で、授業中のなーりー先生のお話にヒントがあることも!正解数はもちろん、速く正解できたほうがより得点を取ることができ、良い順位を獲得できる仕組みです。
クイズに答えている子どもたちの表情は真剣そのもの!答えがでた後の、喜んでいたり残念がっていたり、子どもたちの表情がたまりません。
このように、大盛りあがりのクイズも交えながら、今月のテーマある打ち上げ花火とプログラミングのつながりを学べました。
打ち上げ花火を通して、プログラミングの概念や「Scratch」も学べる!
これからKIDSオンラインでは、プログラミングの考え方や小学生から使いやすいプログラミング学習用ソフトの「Scratch(スクラッチ)」についても学べます。
今回の3回目の授業では
- x座標・y座標
- 順次実行
- 乱数
- クローン
まずはScratchで作った花火を見て、


続いて、Scratchの画面や「座標」に関する説明を聞きます。


花火を打ち上げる場所は、「x座標」と「y座標」のプログラムで変えられます。
x座標は右にいくほどプラスで値が大きくなり、左にいくほどマイナスで小さくなります。y座標は上にいくほどプラス。下にいくほどマイナスに数が動きます。
x座標を変えることで、花火を打ち上げる場所が。y座標を変えることで、花火の上がる高さが変わってくる、と教えてもらいます。
なるほど。x座標とy座標をプログラムすることで、好きな位置・高さで打ち上げ花火を上げられるのですね!
上から順番に命令を実行することを「順次処理」といいます。
プログラムを上から下の順番に命令を実行することで、これはプログラミングのルールの一つです!

次は「乱数」と「クローン」を学びます。
さっきの花火、たくさんの場所から、いろんな高さで上がっていたよね。あれは「乱数」を使っています。
そして「クローン」によって、花火をたくさんコピーすることもできちゃうんだよ!


「乱数」とは指定された範囲の数値からランダムに取り出すことです。それを使うことによって、様々な場所・高さで花火が打ち上げられる、ということですね。
また、Scratchは色も番号で変えられるので、乱数と組み合わせることでカラフルな花火も打ち上げられるのだそう!

「クローン」はイメージしやすいですね。クローンでコピーすることによって、たくさんの花火を打ち上げられます。
つまり、今回教わった「座標」「乱数」「クローン」を使うと、ランダムな位置で大きさや色合いが違う、本物の花火大会のような景色を作り出せる、ということですね!
「プログラミング」と聞くと難しく感じますが、打ち上げ花火が入り口にあることで、グッと身近に感じることができました!

みんな「表彰台に上がれるかな?」とドキドキの表情を浮かべながら、画面を見つめています。

上位3人のお子さんが発表され、インタビュータイム!
インタビューでは
- 「次は1位になりたい!」
- 「プログラミングの話を聞けて楽しかった!」
- 「Scratchで花火のプログラミングを作ってみたよ!」
こうして第3回目の授業は終了です。
1時間と長めの授業にも関わらず、どのお子さんもとても集中して取り組んでいる姿が印象的でした。
なーりー先生の説明に驚いたり、笑ったり、うなずいたり、手を挙げたりと、表情・表現豊かなお子さん達。そして、それぞれのお子さんのお名前を呼びながらコミュニケーションをとる、なーりー先生。体験を通して、充実した時間が過ごせていることがわかりました!
なお、なーりー先生や宮さんと話したいお子さんは、この後30分間の「フリータイム」でお話することができます。参加は自由で、プログラミングに関する質問や授業の感想だけでなく、なーりー先生・宮さんと楽しくお話できる時間です。

オンラインの集団授業だと、どうしても先生とコミュニケーションを取る機会が少なくなってしまいがち。ですが、フリータイムがあることで、先生ともお話できるのが嬉しいですね。
【取材レポート】これからKIDSオンラインのなーりー先生と宮さんにインタビュー
3回目の授業の後、メインファシリテーターをされていた、これからKIDSオンライン校・校長の「なーりー」先生と、サブファシリテーター「宮さん」に、オンライン開校のきっかけや、思いについてお話をうかがいました!
「プログラミングに興味を持つ子を増やしたい」という思いでオンラインレッスンを開始!
——本日はありがとうございました!まずは、これからKIDSオンライン校を開校した時期と、きっかけを教えてください。なーりー先生:
開校したのは2022年7月です。プログラミングに興味を持つ子どもたちを増やしたい、という思いが、オンラインレッスンをはじめた一番のきっかけです。
プログラミングは、今後の社会で必須のものですが、子ども達がプログラミングに触れる機会が少ないのが現状です。現在は4教室で、子どもたちと直接関わりながらプログラミングの学習を深めていますが、プログラミングそのものに興味を持っているお子さんが少ないことに危機感を感じました。
今後どんどん必要になってくる中で、まだまだ興味をもっている子が少ない。その危機感に対してアプローチできないか、というのが、オンラインレッスンを開始した経緯です。
しかし、最初からプログラミングのオンラインレッスンに興味を持って参加するのは難しいのではないか、と感じました。また、学習歴社会において「探究学習」も重要視されていることから、「探究」という切り口で、いろいろなテーマを深堀りして、プログラミングと探究学習を掛け算するレッスン内容を考え始めました。
宮さん:
プログラミングに興味をもってほしいので、身近なものに焦点を当てています。
第1回目は交通整理、第2回目は今月の打ち上げ花火、第3回目の来月は回転寿司、というように、身近なモノ/コトをテーマに、プログラミングと探究ができるようにしています。
身近なテーマを深堀りする「探究型学習」とプログラミング学習が一緒にできるスタイル
——業界でも珍しい「探究型学習」なのですね。具体的には、どのようなスタイルで学習が進むのでしょうか?なーりー先生:
何気なく使っているモノやコトには、当然のようにプログラミングが使われています。プログラミングに興味を持ってもらうために、そのモノ/コトを一つのテーマとして深堀りして展開していくスタイルです。
そのときに「なぜ?」「どうして」という疑問を子どもたちに湧き上がらせて、興味を引いていく。テーマを深堀りして、プログラミングと結びつけることで「プログラミングを学習したい」という意欲につなげていきたいと思っています。
そうなるために、まずは私たちが子ども時代のように「なぜ?」「どうして」を湧き上がらせるようにしています。

宮さん:
また、これからKIDSオンラインは、オンラインならではの強みを生かしていきたい点と、対面レッスンをそのままオンラインにするだけではプログラミング人口を増やすことができない点を考慮して、大人数でのレッスンにしました。
なーりー先生:
ただ、大人数だと、どうしても手を動かすことが難しくなってしまうと考えました。そこで、クイズ形式で一緒に回答していくような流れを作りました。
クイズ形式にしたことで、子どもたちも白熱してレッスンに取り組んでくれています。
宮さん:
実はこのクイズ形式は、ゆくゆくは大学入試などでプラスに働く予定の「プログラミング能力検定」に近い形にしています。プログラミング能力検定は動画を見て、動画と同じプログラムを4つの選択肢から選ぶ、というものです。
選択式のクイズにすることによって、分解して考える力が身につきます。このように、実践的な内容も抑えて取り組みを行っています。

なーりー先生:
そうなんです。第4回目の授業では、まるごとプログラムを表示して、正しいプログラムを選んでもらう問題も準備しています。検定を模した出題形式になっているので、プログラミング能力検定の合格にもつながるような内容になっています。
オンラインでも集中して取り組める!その理由とは
——オンライン学習は、子どもの集中力が続くか不安になるとおっしゃる保護者の方もいます。御校では、お子さまのやる気をアップさせるため、どのような工夫をされていますか?なーりー先生:
やはりクイズは人気ですね。現状は特に景品などを用意しているわけではないのですが、みんな燃えます(笑)。
クイズ前の説明を聞き、それをもとに予想することで解答を導き出せるような問題を出したり、プログラミングの難易度も低いものから高いものまで出したりと、飽きが来ないようにするのが工夫の一つです。
宮さん:
いまのところはクイズに熱中して取り組んでくれているお子さんがほとんどですね。
クイズを入れることで、楽しみながら行ってくれていると感じています。
なーりー先生:
また、私自身がメインファシリテーターとして、画面でみんなの顔を見てレッスンを進めています。子どもたちの顔やスタンプなどの反応を見て、印象的なお子さんの名前を呼びながら「きちんと見てくれているな」と感じてもらえるようにしています。
どうしてもオンラインレッスンは画面という壁によって受動的になりやすいです。そのため、能動的に取り組んでもらうために、子どもたちに体を使ってもらったり、大事なプログラミングは声に一緒に出してもらったりという工夫もしています。
お子さんの声はミュートにしているので聞こえません。ですが、こういった働きかけによって、実際に体を動かしている様子や、口を動かして取り組んでいる様子が見えます。
——お子さまの人数が多いと、なかなか全員への声掛けが難しくなることもあると思うのですが、その点はいかがでしょうか?
なーりー先生:
現在は最大25名のお子さんにご参加いただいていますが、全員のお子さんを見ることができています。ただ、どうしても触れることのできないお子さんもいると思うので、例えば「〇〇したことがある人?ない人?」というアクションを取る挙手制も入れるようにしています。
こちらも子どもたちのやる気につなげるために、心がけていることの一つです。
宮さん:
ビデオをオンにしていないお子さんも、リアクションでスタンプを送ってくれる方も多いですね。
なーりー先生:
そうなんですよ。グッドマークを送っていただいたお子さんに声をかけると、他のお子さんも積極的にグッドマークを送ってくれるようになります。そのようなきっかけづくりも、声掛けで行わせていただいています。

——なるほど、たしかに今日も、どのお子さんも感情表現が豊かなのが印象的でした!また、スライドも非常にふんだんに使われているように感じたのですが、こちらもモチベーションを維持する工夫の一つなのでしょうか?
なーりー先生:
そうですね。スライドも、1回の授業あたり平均120〜130枚くらいは作ります。コンテンツづくりにも非常にこだわっておりますので、こちらも楽しんでもらえたらと思います!
生の声を聞きながら、より良いコンテンツを準備していく
——今回ライターも1回目〜3回目まで参加させていただき、探究教育の魅力を実感しております。今月は1回目から3回目まで、内容がどんどん深まっていき、3回目になるとプログラミングの要素が多くなるように感じたのですが、毎月このような流れで進むのでしょうか?なーりー先生:
いまはまだ決められたスタイルが確立していない状態です。初月である7月のテーマである交通整理から、今月の打ち上げ花火については内容の流れなども変えています。来月の回転寿司についても、グッと改善しています。「プログラミングももっと知りたい」というお声があったため、プログラミングの内容を1回目の授業からふんだんに取り入れる予定です。
実際に実施してみて、学習スタイルが好評でしたら継続。反省点があれば変えていく、というように、流れは固定していません。生の声を聞きながら、より良いコンテンツが作れるようにしていきたいと思っています。
また、探究で得られる感動も重要視しています。深堀りしていくことで見えてくる世界で、感動を抱けるようなストーリーを大切にしています。例えば「映画」はたくさんの伏線が散りばめられていますよね。実は一つに全てつながっていて、それらが最後のクライマックスで感動をもらえる、というようなイメージです。
そのような1つのストーリーを、全4回に分けて味わってもらえたら、と考えています。

毎回授業をパワーアップ!楽しみながら、一緒にプログラミングの力を身につけたい
——これからKIDSオンラインをご検討中のお子さま・保護者の方に向けてメッセージをいただけますでしょうか?なーりー先生:
子どもたちにとって一番良い学習の流れ・教え方を模索し続け、回を重ねるごとにパワーアップしていきたいと思っています。
お子さんたちに楽しんでもらえるようにと、メンバー全員でコンテンツを作っているので、ぜひ楽しんでいただけたらと考えています。そして、プログラミングの力を一緒に身に着けていきたいです。
また、プログラミングは身近に、たくさんあふれています。
レッスンでプログラミングの力をつけるのと並行して、身の回りにあるプログラミングに、お子さまご自身が気づくきっかけにしてほしい。そして、お母様・お父様にとっても、お子さまの興味のあるものに気づくきっかけにしていただきたい。それを深めることが、今後の社会で必要な力を身につけることにつながると考えております。
お子さまにも、お母様お父様にも、種まきとなるような授業・コンテンツを提供したいと思っていますので、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいです。
宮さん:
体験授業を通して楽しんでいただけた方は、絶対次のテーマも楽しめる。そんな内容にさせていただいております。
テーマも、次は回転寿司、その次はゲーム、コンビニ、というようになっているので、身近なところにプログラミングを感じてもらえると思います。
「楽しい」と感じたら、次のテーマももっと楽しいので、ぜひ継続してご参加いただけましたら幸いです。

これからKIDSオンラインの無料体験はこちら!
オンラインで楽しく探究学習×プログラミングを学べる、業界でもめずらしい授業スタイルの「これからKIDSオンライン」。プログラミングと聞くと難しそうに感じますが、これからKIDSオンラインでは、身近なモノ/コトをテーマに学習を進めるため、プログラミングを身近なものに感じることができます。これからKIDSオンラインでは、2022年9月まで、1ヶ月間(全4回)のレッスンを無料でお試しできちゃうキャンペーンを実施しています!1回目から4回目まで、1つのテーマの探究学習をしっかり体験できるため、スクールや学習方法がお子さんに合っているかどうかも判断しやすいでしょう。
10月以降も、毎月第1回目の授業は何度でも無料で参加可能でき、また入会後も同様に1回目のみの参加であれば月額料金はかかりません。まずは気軽に体験してみて、続きが気になった場合は、ぜひ第2回目以降のレッスンを受けることも検討してみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下のボタンからチェックできます。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
【憧れのお仕事体験×プログラミング】女の子向けプログラミングイベント「KIKKAKE」ロボ団講座を徹底レポート!
今回レポートするのは、大人気プログラミング教室・ロボ団による「女の子の職業体験」をテーマにした高学年以上向け(小学4年生〜中学3年生向け)の講座「ワクワクなりきりお仕事ミッション!〜プ...
2025.06.03|安藤さやか
-
これからKIDS 築地口教室|名古屋市・慶和幼稚園内に開校!ロボット&マイクラでプログラミング!
「これからKIDS」は4歳から楽しく、自走力や論理的思考力を育むプログラミングスクールです。この度、名古屋市の慶和幼稚園内に、新たに「これからKIDS 築地口教室」を開校!教室は幼稚園...
2025.05.30|大橋礼
-
個別指導Axisロボットプログラミング講座 体験授業に行ってみた!
個別指導Axisは、全国47都道府県に350校以上展開する学習塾です。Axisでは、2018年4月から、小学3年生から6年生を対象にした「ロボットプログラミング講座」を開講。今回は、愛...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
Tech Kids School オンライン校の魅力とは?授業・カリキュラム・評判を徹底解説!担当者に聞いてみた
Tech Kids School (テックキッズスクール)オンライン校は、プログラミングの入門から本格的なゲーム開発まで、幅広いカリキュラムで体系的に学べるのが特徴。2013年の設立以...
2025.09.10|大橋礼
-
(取材)これからKIDS/これからTECH有明ガーデン校|有明エリアに新規オープン!中高生向け本格コースも
ロジカル/クリティカル/クリエイティブ・シンキングの3つの思考法を育成し、子供の将来の可能性を広げるプログラミング教室「これからKIDS」。これからKIDS/これからTECH 有明ガー...
2025.09.10|大橋礼













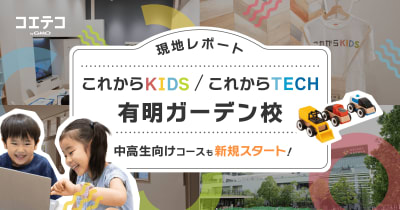
学校でお友達に話したくなっちゃうような豆知識がたくさん!科学や物理、歴史などの勉強も先取りできますね。
既に単語や現象について知っている大人でも「なるほど!」「そうなんだ!」と目からウロコの情報ばかりです。