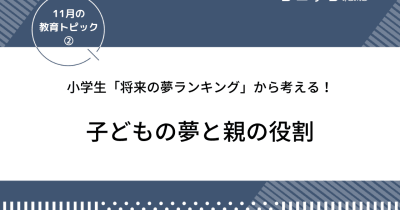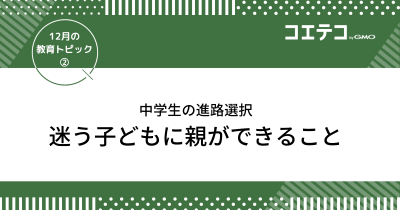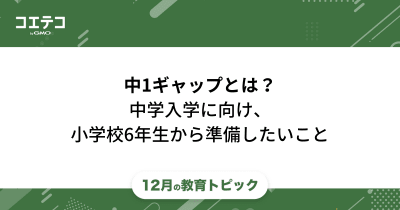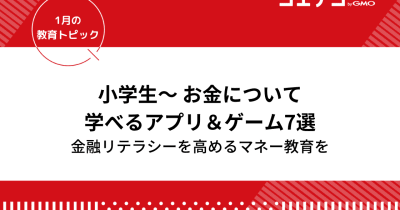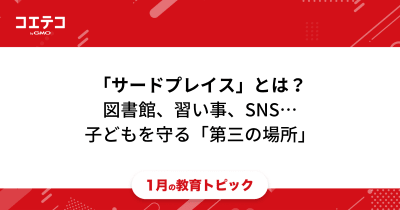ゲームが子どもに与える良い影響と悪い影響を徹底解説!やりすぎるとどうなる?
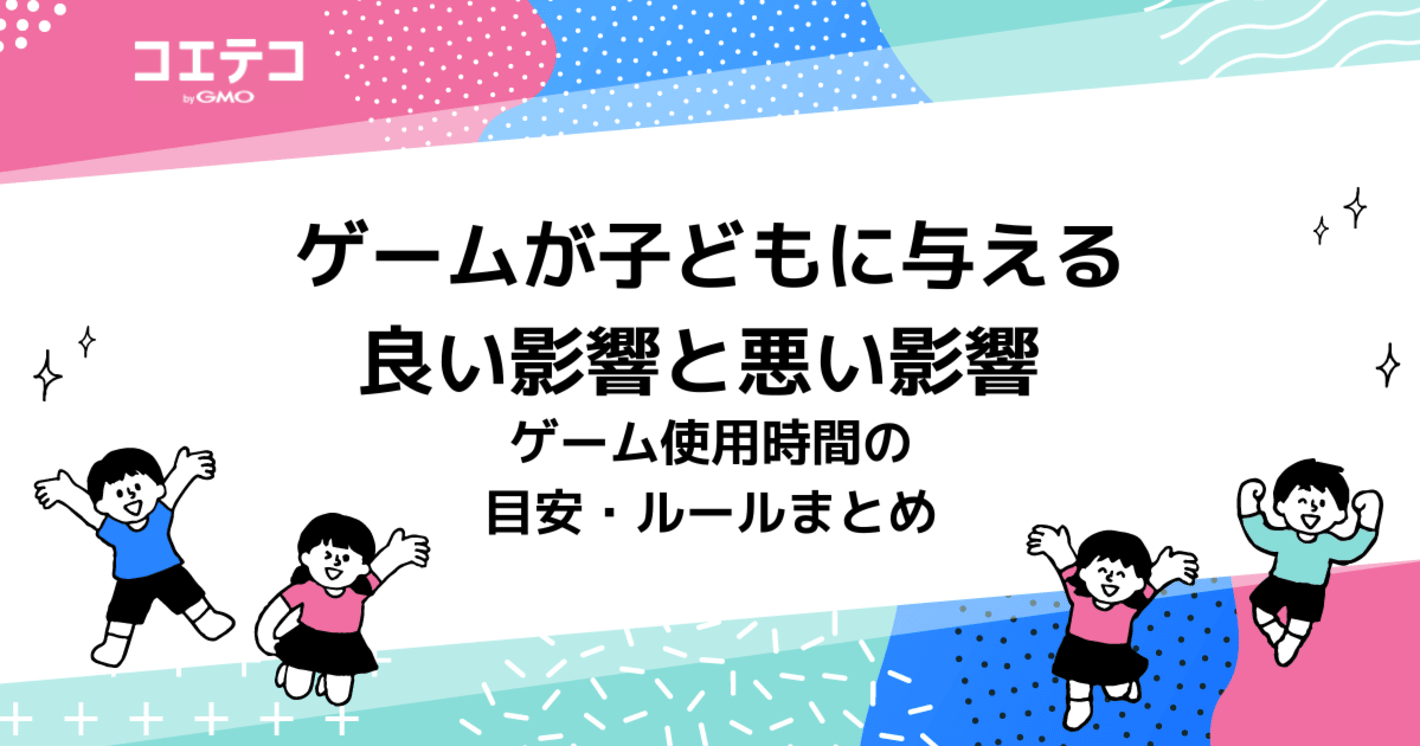
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
1人で遊んだり複数の友達と楽しんだりできるゲームには、子どもが夢中になる要素がたくさん含まれています。
しかし、親にとっては子どもへの影響も心配です。
今回は、ゲームが子どもに与える影響と、ゲームと上手につき合っていくためのルールについて考えていきます。
ゲームが子どもに与える悪い影響は?

- ゲーム中心の生活になる
- 視力の低下につながる
- 外で遊ばなくなる
ここでは、ゲームによって生じる可能性のある上記3つの悪影響について解説します。
ゲーム中心の生活になる
ゲームは、続けたくなるように作られています。そのため、子どもが自分で時間を区切って遊ぶことは、そう簡単なことではありません。
学校から帰ってきてすぐにゲームを始め、家にいる時間のほとんどを費やしてしまうこともあります。
勉強をしていてもゲームのことが気になり、集中できない原因にもなりえます。
常にゲームに触れていると、ゲーム依存症へと進んでしまうこともあるようです。
2019年5月、世界保健機関(WHO)はゲーム依存症をゲーム障害と称して、国際疾病として正式に認定しました。
視力の低下につながる
テレビやスマホを見ながら長時間ゲームをしていると、疲れ目を起こして一時的に裸眼の視力が下がると言われています。また、幼少期にテレビを長時間見ていたことと小学校になってからの視力低下に、関連性があることがわかったという研究結果もあります。
視力低下とゲームの因果関係を明確に示した調査結果はありませんが、子どもの視力になんらかの影響を及ぼす可能性はあります。
外で遊ばなくなる
子どもの外遊びが減った理由はゲームだけではありませんが、室内で過ごす時間をより多くする要因のひとつではあるでしょう。外で遊ぶ時間が減って体を動かす機会が減ると、体力の低下も考えられます。
ゲームが子どもに与える良い影響とは

コミュニケーション力を磨ける
現代の子どもにとって、テレビやパソコンのゲームは身近な遊びのひとつです。複数の友だちと一緒に遊ぶこともできるので、ゲームを通してコミュニケーションや遊びのルールを身につけていくことにもつながるでしょう。
いまやゲームをしていない子どもの方が珍しいこともあり、ゲームを通じてコミュニケーションを図る場面は多く、社交性やコミュニケーション力が養われることにもつながります。
ゲームが周囲と関わるきっかけになり、そこから視野が広がることもあるでしょう。
米国小児科学会が発行している学術誌「Pediatrics」に公開された過去の研究報告では、1日1時間程度のゲームは子どもの生活への満足感や社交性を高めているという調査結果も報告されています。
とはいえ、一方では1日3時間以上ゲームをしている場合に、その逆となる結果も報告されているため、やはり限度を意識する必要はあると言えるでしょう。
視覚空間認知力や瞬発力が鍛えられる
横に画面がスクロール展開していくアクションゲームは、サポートアイテムの出現や敵の攻撃への素早い対応など、瞬発力や即座の判断力が必要です。次の行動を予測しながら、タイミングを見計らった速度でボタン操作することは、脳の活性化にもつながるでしょう。
遊びながら英語に触れられる
オンラインのネットゲームでは、国外のプレーヤーとプレイすることも可能です。そのためゲームをしながらネイティブスピーカーの英語を聞いたり、簡単な英話を話したりする場面も出てきます。
相手とコミュニケーションをとりたい、もっとゲームを楽しみたいという気持ちから、自然に英語を覚えようとすることにもつながるでしょう。
ゲームのやりすぎと子どもの学力低下には相関関係がある?

独立行政法人経済産業研究所のプロジェクトチームの研究では、ゲームやテレビに1時間使うと男子で1.86分、女子で2.70分の勉強時間が減ったという結果が報告されており、テレビやゲームが勉強時間の減少に与える影響は、ほとんど無視できるほどに小さいと言われています。
また、ゲームの時間を減らしたとしても勉強時間が増えるわけではない、ということも示されており、ゲームをすることそのものが直接学力の低下につながるとは言えないでしょう。
ゲームのやりすぎはゲーム依存のリスクを高める?
最も気をつけたいのが、ゲームをやり過ぎることによるゲーム依存症になることです。ゲームは、脳が興奮状態になるように作られており、クリアすることで得られる達成感によって興奮状態となった場合、脳は快楽物質であるドーパミンを大量に分泌、少なくなると脳に催促するという負の連鎖につながり、ゲーム依存症となってしまいます。
常に眠そう、外で遊ばない、常にゲームのことを考えているなどの症状があれば、ゲーム依存症の可能性があるかもしれません。
依存の可能性が高いのは、ゲーム機を使う通常のゲームよりも、ネットでコミュニケーションが取れるオンラインゲームです。
自分がいなくてもゲームが進行していくため、何をしていてもゲームが気になるなど、やればやるほど依存度が高まるケースが多いようです。
ゲーム依存防止に!ゲームのルールの作り方
子どもにゲームを与えたまま放置してしまうと、ゲーム依存症になってしまう可能性も高まります。ゲーム依存を防止するためには、ゲームのルールを定めることが大切です。ルールの作り方について、詳しくチェックしていきましょう。
ルールは親ではなく子ども主体で決める
ゲームのルールは、親が一方的に決めるのではなく、子ども主体で決めるのがベストです。押しつけられたルールには反発したり守らなかったりすることもありますが、自分で決めたルールなら達成しやすくなる傾向にあります。
子どもがゲームのルールを自主的に守れるよう、子どもの意見を聞きながら一緒にルールを決めることで、子どもの気持ちを尊重することにもなるはずです。
ルールにはイレギュラーな変更も良いことにする
時にはイレギュラーな対応や変更をしても良いと決めておくのがおすすめです。ルールを定めていても、「きりが悪いのですぐに終わらせられない」など、なかなか守れない場面もあるでしょう。
ゲームのきりが悪いときは数分の延長はOKとするなど、微妙な判断が必要なこともあるかもしれません。
ただし、「イレギュラーな変更を希望するときは親の了承を得る」など、なんでもありではなく、イレギュラーについてのルールも盛り込んでおきましょう。
ルール作りの際には親の心配事も伝える
ルール作りの際には、親の心配事をきちんと子どもに伝えることで、ルールを決めやすくなります。例えば、「ゲームを買ったら宿題の時間がなくなったり寝る時間が遅くなったりしないかな」「ゲームをやり過ぎて目が悪くなっちゃうんじゃないかな」など、ゲームをすることで懸念される事態を伝えましょう。
心配事を事前に伝えておくことで、解消するルールを自分で考えられるうえ、自分で決めたルールならきちんと守ろうと行動します。
課金ゲームができないように設定する
本人の自覚の有無に関わらず、気が付いたら課金しているケースも考えられるため、課金ゲームができないよう、事前に設定しておくことも大切です。課金の請求が来て気が付いた、なんてことのないよう、前もって対策しておきましょう。
ゲームのルールの例

勉強時間に比例してゲームできる時間を決める
たとえば1時間勉強したら、ゲームも1時間遊べたり、勉強を30分多く頑張ったらご褒美にゲーム時間も15分増やせたりなど、勉強時間に比例してゲームの時間を決めてみましょう。ゲームしても良い時間帯を決める
勉強を終わらせてからゲームをする、夕食が終わってから1時間だけ遊ぶなど、ゲームをしても良い時間を決めましょう。各家庭の生活リズムなどに合わせたり、子ども自身に決めさせるのもよいです。
ゲームをして良い時間以外は親がスマホやゲーム機を預かる
ゲームをしない時間は、親がゲーム機を預かって子どもから見えない場所にしまっておきましょう。勉強が終わったらゲームを出してあげるなどと決めておけば、がんばって勉強を終わらせようというモチベーションにもつながります。
親の目が届く場所で遊ばせる
ゲームをするときは、必ず親から見える場所で遊ばせましょう。どんなゲームをしているのか、どのくらいの時間遊んでいるのかを把握することができます。
子どもがゲーム感覚で学べるおすすめ通信教育4選
ここでは、ゲーム感覚で学べるおすすめ通信教育を紹介します。参考:通信教育小学生
スタディサプリ

スタディサプリは、幼児~小学3年生を対象とした0円~楽しく学べる通信教育です。
0円コースでは、無料で月最大60レッスンほどを受けられます。
有料コースのレッスンの一部が無料開放されているため、無料といえども質は確かです。
アニメーションによるわかりやすい解説が採用されており、子どもだけでも問題なく取り組めます。
自動採点形式なので、保護者の丸つけも不要です。
ゲーミフィケーションを取り入れた学習設計により、ゲーム感覚で楽しみながらレッスンに取り組めるでしょう。
0円コースは、利用期間に制限がなく、望めばずっと学べます。
家にパソコンかタブレットがあればすぐに学習をスタートできるため、気になる方は気軽に始めてみてはいかがでしょうか。
お支払い登録をせずとも利用を開始でき、手続きは約60秒で完了します。
東進オンライン学校小学部

小学1年~6年生の「脳力」を鍛えられる通信教育は、東進オンライン学校小学部です。
日本一の東大現役合格実績のある東進と「予習シリーズ」が評価を得ている四谷大塚がタッグを組んだ東進オンライン学校小学部では、わかりやすく質の高い授業を受けられることが魅力です。
実力のある講師陣が授業を行うことで、実際に教室で授業を受けているような臨場感を味わうことができます。
講座のほかにも月例テストや年に2回実施される実力テストなどがあり、学力を定期的にチェックすることが可能です。
基礎力を伸ばしたいなら標準講座、中学や高校につながる応用力を伸ばしたいなら演習充実講座を選ぶことがおすすめです。
受講料は小学1~2年生で月額2,178円(税込)で、小学3~6年生で月額3,278円(税込)となっています。
進研ゼミ小学講座

「イード・アワード2022 小学生が好きな通信教育」で3年連続で1位を獲得しているのは、進研ゼミ小学講座です。対象年齢は、年長から小学6年生までとなっています。
レッスンの自動提案が行われることで、学習習慣が身に付きやすいことが特徴です。
赤ペン先生が最短翌日から3日間で添削してくれるから、お子様のやる気につながりやすいことがメリット。
タブレットで手軽にさかのぼり学習ができることで、苦手な問題を解消しやすいでしょう。得意科目は先取り学習もできるから、得意な分野を伸ばすことも可能です。
小学1年生の場合は、受講費が毎月払いで月額4,020円(税込)で、12ヵ月一括払いでは月額3,250円~(税込)となっています。
タブレットの破損が心配な場合は、3,600円(税込)で利用できる「チャレンジパッドサポートサービス」を利用したいですね。
すらら

小学校から高校までの5教科に対応したオンライン教材は、すららです。
すららでは、無学年式のAI教材と1人ひとりの学習法に合わせたアダプティブラーニングを採用していることが特徴です。
学習継続率は89.1%を誇り、お子様が飽きずに学習を継続しやすい点がメリット。
すららで学習すると、目標達成するごとにポイントをゲットできます。
ポイントを欲しいアイテムと交換して、自分だけのマイページをカスタマイズできるなどの楽しみもあるのが嬉しいポイント。
18万問の豊富なドリルが搭載されているから、お子様の学習レベルに合わせた問題を選ぶことが可能です。
入会金は7,700~11,000円(税込)となっており、国語・算数・英語の3教科コースは4ヵ月継続コースが月額8,228円(税込)で、毎月お支払コースが月額8,800円(税込)となっています。
カリキュラムの内容が気になる場合は、無料体験を利用してみましょう。
そもそもゲームの使用時間の目安はどれくらいにすべき?

ゲーム時間は何時間にすべきかという質問には、1時間(47.6%)という答えが一番多く、次いで2時間(15.7%)、30分以下(12.7%)、1.5時間(11.4%)という結果でした。
全体の平均は1.183時間。半数近い家庭が、ゲーム時間は1時間ほどが適切だと捉えているようです。
ルール運用時に注意すべきこと
子どもにゲームを使用するときのルールを守らせるためには、どのようなことに気をつけたらよいでしょうか。ルールを上手に運用するためのポイントを紹介します。
守れないときはペナルティを与える
ルールを守らなかったときは、ペナルティを与えることも必要です。たとえば、決められた時間より長くゲームをしてしまったときは次の日のゲームは禁止するなど、ペナルティの内容も子どもと一緒に決めておくとよいでしょう。
例外を作らない
イレギュラーの対応にもルールを決めておきましょう。「今日だけは」とか、「特別に」などのようにルールにない例外を作らないようにしましょう。例外を作ってしまうと、せっかく決めたルールが意味のないことになってしまいます。
どうしてもというときは、代わりに次の日のゲーム時間を減らす、勉強時間を増やすなど、トレード内容を決めましょう。
子どものストレスにならないよう柔軟に運用する
ルールを守らせるためとはいえ、過度に厳しくして子どもにストレスを与えないように注意しましょう。そのためにも、子どもが守れるような内容のルールを親子で一緒に考えて決めることが大切です。
まとめ

ゲームには現実の世界では味わえない経験ができるといったメリットもあるため、子どもに悪い影響ばかりを与えるともいえません。
家庭内のルールを決めるなど、上手につき合っていく方法を親子で一緒に考えていきたいもの。
または、学びに直結する遊びと出会えるよう、ゲームを楽しむように学べる「ロボット・プログラミング」などの習い事の無料体験に申し込み、子どもが楽しめるかどうかを検討するのも方法の1つです。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
小学生「将来の夢ランキング」!子どもの夢と親の役割
「大きくなったら何になりたい?」親なら一度は子どもに聞いてみるセリフですね。4~5歳の子どもは元気に「ウルトラマン!」「プリンセス」なんて答えて微笑ましいものですが、だんだんと子どもの...
2025.11.12|大橋礼
-
中学生の進路選択「迷う子どもに親ができること」
「うちの子、将来のことを全然考えていなくて心配」そんな悩みを抱える保護者の方は少なくありません。しかし、中学生が進路について明確な目標を持っていないのは、実は珍しいことではありません。...
2026.01.08|大橋礼
-
中1ギャップとは?中学入学に向けて小学校6年生が準備しておきたいこと
今回の教育トピックでは「中1ギャップ」に対する不安を少しでも解消できるよう、小学校6年生から準備できることをご紹介します。 小1ギャップ・中1ギャップ・高1クライシスなどを耳にす...
2025.09.10|大橋礼
-
子ども向けお金の勉強アプリ・ゲーム!投資の金融教育もおすすめ
日本ではあまり「お金の教育」に対して積極的ではありませんでした。しかし最近は金融教育の重要性が見直されています。 人生設計とマネープランが重要なことは明らかなものの、いったいどうやっ...
2025.12.12|大橋礼
-
サードプレイスとは?〜子どもに学校・家庭以外の“もうひとつの居場所”を〜
子どもだって、学校で嫌なことがあったり、友だちとうまくいかなかったり、あるいは家庭に不満を抱いたりすることもあるでしょう。そんな時に、家と学校以外にもうひとつ、子どもが駆け込める場所が...
2025.09.10|大橋礼