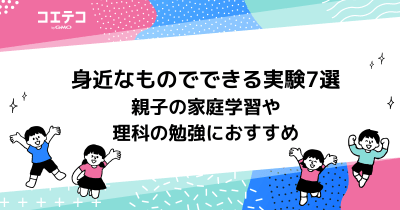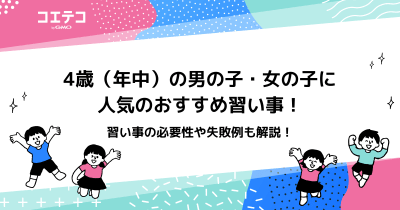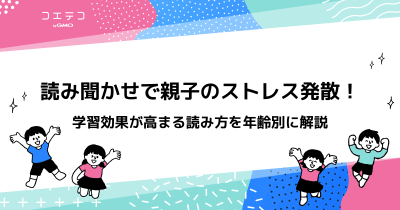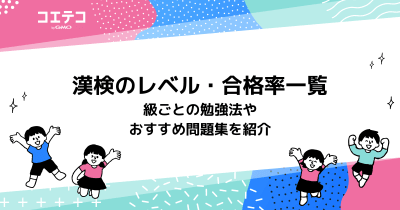理科実験教室おすすめ12選!子どもの科学的思考力を伸ばす教室の選び方
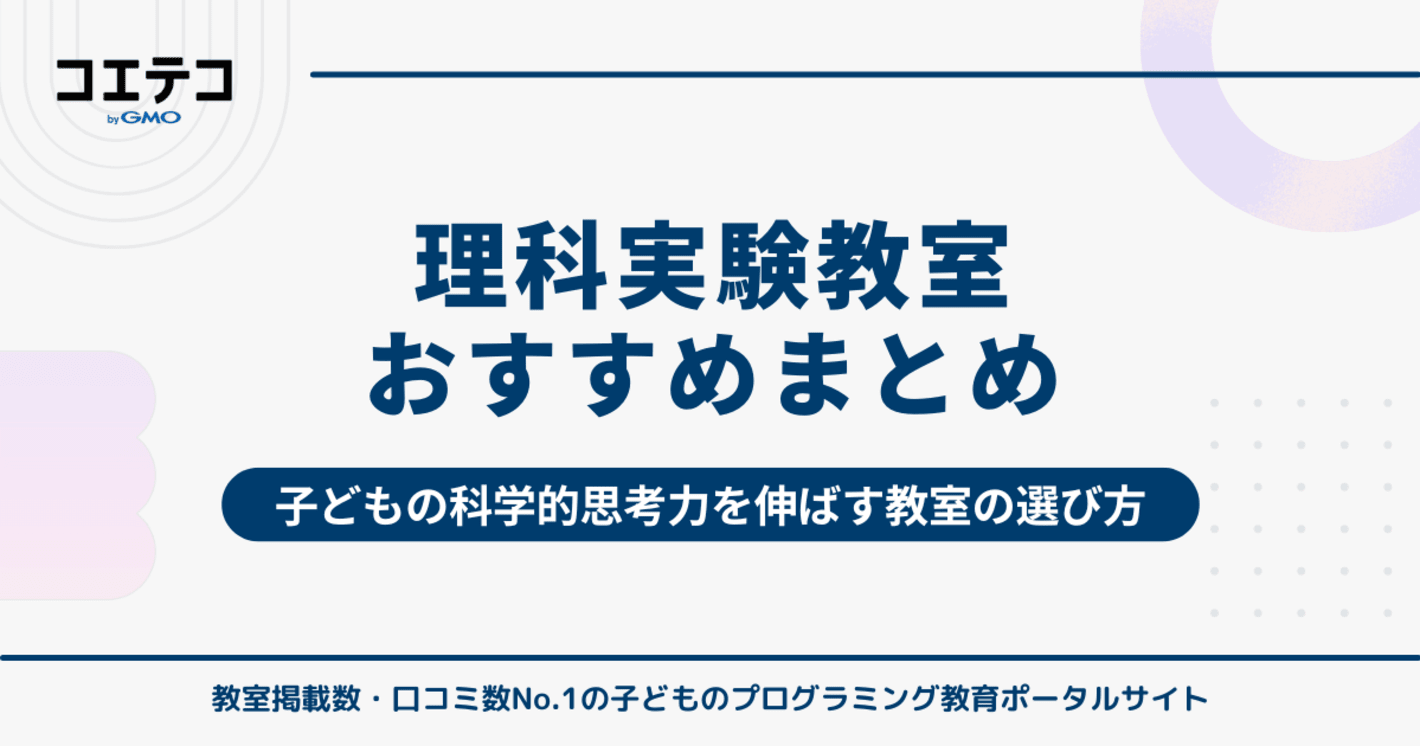
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
理科実験教室は、子どもたちが実際に手を動かして学ぶことで、科学的思考力や問題解決能力を育てる絶好の機会です。しかし、数多くある教室の中から、わが子に合った教室を見つけるのは簡単ではありません。
この記事では、おすすめの理科実験教室12選と選び方のポイントをご紹介します。年齢別カリキュラムの効果から中学受験への活用法まで詳しく解説しているので、教室選びの参考にしてください。
理科実験教室おすすめ12選「比較表」
カンタン比較!
注目ポイントを比較表でチェック!
気になる特徴を一覧化!表内の名称をクリックすると、記事内の詳しい説明箇所に移動します。
スクロールできます
| 教室名 | 画像 | 特徴 | 頻度・回数 | 受講料の目安 |
|
ヒューマンアカデミーサイエンスゲーツ説明を 見る |
 |
STEAM教育の考え方を取り入れた科学実験教室 | 月2回 90分授業 | 問合せ |
|
サイエンス倶楽部説明を 見る |
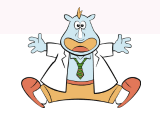 |
1992年に創立された理科実験教育のパイオニア | 月1回 90分〜 学年による |
入会金24,200円 8,250円〜/月 学年による |
|
学研 科学教室ぷらす説明を 見る |
 |
科学マジックと実験、プレゼン練習をセットに | 1回完結 | 1,760円/1回 |
|
ベネッセサイエンス教室説明を 見る |
 |
課題発見→仮説→検証・考察の思考プロセスを重視 | 月1回 120分 | 登録料11,000円 小学生コース 12,100円/月 |
|
栄光サイエンスラボ説明を 見る |
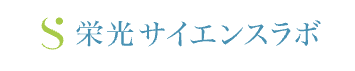 |
英語で実験を行うイングリッシュコースや中学受験対応コースも | 月2回 90分 | 問合せ |
|
四谷大塚 理科実験教室説明を 見る |
 |
学年に応じたカリキュラム 中学受験コースあり | 年10回 90分〜120分 |
10回分の受講料 67,100円〜 学年・コースによる |
|
ScienceAcademia説明を 見る |
 |
400種類以上の実験を体験できる | 月1回 120分 | 受講料5,489円/月 材料費2,189円/月 年会費あり |
|
サイエンスラボ説明を 見る |
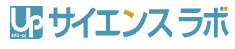 |
修士・博士号を取得した研究者が講師 | 月1回が標準 | 問合せ |
|
アインシュタインラボ説明を 見る |
 |
幼児から高校生まで一貫した専門性の高い実験教室 | 月1回〜2回 120分〜150分 コースによる |
5,460円〜/1回 コースによる |
|
NEST LAB説明を 見る |
 |
小中学生のオンライン研究スクール | 月2回 90分〜150分 コースによる |
入会金23,100円 授業料6,600円〜/月 教材費3,300円〜/月 コースによる |
|
キッズラボ説明を 見る |
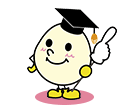 |
キャンプや野外活動などの課外活動も豊富 | 問合せ | |
|
サイエンス教室(メンデル工房)説明を 見る |
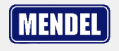 |
幼児・小学生のための理科実験専門教室 | 月2回 60分 教室・コースによる |
入会金22,000円 年間授業料 92,400円〜 |
理科実験教室で子どもに身につく3つの力

理科実験教室に通うことで、子どもたちにはどのような力が身につくのでしょうか。実際の実験体験を通じて育まれる能力は、単なる知識の習得を超えた本質的な成長につながります。
- 好奇心と探究心
- 論理的思考力と問題解決能力
- 表現力とコミュニケーション能力
実験教室で培われる3つの力とその具体的な成長効果をご紹介します。
1. 好奇心と探究心が自然に育つ
子どもたちの「知りたい!」という気持ちは、学びの出発点です。理科実験教室では、普段の生活ではなかなか体験できない"ちょっと不思議な現象"に出会うことが多くあります。たとえば色水が思いがけない色に変わったり、風船が予想外の動きをしたりすると、子どもは目を輝かせて「どうなっているんだろう?」と考えます。こうした驚きは、教科書を読むだけでは得られない感覚です。
ワクワクしながら「もっと知りたい」「自分でも試してみたい」という気持ちが次の行動につながり、好奇心の芽を大きく育てていきます。
さらに、繰り返し実験に取り組むことで「一度の発見で終わらせず、もっと深く探ってみよう」と、自然と探究心も養われます。
好奇心と探究心は、理科に限らず算数や読書、さらには日常生活の小さな疑問にも向けられるようになります。実験を通じて「知るって面白い!」という実感を持てることが、学び全体への前向きな姿勢につながります。
2. 論理的思考力と問題解決能力が身につく
理科実験教室では、「疑問を持つ→予想する→実験で確かめる→結果を考える」という科学的思考プロセスを繰り返し体験します。これにより、筋道を立てて物事を考える論理的思考力が自然に育ちます。失敗から学ぶ問題解決能力
実験では予想と違う結果が出ることがよくありますが、この「失敗体験」こそが貴重な学習機会です。「なぜうまくいかなかったのか?」と原因を考え、「次はこうしてみよう」と改善策を試す中で、問題解決能力が身につきます。この「やってみる→うまくいかない→原因を考える→改善する→再挑戦」のサイクルを通じて、以下の力が同時に育ちます。
- 観察する力:結果を正確に把握する
- 分析する力:原因を論理的に考える
- 改善する力:解決策を判断し実行する
脳科学研究でも、学習初期段階での失敗体験が、最終的な学習効果を向上させることが実証されています。理科実験教室は、文部科学省が重視する「自ら問いを立て、解決方法を考えて実行できる力」を楽しみながら身につけられる貴重な機会なのです。
参考:
文部科学省「学習指導要領等が目指す姿」
誤答の研究─脳科学の研究で分かった「失敗こそが学び」/池谷裕二教授
3. 表現力とコミュニケーション能力が向上する
理科実験教室で作る実験ノートや発表体験は、子ども達の表現力とコミュニケーション能力を大きく伸ばしてくれます。実験ノートで育つ表現力
実験ノートを作ることで以下の表現スキルが身につきます。- 順序立てて情報を整理する文章力
- 見たことや感じたことを具体的に表現する描写力
- 理由を示しながら自分の考えを説明する力
実験ノート(実験記録・シートなど種類や呼び方は教室によりさまざま)には「目的→方法→結果→考察」を順番に書きます。この習慣によって、筋道の通った文章を書く力が自然と身につきます。
観察した現象を「色が赤から青に変わった」「甘いにおいがした」「泡がブクブク出てきた」など、五感を使って具体的に言葉で表現することで、豊かな語彙力と説明する力も育ちます。
発表体験でプレゼンテーション能力も育つ
多くの教室では、完成したノートを友だちや先生の前で発表する機会も設けられています。発表の体験を通じて、書く力だけでなく「話して伝える力」も同時に磨かれていきます。国語力向上への効果も実証済み
文部科学省の全国学力・学習状況調査(理科の結果を活用した専門的な分析)の結果によると、観察・実験活動を重視する学校では、国語の「思考・判断・表現」を問う問題の平均正答率が全国平均よりも5.3%から12.3%高くなっています。実験での観察・考察・記録という活動が、総合的な言語能力の向上に寄与していることがわかります。
理科実験教室で身につく3つの力は、どれも将来の学習や社会生活の基礎となる重要な能力です。手を動かし、失敗を恐れずに挑戦し、結果を記録し、新しい発見を喜ぶ。こうした体験を通じて、子ども達の可能性は大きく広がっていくでしょう。
理科実験教室の失敗しない選び方3つのポイント

理科実験教室を選ぶ際に失敗しないためのポイントは3つあります。
- 子どもの成長段階に応じたカリキュラムか
- 指導体制の質と安全性
- 継続して学習できる環境
ひとつずつ、詳しく解説しますね。
子どもの成長段階に応じたカリキュラムかどうか
最も重要なのは、お子さんの年齢と発達段階に適したカリキュラムが組まれているかです。年齢別の適切なカリキュラム例の目安
| 幼児期 4歳〜6歳 |
五感を使った体験型実験が中心 | 色が変わる実験 シャボン玉の科学など |
| 小学校低学年〜中学年 7歳〜9歳 |
身近な現象を題材にした実験 | 磁石の力 植物の観察など |
| 小学校中学年〜高学年 10歳〜12歳 |
より本格的な実験器具を使用 理論的な内容も含む |
化学反応 電気の仕組みなど |
たとえば、
- 理科に強い興味を示すお子さんには、少し難易度の高い内容を扱う教室
- 楽しみながら学びたいお子さんには、面白い講師や魅力的なカリキュラムの教室
まずは体験教室に参加して、実際のレベル感や雰囲気を確認することをおすすめします。
指導体制の質と安全性
理科実験では化学薬品や実験器具を扱うため、指導体制の質と安全管理はとても重要です。チェックすべき指導体制のポイント
-
講師の資格
理科教育の専門知識を持つ講師が在籍しているか -
生徒比率
1人の講師が担当する生徒数が適切か -
安全管理
実験器具の取り扱い説明、保護具の着用、緊急時の対応体制が整っているか -
個別指導
子ども一人ひとりの理解度に応じた指導ができているか
優良な教室では、実験前の安全説明を徹底し、常に複数の講師が教室内を巡回して安全を確保しています。また、万が一の事故に備えた保険加入状況も確認しておきましょう。
継続して学習できる環境
理科実験教室に限りませんが、習い事は何より「続けやすい・続けられる」ことが重要です。継続学習のための環境チェックポイント
-
通いやすさ
自宅からのアクセスが良好で、送迎に負担がないか -
スケジュールの柔軟性
振替授業や時間変更に対応してもらえるか -
進級システム
年齢や習熟度に応じて段階的にレベルアップできる仕組みがあるか -
コミュニティ
同年代の仲間と切磋琢磨できる環境があるか
料金体系の透明性も重要
月謝以外にも教材費や実験材料費がかかる場合があります。年間を通じてどの程度の費用が必要か、事前にしっかりと確認しておきましょう。明確な料金体制を説明できないようであれば、それは注意信号のひとつです。特に実験教室は、たとえば白衣を購入するとか、教材費といった項目も多いので、きちんとすべて確認しましょう。
月謝の負担も考える
長期間通うことを考慮し、家計に無理のない範囲で選択することも大切です。お子さんが目を輝かせて実験の話をする姿を見ていると、「少し無理をしてでも続けさせたい」と感じる保護者の方も多いでしょう。
一方で、現実的な視点も大切です。
他の習い事との兼ね合いや、将来の教育費全体を考えると、無理は禁物です。「やりたいことは全部やらせてあげたい」という親心はとてもよく分かりますが、家計の安定があってこその習い事です。
長期間通うことを前提に、無理のない範囲での教室選びを心がけてくださいね。
理科実験教室は中学受験対策と理系進路にどう役立つ?

中学受験の理科では実験を題材にした問題が頻出しており、従来の暗記中心の学習だけでは対応が困難になっています。
理科実験教室では、こうした変化に対応できる実践的な力を身につけることができます。
中学受験での具体的なメリット
実験問題への対応力向上
私たちは「聞いただけの知識」よりも「実際に体験したこと」の方が、はるかに記憶に残りやすいものです。たとえば、初めて行く場所への道順を口頭で説明されるより、一度でも実際に歩いて行った方が、その道のりを鮮明に覚えていますよね。
理科実験でも同様で、教科書で「酸素と水素が結合すると水になる」と読むだけでなく、実際に気体を混合させて水滴ができる瞬間を目で見て、手で触れることで、その知識は深く記憶に刻まれます。
体験による学習効果は、応用問題や初めて出会う問題に直面したときに特に威力を発揮します。過去の実験体験が「あの時こうなった」という具体的な記憶としてよみがえり、問題解決の重要な手がかりとなるのです。
記述問題への対応力
実験ノートの作成を通じて身につけた論理的な文章構成力は、理科の記述問題で威力を発揮します。「なぜそうなるのか」を根拠を示して説明する能力は、国語の論説文読解や社会の記述問題にも応用できます。
理系進路への長期的メリット
高校進学後も、理科実験教室の経験は大きな財産になります。高校理科への準備
実験ノートの作成や結果の分析を通じて身につけた論理的思考力は、高校の化学・物理の理解を深めるだけでなく、大学入試の記述問題への対応力も向上させます。理系への興味・関心の維持
理科への苦手意識を持つ前に、実体験を通して科学の面白さを知ることは、将来の理系進路選択にも良い影響を与えます。多くの理系大学生や研究者が「子どもの頃の実験体験が進路選択のきっかけになった」と振り返っていることからも、その効果の大きさが分かります。
おすすめ理科実験教室12選「各教室をくわしく紹介」
ヒューマンアカデミーサイエンスゲーツ

対象年齢:年中(4歳)〜小学3年生
STEAM教育の考え方を取り入れた科学実験教室で、身近な科学現象をテーマにした約200種類の実験を4年間で体験します。
「仮説→実験→結果→考察」の4つの基本ステップを通じて論理的思考力を習慣づけます。SDGsやノーベル賞などの最新科学研究を取り上げたコラムも充実しており、知識だけでなく好奇心・探究心を育む「生きる力」を身につけることができます。
サイエンス倶楽部

対象年齢:幼児(年中・年長)〜中学生
1992年に設立された理科実験教室のパイオニアで、現在首都圏に14教室を展開しています。
「なんで?どうして?」という子どもたちの疑問を大切にし、実験を通して科学の原理原則を学びます。五感をフル活用したドキドキ・ワクワクする体験を重視し、間違いや失敗も貴重な学びの機会として捉えています。
本格的な実験器具を使用し、子どもたちの探究心を刺激し続ける教育を行います。
学研 科学教室ぷらす

対象年齢:小学生
科学のチカラを使ったマジックを取り入れた新しい科学教室です。
テキスト、科学キット、まとめシート「グリモワール」を使用し、科学的な考え方と表現力を同時に育みます。マンガでスイスイ読めるテキストと、実験結果をまとめるレポート作成で知識を定着させます。
マジックを人前で発表することでプレゼンテーション力も養い、1回90分程度の単発講座として参加費1,760円で受講できます。
ベネッセサイエンス教室

対象年齢:年中〜小学6年生
科学実験を通して「自ら考える力」と「失敗を恐れず取り組む姿勢」を育む理科実験教室です。
課題発見→仮説→検証・考察の思考プロセスを重視し、問題解決力を養います。4~6人のグループに理系出身の専門講師が一人ずつ付き、個別にフォローします。
振替制度も充実しており、透明性の高い料金体系で安心して通うことができます。
栄光サイエンスラボ

対象年齢:年中〜中学生
子どもたちが自ら未来を切りひらく5つの力(問題発見力・問題解決力・論理的思考力・表現力・創造力)を身につける科学実験教室です。
少人数定員制でディスカッションが活発に行われ、PDCAサイクルを習得することをめざします。
専門知識を持った理系大学出身の教師が多く在籍し、英語で実験を行うイングリッシュコースや中学受験対応コースも用意されています。
四谷大塚 理科実験教室

対象年齢:小学生
入門コース(小1~3年生)、中学受験コース(小4~6年生)、最上級コース(小4~6年生)の3つに分かれています。
入門コースでは実体験に基づく科学的思考の構築を重視し、中学受験コースでは「予習シリーズ」と連動した入試対策を行います。最上級コースでは高校・大学レベルの高度な実験に挑戦します。
ScienceAcademia

対象年齢:年中・年長〜小学6年生
物理学・化学・生物学・地学・工学の幅広い分野で400種類以上の実験を体験できる理科実験教室です。
α1~α5の5つのコースに分かれ、小学校の内容から中学生レベルまで段階的に学習します。実験前の予想、結果記録、考察をまとめるレポート作成を通じて科学の基本を身につけます。月1回コース(120分で2つの実験)と月3回コース(70分×3回)があります。
サイエンスラボ

対象年齢:小学生・中学生・高校生
ホンモノの科学実験に取り組みながら、世界に挑んでいくためのチカラを伸ばしていく教室です。
修士・博士号を取得した研究者が講師を務め、専門性の高い指導を行います。自由研究コンクール「LABOCON(ラボコン)」の開催や、夏の体験講座「サマートライアル」など多彩なイベントも実施しています。
アインシュタインラボ

対象年齢:幼児(4歳)〜中学生
物理・化学・生物などいろいろな分野の理科実験を通して「生きた学力」と「科学する精神」の育成をめざす教室です。
通常コース(C・T・I)と入試対応コース(中学入試A・高校入試V)の5コースを用意しています。
幼児期は好奇心を引き出し、小学校低学年では実験器具の扱い方を習得、高学年・中学生では本格的な実験で科学者・研究者の視点を身につけます。
NEST LAB

対象年齢:小学生・中学生
「好きを究めて知を生み出す」をテーマとした小中学生のオンライン研究スクールです。
NEST(Nature、Engineering、Science、Technology)の概念に基づき、子どもたちの「好き」を起点に世界中の誰も知らないことをテーマに研究活動を行います。修士・博士号を取得した研究者が講師を務め、全国どこからでも受講可能です。
中高生向け学会「サイエンスキャッスル」での発表機会もあり、本格的な研究者としての道筋を提供しています。
キッズラボ

対象年齢:年中(4歳)〜中学生
専修グループが運営する理科実験専門教室で、つくば校・宮原校・春日部校の3校を展開しています。
化学・生物・物理・地学の4分野にスポットを当て、実験→仮説設定→検証→レポート作成の流れで科学的思考力を育てます。キャンプや野外活動などの課外活動も豊富で、海辺の生物採集や鉱物採集、天体観測など多彩な体験学習を実施しています。
体験から考えることを大切にし、主体的な学びを重視した教育を行っています。
サイエンス教室(メンデル工房)

対象年齢:幼児・小学生
幼児・小学生のための理科実験専門教室として、科学する心を育てることを目的とした教育を行っています。
幼児コースと小学生コースに分かれており、年齢に応じた実験カリキュラムが組まれています。メンデル工房は札幌と東京(吉祥寺)に展開しており、実験を通じて子どもたちの探究心と科学への興味を育みます。
お子さんにぴったりの理科実験教室を見つけよう
理科実験教室は、子どもたちの科学的思考力、問題解決能力、探究心を育む貴重な学習機会です。単なる知識の習得を超えて、論理的に考え、表現し、継続的に学ぶ力が身につきます。教室選びの最重要ポイント
- お子さんの年齢と興味に適したカリキュラムがあること
- 安全で質の高い指導体制が整っていること
- 継続して通える環境が揃っていること
中学受験を控えているお子さんには、実験問題に対応できる実践力を重視した教室を、将来の理系進路を見据えているなら、より本格的な研究体験ができる教室をおすすめします。
一方で、体験型の学習が大好きな子も多くいます。実験は、好きな子どもたちにとっては「面白すぎる」体験です。わが子の「好き」や、「進路」を総合的に考慮してくださいね。
まずは体験教室から始めましょう
どの教室がわが子に合うかは、実際に体験してみなければ分かりません。多くの教室で無料体験レッスンを実施していますので、まずは2〜3校の体験教室に参加してみることをおすすめします。理科実験教室での体験は、お子さんの将来の可能性を大きく広げる投資となるでしょう。この記事を参考に、ぜひお子さんにぴったりの教室を見つけてください。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
小学校の派手でおもしろ理科実験!材料が少なくても可能なネタ解説
小学生が大好きな理科の「科学実験」。この記事では、家庭でも簡単にできる、簡単・手軽で面白い実験を5つをピックアップ。科学実験が習えるおすすめの教室も紹介します。
2025.11.17|コエテコ教育コラム
-
身近なものでできる実験7選|親子の家庭学習や理科の勉強におすすめ
子どもにとって、日常生活はたくさんの疑問に満ち溢れている実験の場のようなもの。この記事では、夏休みの自由研究などにもぴったりな身近なものでできる実験や、本格的に理科を習いたいという親子...
2025.11.17|コエテコ教育コラム
-
4歳(年中)の男の子・女の子におすすめ習い事19選【2026年最新版】
幼稚園や保育園で年中にあたる4歳児は、習い事を始めるには早すぎるという見方もあるかもしれませんが、4歳から始められる習い事は数多くあり、レッスンを楽しむ子どもはたくさんいます。心と体が...
2026.01.02|コエテコ教育コラム
-
読み聞かせの学習効果は?高まる読み方を年齢別に解説
近年、読み聞かせによる脳科学的な学習効果やリラックス効果が話題を呼んでいます。しかし「読み聞かせができない」と悩みや負担を感じる場合、まずは家庭に合った方法を無理なく実践しましょう。今...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
漢検のレベル・合格率一覧!何級からすごいのか目安を解説
2020年度は140万人超の受験者がいた漢検。3歳から102歳と子どもから社会人まで幅広い年齢層が受験しています。この記事では、漢検の公式情報を中心に、各級のレベルの目安やおすすめの勉...
2025.11.17|コエテコ教育コラム