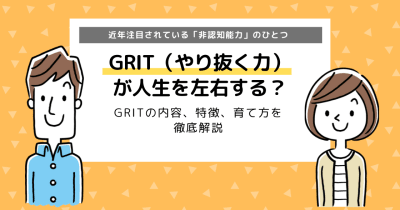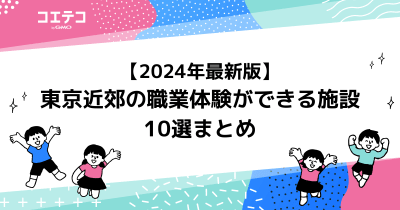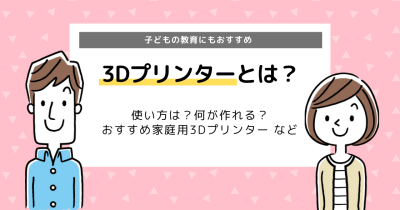あの職業がなくなる!?あと10年で消える職業10選
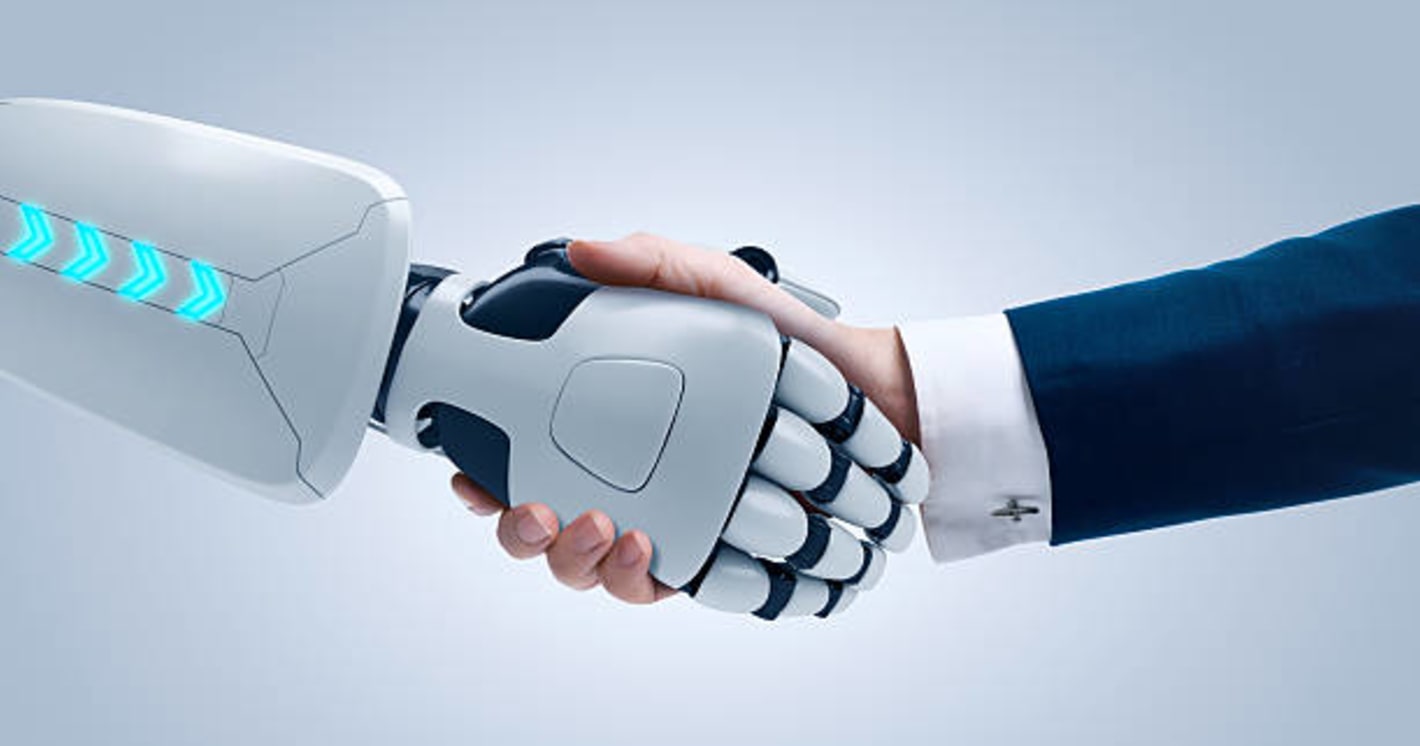
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
このような議論は、とある論文が発端とされています。この記事ではその論文について紹介すると共に、コンピューター化が人間の生活にもたらす影響や、実際にどのような職業がコンピューターに奪われてしまう恐れがあるのかについて解説します。
1.話題の論文『雇用の未来-コンピューター化によって仕事は失われるのか』
この論文は、オックスフォード大学のマイケル・A・オズボーン准教授、及び同大学のカール・ベネディクト・フライ研究員によって2014年に発表されました。論文の中では、アメリカ国内における702の職業を「クリエイティビティ」「社会性」「知覚」「細かい動き」といった項目に分類・分析することにより、それらの職業が10年後にコンピューター化のあおりを受ける形で消滅する可能性を試算。その結果、702の職業のうち47%が10年~20年後には機械に取って代わられるという結論に至っています。
また2015年には、日本の野村総合研究所がオズボーン准教授と共に、日本国内の職業を対象とした同様の調査をしました。結果、日本国内でも49%の労働人口が10年~20年後には機械に代わられる可能性が高いという結論に至っています。
これらの調査結果は、一時的にテレビや雑誌などの各種メディアでも大きく取り上げられたことから、一般層においても話題となりました。それと同時に自身の将来、あるいは子どもたち世代の働き方について、改めて考え直した方も少なくないのではないでしょうか。
2.コンピューターに人間の雇用が奪われる
コンピューターに仕事を奪われる、という状況について、同論文では「各仕事に必要なスキルはどのようなもので、そのスキルを機械がどれだけ自動化できるのか」という観点から定義しています。つまり、仕事を行うために必要なスキルが少なければ少ないほど、機械に取って代わられる可能性は高いといえるのです。この現象が起きていることの大きな要因のひとつとして技術の飛躍的な発展が挙げられます。なかでも、49%という数値に大きな影響を及ぼしているのが「センサー技術」です。オズボーン准教授も、センサー技術の進化や普及を重要視しています。
例えば、従来の工場における機械の役割は、コンベアーなどによる商品の運搬が限度であり、商品の選り分けは人間が行っていました。しかし、センサー技術が発展すると、それらを搭載した産業ロボットが商品の選り分けから運搬まで全てをこなしてしまうため、人間を雇用する必要はなくなってしまうのです。このような高度なセンサー技術が搭載されたロボットは、やがて産業以外の分野でも活躍するようになり、人間の雇用機会が大きく減少すると予想されています。
3.あと10年で消える職業・消えない職業
同論文では、10年で消える職業と消えない職業を具体的に示しています。どんな職業が挙げられているのか、主なものを見ていきましょう。<消える職業>
- 電話オペレーター
- 証券会社の社員
- レジ係
- データ入力作業員
- オフィス事務員
- ホテルの受付係
- 農業労働者
- スポーツの審判
- 銀行の融資担当
- 歯科検査技師
これらの職業は、AIが監視すれば済んでしまうものや、コンピューターを導入することで、人を配置しなくてもよくなりつつあるものです。例えば、近年小売店などで導入が進みつつある「セルフレジ」もそのひとつ。セルフレジの導入によって、レジ係の雇用機会が減っているのは紛れもない事実でしょう。
一方で、消滅する可能性が低いとされている職業は以下のとおりです。
<消えない職業>
- ソーシャルワーカー
- 聴覚訓練士
- 外科医
- 内科医
- 看護師
- セールスエンジニア
- 小学校教員
- 心理学者
- 聖職者
- 経営者
今後10年の間に消えないとされている職業は、人間の心や精神活動に深く関係する分野であることが特徴的です。確かに聖職者の仕事は、人間の精神活動にとって大切な役割を担っており、安易に代替できるものではありません。
また、ソーシャルワーカーや心理学者なども精神活動をフィールドとした職業のひとつです。医療系の職業は、技術的な部分は現在でも著しく機械化が進んでいますが、患者に寄り添う、あるいは患者を説得するという行為などはコミュニケーションが大切なので、機械に取って代わられるとは考えにくいのも納得です。
抽象的概念を扱う分野や、コミュニケーション次第で結果が変わってしまうような職業は機械化されにくいと考えられるので、将来の職業選択の参考にしてみても良いかもしれませんね。
4.自動化する側になる
上記の論文の中では「自動化」という言葉が出てきました。業務を自動化することができれば、それにまつわる人件費などを削減することができますし、他の活動に時間を当てることができます。これは、「自動化される側」からすると働き口が減って損ですが、「自動化する側」から考えると大きく得をすることになります。コンピューターの誕生以前から、人類は自動化することで生産性を向上させてきました。小麦を引くのに水車を使ったり、それをさらに高速化させるために機械を導入したり。放っておいても、あらゆるものは自動化される方向に向います。その中で自分にしかできないことを確立するためには、自分が「自動化する側に」なっていくことが大事でしょう。自動化できるものがないか常に探し、できそうであれば試してみる。その繰り返しが、将来的なスキルの獲得に繋がっていきます。
まとめ
コンピューターを始めとした技術革新には目覚ましいものがあり、今後人間の生活に大きな影響を及ぼすことは間違いないでしょう。特に現在の子どもたちはこれらの影響を大きく受ける最初の世代であるということが言えるでしょう。お子さんに「働くこと」について教える際には、自身の世代の仕事に対する考え方や価値観を押し付けるのではなく、現在、さらには将来における仕事のあり方を十分に考慮することが大切です。この機会に、お子さん自身にも自分の将来についてよく考えるよう提案してみてはいかがでしょうか。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
GRIT(グリット)とは?やり抜く力「非認知能力」
人生において、成功のカギを握っている能力とは一体何なのか、どのような能力が学歴や将来の年収などに影響を及ぼしているのかについて近年様々な議論が展開されてきました。その中で注目されている...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
小学生の子どもがショート動画ばかり見ている!親が知っておくべき影響と対策
最近の調査によると、小学生の67%がテレビよりも動画配信サービスを視聴しており、その中でもショート動画の人気は急上昇しています。子どもたちの生活の一部となったショート動画ですが、その影...
2026.01.19|大橋礼
-
東京近郊の職業体験ができる施設10選まとめ!
世の中にはさまざまなお仕事があります。そんな中で、子どもが将来なりたい仕事を考えるきっかけになるのが「職業体験」ではないでしょうか。 今回は小学生以下のお子さんが楽しめる、東京近郊の...
2026.01.02|コエテコ byGMO 編集部
-
家事代行サービスおすすめ5選|塾や習い事の送迎に使えるかも?
子どもを習い事に通わせるとなると、保護者のスケジュールにも大きな影響がありますよね。 そんなときに役立つかも知れないのが家事代行サービスです。 今回は、おすすめ業者や費用の目安、頼...
2025.11.12|コエテコ byGMO 編集部
-
3Dプリンターで作れるものは?おすすめ家庭用プリンターを紹介
3Dプリンターという製品が世間に知られるようになってはや数年経ちますが、実際に使ったことがあるという人は少ないと思います。この記事では3Dプリンターの仕組みや使い方、どんなものが作れる...
2025.11.12|コエテコ byGMO 編集部