小学生の子どもがショート動画ばかり見ている!親が知っておくべき影響と対策

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
「あと1個だけ…」と言いながら、結局30分以上経っても画面から目を離さない。何をそんなに夢中になっているのかとのぞくと、ずっとショート動画を見ている。
そんなわが子の姿に、頭を悩ませている保護者の方も多いのではないでしょうか。
最近の調査によると、小学生の67%がテレビよりも動画配信サービスを視聴しており、その中でもショート動画の人気は急上昇しています。
子どもたちの生活の一部となったショート動画ですが、その影響について知っておくべきことと、家庭でできる対応策をご紹介します。
子どもにショート動画を見せたくない!そんな時は

小学生に「ショート動画を見せない」を徹底するためには、結局のところスマホやタブレットを取り上げるしかありません。
テレビでも見られないようにするには、テレビ側での制限モード等をオンにするとか、アクセス制限をかけて、映らないようにする以外に方法はありませんが、テレビの機種にもよります。
現実的な対策としては、利用時間の決まりやペアレンタルコントロール等を用いて管理する方法があります。
これがなかなか実際には守られないし、できないのが親としては悩みどころです。
なぜ子どもがそれほど夢中になるのか、ショート動画を見すぎることの影響、こうした背景をなぞりつつ、先輩ママ・パパ達の意見も参考にして、「あなたの家でできそうなショート動画を見続けさせない方法」を見つけて実践していきましょう!
ショート動画とは

ショート動画は、「短い動画」で、縦型動画とも言われています。
代表的なショート動画の媒体
- YouTube Shorts
- Tik Tok
- Instagram Reels
ショート動画は、だいだい60秒〜数分です。小学生はYouTubeのショート動画を見ているケースが多いようですが、高学年にもなるとインスタやTikTokの視聴も多い印象があります。

上記の10代は15歳〜なので、小学生は含まれていません。
しかし、幼少期からタブレットで動画を視聴し育っているデジタルネイティブ世代である今の小学生は、これに近い(もしかしたら、もっと多い!?)割合でショート動画を視聴している可能性があります。
参考:小学生とSNS「LINE・Twitter・Facebook・TikTok」との関わりを親は本当に把握してる?
小学生とショート動画の関係性、知っておきたい影響

ショート動画が小学生に与える影響については、さまざまな研究結果が報告されています。
- 学業成績との負の相関関係
- 注意力持続時間の減少
- 睡眠の質の低下
- 現実世界での対人関係スキルへの影響
良い影響よりも、リスクの方が高い印象です。それだけに心配ですね。
特に懸念されるのは、AIによるレコメンド機能です。子どもの好みを学習したアルゴリズムは次々と「見たくなる動画」を提案するため、視聴が長時間化しやすい特徴があります。
動画視聴もある程度は、息抜きや楽しい時間として良いかもしれません。
ところが、ショート動画はあっという間に終わり、次から次へと見たくなる動画があらわれて、やめるタイミングもなく、子どもは沼にハマるように見続けてしまうことも少なくありません。
ショート動画が悪いというよりも、想像以上に長時間見続けてしまうこと、制限をかけないと本来子どもが視聴するには適切ではない動画を見てしまう可能性があることが問題なのです。こうした状況を踏まえた上で対策を考えることが必要です。
小学生の7割がテレビよりも動画視聴派!

この調査によると、小学生の実に7割近くが、テレビよりも動画配信(YouTubeなど)を視聴していることがわかります。興味深いのは次の調査結果です。

これは、動画を倍速にして見たことはあるか?の回答です。
小学生の約6割が動画を倍速で視聴する習慣があるわけです。「早いほどいい」「短いほどいい」という今の子どもたちの嗜好。ショート動画はまさに彼らの心理にぴったりとマッチした形式と言えるでしょう。
今の子は「せっかち」なのか!?
集中力が足りないのか?長い動画はつまらんのか?
「次の動画」が止まらない!小学生がショート動画に夢中になる理由

小学生がショート動画に夢中になる理由はいくつかあります。
- 15〜60秒という短時間で完結する満足感
- 次々と新しい刺激が提供される仕組み
- 視聴者の反応を分析した個人向けコンテンツ提供
テレビ番組の多くは30分以上です。冒頭の調査結果にあったように、テレビよりも動画を好む子どもが増えているのは、「短い時間でより多くの情報や刺激を得たい」という欲求が根底にあるのかもしれません。
こうした子どもたちにとって、ショート動画は魅力にあふれたコンテンツなのです。

しかも、ショートに限りませんが動画は、好みそうなものを選択して紹介してくるのですから、いつまでたっても「飽きる」ことがない困った仕組みになっています。
脳科学の観点からも、短い動画を視聴するたびに脳内で分泌されるドーパミンが、「もうひとつだけ」という行動を促す要因になっていることが指摘されています。
では、こうした状況にどのように対応すればよいのでしょうか?次は具体的な対策をご紹介します。
家庭でできる!ショート動画との上手な付き合い方

スマホやタブレットを取り上げるのは、実際には難しいですよね。となれば、ショート動画を完全に禁止するのではなく、適切な利用方法を身につけさせることが大切です。
- 視聴時間の明確な設定
- 動画アプリのペアレンタルコントロール機能の活用
- 食事中や就寝前の利用禁止ルールの設定
- 「画面を見ない時間」を積極的に作る
これらのルールを設ける際に重要なのは、子ども自身にも理由を理解してもらうことです。「なぜ制限が必要なのか」を丁寧に説明し、子どもと一緒にルールを決めると、より効果的です。
ショート動画に限らず、ゲームも似たような「家庭の悩み」があるわけですが、まずはとにかく、決まりを作り、子どもが守れるよう全力で戦いに挑むしかありません。

そのためには、時間設定をして自動的に「動画を見られなくする」ツールやアプリを導入したり、守れなかった場合の罰則を決めたり、その取り決めを断固として行い続けることが重要です。
とはいえ、旅行先だとか親が忙しい時とか、ついつい(今日だけは特別)となりがちで、そこから「なしくずし」になりやすい。ここで、どれだけ親が踏ん張れるかが勝負です。
東京都在住の小4の子を持つママは、「息子と話し合って、平日は30分、休日は1時間というルールを決めました。最初は不満そうでしたが、タイマーをセットして『残り5分』などと声をかけるようにしたら、少しずつ守れるようになりました」と話してくれました。
タイマーが誰にでも有効かどうかは別にして、それぞれの家庭で、それぞれの子どもの性格に合わせた方法を工夫するのもポイントですね。
毎日できるわけではありませんが、たとえば休日に子どもが動画を見続けているようなら、トランプをやろうと誘う、一緒に料理を作る、お手伝いをさせる、買い物に出かける、とにかく「画面」から離れる時間を意識的に作ってみましょう。
次では保護者の体験談をご紹介します。
「うちの子もそう!」親たちの本音と対応策

Nさん(小4男子の母親)
息子はショート動画にハマっていて、声をかけても『あとひとつだけ』と言い続けるのが悩みでした。
結局、スマホ利用時間管理アプリを導入して、1日の上限を設定しました。
初日は『なんで見ちゃダメなのッ!』と怒鳴ってきて、その勢いにビックリ。でも、ここでケンカしても不毛なので、心おちつけて『使い方を自分で考える練習』と説明しました。
何度でも、繰り返し、ずっと見ているとこういう悪影響がある、見てはいけないわけではなく、1日24時間しかないのだから時間を大切に使おうよ、と(子どもは不満げで納得はしていませんでしたが)話しましたよ。
最近は、何度でも説明する私に根負けしてきたのか、あまり言わなくなり、上限時間を守っています。
Sさん(小5・小2女子の父親)
自分が子どもの頃はテレビでアニメを見ていると親に怒られたものですが、テレビだからずっと見っぱなし(アニメの時間帯が終わってしまうから)ってことはなかった。
でも、ショート動画は次から次へと出てきて、途切れる暇がなく、永遠に出てくるんですよね。
うちではYouTubeをタブレットで見ているので、今は、YouTube Kidsにして視聴時間を制限しています。
また、『動画を見る前に宿題を終える』『45分間』というルールにしています。
でも上の娘は最近スマホをもたせたので、他のSNSのショートも見ているみたいです。反抗期もあるのか、わたしが叱るとにらみつけるように部屋を出ていきますが、心を鬼にして、あまりにひどい時にはスマホを取り上げ、タブレットも使わせませんでした。
そうでもしないと、本当にずーっとショート動画を見続けるので。
とりあえず、スマホを取り上げ&タブレット禁止が堪えたのか、今のところはルールを守っています。
Yさん(小6女子の母親)これらの体験談から共通して見えてくるのは、「禁止」は難しい以上は「適切な利用方法を教える」という姿勢の大切さです。
TikTokのショートが大好きで、暇さえあれば見ていた娘。正直、最初は『今どきの子はみんなそう』と放任していました。
でも、夜更かしが増え、朝起きられなくなったため危機感を持ちました。
今は就寝1時間前からはスマホもタブレットも使わないルールで、リビングに置いて子供部屋には持っていかない決まりです。
また、娘に『いま、何を見ているの?面白い?一緒に見ようかな』と話しかけ、流行っているらしいダンスは『このファッションいいね』と、興味を持って会話しています。わたしが話しかけるとうざったそうにしていることもあるけど、気づかないふり(笑)
鈍感力で対応しないと、子どもに対して苛立ちが募るばかりですから。
でも、ショート動画を一緒に見ることで、親子の会話が広がることもあるし、子どもの関心がどこにあるのかもわかります。『どんどん好きそうな動画が紹介されるから、どこかで区切りをつけようよ』と、声をかけるようにもしています。
いずれ子どもも成長し、それこそ親がスマホを取り上げることもやりづらくなります。そこで、長期的な視点で子どもたちに何を教えるべきなのかを次で考えていきましょう。
「自分で考える力」を育てる、小学生向けデジタルリテラシー教育のポイント

子どもたちがこれからの時代を生きていくためには、ショート動画を含むデジタルメディアと上手に付き合う力が不可欠です。その核となるのがデジタルリテラシー教育です。
- 情報の信頼性を判断する力
- 適切な利用時間を自分で管理する習慣
- 現実世界とオンラインの違いを理解する
- SNSやコメントでの適切なコミュニケーション方法

これらを家庭で教えるポイントは、普段の会話に上手に取り入れること。
たとえば「へぇ、これって面白いの?どこが一番面白い?」「見終わってどうだった?」「この情報は本当だと思う?どうやって確かめられる?」といった問いかけを通じて、批判的思考力を育てることができます。
批判的思考力?何それ?疑ってかかれってこと?
批判するわけではなく、物事をさまざまな方向から見て、根拠を確認し、論理的に考えることです。私たちは常に判断や決断をしなくてはなりませんが、そのために大切なのが批判的思考力です。

情報があふれる世の中に生まれた子どもたち。日常生活でも、常に流れ込んでくる情報から賢い選択をして、間違った情報に惑わされないように、幼少期から少しずつ学んでいく必要があります。
また、自分の時間をどう管理するかも少しずつ覚えていきたいですね。
タイムスケジュールや1週間の予定を自分なりにたてて、どうすれば「自分の自由な時間を作れるか」考えたり、習い事や塾の日程を親子で見直したり、時間の使い方を親子で一緒に考えてみませんか。
こうした親子の会話から、子どもはコミュニケーション力も習得します。
どうしたら相手にわかりやすく伝えられるか、自分の意見をどう主張するか。相手の言葉をきちんと聞いて受け止めることも、最初は難しいかもしれませんが、経験を積むうちに次第に慣れてくるでしょう。
長い物語を読む習慣や、じっくり取り組む趣味を持つことも大切です。「タイパ(時間対効果)」を重視する効率的な考え方にもメリットはありますが、それだけではないことも教えたいですね。

忙しい毎日ですが、時には目的もなく親子でのんびり散歩をしたり、ジグゾーパズルを何日もかけて完成させたり、一緒にコトコト煮込むシチューを作ってみるのはどうでしょう?
「じっくり煮込むとおいしくなるんだよ〜」と話しながら、「時間をかけて、より大きな達成感や充実感を味わう」経験も、子どもの成長にきっと良い影響を与えてくれるに違いありません。
もちろん、学校での体験や友だちとの関わり、先生との会話からも子どもたちは多くを学びます。
しかし、最も身近な家族との日常的なやりとりの中で自然と身につけていく力こそが、子どもにとって生涯の財産になるのではないでしょうか。その過程で、ITリテラシーをしっかり身につけ、デジタル・テクノロジーを存分に活用できるよう導いてあげたいですね。
子どもの教育には学費だけでなく、習い事や塾の費用など何かとお金がかかるもの。 小学生のうちは、家庭学習に「費用がリーズナブルで内容が充実した通信教育を取り入れたい」と考えるご家庭も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、失敗しない通信教育の選び方と教材選びの際に注目したいポイントを解説すると共に、安い通信教育の中でも充実したコンテンツを提供するおすすめの教材を紹介します。


2026/01/02

ショート動画時代の子育て、大切なのは対話と理解
ショート動画が子どもたちの生活に与える影響は、使い方次第で大きく変わります。まずは制限をかけたりルールを決めたりして、「ショート動画漬け」にならないよう環境を整えること。そして、親子の対話と寄り添う理解の力をもって、長い目で見たデジタルリテラシー教育を行っていきましょう。
子どもたちが夢中になっているものに関心を持ち、時には一緒に笑い、感動を共有しながら、適切な距離感を教えていくことこそ、デジタル時代の子育てには必要ではないでしょうか。
子育ての悩みは、寄せては返す波のようにやってきます。
ショート動画はどうやら卒業したのか?と思ったら、次にはまた、何やら新たな問題が出てくることでしょう。
多くの悩みは、数年たって振り返ると(そこまで悩まなくてもよかったなぁ)と思うものです。その時は「大問題だ!」と思ったことも、(成長過程で通る道だったのかな)とも感じるようになります。
とはいえ、真っ只中は、イライラ、ムカムカ、おろおろ、ヒヤヒヤしっぱなし、ですよね!
でも、なんだかんだと子どもとやり合いながら、育まれるのが親子の絆。
とにかく、「どうでもいいや」と完全放棄せず、子どもに語りかけ、言い合い、ケンカしながらも、子どもと関わり合い続ける、向き合い続けることが大切なような気がします。
参考:
The Effects of The Addictive Nature Of Short-form VideosOn Users’ Perceived Attention Span And Mood
ショート動画の依存症に対して操作の有無が与える影響の大きさについての研究/広島大学


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
子どもの話、聞いてますか?聞く力・話す力・コミュニケーション力は親が伸ばす!
子どもが話しかけてくるたび、ついついその場しのぎの対応をしてしまう。気がつけば、子どもの話を心から聞いていない自分がいる……。共働き世帯が増え、時間に追われる毎日。子どもとゆっくり向き...
2025.05.30|大橋礼
-
在宅フリーランスママの働き方|子育てと仕事の両立・稼働時間の変化・3大ピンチの乗り越え方
フリーランスとして働きながら子育てをする毎日は、想像以上に大変。小1の壁、夏休み、急な体調不良――フリーランスママが直面しやすい3大ピンチをどう乗り越えるか。保育園と小学校、中学まで各...
2025.07.31|大橋礼
-
スマホのルールを守らない小学生・中学生!勉強しない!を解決しよう
最近はスマホを持つ小学生も増えました。購入前には親子で話し合いをし、使い方のルールを決めているご家庭がほとんどです。 しかし、約束やルールを守らずに親子喧嘩になってしまうのも、これま...
2026.01.30|大橋礼
-
小学生の留守番「安全対策からキッズシッターまで」子どもの預け先がない時の対処法
今回の教育トピックは「子どもひとりでお留守番」の方法についてです。 預け先が見つからない急な外出や、どうしても子どもひとりで「まるまる1日過ごさせなくてはならないとき」もあるでしょう...
2025.10.29|大橋礼
-
小学生の生活リズムの乱れを整える「6つのステップ」夜ふかし・朝起きられないを改善しよう!
「最近、子どもがどんどん寝るのが遅くなっている」 「朝はなかなか起きてくれない」 多くの親が直面する悩みですよね。「ちゃんとしなきゃ」と思っても、実際は難しいのが現実。今回の...
2025.05.30|大橋礼













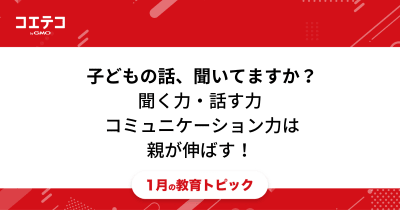

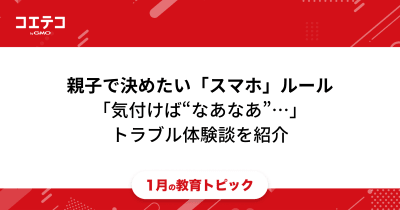
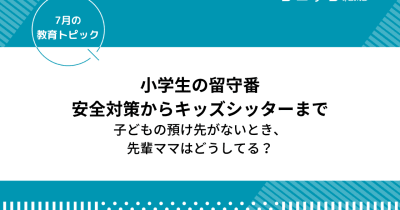
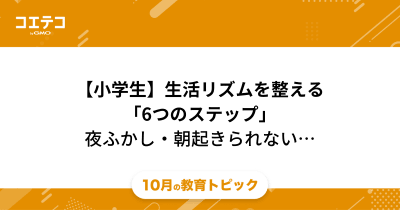
親自身も『あるある!』な現象ですよね。
ちょっと暇つぶしに見始めたショート動画、そのままズルズルと視聴し続けて、気づいたらあっという間に1時間とか。
『子どもに強く言えないなぁ』なんて本音もちょっぴりあります……。